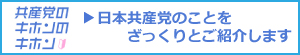速やかに物価高騰対策を!県水道料金値上げに抗議すべき! あぐい初美議員 代表質問〔2024年第4回定例会〕
あぐい初美議員の代表質問 2024.12.5
1、市政運営の基本姿勢について

(1) 国政との関連について
先の衆議院選挙の結果は自公が過半数割れになり、自民党1強政治が終わりを告げました。この結果は物価高騰への無為無策、マイナ保険証のごり押し、能登の地震災害の復旧の遅れなど自民党政治では命も暮らしも守れないと危機感を持った国民が増えたこと、そして何より自民党の裏金問題への国民の怒りとともに、政治改革を願う人が多かったことが表れているのではないかと思います。
自民党の裏金問題の追及は我が党のしんぶん赤旗がスクープをし、その後も選挙最終盤で裏金非公認候補に政党助成金から2000万円が支給されていたと立て続けにスクープをしたことが自公を過半数割れに追い込む結果につながったのは周知の事実であり、他党議員からも「赤旗のお陰だ」と言っていただき、多くの国民の皆さんから「赤旗、よくやった」と評価していただきました。引き続き権力を監視するジャーナリズムの基本に立った報道を行っていくものです。
今回の選挙結果によって、今まで自民党によって阻まれていた企業・団体献金の禁止や選択的夫婦別姓の導入、紙の保険証廃止の中止などの国民の要望が、前に動く方向性が出てきたことに大いに期待をするものです。そこで伺います。
○ 市長はこの選挙結果についてどのように考えていますか。
103万円の壁の問題がクローズアップされ、様々なところで議論がおこなわれており、日本共産党も物価上昇に見合った課税最低限の引き上げには賛成しています。ところが、103万円の壁を引き上げると国は7兆~8兆円の減収に、地方は4兆円の減収になるとの試算が発表されたことから、全国知事会の会長をはじめ、指定都市市長会や全国町村会会長も大幅な減収が見込まれると懸念を表明しています。
そこで伺います。
○ 103万円の壁の引き上げについてどのようにお考えですか。また、仮に178万円に引き上げた場合の千葉市の税収減額と、市民サービスへの影響はあるのかどうか伺います。
(2) 平和の問題について
日本被団協がノーベル平和賞を受賞しました。被爆者の方が自身の被爆体験や核兵器の非人道性を訴え、核兵器全面禁止の国際的な大きなうねりを生み出してきたことが評価をされたものであり、核の脅威が強まる下での受賞はとりわけ大きな意味があります。
被爆者の方がたの核兵器廃絶の運動が大きな力になり、2017年7月国連で核兵器禁止条約が採択され、2021年1月に条約が発効しました。しかし、唯一の被爆国である日本は核兵器禁止条約に未だに署名・批准していません。今回の受賞は核兵器はいかなる理由でも2度と使用してはならない、核戦争は絶対に起こしてはならない、核兵器は廃絶しなければならないというのが国際社会の明確なメッセージです。唯一の被爆国である日本が核兵器の惨禍を訴える先頭に立ち、核廃絶を進めていくべきです。
そこで2点伺います。
1点目、日本被団協のノーベル平和賞受賞について市長はどのようにお考えですか。
2点目、「平和都市宣言」をした千葉市の市長として、また平和首長会議の一員として核兵器禁止条約に参加するよう国に求めるべきではありませんか。
来年5月に幕張メッセで開催されるDSEI JAPAN2025は世界中の兵器企業が集まり、自社の製品を展示して売り込む武器見本市となります。ウクライナやガザで行われている戦争にも武器見本市に出品された兵器が使用される恐れがあり、憲法9条を持つ日本で、また平和都市宣言をしている千葉市で武器売買が行われることは許されません。
幕張メッセを武器見本市に貸し出さないように市に求めても指定管理者である株式会社幕張メッセが判断するものであるとして責任転嫁をしています。
そこで伺います。
○ 市長は武器見本市に賛成ですか。反対ですか、見解を伺います。
(3) ジェンダー平等について
国連女性差別撤廃委員会は日本の女性差別撤廃条約の実施状況を審議し選択的夫婦別姓の導入について4回目の勧告を行いました。
勧告では選択的夫婦別姓について2年以内に実施をと強く求めています。国民の大多数が賛成し、経団連も早く実施を求める提言を行うなど選択的夫婦別姓制度導入をすべきとの声は高まっています。その声に耳を傾けず、家族の在り方が変わるなどと言って拒み続けているのが自民党です。そこで伺います。
○ 選択的夫婦別姓制度の導入を急ぐよう実施を迫るべきではありませんか。
(4) 市長1期目の総括について
神谷市長は2021年3月に市長に就任してから3年9ヶ月、前市長の市政を引き継ぎ新庁舎、幕張豊砂駅、千葉公園体育館などの大型公共事業を推進し、稲毛海浜公園のリニューアル、千葉公園再整備など公共の都市公園を儲けの場とする事業を展開し、ウオーカブルなまちづくりを進めるとして中央公園・通町公園連結事業や千葉駅前再開発事業などにも取り組むとともに、企業立地に20億円の予算を充てるなど必要のない開発に多額の税金をつぎ込んできました。
一方、高齢者や低所得者の生活を圧迫する国保料や介護保険料の引き上げを行い、福祉カットを行うとともに、子育て世帯の切実な要望である学校給食無償化については国がやるべきものとして住民の願いに背を向けてきました。そこで伺います。
○ 市長の4年間の市政運営についてどのように総括しているのかお聞かせください。
(5) 新年度予算編成について
物価高騰が続く中、家計が厳しい状況が続いており、市民生活を支える継続的な物価高騰対策とともに、子育て支援策の充実や若者支援対策、高齢者が元気に活動できるまちづくりへの予算拡充が求められています。
日本共産党千葉市議会市議員団が毎年行っている市民要望アンケートに、今年は約1550通の回答があり、生活に関する切実で多様な要望が寄せられました。これらを基に作成した2025年度の予算要望書を9月19日に提出し、これまで寄せられた市民の声を紹介しながら、デマンドタクシーの運行、第2子までの保育料無料化、新病院への交通アクセス確保、介護保険料の軽減、市独自の物価高騰対策などの要望を伝え、改善や充実、実施を求めたところです。そこで2点伺います。
1点目、R7年度の重点施策として指示した施策についてお示しください。
2点目、日本共産党千葉市議会議員団が提出した予算要望の受け止めと反映状況についてお答えください。
次に予算編成の基本的な考え方について伺います。
初めに今緊急に求められている物価高騰対策について2点伺います。
1つに、物価高騰が続くなかで価格転嫁も進まず苦境にある中小事業者への新たな給付金に取組むべきではありませんか。また、これまでの支給要件光熱費3万円も引下げるよう求めますが、いかがですか。
2つに、食材費の値上がりが継続しているため、学校や保育所の給食食材費の支援を継続するよう求めますが、いかがですか。
2点目は保育料支援です。保育標準時間の3歳未満児の保育料の最高額は70,900円であり、2人目は半額になるものの合わせると106,350円と大変高額になります。子育て家庭の負担軽減を図ることは少子化対策にも有効だと考えます。幼児教育無償化の対象になっていない3歳未満児の保育料の負担軽減を図るため、千葉市も他市に学び、保育料の第2子無償化を実施すべきではありませんか。
3点目は学校給食無償化です。給食費無償化は義務教育は無償とするとした憲法26条に則れば国が財政措置をして実施することが求められますが、具体的方策を検討するとした「こども未来戦略」で方針が示されてからなんら具体化はされていません。国が無償化に踏み出すのはいつなのか全く先が見えない中、国がやるまで待てというのはあまりにも子育て家庭に冷たい行政と言わざるを得ません。千葉市なら安心して子育てができますと胸を張れる施策を行うべきです。そこで伺います。
○ 学校給食の無償化は優先順位を上げて急ぐべきではありませんか。
4点目は教育関連予算の拡充です。教員不足の解消やいじめや不登校対策、少人数学級の早期実現などを行うためには人員増が必要です。
人員を増員してゆとりある教育を実践するため大幅な教育予算の拡充を求めるがどうか。
5点目は高齢者支援です。高齢者の買い物、文化活動、友人との交流、通院等の外出を支援することは、高齢者を元気にし、認知症予防にもなって高齢者医療費を削減するとともに経済的効果にもつながると考えます。
高齢者の外出のための施策に積極的に取り組むべきではありませんか。
6点目は若者支援です。学費が高く、深夜までアルバイトをせざるを得ない学生の実態は深刻です。市として返済不要の奨学金創設や奨学金の返済の補助等で学費支援に取りくみ、学生への支援を行うことを求めるがどうか。
2、総合政策行政について
(1) 災害関連死を防ぐ取り組みについて
能登地震では災害関連死が235人になる見込みであるとして直接死の227人を上回ると石川県が発表しました。慣れない避難所での生活や避難が長期化することで災害関連死に至らないような配慮が求められると思いますが、本市では災害関連死を防ぐためにどのような対応を行っていくのですか。
(2) 災害時の電気自動車の活用について
災害時に停電になった際、避難所では太陽光発電施設によって電気の供給が可能になりますが、公用車の電気自動車を活用した電気の供給も可能です。
○ 公用車の電気自動車の数と配置状況及び災害時の活用計画についてお示しください。
(3) 不公平な県単独事業補助金の扱いについいて
日本共産党千葉市議会議員団は、千葉県との協議の中で、不公平な扱いの県単独事業補助金の是正を求め、公平な支出を実現することを求めていますが、進展はあったのか伺います。
3、市民行政について
闇バイトによる強盗事件が相次ぎ、県内でも事案が発生していることから市民から不安の声が寄せられています。市民の防犯意識を高めるとともに市民の命と財産を守っていく対応が求められます。そこで伺います。
○ 防犯意識の向上のための取り組みと安全対策についてお示しください。
高額なお金がすぐ手に入るからと安易に申し込んだ後に闇バイトだとわかり、個人情報を提供してしまったために脅されて断ることができずに犯罪に加担してしまうケースが多いと聞いています。犯罪に巻き込まれないために中高生はもちろん若者に対するSNSに対する注意喚起とともに相談できる窓口の設置が必要ではないでしょうか。
○ 若者を闇バイトから守っていく対策及び相談窓口設置についてお示しください。
4、保健福祉行政について
(1) マイナ保険証について
多くの国民や医療機関の反対を押し切り、12月2日から保険証の新規発行が廃止されました。紙の保険証が使えなくなると勘違いしている方が大勢います。また、マイナ保険証によるトラブルが多数報告されていることへの不信感や常時持ち歩くことへの不安感、高齢者施設でのマイナ保険証が適切に管理できないことなどからマイナ保険証を解除して資格確認書に切り替えたい方が出てきています。
そこで3点伺います。
1つに、新規保険証発行廃止後の利用について周知状況はいかがか。周知は十分だったのか。
2つに、マイナ保険証利用についての不安の声に対してどのような認識をもっているのか。
3つに、マイナ保険証の解除手続きの流れについてお示しください。
(2) 介護について
4月の介護報酬引き下げで廃止や休止に追い込まれている訪問介護事業所が増加しています。第3回定例会でのじま議員の質問に対して今年度経営悪化を理由とする廃止は9月1日現在4件あったと回答されています。今後、さらに数が増えていくことが予想されます。
地域で高齢者を支え、手のかかるサービスを提供できるのは中小の訪問介護事業所です。報酬減で経営が成り立たなくなってしまうことがないように自治体が支援をしていくことが求められます。そこで2点伺います。
1つに、訪問介護事業所の厳しい経営実態についてどこまで認識しているのか。
2つに、訪問介護事業所が事業継続できるよう支援金を支給すべきではありませんか。
介護を担う職員が不足し、介護の職場は疲弊しています。介護人材不足の主な要因は全産業平均給与より月約7万円低い賃金にあります。今後さらに介護需要が増えることが見込まれている中で、介護人材の確保は最重要課題と位置付けるべきではないでしょうか。そこで伺います。
○ 介護職員の確保のため処遇改善にかかる手当の支援を行うべきではありませんか。
○ 教員は奨学金返還サポートが、保育士は修学資金貸付があり、千葉市に就職すれば奨学金の返済が免除されます。介護福祉士についても人材確保のために奨学金返済制度などを導入すべきと考えますが、見解を伺います。
(3) 特別養護老人ホームについて
全国的に特別養護老人ホームの待機者数は減少傾向にあるとはいえ、解消に向けた対策は今後も講じていく必要があるものと考えます。第9期介護保険事業計画の策定にあたり千葉市が行った推計では、令和8年4月時点で、総ベッド数は4,857床になるとのことですが、待機者数は、令和5年10月時点で1,374人、それが令和6年に1,360人程度、令和7年に1,340人程度と待機者数がなかなか減少していかないのが現状です。これからますます高齢化が進むことが予想されます。そこで2点伺います。
1つに、整備予定の事業者が2回続けて辞退していることの受け止めについて。
2つに、安心安全の老後を過ごすためにも、家族の介護疲れでの事故を防ぐためにも、一刻も早く特別養護老人ホームの整備を進めることを求めるがどうか。
(4) 補聴器の購入助成について
全国保険医団体連合会・地域医療対策部会の調査によると2024年9月1日現在18歳以上を対象とした補聴器購入助成を行っている自治体は361あり、今年度から新たに100以上の自治体が補聴器購入助成を開始しています。県内でも市川市など新たに導入している自治体も出てきています。これは補聴器の使用が高齢者の生活の向上に大きな役割を果たすということが認知されてきたからではないでしょうか。
そこで伺います。
○ 加齢性難聴を対象にした補聴器購入助成制度の創設を求めますが見解を伺います。
(5) 国保について
国民健康保険は自営業やフリーランス、年金生活者、非正規の方など経済的に厳しい方が加入しているにもかかわらず、国保の保険料は同じ年収の会社員と比較して2倍も高いのが実態です。他の健康保険と比較して保険料が高すぎ、すでに所得の1割を超えていることから払いたくても払えない状況があります。国保加入者の高齢化・貧困化が進む一方、自公政権が国庫負担の削減・抑制を続けてきたためです。国保料を値上げすれば、物価高騰で厳しい暮らしに追い打ちをかけることになります。千葉市国保を考える会から国民健康保険料の引き下げを求める請願が提出されていますが、国保料の引き下げは国保加入者の切実な願いです。そこで3点伺います。
1つに、国保料は一般会計から繰り入れをして保険料を引き下げるべきではありませんか。
2つに、国保料引き下げのために国に公費の大幅な増額を強く要望すべきではありませんか。
3つに、市独自で18歳までの均等割りを廃止することを求めますが見解をお聞かせください。
5、こども未来行政について
(1) 公立保育所の主食提供について
日本共産党千葉市議会議員団が長年要望してきた公立保育所の主食提供が10月1日から始まりました。今年度は10月開始が21か所、来年1月開始が6か所の27か所で実施することが決まっています。
先日、主食提供が始まった保育所を視察し、新たに雇用した会計年度任用職員の仕事内容や子どもが「あったかい」と喜んで残さずに食べる姿がみられること、茶碗の正しい持ち方の指導を実践していること、お弁当箱の出し入れがなくなったことで子どもも職員も負担が減っていることなどを所属長から話を聞き、主食提供実施のメリットを確認することができました。未実施になっている保育所についても早急に実施することが求められます。そこで2点伺います。
1つに、主食提供を実施した保育所からのこどもや保護者、職員の反応について。
2つに、未実施の保育所について一刻も早く実施するよう求めますが、見解を伺います。
(2) 子どもルームについて
子どもルームを毎年10校ずつアフタースクールに移行する方針が出されたことから、子どもルームの指導員は子どもルームに残って働くか見切りをつけて早めに転職をするかを悩みながら不安な雇用環境の中で仕事をしています。そこで伺います。
これまで千葉市の子どもルームを支えてきた指導員の待遇を保障すべきではありませんか。
家庭科室や図書室などの特別教室を高学年ルームとして使用している実態があります。特別教室は勉強をする場であり、子どもが安心してくつろげる場所としては適さないことから特別教室を保育室代わりに使うことをやめ、専用室の確保を求めますが見解を伺います。
6、環境行政について
(1) プラスチックごみ分別収集・再資源化について
市内2か所でプラスチックごみ分別収集モデル事業が12月まで実施されており、その後アンケートを実施して千葉市のプラごみ分別のルールを作成するとしていますが、地球温暖化対策はまったなしであり、自治体として温室効果ガス排出抑制に早急に取り組む必要があります。そこで伺います。
○ モデル事業実施後の全市展開はどのように進めていこうとしているのかお示しください。
市民にプラごみの分別によって焼却しない方法でごみを削減して地球温暖化をくいとめていく必要があるということを理解してもらうこと、分別によってどんな効果があるのかを見える化することが分別を進めていくときに大事な点だと考えます。
そこで伺います。
○ 出前講座やワークショップなどを自治会単位などで多数開催して意見交換する場を作り、市民の意識醸成を図っていくべきではありませんか。
(2) CO₂排出削減について
世界気象機関は2024年が史上最も暑い年になる見込みだと発表しました。猛暑の日が続き、世界各地で気候変動に関連する自然災害が続発するなど気候変動の影響は深刻です。千葉市は脱炭素先行地域に選定され、CO₂削減の取り組みを強化していると聞いています。そこで2点伺います。
1つに、千葉市地球温暖化対策実行計画の進捗状況及び今後の見通しについて
2つに、排出量が多い産業への指導を徹底すべきと考えるが、取り組み状況についてお聞かせください。
7、経済農政行政について
〇農業施策について
農業の担い手の高齢化、飼料価格の高騰、有害鳥獣への対応など、農業を取り巻く課題は山積しています。先般、千葉市としても農政センターにおいてオール電化ハウスによる実証実験などの取組も進むなかではありますが、一層の農業振興策が求められています。そこで3点伺います。
1つに、千葉市農家ではイチゴ農家やトマト農家が増加しているなかで、新規就農や後継農家がハウス等の設備投資が困難なケースも多いと聞いています。中古ハウス活用や機器のレンタル、設備投資への負担を軽減して、意欲ある農家をより積極的に支援すべきではありませんか。
2つに、農家や酪農家から肥料価格高騰や飼料価格高騰に苦しむ声が引き続き届いているため、離農をくい止めるためにも、肥料や飼料価格高騰対策に緊急に取組むべきと考えますが、見解を伺います。
3つに、若葉区や緑区を中心にイノシシやアライグマなどの被害が増加しており、有害鳥獣対策の強化を求められています。重点地区を広げることや農家への電気柵や罠の拡充など、一層の対策強化が必要と考えますが、今後の対応について伺います。
8、都市行政について
(1) 公共交通の維持について
運転手不足によるバス路線の廃止やバスの減便が増加しており、通勤通学や買い物、病院への通院など市民生活に支障をきたしています。市はこれまで公共交通維持のために燃料代支援やバス運転手養成支援、バス路線維持のための支援などを行ってきたにもかかわらず、更なるバスの減便が続いているのが実態です。そこで2点伺います。
1つに、公共交通維持のための施策についてどのような評価をしていますか。
2つに、運転手確保のために思い切った財政支援をするべきではありませんか。
バス路線維持のためには運転手の確保と合わせて利用者を増やしていくことがバス事業者の経営安定につながります。新しい千葉・みんなの会から出ている請願や我が会派がたびたびとりあげてきた堺市のおでかけ応援カードは、高齢者の外出を支援し、公共交通の利用を促進することを目的に65歳以上の高齢者が100円でバスや電車を利用することができる制度であり、おでかけ応援カード導入により、市内消費が増えるとともに高齢者が外出することで健康になって医療費の抑制にもつながり、経済効果が大きいと報告されています。そこで伺います。
○ 高齢者の外出を支援するための外出応援パスの導入を求めますが、見解をお聞かせください。
(2) 公園について
稲毛海浜公園リニューアルや千葉公園再整備では民間活力を活かした儲け優先のP―PFIでの多額な予算を使った整備が進められている一方で、老朽化して利用されなくなった公園の統廃合を進めようとしており、住民のニーズに応じた公園設置になっているかは疑問があるところです。中央区や花見川区で共産党が行った公園ウオッチングでは、整備不足の公園が多数確認されており、改善が必要です。そこで伺います。
○ 地域に密着した身近で利用しやすい公園整備を進めるべきではありませんか。
(3) 中央公園プロムナードについて
中央公園プロムナードの未来を考えるシンポジウムに参加し、講演やパネリストの話を聞かせていただきました。中央公園プロムナードと聞いてもいったいどこかなのかわからないけれど、千葉駅前大通りと言えばぴんとくる人が多いという現状にあって、今現在人通りがまばらな中央公園プロムナードを人が集い対話が生まれる通りに作り替えていくために、中プロ・デザインラボを発足させるというお話でした。街のにぎわいを作り出すと言いますが、時間もお金もかかることであり、限られたエリアに税金を投入していくことが市民の要望なのか、この施策が市民の豊かさにつながるのか違和感を覚えたところです。そこで3点伺います。
1つに、まちづくりを進めるには住民のニーズをきちんと確認すべきではないですか。
2つに、仮称「中プロ・デザインラボ」の構成についてお示しください。
3つに、中プロ・デザインラボの活動の目的についてお示しください。
9、建設行政について
(1) 新湾岸道路についてです
昨年度から国への新湾岸道路整備に向けた要望活動が実施され、今年8月2日に「新湾岸道路有識者委員会」が設立され、コミュニケーション活動を通じて沿線住民や企業・団体などの利害関係者の意見を聴取し、道路の構想段階へと今後進んでいくことになります。9月6日には、有識者委員会の開催を受けて「新湾岸道路ポータルサイト」が立ち上げられ、11月15日に国土交通省関東地方整備局・千葉国道事務所名で、「新湾岸道路について地域のみなさまへの情報発信と意見聴取を実施します」ということで、対話方式による説明会とアンケート調査を行うことが明らかにされました。
有識者委員会の資料の「湾岸地域の土地利用状況」の千葉市美浜区の項目で「住宅団地等が広がり」と沿線に住宅が近接しているとされています。そこで2点伺います。
1つに、高規格道路・高速道路にトラック等の車両が流入するなどして、排気ガスによる住環境や市民の健康を壊して良いと考えているのか。
2つに、事業費も自治体の負担割合も明らかになっていない中で、千葉市財政にも影響を与える新湾岸道路はやめるべきではないですか。
(2) 道路の維持管理について
近年、気候危機の影響で猛暑が続くなか、道路脇などの木や草が伸びすぎて危険という相談が急増しています。本市においては、基本的には道路の草刈りについては年に1回分の予算しか確保しておらず、市民要望に十分に応えられていないことは問題と考えます。そこで2点伺います。
1つに、市民の安心安全を守るためにも、年1回の道路の草刈り予算を2回に増やすよう求めますが、見解を伺います。
2つに、千葉県管理から千葉市に移管された旧千葉外房有料道路の生実本納線は千葉県管理の際は2回の除草対応を行っていたものの、千葉市に移管されたのちは1回となっているため、千葉県管理と同じように予算確保して対応を図るよう求めますが、いかがですか。
10、教育行政について
(1) 教職員職場の現状について
教員不足が全国的に問題になっており、千葉市も例外ではありません。本市では担任が産休育休病休などで不在となった場合に代替職員の補充ができず、教務主任や教頭等が担任を掛け持ちするという実態があるため、教員の未配置の解消が求められています。
R7年度の千葉県・千葉市の公立学校教員採用候補者選考志願者は昨年から389人減少し、志願倍率は2.9から2.4に下がり教員の不人気が見て取れます。働き方改革が進んでいるとは言え、依然として長時間労働の職場であるにもかかわらず、給特法により残業代制度の例外とされ時間外勤務手当はつきません。授業準備以外の諸々の業務に追われ、保護者対応にも気を配らなければならないなど職場環境はますます厳しくなっているのではないでしょうか。そこで5点伺います。
1つに、教員の未配置の状況について3年間の推移及びメンタルが理由で未配置になっている人数についてお示しください。
2つに、教員未配置が起きてしまう要因について、また、教員未配置を解消するための取り組みについてお示しください。
3つに、教員採用候補者選考の志願者が少ないことについてどのように考えていますか。
4つに、志願者を増やすための取り組みについてお聞かせください。
5つに、教員の多すぎる業務を分担し、授業準備や子どもと丁寧に関わる時間を保障することができるようにスクールサポートスタッフの増員や教頭のサポートのための人員増を求めますが、見解を伺います。
(2) 学校体育館エアコン設置について
気候変動により年々気温が上昇しており、エアコンなしの生活は熱中症をもたらし、命の危険にもつながりかねない状況になっています。夏場の体育館は大変暑く、扇風機やスポットクーラーでは対応しきれずとても運動する環境にありません。防災の観点からも避難所となる体育館にはエアコンが必要であり、一刻も早く全部の学校への設置が求められます。
○ 学校体育館のエアコン設置についての考え方と今後の見通しについてお示しください。
毎年30校ずつの設置では全校設置までに5~6年かかってしまいます。小学1年生が卒業するまでエアコンのない体育館で過ごさなければならないのはあまりにも過酷であり、人権侵害にもなるのではないでしょうか。
○ 来年度までの国の補助金の補助率引き上げを利用して一気に設置することを求めますが、見解を伺います。
11、選挙管理行政について
(1) 選挙について
投票所が遠いために、歩いて行けず投票をあきらめたという方が少なくありません。移動が困難なために選挙の権利が侵害されることのないように対策が必要ではないでしょうか。
・期間限定のタクシー券を配布して投票所までの移動を保障することを提案しますが、見解を伺います。
衆議院総選挙の小選挙区での投票率は53.85%と2021年の55.93%を下回っており、投票率の低下が続いている中で投票率アップの取り組みに力を注いでいくべきと考えます。そこで3点伺います。
1つに、今後、市長選、知事選、参院選と選挙が続きますが、投票率向上のための計画はありますか。
2つに、共通投票所の設置を求めますが、見解を伺います。
3つに、教育委員会や大学と連携し主権者教育を充実させていくべきではありませんか。
<代表質問2回目>
1、暮らしを応援する政治に
私ども日本共産党千葉市議会議員団は、暮らし最優先の政治を求めて質問してきました。今は、物価高騰で、暮らしが本当に大変です。だからこそ、石破首相や官僚まで自分たちの手当を自粛する立場まで取っているのです。
ところが、市では、今議会でも物価高騰対策は何ら講じられておりません。その上、住民の暮らしを応援しなければならない県が水道料金を20%も値上げすると発表したではありませんか。突然の大幅値上げの提案には驚くばかりです。
・市長は物価高騰の時に水道料金の値上げをすると発表した熊谷知事に抗議の声をあげるべきだと思うが、水道料金の値上げについての見解を伺います。
物価高騰で経済的に苦境にあえいでいる方々に、政府の経済対策に盛り込まれた「重点支援地方交付金」を活用して暮らしを支える支援を行うことが必要です。「重点支援地方交付金」の活用について2点伺います。
・1点目、低所得世帯支援として住民税非課税世帯1世帯あたり3万円、住民税非課税世帯の子ども一人当たり2万円追加給付が示され、自治体の上乗せも可能とされていることから非課税世帯にとどまらず、対象を広げて急いで支援を届けていくべきではありませんか。
・2点目、令和5、6年度に実施した中小企業事業者への支援金のような支援を、対象も広げて実施を急ぐべきではありませんか。
・手取りを少しでも増やしてほしいとの願いに応えるためにも、中小事業者が最低賃金を引き上げるための支援に取組むことや国民健康保険料や公共料金の引下げに取組むべきではありませんか。
2、学校給食無償化について
・石破首相は地方創生臨時交付金を2倍にして地方の施策を推進する支援を行うと表明しています。市長は子育て支援を公約に掲げてきましたが、市民の切実な要求である学校給食無償化の実施は国が行うべきものと自治体独自の支援に取り組もうとしないのは公約に背くものと言わざるをえません。
・市独自に財政措置ができないというなら、地方創生臨時交付金を使って1年間学校給食費を無償にすることを提案しますが、見解を伺います。
3、不要不急の開発をやめて市民の暮らし優先の施策展開を
千葉神社の参道整備に30億円、稲毛海浜公園のリニューアルに24億円、千葉公園整備は16億円を超え、企業立地に20億円、今後は新湾岸道路整備にも莫大な税金が投入されようとしていますし、中央公園プロムナードの整備についても同様のことが考えられます。
急ぐ必要のない開発などに税金を投入するのではなく、市民が日々の暮らしを豊かに過ごすことができるようなお金の使い方が重要です。住み慣れた地域で住み続けられるように公共交通の維持や、身近な公園の整備や市民の暮らしを支える施策などに使うべきです。お答えください。
4、高齢者が生き生きと暮らせるために
〇介護への支援について
今後、介護需要は増大する見込みであり、人材確保が最重要課題であるにも関わらず、国の責任で対応すべきとして市独自の対応は全くやる気がありません。
世田谷区では、介護サービス事業所などに、人材確保や経営に必要な経費の緊急安定経営事業者給付金を1事業所当たり年間88万円が支給されています。
また、流山市では介護人材確保のため、市内の介護サービス事業所に勤務する介護職員等に、月額9000円の賃金補助を行っています。
千葉市は保育士不足に対応するため、来年度から千葉市手当3万円を4万円に引き上げるのに介護職員の手当はゼロです。この違いはあまりにも大きすぎます。
国任せの姿勢に終始することなく、市独自に職員の処遇改善を直ちに取り組むべきです。お答えください。
〇補聴器購入助成について
市のホームページで補聴器の項目は、早期に補聴器を使用することが人とのコミュニケーションが活性化し、生活の質が向上することや耳鼻科受診の勧め、補聴器購入の際の注意点、医療費控除の取り扱い、ヒアリングループについてなど今まで我が会派が周知を求めてきたことが分かりやすく掲載されており、多くの方に知ってもらいたいと思います。ですが、補聴器の購入助成には消極的です。
新潟県ではすべての自治体で補聴器購入助成を行い、新潟市では認知症予防のための補聴器購入助成として50歳から74歳の中等度難聴者に補聴器の購入費を助成しています。
・現在千葉市では推定認知症の方は約2万6千人に上り、2040年には約4万人にまで増加していると推計しているのですから、早急に補聴器購入の補助を行うべきです。お答えください。
〇高齢者の外出支援及び公共交通の維持について
・高齢者の外出が促進された場合の介護利用者や認知症者が減るなどのクロスセクター効果を具体的に検証すべきではありませんか。また、まずはバス無料デーや割引デーを設けて効果検証を図るよう求めますが、見解を伺います。
・バス路線の減便、廃止が続くなかでバス路線維持への一層の財政支援強化が必要であり、バス路線維持補助は7500万円で1社あたりわずか750万円では路線維持への実効性が乏しいため、路線維持補助を大幅に増額するよう求めますが見解を伺います。
・デマンドタクシー運行の社会実験では、運賃を下げてほしいという声もあるため300円で運行できるよう、また、地域を拡充していけるよう予算編成に取組むよう求めますがいかがですか。
5、教員の増員について
新年度予算編成で先ほど教員の人員増を求めたところ、正規教員は国に要望するのみで市独自で教員の確保をしようとしていません。
教育現場では「教育は人だ」とその確保が切望されています。
教員不足の要因は、様々指摘されており、現状を危惧する現場の意見も寄せられています。そこで2点伺います。
1つに、年度初めの段階で教員を大幅に増員して正規職員を配置することを求めるがどうか。
2つに、教員の労働荷重の抜本的な軽減と子どもが通える環境を保障する為にステップルームティチャーの大幅な増員など様々な職種を増やすよう対策強化を図るよう求めるがどうか。
以上で2回目の質問を終わります。
★あぐい初美議員の代表質問に対する答弁
【神谷市長答弁】
ただいま、日本共産党千葉市議会議員団を代表されまして、安喰初美議員より市政各般にわたるご質問をいただきましたので、順次お答えいたします。
1、国政との関連について
まず、衆議院議員選挙の結果に対する見解についてですが、国政に関する様々な論点や課題についての各候補者の主張に対し、有権者の意志が示されたものと認識しております。
次に、「103万円の壁」の引き上げについてですが、いわゆる「年収の壁」が、就労調整、人手不足の要因の一つにもなっているとの指摘がなされているほか、基礎控除等の水準については、賃金上昇や物価上昇があっても、過去30年間、ほぼ変わらない水準で、これまで推移してきたところであります。その103万円という水準が妥当なのかどうかという議論自体は必要であると考えております。併せて、引き上げに伴う地方財政への影響に強い危機感を持っております。
次に、178万円に引き上げた場合の本市の税収減額と市民サービスへの影響があるのかどうかについてですが、仮に、178万に引き上げた場合、本市においては約253億円程度の非常に大きな個人住民税の減収が見込まれます。そのため、市民サービスへ影響を及ぼすことのないよう、国に対して、代替となる財源の確保を、指定都市市長会を通して強く求めております。
2、平和の問題について
まず、日本原水爆被害者団体協議会のノーベル平和賞受賞についてですが、日本被団協は、長年にわたり、核兵器の非人道性とその廃絶を、証言活動を通じて訴え続けてこられ、核兵器のない世界に向けた国際社会の取り組みに寄与された団体であると高く評価されたものと認識しております。
次に、核兵器禁止条約に参加するよう政府に求めることについてですが、本市が平成21年から加盟し、すべての政令指定都市を含む国内1,740都市が加盟する平和首長会議において、日本政府に対し、核兵器禁止条約の早期署名・批准を求めており、引き続き同会議を通じて参加等を求めて参ります。
次に、幕張メッセで開催される展示会に対する見解についてですが、民間事業者が実施する展示会の開催そのものや、当該施設の指定管理者が県条例等に基づき施設利用の可否を判断したものについて、その内容を個別に評価し、施設利用の是非を申し上げることは適当ではないと考えており、また、法令等に反しない限り、民間や団体の活動を最大限に考慮すべきものと認識しております。なお、市民共通の願いである世界の恒久平和の実現に向けては、市民の皆様に本市の平和都市宣言の理解を深めていただくとともに戦争の悲惨さや平和の尊さを伝えて行くことが重要と考えております。
3、市長1期目の総括について
4年間の市政運営の総括についてですが、令和3年3月の市長就任にあたり、市政運営の基本的な方向性として「市民生活を守る」、「雇用を創り出し経済を動かす」の2つを掲げ、これまで、中心市街地の活性化や、公園・スポーツ施設の整備など、都市の魅力・活力の向上に資する施策とともに、企業立地の促進や創業支援の強化などにより雇用を創出しながら、子育て、教育、高齢者・障害福祉など、だれ一人取り残さないインクルーシブなまちづくりにつながる、市民生活向上のための施策の充実に取り組んで参りました。その結果、子ども医療費助成の拡充、様々な事情により十分な教育を受けられなかった方などの学び直しを支援する、公立夜間中学校の開校、制度のはざまにある方々に対し、分野横断的に、相談に応じる「福祉まるごとサポートセンター」の開設、未就学児の発達に関する相談を受ける「こども発達相談室」の開設など、子育て環境の整備や健康・福祉増進のための施策の充実を図ることができ、議会をはじめ市民の皆さまのご理解・ご協力のもと、一定の成果を上げることができたものと考えております。
4、新年度予算編成について
まず、重点施策として指示した施策についてですが、新年度の財政見通しは、歳入については、市税収入が堅調であるものの、税制改正による影響が懸念されるとともに、財産収入等の臨時的収入も多くは見込めない状況にあるほか、財政調整基金の活用額に限りがある中、歳出については、社会保障経費の増加や金利上昇に伴う公債費の負担増に加え、物価高騰の影響などによる各種行政コストの増加が見込まれており、厳しい収支状況になるものと認識しております。この認識のもと、引き続き、歳入確保の徹底や、必要に応じて既存の事務事業の見直しを行なうほか、財政の健全性に配慮しながら、最終年度を迎える第1次実施計画事業について、「こども・教育」や「健康・福祉」、「安全・安心」、「地域経済」などの幅広い分野に対して、限られた財源の効率的な配分に努めることにより、市民生活・市民福祉の向上と、本市の持続的発展に取り組むこととしております。
最後に、予算要望の受け止めと反映状況についてですが、これまで、長期化する物価高騰下において、市民生活・市民福祉の向上と、本市の持続的発展につながる取り組みの両面から、施策の着実な進捗に取り組んでいるところでありますが、引き続き、国の予算編成や総合経済対策の動向を注視しながら、的確な対応に努める必要があると認識しております。新年度予算の財政見通しは、先ほど申し上げましたとおり、厳しい状況ではありますが、この度の要望における、物価高騰対策や市民本位の市政の進捗など、提言された内容につきまして、市民サービスのより一層の向上が図られるよう、予算編成の中で検討して参ります。
【大木副市長答弁】
市長答弁以外の所管についてお答えいたします。
ジェンダー平等について
選択的夫婦別氏制度の導入についてですが、10月30日の内閣官房長官の記者会見では、「関係省庁で国連女子差別撤廃委員会の最終見解の内容を十分検討したうえで、国民各層の意見や国会における議論の動向などを踏まえ、適切に対応して参りたい」としており、国において十分に審議されるべきものと考えております。
新年度予算編成について
まず、学校や保育所の給食食材費支援の継続についてですが、給食食材費の支援は、物価高騰が継続する中、従前どおりの栄養バランスや量を保った給食を提供できるよう、令和4年度及び昨年度は国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、また、今年度は市単独事業により、食材費高騰分を支援している者でございます。来年度における支援継続については、国の動向や物価上昇率の推移等を見ながら、新年度予算編成に中で検討して参ります。
次に、保育料の第2子無償化の実施についてですが、年齢制限等の撤廃により、居住地や世帯構成の違いによる格差を解消するとともに、多子世帯の経済的負担軽減につながるものと認識しております。本来であれば、国の責任において一律の基準を設けたうえで実施すべきものと考えていることから、これまでも機会を捉えて国に要望を行っているところではありますが、本市独自での実施に関しては、相応の財源を必要とすることから、他の事業への影響を勘案しつつ、今後、検討を進めて参ります。
次に、高齢者の外出のための施策についてですが、高齢者にとって外出することは、通院、買い物など日々の暮らしに欠かせないものであるとともに、適度な運動による心身の健康維持、様々な活動への参加による生きがいづくり、人とのコミュニケーションによる孤立化防止など、多くの面で効果があると認識しております。
これまで心身の障害により外出が困難な高齢者には、介護保険や障害福祉サービスなどのほか、福祉有償運送や階段昇降、社会福祉法人の買い物バス等による支援を実施するとともに、外出を促す取組みとして生涯現役応援センターによる就労支援や、いきいきプラザにおける体操やeスポーツ、そして生きがいにもつながる趣味の講座なども実施しております。今年度は特により多くの方に参加いただけるよう町内自治会館やマンションの集会室などにプラザ職員を派遣して実施する出張講座を増やしております。「家の近くの開催だったので参加できた」などの声も届いており、引き続き、地域に出向いた講座の開催などを通じて外出を促す取組を進めて参ります
次に、奨学金の返還補助や返還不要の奨学金創設等による学生への支援についてですが、本市に採用された教員のうち、日本学生支援機構から第一種奨学金の貸与を受けた方の奨学金を全額補助する「教員奨学金返還サポート」を実施するほか、市内ものづくり企業への就労促進を図るため、千葉職業能力開発短期大学校等の対象校に在学中に貸与型奨学金を利用し、卒業後に市内企業に就職した方を対象に奨学金の返還を支援する「奨学金返還サポート制度」を設けるなど、奨学金の返還に関する支援を行っております。また、返還不要の奨学金制度の創設については、令和2年4月より国において「高等教育の就学支援新制度」として大学等の授業料等減免及び給付型奨学金が実施され、令和5年12月に閣議決定された「子ども未来戦略」における「こども・子育て支援加速化プラン」の中では、当該制度のさらなる充実が示されているため、引き続き、国の動向を注視して参ります。
総合政策行政について
次に、災害関連死を防ぐ取組についてお答えします。
災害関連死を防ぐためにどのような対応を行っていくのかについてですが、災害関連死は被災したことによる直接的な要因に加えて、避難後の生活による肉体的、精神的ストレスが大きく影響していると言われております。本市では、被災以後も可能な限り被災前に近い生活環境やストレスの少ない避難生活を確保することが重要と考え、分散避難の取組を進めており、特に在宅避難を可能とするための住宅の耐震化や家具転倒防止策、トイレ・食料などの備蓄を啓発するとともに、指定避難所以外に避難する方も、指定避難所で物資などの支援を受けられることについて周知を図っているところです。また、指定避難所でも、空調設備整っている教室、公民館の和室など、避難者が生活しやすい場を確保することや、マンホールトイレ整備や受水槽への蛇口設置など避難所の生活環境の向上を図っているところです。さらに、必要に応じて医師や看護師、保健師等の派遣調整を行い、避難者の健康状態の把握や医療の提供を行うことなど、良好な生活環境の確保や避難者の健康保持に関する対応を進めるとともに、介護が必要な高齢者や障害者など在宅生活や指定避難所での生活が困難な方が、安心して避難生活を送れるよう拠点的福祉避難所の整備を進めているところです。
次に、災害時の電気自動車の活用についてお答えします。
公用車の電気自動車の数と配置状況及び災害時の活用計画についてですが、本年7月1日時点で、公用車全体987台のうち、災害時に活用可能な電気自動車等30台を本庁舎、区役所、保健福祉センターなどに配備しております。災害時には、被災時等の状況に応じて、公用車のほか、電気自動車等を保有する企業との災害時応援協力により、電気を必要とする施設等へ電力を供給することとしております。
次に、不公平な県単独事業補助金についてお答えします。
不公平な扱いに対する是正要求の進展についてですが、県単独事業補助金については、令和3年7月に、知事と市長との意見交換の場において、市長から知事に県単独事業補助金の改善を要求し、これを受けて、現在、窓口を県市とも一元化しており、今年度新設された補助金においては、全て本市も対象となっております。引き続き、新設の補助金については、他市町村と同様とすることを求めて参ります。また、既存の補助金についても、社会情勢の変化や、市民等への影響などを考慮しながら、県に対して改善を求めて参ります。
市民行政について
次に、闇バイトについてお答えします。
まず、防犯意識の向上のための取組みと安全対策についてですが、第5次千葉市地域防犯計画に基づき、犯罪発生情報の提供や最新の防犯知識の普及、町内自治会等に対する防犯街灯・防犯カメラの設置や防犯パトロール活動などに対する支援をはじめ、幅広く防犯対策に取り組んでいるところであります。また、いわゆる「闇バイト」に関連する強盗事件の発生を受け、ちばし安全・安心メール、ホームページ、市政だよりなど、さまざまな媒体を活用し、注意喚起を行って参ります。
次に、若者を闇バイトから守っていく対策及び相談窓口設置についてですが、若者がいわゆる「闇バイト」に加担することを防止する取組みとして、LINEやX等を活用し、その特徴や恐ろしさなどを周知するとともに、困った際の相談先として「警察相談ダイヤル」や「ヤング・テレホン」を案内しております。今後も、警察や大学等と連携し、若者に対して更なる周知を図って参りたいと考えております。
保健福祉行政について
次に、マイナ保険証についてお答えします。
まず、新規保険証発行廃止後の利用にかかる周知状況についてですが、現行の保険証の新規発行が終了となり、マイナ保険証を基本とする仕組みへの移行については市民等に影響する大きな制度改正であると認識しております。このため、市ホームページや市政だよりへの掲載のほか、SNSでの情報発信、市役所や商業施設などに設置しているデジタルサイネージなど様々な広報媒体を使い、周知に努めているところです。今後も、市民の皆さまに、制度をご理解いただけるよう周知に努めて参ります。
次に、マイナ保険証利用に関する不安の声についてですが、制度の移行にあたり、不安に感じている方がいることは認識しております。本市としては、マイナ保険証を利用することのメリットや、全ての方がこれまでどおり安心して保険診療が受けられるよう、資格確認書の仕組みが設けられていることなどを周知することで、誤解や不安を解消できるよう丁寧に周知を行なって参ります。
次に、マイナ保険証の解除手続きの流れについてですが、マイナ保険証の利用登録の解除を希望される場合は、解除申請書を各区市民総合窓口課に提出もしくは郵便で送付していただくこととしており、本市では、今月2日から受付を開始しております。解除申請を受け、本市では申請者に保険証に代わる資格確認書の交付を行います。
次に、介護についてお答えします。
まず、訪問介護事業所の経営実態についてですが、経営悪化により事業を廃止する事業所が昨年度よりも増えており、特に小規模の事業所においては、今年度の介護報酬改定による影響もあると認識しております。
次に、訪問介護事業所への支援金の支給についてですが、介護事業運営に要する経費は、国が定める介護報酬において適切に評価されるべきものと認識しており、本市独自の支援を行うことは考えておりませんが、引き続き、事業の継続が可能な報酬体系となるよう、国に対して要望して参ります。
次に、介護職員の処遇改善にかかる手当についてですが、一義的には国の責任において対応すべきであり、市独自の手当の支給は考えておりません。本市としては、これまでも国に対し、改善を求めてきたところであり、人材育成の取組みに対する介護報酬の加算など、段階的措置が講じられて来たものの、引き続き、さらなる改善を要望して参ります。
次に、介護福祉士にかかる奨学金返済制度美ついてですが、県が実施の主体となって、指定の介護福祉士養成施設に在学し、介護福祉士の資格を取得後、県内で介護の仕事に従事する医師のある方を対象に、学費や入学準備金などの修学資金について、無利子で貸し付けっを行っております。卒業後1年以内に資格を取得し、県内で5年間継続して介護の仕事の従事した場合には、全額返還免除となるものです。本市では、本制度について、チラシの配布や市ホームページ根の掲載など、広く周知に努めて参ります。
次に、特別養護老人ホームについてお答えします。
まず、特別養護老人ホームの整備事業予定者が2回続けて辞退していることの受け止めについてですが、特別養護老人ホームは、今も多くの待機者がおり、そうした中で、事業者から辞退があったことは重く受け止めております。
次に、特別養護老人ホームの整備を進めることについてですが、入所を待つ方が大勢いらっしゃることは認識しており、本年3月に策定した「第9期介護保険事業計画」で設定した3年間で580床の目標に向けて、着実に整備できるよう努めて参ります。
次に、補聴器の購入助成についてお答えします。
加齢性難聴者への補聴器購入助成制度の創設についてですが、本市では、平成22年度までに実施していた、高齢者を対象とした補聴器の購入助成を、障害者手帳所持者向けの制度があることなどを理由に廃止しておりますが、加齢性難聴により、日常生活の中で様々な困難を抱えている方にとって、補聴器を装着することは、人とのコミュニケーションを活発化させ、生きがいや、生活の質の向上に寄与するものと考えております。「加齢により難聴のある方」を対象とした助成制度については、他の指定都市とともに、国に対して全国一律の制度の創設を要望しており、引き続き、国の動向を注視して参ります。
次に、国保についてお答えします。
まず、一般会計からの繰入を行い、国保料を引き下げることについてですが、国民健康保険は、国民皆保険制度を支える基盤的役割を担っていることから、安定的な運営をしていくことが死の責務と考えております。国民健康保険の財政状況は、他の被用者保険と異なり、高齢者や低所得者の加入割合が高いことや、医療の高度化などによる医療費の増加により、厳しい財政状況が続いております。このような状況において、保険料改定にあたっては、低所得者の負担に配慮するとともに、保険者として歳入確保と歳出抑制の取組みを推進し、保険料上昇の抑制に努めているところであり、一般会計からの繰入により、保険料引き下げを行うことは考えておりません。
次に、国への公費の増額の要望についてですが、国民健康保険は、他の医療保険と比べ、高齢者や低所得者が多いなどの構造的な問題を抱え、財政基盤は極めて脆弱であります。このことから、国の責任において、国庫等の公費負担の更なる引き上げ措置を強く要望しております。
次に、18歳までの保険料の均等割り廃止についてですが、国民健康保険は、、国による全国統一した制度で運用することが望ましいことから、引き続き、国に対して対象年齢などの拡大について要望して参ります。
こども未来行政について
次に、公立保育所の主食提供についてお答えします。
まず、主食提供を実施した保育所の反応についてですが、児童や保護者からは、 ○温かいご飯はおいしい、○子どもが喜んで食べている、○お茶碗やお箸の使い方が上手になったと感じる、○朝の忙しい時間に家庭で主食を準備する手間が省けふたんけいげんになった、といった好意的な反応をいただいております。また、職員からも、子どもが喜んで食べている様子などについて報告を受けております。
次に、未実施の保育所における早期実施についてですが、主食の提供にあたり、保育所によっては厨房機器の設置や電源工事などが必要であることから、これらの準備が整った保育所から順次実施することとしております。そのためにも、来年度以降に提供開始を予定している保育所につきましても、着実に準備を進めて参ります。
次に、子どもルームについてお答えします。
まず、指導員の待遇保障についてですが、アフタースクールへの移行にあたっては、運営事業委託の仕様書に中で、子どもルームで勤務している指導員の雇用に配慮するよう定めています。当該指導員に対しては、新たな運営事業者は雇用条件等を示したうえで、当該アフタースクールでの勤務の継続について意向を確認しています。今後も、指導員に対して運営事業者とともに丁寧な情報提供を行うことにより、指導員の抱える不安の解消に努めて参ります。
最後に、特別教室を使わずに、専用室を確保することについてですが、子どもルームを必要とする全ての児童を受け入れることができるよう、受け皿の確保に努めており、学校運営に配慮しながら、余裕教室の活用が可能な場合には、専用室を確保しておりますが、それが難しい場合には特別教室等を利用することとしております。特別教室等の利用にあたっては、子どもたちがより良い環境で放課後の時間を過ごすことができるよう、エアコンの設置や背もたれ椅子の用意、床にクッションフロアを敷くなど、運営事業者の声も聞きながら、環境改善に努めているところです。
【橋本副市長答弁】
市長答弁以外の所管についてお答えします。
新年度予算編成について
物価高騰対策に係る中小事業者への給付金及び支給要件についてですが、先月閣議決定された国の総合経済対策には、地方公共団体が行う事業者へのエネルギー価格等の物価高騰に対する支援に交付される「重点支援地方交付金」が盛り込まれております。冬期の電気・ガス料金の負担軽減支援をはじめとする、国または県などの経済対策や、今後のエネルギー価格をはじめとする物価高騰の影響、市内の事業者の動向等を注視しつつ、必要な対応を検討して参ります。
環境行政について
次に、プラスチックごみ分別収集・再資源化についてお答えします。
まず、モデル事業実施後の全市展開についてですが、千葉市廃棄物減量等推進審議会においてプラスチックの資源の一括回収の方法等についてご審議いただいているところであり、今後、2地区で約2,000世帯を対象としたモデル事業の検証結果を踏まえつつ、さらなる検討を進め、全市展開に向けた実施体制を整えて参ります。
次に、出前講座など意見交換の場を通じた市民の意識醸成についてですが、これまでも、プラスチックごみの削減・再資源化に向けた出前講座、ワークショップ等を実施しており、引き続きこれらの取組みを進めることにより、市民の皆様の意識醸成を図って参ります。
次に、CO2排出削減についてお答えします。
まず、千葉市地球温暖化対策実行計画の進捗状況及び今後の見通しについてですが、市域における温室効果ガス排出量を2030年度までに2013年度比36%削減することを目標としているなかで、直近の2020年度時点では18.1%削減となっております。排出量は着実に減少していますが、目標の達成に向けては、さらなる削減の加速化が不可欠であると考えております。
次に、排出量の多い産業に対する取組状況についてですが、各事業者は2050年のカーボンニュートラルの達成に向けてロードマップを作成し、計画的に取り組んでいることから、本市においては、脱炭素効果の高い革新的技術開発や設備投資への財政支援を国へ要望するなど、各事業者の取組みが着実に進むよう支援しております。
経済農政について
次に、農業施策についてお答えします。
まず、新規就農や後継農家への積極的な支援についてですが、昨年度に「リユース農業施設データ収集提供事業」を創設し、中古のハウスや機械の情報収集を行い、今年度から新規就農者を対象にそれらの情報を提供し、所有者との個別マッチングを開始したところです。また、昨年度創設した、施設や機械導入への助成制度である「未来の千葉市農業創造事業」のうち「新規就農支援タイプ」では、新規就農者を、「経営拡大支援タイプ」では、後継農家を含めて助成するなど、新規就農や後継農家への支援を強化したところです。
次に、肥料や飼料価格高騰対策についてですが、これまで、国の地方創生臨時交付金を活用するなどして、令和4年度及び昨年度に飼料価格高騰対策を実施し、価格高騰分を給付金として支給してきたところです。また、中長期的なコスト削減につなげる取組みとして、農政センターにおいて、適正な施肥と肥料コスト低減につながる、土壌診断や営農指導を行うとともに、家畜ふん堆肥の活用と飼料の生産を連携させた取組みを推進するなどし、耕種農家と畜産農家の経営安定化を支援して参ります。
次に、有害鳥獣対策の一層の強化についてですが、本市では、農作物被害を軽減するため、わなによる「捕獲」や電気柵による「侵入防止」対策などを実施しております。わなの増設、電気柵の延伸など、年々対策を強化しており、加えて、近年のアライグマ等中型獣やイノシシによる農作物被害の増加、生息範囲の拡大に対応していくため、現在、「中型獣集中捕獲モデル地区事業」や「イノシシの出没前線地域集中捕獲事業」を実施しているところです。今後も引き続き、捕獲や侵入防止等の対策強化を進めるとともに、より効果的に実施するため地域の体制整備に取り組んで参ります。
都市行政について
公共交通の維持についてお答えします。
まず、公共交通維持のための施策の評価についてですが、新型コロナウイルス感染症の流行などを契機として、公共交通の利用者が大きく減少するなか、バス事業者に対して、令和2年度から新型コロナウイルス感染症拡大防止対策への補助や、燃料費高騰対策などの事業継続のための支援を実施してきており、事業者からは、経費の負担軽減につながり、ありがたかったとの声が届いております。また、バスの運転手不足への対策として、運転手養成に係る経費への助成を実施しており、令和2年度から昨年度までの4か年で、6社、延28人の大型二種免許取得につながっております。
次に、運転手確保のための財政支援についてですが、路線バスの運行の維持には、運転手確保が何よりも重要であることから、大型二種免許取得への支援に加え、今年度からは、取得要件が緩和される受験資格特例教習に係る経費や、求人のためのイベントや広報などの経費も対象とし拡充し、支援に努めております。また、自治体単位での支援には限界があることから、今月3日、九都県市首脳を代表して、国に対し、路線バスの維持確保にために運転手の労働環境改善等の支援を拡充するよう、要望してきたところです。引き続き、国の動向等について情報収集に努めるとともに、関係自治体や事業者とも連携し、バス路線維持のための取組みを進めて参ります。
次に、高齢者の外出を支援する外出応援バスの導入についてですが、路線バスは市民の移動を支える重要な社会インフラですが、昨今の厳しい経営環境を踏まえ、これまでも路線の維持・存続のために各種の支援策を実施しているところです。 高齢者向けのサービスとしましては、既に市内のバス事業者が自ら、運転免許の返納者への運賃割引や乗り放題となる年間パスポートの販売を行っていることも踏まえ、外出応援バスの導入は、考えておりません。なお、路線バス事業の持続性を高めることが重要であるため、今後とも事業者のほか庁内関係部局とも連携し、バス事業者への支援に取り組んで参ります。
次に、公園についてお答えします。
地域に密着した身近で利用しやすい公園整備についてですが、市内には、1,000箇所あまり身近な公園があり、そのうち面積が300平方メートル未満の極小な公園が2割を占めるとともに、地域ごとに公園の配置状況も異なっており、また、施設の老朽化も進んでおります。このような状況において、人口減少・少子高齢化といった環境の変化や、公園に求められる様々なニーズに対応するため、モデル的に改修や機能再編などを検討する4地区を選定しており、地区内でのアンケートも踏まえながら、方向性を整理して参ります。
次に、中央公園プロムナードについてお答えします。
まず、住民ニーズの確認についてですが、まちづくりを進める際には、住民の方々や地権者をはじめとする関係者のニーズや意見を把握することが重要であると考えており、これまでもまちづくりの内容に応じて、説明会や公聴会を開催するほか、ワークショップや意見交換会等を実施してきております。
次に、仮称「中プロ・デザインラボ」の構成についてですが、中央公園プロムナードは、沿道に商業・業務などの多様な機能が集積する、本市の顔であるメインストリートです。近年、人々の価値観の変化も含め、プロムナードに寄せられる期待が変化してきたと感じており、憩いや安らぎがあり、また、出会いや交流が生まれる様な、通り自体が目的となる空間に生まれかわる必要があると考えております。 仮称「中プロ・デザインラボ」を設立する際には、様々な立場からプロムナードへの期待やご意見をいただけるよう、他都市の事例も参考にしながら、住民の方々、民間事業者、まちづくり団体、経済団体等の様々な関係者及び学識経験者に参加を呼び掛けて参りたいと考えております。
次に、仮称「中プロ・デザインラボ」の目的についてですが、参加していただいた関係者及び学識経験者と協働して中央公園プロムナードの将来像を考え、描き、ビジョンを取りまとめ、市民の皆様と広く共有することを目的としております。
建設行政について
次に、新湾岸道路についてお答えします。
まず、排気ガスによる影響についてですが、国から、ルート・構造案の決定にあたっては、十分に環境に配慮した計画になるよう検討していくと伺っております。 今後も、様々な方からのご意見の把握に努め、周辺環境などに配慮された計画となるよう、国に申し入れしていくこととしております。
次に、新湾岸道路はやめるべきではないかについてですが、本市の広域的な道路ネットワークが強化され、持続的な発展に大きく寄与することから、極めて重要な道路と認識しており、引き続き計画の早期具体化に向け、国に協力して参ります。
次に、道路の維持管理についてお答えします。
まず、草刈り予算についてですが、草軽は、年1回の実施を基本に、車両や歩行者の通行の妨げになるような場合には、複数回実施することとしております。また、今後、交差点周辺や中央分離帯などをコンクリートや防草シートで覆い、草刈りの全面積を減らす取組みを推進することとしており、草刈り業務の効率化を図ることで、増加している草刈り要望に対応して参ります。
最後に、旧千葉外房有料道路である生実本納線の草刈りについてですが、当該路線についても、他の路線と同様に、年1回の実施を基本としており、通行の妨げとなるような場合には、適宜、対応して参ります。
以上でございます。
【教育長答弁】
新年度予算編成について
まず、学校給食費無償化についてですが、学校給食については、現状の運営においても、人件費や施設管理運営費等に市債を投じ必要な栄養バランスを考慮しながら、安全安心な給食の提供に取り組んでいるところです。また、第3子以降のほか、生活保護や就学援助制度により、昨年度は合計17.5%の児童生徒が給食費無償化の対象となり、事業費約6億円を投じていることに加え、完全無償化を実施する場合はさらに年間約37億円の追加費用が必要となります。国においては、本年6月に、学校給食に関する全国調査の結果を取りまとめ、その結果を踏まえながら、今後、児童生徒間の公平性、国と地方の役割分担、政策効果といった観点や、法制度の面から課題を整理していくとされたことから、引き続き、国の動きを注視して参ります。今後、超高齢社会への進展への対応や公共施設の老朽化対策、学校体育館への冷暖房設備の整備を予定しており、財政需要の増加が見込まれる中、教育や子育て支援の施策全体においても、限られた財源の中で、優先度を見極めて、実施すべき施策を総合的に検討する必要があり、現時点では、市単独での完全無償化の実施は困難であると考えておりますが、こうした子育て施策については、地域間格差が生じないよう国の責任において実施するべきであり、今後も強く国へ申し入れたいと考えております。
次に、人員の増加に係る教育予算の拡充についてですが、正規教員の増員については、教員の人件費を主に国庫負担金等の国費で賄っていることから、更なる増員は、国の財源とともに実施されるべきと考えており、引き続き国に対して加配定数の拡充を要望して参ります。また、児童生徒への教育の充実や教職員の負担軽減のため、専科指導のための非常勤講師を計画的に配置するほか、スクール・サポート・スタッフや、不登校児童生徒を支援するステップルームティーチャーなどを配置しております。このほか、本市単独で、教員が研修に参加する際の一時的な不在へ対応するため、初任者研修後補充講師を配置するとともに、1年目の教員の資質向上のため。初任者指導講師を配置するなど、教職員が働きやすい環境整備に努めております。引き続き様々な専門スタッフを適切に配置するため、必要な予算の確保に努めて参ります。
教育行政について
次に、教職員職場の現状についてお答えします。
まず、担任の未配置の状況についてですが、先月1日現在における直近3年間の推移としましては、令和4年度が15人、昨年度が11人、今年度が37人となっております。そのうち、精神疾患が理由で病気休暇等となり、未配置となっている人数は、4年度が9人、昨年度が7人、今年度が7人となっております。
次に、教員未配置の要因を解消するための取組みについてですが、教員未配置の要因としては、病気休暇や育児休業などの取得に伴い、代替職員が配置できなかったことによるものです。解消するための取組みとして、定期的な講師登録説明会を開催するほか、過去に本市で働いていた人材に電話連絡をおこなうなど、人材確保に努めております。なお、年度当初において、産前産後休暇等の取得予定がある教員に対しては、4月当初から前倒しで代替職員を配置し、円滑な引継ぎを行えるように配慮しております。さらに、未配置が発生している学校につきましては、教員が病気休暇等を取得した際などに緊急で対応するための正規休暇等の補助教員や、会計年度任用職員を配置するとともに、教務主任等が担任を代行するなど、児童生徒への教育活動に影響が無いよう努めております。
次に、教員採用候補者選考の志願者数の減少についてですが、合格者数を一定数確保する必要がある中で、志願者数の減少は、教育の質や学校運営に影響しかねない喫緊の課題であると認識しております。本市が求める人材の更なる確保のため、志願者数の増加を図り、教育の質の維持・向上に努めていく必要があると考えております。
次に、志願者を増やすための取組みについてですが、今年度から、大学3年時等を対象に、「千の葉の先生養成塾」を新設し、研修や講座の修了者は次年度に実施する千葉県・千葉市教員採用候補者選考の第1次選考を免除するほか、「教員奨学金返還サポート」や「教員採用プロモーション事業」を開始し、志願者数の増加に努めております。また、県下複数会場にて実施していた候補者選考を幕張メッセで集中実施するほか、県内のみならず、盛岡をはじめ3つの地方選考会場を設けるなど、様々な志願者が受験しやすいよう、利便性を高めております。
次に、スクール・サポート・スタッフの増員や教頭をサポートするための人員増についてですが、教職員を支援する専門スタッフの配置により、学校から業務負担が軽減したとの声も寄せられていることから、教職員が働きやすい環境づくりに必要な人員が適切に配置できるよう、必要な予算の確保に努めて参ります。
次に、学校体育館のエアコン設置についてお答えします。
まず、エアコン設置の考え方についてですが、熱中症対策の観点から、部活動がある中学校・高等学校・中等教育学校や特別支援学校の整備を優先し、その後、小学校への整備を予定しております。また、今後の見通しについては、多額の費用を要する事業であり計画的な整備が必要であることから、次期実施計画等に位置づけることにより、着実に推進したいと考えております。
最後に、来年度までの国の補助金の補助率引き上げを利用して一斉に設置することについてですが、本事業は多額の費用を必要とすることから、全ての市立学校に短期間で集中して整備することは財政負担も過大なものとなるため、難しいものと考えております。引き続き、本市にとって有効な財源をいかに確保し、どのようにすれば他の事業と並行して進めていくことができるか、さまざまな視点から検討して参ります。なお、補助率の引き上げの延長については、引き続き国への要望を行って参ります。
以上でございます。
【選挙管理委員会事務局長答弁】
選挙管理行政について
まず、タクシー券を配布して投票所までの移動を保障することについてですが、 現在、他都市で実施されている移動支援の事例は、投票所の統廃合による代替措置として実施されているものがほとんどであり本市とは状況が異なるものと考えております。また、実施に当たっては、対象者や経費のほか、行政サービスの平等性や見込まれる利用者数など、様々な課題も考えられることから、直ちに実施することはできませんが、地域の実情を踏まえて研究して参ります。
次に、投票率向上のための計画についてですが、来年度予定されております選挙においては、選挙管理委員会としても積極的な投票参加につながるよう周知啓発に努めていかなければならないと認識しております。まず、選挙の認知度を高めるための選挙時啓発として、市政だよりや投票所入場整理券、ポスター掲示場等を活用した選挙期日や投票所等の周知のほか、横断幕や懸垂幕等の屋外広告、街頭啓発や広報宣伝車の巡回などに加え、市広報番組の活用や市ホームページに選挙特集ページを開設するほか、「X」や「フェイスブック」等の市公式SNSによる周知など、様々な媒体を活用した啓発を実施する予定です。また、将来の有権者への啓発と保護者の投票を促すための「親子で投票に行こうキャンペーン」のほか、若者の政治意識を高めるため、実際の選挙事務を体験してもらう高校生の選挙事務従事なども検討しており、若年層を意識した啓発にも努めて参ります。
次に、共通投票所の設置についてですが、共通投票所を設置することは、投票環境の向上に資する方法の一つだと認識しておりますが、課題として二重投票防止のためのネットワークに対応した当日投票システムの改修が必要となります。この改修にあたっては、国が推進する自治体情報システムの標準化によるシステム改修・切り替えの影響を受けることからその見通しが立ち次第、実施できるよう引き続き研究して参ります。
最後に、主権者教育の充実についてですが、これまでも、児童や生徒のそれぞれの発達段階に応じて、大学や千葉県弁護士会と連携した小学校模擬選挙の実施、中学校や高校での出前授業のほか、明るい選挙を呼びかけるポスターや標語、書初めといった「明るい選挙啓発作品」の募集やインターンシップの大学生により作成した「明るい選挙だより」を市内全中学校に配布するなどの主権者教育を実施してきたところです。引き続き、教育委員会などの関係機関と連携し、政治屋選挙に関する意識向上を促すために主権者教育の取組みを進めて参ります。
以上でございます。
<2回目>
【神谷市長答弁】
市政運営の基本姿勢について
2回目のご質問にお答えします。はじめに、暮らしを応援する政治についてお答えします。
水道料金の値上げについてですが、近年、資材価格や電気代など光熱費の高騰で、下水道も含め、事業を行っていく際の経費が増加しており、同様な状況にある県営水道におきましても、今後数年間の財政収支見通しは厳しいものになっていると承知しています。一方で、料金の値上げは、長期化する物価高騰より、厳しい状況にある市民生活に影響を与えることから、県には、値上げ幅の抑制や市民への丁寧な説明をしていただきたいと考えております。なお、市営水道については、県から水を購入して給水しており、県からの購入価格が上がれば、市営水道の水道料金にも影響する可能性があることから、その場合には、県に値上げの考え方、背景等について説明を求めて参りたいと考えております。
次に、学校給食費無償化についてお答えします。
交付金を活用した学校給食費の無償化についてですが、先週、閣議決定された国の総合経済対策を盛り込んだ補正予算案では、自治体独自の物価高騰対策に活用できる交付金として、全国総額で6,000億円が計上されており、直近の令和5年11月に配分された交付金について、全国総額約5,000億円に対して本市配分額が12億円であったことから、今後、同程度の配分額が見込まれているところです。国の補正予算案は、年内の成立を目指すこととされていることから、引き続き、国・県の動向を注視しながら、今後示される具体的な配分額を踏まえ、必要な支援を速やかに検討し、市民・事業者の皆様に対して、できる限り早期に幅広い支援を届けるべく、迅速な事業化に努めて参ります。なお、本市独自による学校給食費無償化の対象拡充は、多額の追加費用を要するものであり、財源が限られる中、教育・子育て支援施策全体において総合的に検討する必要があり、現時点では、市単独による完全無償化の実施は困難であると考えております。
最後に、都市基盤整備優先から暮らし優先の施策展開についてお答えします。
市民のくらしを支える施策への財源配分についてですが、本市では、これまで、バス路線の廃止に伴う公共交通不便地域の解消といった持続的な公共交通ネットワークの形成や、市民生活に身近な公園整備、公園トイレの環境改善のほか、子ども医療費助成の拡充や福祉まるごとサポートセンターの開催といった市民のくらしを支える取組など、市民生活・市民福祉の向上に向けた施策の充実を図って参りました。また、人口減少が見込まれる中、引き続き、市民・事業者の皆様に選ばれるよう、本市が持続的に発展するためには、新たな賑わいや交流を生み出す、中心市街地の活性化や公園・スポーツ施設の整備のほか、将来の税財源の涵養に資する企業立地の促進に加え、地域間の連携強化や市内渋滞の構造的な緩和につながる広域道路ネットワークに整備など、都市の魅力・活力の向上に資する施策についても、将来負担に配慮しながら着実に推進する必要があると考えております。引き続き、事業の重点化や事業費の精査に努めつつ、市民生活向上への対応と、本市の未来の発展に向けた投資のバランスをとりながら取り組んでまいります。
以上でございます。
【大木副市長答弁】
暮らしを応援する政治について
まず、給付金の対象拡大についてですが、本市では、限られた財源の中で施策の優先度を考慮しながら、様々な物価高騰対策に取り組んでおります。本給付金については、特に物価高騰の影響を受ける低所得世帯の負担を軽減するという国の制度に則って支給することを予定しており、本市独自に対象を拡大することは検討しておりません。
次に、中小事業者の賃金引き上げや国保料・公共料金の引き下げについてですが、中小企業の持続的な賃上げについては、10月に開催された九都県市首脳会議において新たな検討会を設置し、各種支援ツールの事業者への周知など、九都県市が連携して、価格転嫁の円滑化に向けた取組みの検討を進めることとしています。 また、国の総合経済対策において、政府が価格転嫁を後押しすることが鍵となるとの考えのもと、持続的・構造的賃上げに向けた取組みなどの施策を総動員することとしていることから、引き続き、国の動向を注視して参ります。国民健康保険料については、医療費の増加が続く中、将来にわたって制度を持続可能なものとしていくため、一定の保険料をご負担いただくことはやむを得ないものと考えております。引き続き、保険者として実施できる歳入確保と歳出抑制の取組みを推進し、保険料上昇の抑制に努めるとともに、国に対して、保険料高騰を抑制する財政支援措置を要望して参ります。このほか、公共料金については、市民負担の公平性確保の観点や受益者負担の原則、国・県における基準等を踏まえ、市民生活への影響などを勘案し、必要最小限度の改定を行うこととしており、引き続き、最低賃金や物価などの社会情勢を見極めながら、適切な対応に努めて参ります。
保健福祉行政について
次に、介護への支援についてお答えします。
本市独自の介護職員への処遇改善についてですが、人材確保・定着にあたっては、従事者への支援が重要であると認識しておりますが、介護職員の処遇改善は、抜本的な改善が必要であることから、一義的には国の責任において対応すべきと考えております。
最後に、補聴器購入助成についてお答えします。
早急に補聴器購入の補助を行うべきとのことですが、加齢性難聴により日常生活の中で様々な困難を抱えている方にとって、補聴器を装着するメリットは認識しておりますが、高齢者福祉に対するニーズは今後も増え続けていく見通し施あることから、現時点での導入は困難であり、今後も国の動きを注視し、他のニーズとの優先度を考えながら検討すべきものと考えております。
以上でございます。
【橋本副市長答弁】
暮らしを応援する政治について
中小企業者への支援についてですが、国又は県が実施する、冬期の電気・ガス料金の負担軽減支援などの経済対策や、今後のエネルギー価格をはじめとする物価高騰の市内事業者への影響を注視し、政令市をはじめ近隣市の動向などを踏まえ、必要な対応を検討して参ります。
都市行政について
次に、高齢者の外出支援についてお答えします。
まず、高齢者の外出が促進された場合のクロスセクター効果の検証についてですが、公共交通の維持は、維持されなかった場合と比べて健康の増進を含め、様々な分野に波及する、いわゆるクロスセクター効果があると考えており、介護利用者や認知症者の減少などの具体の効果検証を実施する予定はありませんが、今後とも、公共交通の利便性の向上や利用促進を、庁内で連携して進めて参ります。
次に、バス路線維持補助の増額についてですが、今年度創設したバス路線維持確保事業につきましては、現在、事業者と意見交換を行いながら、予算の範囲内で、効果的に生活路線として必要なバス路線の維持につながるよう事業者との調整を進めております。今後とも必要な予算の確保に努めて参ります。
最後に、デマンドタクシーの運賃の引き上げと他地域への拡充についてですが、 運賃も含む運行計画につきましては、地元交通協議会で議論したうえで決定しており、まずは、現行計画による利用実態の把握に努めて参ります。また、地域の拡充につきましては、高津戸町に加えて今年度から大椎台・大木戸台地区と下大和田町・上大和田町地区においても社会実験を進めており、その中で蓄積した知見やノウハウを活かし、他の公共交通不便地域への展開も検討して参りたいと考えております。
以上でございます。
【教育長答弁】
教員の増員について
まず、年度初めに正規教員を増員することについてですが、本市においては、これまで国の学級編成の標準を上回る、独自の学級編成基準で少人数学級を実現しており、正規教員として専科教員等の配置などもおこなっております。一方で、教員の人件費は主に国庫負担金等の国庫で賄っていることから、教員の更なる増員は、国の財源とともに実施するべきと考えており、引き続き国に対して加配定数の拡充を要望して参ります。
最後に、様々な職種を増やすよう対策強化を図ることについてですが、教職員の負担を軽減し、児童生徒の教育環境を整えるためには、教職員を支援する専門スタッフの配置充実が重要であると考えております。不登校児童生徒を支援するステップルームティーチャーを含め、必要な人員を適切に配置できるよう、予算の確保に努めて参ります。
以上でございます。
<代表質問3回目>
3回目は意見要望を申し上げます。
マイナ保険証についてです。2日から新規の健康保険証の発行が廃止となったものの、制度について誤解している方や理解していない方が多くいるため、さらなる情報発信が必要です。医療機関はもちろん、市民が多く利用する区役所やコミュニティセンター、公民館などで様々な媒体を使って、今後の保険証等の取扱いについて、また更新手続きが必要であり更新をしないと無保険状態になり10割負担の請求がされることなどの説明を分かりやすく周知するよう求めておきます。
物価高騰対策です。
我が会派の様々な物価高騰対策についての提案に対して、市長は国や県の経済対策の動向を注視していくとの答弁に終始しており、市として独自の物価高騰対策を何ひとつ具体化しようとしない姿勢を改めるべきです。市民の生活実態をつかんで今困っている方々に支援を届けていくのが公共の役割であり、市民のためになる税金の使い方ではないですか。新年度予算を待たずとも補正予算で緊急に物価高騰対策に取り組むよう再度求めておきます。
次に子育て支援についてです。子育て家庭の経済的な負担軽減のために保育料の第2子の無償化を求めたところ、「他の事業への影響を勘案しつつ、今後、検討を進めて参ります」と答弁されました。実施に向けた前向きの答弁と受け止め、実施に向けての検討を早急に進めるよう要望するものです。
学校給食無償化については多額の財源が必要なため、国の責任において実施されるべきものと相変わらず後ろ向きの答弁です。市長は以前、子ども医療費無償化のように自治体がやりすぎると国が本来やるべきことをやらなくなってしまうので、自治体がやり過ぎてはいけないという考えを発言されていましたが、地方自治の本旨に照らせば誤った考え方ではありませんか。千葉市に住んでいる子どもや保護者が望む学校給食無償化を国に先駆け実施していくことこそ住民福祉の増進がはかれるのではないでしょうか。市長は実施には多額の財源が必要と言いますが、学校給食無償化のための予算は一般会計予算の1%にも満たないものであり、不要不急の事業を後回しにすれば実施は可能です。中学生から段階的に実施すると13億円が必要とされていることから段階的に実施することも検討すべきです。国の補正予算では自治体が独自に物価高騰対策に活用できる交付金の本市配分額が12億円程度と見込まれるとのご答弁でしたので、交付金の半分を使って中学生の無償化を半年間実施していくことを求めるものです。千葉市の未来を担う子どもたちの成長を支えるために学校給食無償化の決断をすべきと求めておきます。
学校体育館のエアコン整備について次期実施計画等に位置付けるとの答弁でしたが、2年後の計画では整備完了は5年も6年も先送りになってしまうではありませんか。あまりにも遅すぎます。船橋市や習志野市では体育館へのエアコン設置が進んでおり、千葉市も遅れをとることなく、急いで取り組むべきです。
高齢者支援についてです。
市長が掲げてきた政策の一つに「高齢者が生涯安心して暮らし、健康寿命を延ばせる社会を、障害の種別程度にかかわらず、安心して暮らせる社会をつくります」とありますが、この政策実現のために高齢者の外出応援パスや補聴器の購入助成が寄与するものと考えます。そして、介護が必要になった時に頼れる介護サービスがあることが安心して暮らせる保障になります。そのためにも介護を担う職員の処遇改善に今こそ踏み出すべきと申し上げておきます。
高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせる社会をつくっていこうではありませんか。
最後に市長選についてです。
市長は昨日の代表質問に対する答弁で市長選に出馬すると表明されましたが、それに先駆けて2日に政治資金パーティーを開いたと新聞報道がされております。政治とお金の問題がこんなにも取りざたされている中で、あえて政治資金パーティーを開催した市長の政治姿勢はお金にクリーンな政治を願う市民感覚と乖離していると指摘しなければなりません。
我が会派は新しい千葉・みんなの会に政党として参加をして市民本位の市政を作っていくために活動をしてまいりました。3月に行われる市長選挙では新しい千葉・みんなの会から候補者を擁立して公約した政策を市民に訴えていくという決意を申し上げて会派を代表しての質問を終わります。