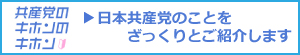新千葉市民会館は市民参加で整備を! 中村きみえ議員一般質問〔2024年第4回定例会〕
中村きみえ議員の一般質問 2024.12.6

- 市民会館について
【中村きみえ議員】
- アーラについて
8月30日に、NPO法人千葉演劇を観る会主催で新千葉市民館学習会があり、文学座演出家の西川信廣さんの講演を聞き、可児市文化創造センターは、市民が参加しながら施設運営していることなども紹介されており、現地を観たいと思い、10月に可児市文化創造センターAla(アーラ)の視察をしました。
岐阜県可児市は、人口約10万人、県の中南部で岐阜市や名古屋市から30キロに立地します。住宅団地が増加し、東京からは新幹線、私鉄経由し3時間で移動可能です。可児市には、そもそもホールや映画館がなく文化的な施設が欲しいということで市民とともに施設の建設、運営がされてきました。平成14年7月に開館し、敷地面積は35,344.54㎡、建築面積8,743.29㎡、延べ床面積18,410.87㎡地上4階、地下2階で駐車場は437台、レストランは併設され、建設費は総額128億3,726万7千円です。施設は芸術文化振興財団が運営し、館長は、元教育長が行っているとのこと。主劇場は1,019席あり、舞台も幅、奥行きも17メートルあり、オーケストラも十分できます。小劇場は311席、演劇や舞台として利用できます。そのほかに、映像シアターは100人程度、音楽練習室、木工作業室、演劇練習室、美術・演劇・音楽ロフト、レセプションホール、ワークショップ、研修室と施設の中で様々な取り組みが実に多彩に展開されています。
アーラまち元気プロジェクトとして文化芸術の力で生きる力とコミュニティを創出し、町を元気にすることを目的に活動されています。例えば、障害のある方もない方も参加する「みんなのディスコ」、障害のある方や小さなお子さんも利用できるクラッシックコンサートを新日本フィルが実施、みんなのピアノプロジェクトでは、寄付者の協力で、地域のピアノ講師や音大生が指導してピアノを弾きたくても家庭環境で習えない子に教えるなど単に箱モノを整備して演奏、観劇することにとどまらず、地域の課題を解決するために居場所として利用されており素晴らしいものでした。休日も庭の噴水に子どもが集まり、イベント以外でも親しまれる施設となっています。
1つに、こうした施設や運営について市はどう受け止め、また今後の市民会館の建設に活かしていこうと思われますか。
【市民局長答弁】
文化芸術の価値を高めながら、子どもや若者から高齢者まで幅広い年齢層を対象とした取り組みや、国籍や障害の有無に関わらず参加や交流できる機会の創出などにより、文化芸術基本法の主旨に合った取り組みであると承知しております。本市においては、同法の主旨を踏まえ、令和3年度に策定した千葉市民会館再整備にかかる基本計画において、再整備の3つの基本コンセプトとして「千葉市の文化芸術の振興・創造」「地域活性化、観光振興等への貢献」「持続可能な施設・管理運営」を示しており、この実現に向けて施設整備と運営の検討を行っております。
【中村きみえ議員】
(2)市民参画について
2つに、千葉市では、市民団体にヒアリングをした程度で、その後、市民も含めてどう市民会館を整備していくのかを市の関係者だけで進めていこうとしています。しかし、今回の可児市のように市民の声を聴きながら施設の運営をしていく場合にその整備内容をよく検討したうえで整備していくことが必要です。
市原市でも文化交流施設整備基本構想の中で、まち・文化・ひとが育つ場所を基本理念としてニーズ把握としても市民アンケートや利用者アンケート、文化交流施設検討ワークショップを5回開催、文化交流施設検討委員会では学識経験者、関係団体、市民の意見などを反映するために4回開催しています。
千葉市でもこのように設置場所や施設の理念、運営のあり方なども含めて市民参加で検討していくべきではありませんか。
【市民局長答弁】
千葉市民会館再整備にかかる基本計画の策定にあたり、市民意見募集を実施しており、また、策定後においても説明会を行うなど市民のご意見を伺いながら取り組みを進めてきたところです。今後も再整備を進める中で、必要に応じて利用者等のご意見を伺って参ります。
【中村きみえ議員】
3つに、必要に応じて利用者等のご意見を伺うとは、いつ必要と感じるのですか。市民が希望すれば意見を聞き、対応するのですか。
【市民局長答弁】
新市民会館の再整備において、利用者の中心となる市民からの声は大切であると考えており、今後、再整備の進捗に応じた適切な段階において、意見聴取を検討して参ります。
【中村きみえ議員】
4つに、新千葉市民会館建設に関する陳情書が新千葉市民会館をつくる会から提出されました。本庁舎敷地の活用を希望することについての見解を伺います。
【市民局長答弁】
新市民会館の整備場所については、現在、JR東日本との協議を継続しながら、市有地での整備を含め、JR東日本千葉支社跡地と市有地で建設した場合と比較検証するため、概算建設費の積算や周辺環境等の条件整理を行うとともに、交通アクセスや商業施設の立地状況など総合的な観点から検討しているところです。
【中村きみえ議員】
5つに、市が建設費や周辺環境の条件整理、交通アクセスや商業施設の立地状況などで判断する場合、どこに重きを置くのですか。それは、決定する前にどのように検討したのかそのプロセスをきちんと市民にも議会にも開示したうえで検討すべきではありませんか。
【市民局長答弁】
新市民会館の再整備では、建設費などの比較のほか、交通アクセスや商業施設の立地状況など利用者にとっての利便性や、回遊性向上や地域経済活性化など、まちづくりへの影響も含め、様々な観点から総合的に検討する必要があると考えております。なお、民間事業者の駅前開発とも絡む事案であり、情報の公開については慎重に判断して参ります。
【中村きみえ議員】
6つに、芸術ホールだけでなく現状の市民会館のように会議室や活動室、図書室なども併設されたものを希望すると書かれています。現在でも市民が様々な活動をするうえで会議室なども含めて様々な規模で行う場合、会場確保が困難で日程を先延ばしせざるを得ない事態も多々あります。単にホールの整備だけでなく、会議室なども含めて一定の人数が入ることができる整備をしていくべきですが、見解を求めます。
【市民局長答弁】
千葉市民会館再整備にかかる基本計画で示した諸室の考え方に基づき、今後の基本計画等において、市民会館として必要な会議室の規模などについて検討して参ります。
【中村きみえ議員】
7つに、市は1,500席を予定している背景には、劇団四季や宝塚など興行をしていくことを想定しているかもしれませんが、演劇などは1,500席よりも1,000席程度が音響なども面でも適切だとの指摘もあり、大ホールの規模を見直していくべきではありませんか。
【市民局長答弁】
千葉市民会館再整備にかかる基本計画における、文化芸術の振興や地域活性化などの基本コンセプトを実現するため、新市民会館の大ホールは、演劇やミュージカル、バレエなどの大型舞台芸術やクラシック、ポピュラー音楽などのプロの大規模公演から、市民団体の公演や全国レベルの大会、大規模イベントの誘致まで様々なジャンルに対応していく必要があることから、大ホールを1,500席程度としたところです。引き続き、本計画に基づき検討を進めてまいります。
【中村きみえ議員】
8つに、そもそもたくさんの人を呼んで興行することだけが目的ではないはずです。市民が利用するための施設を整備しようとした場合には、関係者の声なども聴きながら検討すべきではありませんか。
【市民局長答弁】
今後、再整備の進捗に応じた適切な段階において、意見聴取を検討して参ります。
【中村きみえ議員】
この間、群馬県太田市民会館、山形県鶴岡市の文化会館を視察し、主に施設や周辺環境の問題を取り上げてきました。しかし、今回のアーラの施設では、ハード面だけではない市民が参加して運営を積み上げてきたことを学びました。すべての人が違いを価値として受容し、自分らしく幸福に共生できる社会の実現のために資金面での協力もあり企業団体、行政、学校、NPO、個人が関わって、市民のよりどころとなる施設になっていることが望ましいと感じます。千葉市では、先の新千葉市民会館建設に関する陳情の際の議論を聞いていても、市側は、興行的なことや地域の経済効果も加味したことなどが大きく影響しているように感じます。ですが、市民本位で市民が利用できる施設となるよう市民参加で進めていくことを強く求めます。
2.住みよい花見川区について
【中村きみえ議員】
- JR幕張駅北口について
先の9月議会でもJR幕張駅北口の階段に屋根の設置を要望しました。都市局長は、「JR幕張駅北口の階段部分への屋根の設置につきましては、駅利用者の皆様の利便性向上の観点から、階段を所有するJR東日本が設置するものと考えており、 今後も引き続き地域の要望を伝えてまいります。」と答弁しました。
花見川区では、もりた市議とともに地域の皆さんと幕張駅北口などで宣伝署名活動を行ってきました。11月20日にJR千葉支社にもりた市議、地域の皆さんとともに420筆の署名を持参して、JR幕張駅北口階段に屋根の整備を求める署名を提出し、懇談しました。
参加者からは、幕張駅北口はマンションが建ち、ビル風も強くて雨の時は大変で、ベビーカーや車いすの移動も大変だと。杖をつきながら傘をさして階段を歩くのは大変と高齢化も進んでいる町で、なぜ屋根が整備されないのか、お子さん連れの方からもぜひ設置をして欲しいと要望もされてきました。JRでは、即座に回答はできないがお話は聞きましたと要望は受け止めてくれました。
1つに、市は、JRに地域の要望を伝えてどんな回答がありましたか。
【都市局長答弁】
JR東日本に対しては、地域からの要望を伝えておりますが、明確な回答はいただいておりません。
【中村きみえ議員】
2つに、市がJRに対して屋根の設置をするように求めるべきではありませんか。
【都市局長答弁】
屋根の設置については、これまでも駅前広場の整備に関するJRとの設計協議などの際に、地域の要望を伝えておりますが、今後も機会を捉えて伝えてまいります。
【中村きみえ議員】
3つに、幕張駅北口では、今後のロータリー整備もされますが、この階段だけでなく、バス停の屋根も含めた通路の上に屋根があると、駅前でのイベントなどがあっても、ずいぶん助かると思いますが、全体に屋根の整備などをしてはどうですか。
【都市局長答弁】
バス停及び幕張駅の階段に接続する通路部分の屋根については、駅前広場と併せて昨年度に整備しており、駅前広場全体に屋根を整備することは考えておりません。
【中村きみえ議員】
今後も屋根の設置がされるまで取り組んでいきます。
- 交番について
花見川区の千葉西警察署管内ではJRの新検見川、幕張、幕張本郷とそれぞれの駅前に交番があり、そのほかには京葉道路の幕張インターチエンジから国道14号千葉方向(下り)約1,200メートル行った国道14号線沿いに幕張交番があります。
落とし物や住民同士のトラブルなども含めて何かあった時に交番に駆け付けることができると地域の皆さんからは、頼りになる施設として担っています。JR幕張駅の北口に移転整備され、南口がなくなることを地元の方から伺いました。
1つに、交番の設置の経緯についてお示しください。
【都市局長答弁】
令和3年2月にJR幕張駅北口周辺の地権者及び自治会等で組織する「東幕張土地区画整理推進協議会」から千葉市長宛に、駅前広場への交番設置の要望が提出され、これを受け本市から千葉県警察へ鋼板設置に関する要望を伝えたものです。
【中村きみえ議員】
2つに、スケジュールをお聞かせください。
【都市局長答弁】
千葉県警察からは、今年度の鋼板の設計を行った後、来年度以降に建設工事を実施する予定と聞いております。
【中村きみえ議員】
3つに、住民からは、幕張駅の南口に交番がなくなることで、治安の面でも北口からは、即座に駆け付けることが難しくならないかとの懸念の声が寄せられていますが、対応策はあるのですか。
【市民局長答弁】
110番通報があった場合には、どの場所においても、必要に応じて管轄区域又は周辺の交番、付近をパトロール中のパトカーなどから、警察官が現場に急行することと承知しております。幕張駅南口周辺においても、事件が発生した際には適切に対応することになるものと考えております。
【中村きみえ議員】
4つに、交番があることで、直ぐに駆けつけたり、地域の方が直接声を掛けたりすることができることにつながり、助かります。幕張の南側は、北側から移動する場合に、物理的に地下道などをくぐらなければ駆け付けられないなど課題もありますが問題ないといえるのですか。
【市民局長答弁】
警察官が対応する必要のある事案が発生した場合、どの場所においても管轄区域又は周辺の交番、付近をパトロール中のパトカーなどから、現場に急行することと承知しております。なお、交番の位置や管轄区域については、千葉県警察において検討のうえ、適切に決定されているものと考えております。
【中村きみえ議員】
5つに、移動交番もこの間活動されていますが、その概要や実績はどうなっていますか。
【市民局長答弁】
千葉県警察の移動交番は、事件・事故の多発地域や交番新設要望地域等において、各種届け出の受理や周辺の警戒に従事するほか、巡回パトロールなどを行い、地域の実情に沿った情報発信や犯罪抑止活動を展開しているものと認識しております。千葉県警察が公表している情報によりますと、幕張駅周辺では、武石町にある真蔵院駐車場、幕張西公民館駐車場が開設場所となっております。
【中村きみえ議員】
交番の移動で市民の安心安全に支障がおきないよう求めます。
3.買い物支援について
【中村きみえ議員】
(1)まいばすけっとなどについて
先の9月議会では、広島県廿日市市の無人スーパーの設置の問題について取り上げてきました。花見川区では、イオンスタイルの買い物バスに利用者も定着しつつあります。11月22日に中央区には富士見1丁目にあらたにまいばすけっとが進出し3店舗に、美浜区では11月29日に稲毛海岸の高洲コミュニティセンターの向かいにまいばすけっとが開店しています。千葉市に4店舗進出し、花見川区をはじめ市内のほかの行政区にもぜひ設置してほしいものです。
千葉市では4店舗進出の動きについて働きかけなどされましたか。
【経済農政局長答弁】
現在、市内で営業している「まいばすけっと」4店舗につきまして、事業者の判断により出店されたものです。
【中村きみえ議員】
(2)買い物難民アンケートについて
さて、今年の4月に買い物の問題でシンポジウムを開催しましたが、その際のアドバイザーである中村智彦神戸国際大学経済学部教授が「買い物難民アンケート」を作成してくださり、それをもとに市内107名にアンケートの協力してもらいました。
アンケートは市内全区で実施しました。年齢は30代から80歳以上までで70代が43人、80代以上が34人で7割以上が高齢者です。買い物で最も利用しているお店などの形態は、スーパーがダントツで57人。次いで、移動販売や生協などを利用しており、自動車の運転については、運転する方も29人いましたが、運転しない方も45人、免許返納者も18人です。日常の買い物に不便を感じているかの問いには約半数が不便と回答し、買い物で感じる不便さについては、重たいものやかさばるものを運ぶのが大変、近くに買い物できる場所がないと答えています。価格の安い店が近くにないとの回答は、物価高で、節約したい表れが示されています。インターネットやスマホの使い方が難しい、生鮮品を買うのが困難、買い物に行くための交通手段が不便、買い物に行くための交通費が負担だとの回答も多くありました。また買い物を手伝ってくれる人がいない、現金を引き出すのに金融機関が近くにないとの回答も気になります。移動スーパーや小型スーパーの利用については、将来的に利用するとの回答が半数近くありました。不便を感じている点を聞くと利用者からは、品ぞろえが少ない、時間が限られており利用しづらい、買い物に出かける楽しさがないとの回答も満足していない実態があります。買い物では、スマホ決済や電子マネーの利用を聞いたところ、現金のみ利用が半数を占めスマホ決済や電子マネーはスイカなどは4分の1ほどの利用にとどまっています。
1つに、まずこのアンケート結果についてどのように評価されますか。
【総合政策局長答弁】
今回、お示しいただいたアンケート結果は、分析をするための回答数が少ないことや、回答者のお住いのエリアなどが不明なことから、評価をすることは難しいものと考えておりますが、高齢化の進行や周辺の環境変化等の影響により、買い物に不便を感じているという声が、一定数あるということを示しているものと考えております。
【中村きみえ議員】
2つに、そのうえで、市として、どのような取り組みが必要と考えますか。
【総合政策局長答弁】
買物支援については、それぞれの地域における買物に関するサービスや地域コミュニティの状況など、実態を的確に把握するとともに、個々の地域の実情に応じた支援を行うことが必要と考えており、これまでも関係部局の連携のもと実施してきたところです。引き続き、あんしんケアセンターなど地域の支援機関や事業者などとも連携・調整を図りながら、地域からのご相談やご要望に対し、適切に対応して参ります。
【中村きみえ議員】
3つに、高齢者が買い物をする際に身近な場所で買い物ができるようにスーパーなども含めた配置が重要と考えないのか。
【経済農政局長答弁】
商業施設の出退店については、周辺地域の需要や競合、採算性などを考慮し、事業者の責任によって判断されるものであると考えております。また、店舗までの移動が困難な方への移動支援、買い物に困難が生じた際に相談できる体制の充実など、関係部局が連携して取り組んでいるところです。
【中村きみえ議員】
4つに、事業者の責任で設置を待っていては、いつまでたっても、必要な場所に整備されません。市が、もっとイニシアチブをとって、整備できるように関係機関と協議や補助金を出すべきではありませんか。
【経済農政局長答弁】
商業施設の出退店については、周辺地域の需要や競合、採算性などを考慮し、事業者の責任によって判断されるものであると考えておりますが、その判断材料となるよう、スーパー事業者などに、買い物支援のご相談やご要望がある地域を伝達するとともに、市内中小企業者が出店する場合には、本市中小企業融資において、運転資金や設備導入資金の借り入れに対する利子補給の制度を用意しているところです。
【中村きみえ議員】
5つに、ネットやスマホを使えばもっとポイントが付いたり、情報もより多く選択できるようにするために使い方を教えてはどうですか。
【総合政策局長答弁】
デジタルデバイドの解消に向け、今年度のスマートフォン講座は、昨年度を上回る開催回数で実施しております。講座では、スマートフォンの基本操作に加え、誰にとっても重要で有益な情報源となる「ちばし安全安心メール」や「防災速報アプリ」などの登録方法をお知らせしているほか、「電子申請」「施設予約」「ちばレポ」など、スマートフォンの「便利な使い方」の紹介や、生活協同組合コープみらいとの包括連携協定に基づく「アプリを活用したお買い物体験」を実施しております。
【中村きみえ議員】
6つに、スマホの講座を実施しているのは承知していますが、そこまで本格的に実施ということではなく、市内各地で、気軽に利用できるような機会を設けたり、スマートフォンに関心を持ってもらう工夫をするなどハードルを下げて、進めていってはどうですか。
【総合政策局長答弁】
昨年度から、町内自治会等を対象に地域の実情に寄り添った「出前講座」を実施しており、地域で既にスマートフォンを活用している方などに、サポート役でご参加いただきながら、気軽に相談し合い、地域で支え合う仕組みづくりに努めております。また、スマートフォンを使うことで、日々の生活に役立つ情報が迅速に得られるなどのメリットを、スマートフォンに関心のない方にお知ってもらい、いきいきプラザや公民館などで実施しているスマートフォン講座等へ参加していただけるよう周知を図って参ります。
【中村きみえ議員】
7つに、現在、移動販売車は使っていない方も多いですが、将来体が効かなくなったら、必要になると答えている方も多く、移動販売車も実施地域や扱い品目などきめ細かく対応することも求められるのではないですか。
【経済農政局長答弁】
移動販売車の運行は、地域における需要や事業の採算性のほか、近隣の店舗への影響や停車場所の確保など、様々な要件を事業者が総合的に勘案し実施されるものと考えております。また、扱い品目については、移動販売で取り扱い可能な範囲で、利用者からの要望等、事業者が顧客ニーズを把握し、採算性を考慮しながら事業活動の中で対応しているものと認識しております。今後も引き続き、地域の住民の皆様から具体的な要望があった場合には、本市が連携している移動販売事業者に対し情報提供を行って参ります。
【中村きみえ議員】
8つに、今回こちらでアンケートを実施しましたが、千葉市としても今後の市民のニーズをとらえる上でもこうした実態調査を市として行うべきではありませんか。ぜひ、実施を求めます。お答えください。
【保健福祉局長答弁】
本年9月に、あんしんケアセンターあてに、担当圏域内における「買い物が困難となっている地区の状況」などについて調査を実施しております。その結果をもとに、「市内の買い物に関するニーズ」について事業者と情報共有する際に活用するなどしております。
【中村きみえ議員】
9つに、あんしんケアセンターあてに調査をしたことでどのようなことが分かったのですか。それを受けて事業者と情報共有することで、買い物支援をすることとなったのですか。
【保健福祉局長答弁】
調査結果から、買い物が困難となる背景としては、「最寄りのスーパーまでの距離が遠い」「坂が多い」といった地域ごとの事情などがあることが分かり、その結果を踏まえ「市内の買い物に関するニーズ」について、事業者と意見交換を実施しております。なお、今回のアンケートも含め、地域の買物支援に係るご相談やご要望等について、以前から事業者とは情報共有してきているところであり、また、買い物に対するニーズ等を踏まえ、利用可能な宅配などの買い物サービスのご案内、支援機関を通じた家事援助など、個々の地域の実情に応じた支援に関係部局が連携して取り組んでいるところです。
【中村きみえ議員】
10に、市は、私たちが行った107件のアンケートでは、評価が難しいということでしたが、それでも、移動販売車を利用している方も、不満を持っていることが分かり、また将来的に不安を抱えている方があるなど、将来的にもどう対応していくのかいくつかヒントがあったように感じます。本来は、千葉市がモデル的にでも実態調査を行って、今後の対策を講じることを求めます。お答えください。
【総合政策局長答弁】
買物支援の検討にあたっては、それぞれの地域で提供されているサービスや地域コミュニティの状況などを含め実態を的確に把握することが必要であり、その一環として地域における支援機関の一つであるあんしんケアセンターを対象に実態調査を行ったところです。地域の支援機関や事業者など、多様な主体と連携・調整を図りながら、それぞれの地域の実情に応じた適切な支援が行えるよう、関係部局で連携しながら取り組んでまいります。
【中村きみえ議員】
利用する店舗の交通手段を聞くと徒歩33人、自転車21人と身近なところで買い物することの必要性を感じます。先日も元気にボランティアをしている75歳の女性が坂で転んでから自転車に乗るのが怖くなって歩いていると言っていました。いつ何時、動けなくなるかわかりません。公共交通も頼れず、身近で暮らせるには宅配だけでなく、買い物できる場所がたんに買い物をするというだけにとどまらず、地域のコミュニティとしても重要であることは今までも訴えてきたところです。市が事業者の支援待ちでは、必要な地域に整備は進みません。
地域で住み続けられるようにしていくために、財政的な支援も含めて検討していくことも求めて終わります。