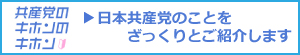不登校対策は学校復帰を前提とせず支援拡充を! のじま友介議員一般質問 〔2024年第4回定例会〕
のじま友介議員の一般質問 2024.12.6

1.不登校対策について
文科省によれば昨年度の小・中学校における不登校児童生徒数は全国で34万6千人であり、前年度から4万7千人 増加しました。11年連続増加し、過去最多となったとのことです。増加の背景として、保護者の学校に対する意識の変化などがあり、学校へ必ず行かせなくてはいけないという考えが減っていることがあげられるようです。一方で不登校は「子どものわがまま」「親の責任」だという誤解や偏見がまだまだあります。『子どもが、学校が怖い、息苦しいと言っている』と親から相談を受けます。「子どもが過剰なストレスを受け“心の傷”を負った結果、ストレスの主要な現場である学校にいられなくなり、本能的に防衛するために家庭に退避していると考えられます。文科省の調査では、全体の7割以上は本人と家庭に起因するとしています。この調査は不登校を本人や家庭の責任にしており、それが世論の誤解や偏見の温床となっているのではと思います。更に不登校は競争社会の中で「落ちこぼれ」とみなされ、親自身もそう思ってしまう傾向にあるといいます。親は当たり前のことができなくなったと思い戸惑い、どうしていいか分からず、とにかく学校へ行かせようとしますが、たいてい効果はありません。学び直し以前に子どもが安心し“心の傷”を回復させる家庭環境の保障が重要です。そのために保護者への財政的支援や相談支援が必要です。そこで伺います。
1、本市における直近3か年の小学生と中学生の不登校児童生徒数は。
- 国が言う教育支援センター、千葉市のライトポートの数、直近3か年の利用数はどうか。
- ステップルームティーチャーを配している学校は現在どれくらいか。また、教室とは別の場所で指導、支援を実施した学校の実績はどれくらいか。
- 本市のフリースクール等を利用している児童生徒数はどれぐらいか。また、フリースクール等の平均利用料はどれぐらいか。
- 今年度、スクールカウンセラーが拡充されましたが、今年度拡充された人数と各学校の配置時間がどのように変化したのか。
- 「3週間で再登校できる」「早く対応しないと手遅れに」などと、不登校の親子の不安に付け込み、高いお金を払わせて支援する「不登校ビジネス」というものがあると聞きましたが本市の見解を伺います。
2.新型コロナワクチンについて
10月から定期接種が始まりまして、自己負担があるということで接種率なども気になる所ではありますが、そんな中、厚生労働省は先月25日、新型コロナウイルスのオミクロン株対応ワクチンの副反応状況を発表し、100万回接種当たりの死亡件数に換算すると多いもので8.6件、モデルナ4.9件、ファイザー1.6件と続いています。厚労省は、同ワクチンと死亡との因果関係が評価できないとし、「現時点においてワクチンの安全性の新たな懸念は認められない」としています。新型コロナワクチンをめぐっては、10月から新しいタイプのレプリコンワクチンが定期接種の対象になっています。このレプリコンワクチンは、 世界で唯一日本のみで認可されていることから、安全性および副反応に関する懸念が広まっています。その懸念とは、レプリコンワクチン自体が接種者から非接種者に伝播(シェディング)するのではないかというものです。このことから、従来のワクチンでも指摘されていた心筋炎やアナフィラキシー等に加え、上述したシェディングの可能性など、接種の時点で判明しているリスクを、被接種者に十分に説明し、理解をしてもらうことが重要であると考えます。 また、「レプリコンワクチン接種者はお断り」を表明している、病院や歯科医、動物病院などもあると伺っています。接種における主体的な自己決定権が失われるような状況に追い込まれることは絶対にあってはならないことだと考えます。「医師、専門家、研究者など複数の有識者からは、先にのべましたレプリコンワクチンの安全性等に対する懸念も多く表明されております。現在、本市でもレプリコンワクチンが定期接種に用いられていることから、その現状、安全性等も踏まえ、市の新型コロナウイルス感染症予防接種の対応について、質問いたします。
1、この秋からの定期接種新型コロナワクチンは、どのような方法で案内されているか。
2、本市での新型コロナワクチンによる予防接種健康被害救済制度の対象となる健康被害者や死亡者などの状況はどうか。
3、本市の予防接種健康被害救済制度の申請や認定状況について、市民に詳しく公表されているか。
- 今回の新型コロナワクチンは、どのワクチンが使用されているのか。また、医療機関ごとにどのワクチンなのかホームページ等で公表されているのか。
- レプリコンワクチン接種者は診療しないとしている医療機関について把握しているか。
- 市は、自己増幅型 mRNA ワクチン(レプリコンワクチン)の有効性と安全性はどのような見解でいるか。
3.介護施設について
9月末で閉鎖されましたジャルダン寒川という有料老人ホームについてです。全国に複数展開されている住宅型有料老人ホームの一斉閉鎖問題ですが、給料未払いにより職員が一斉に退職し、運営会社の社長は雲隠れ状態となり、入居している高齢者が取り残されるという事態が発生していました。入居者のオムツや布団が交換されずに汚れたまま放置されている、入居者が数週間に1度ほどしか入浴できない、また、一月当たりの入居者の死亡数が異常に多かったという報道もありました。この「ドクターハウス ジャルダン」は株式会社オンジュワールが運営する住宅型有料老人ホームであり、千葉市の寒川の他に、東京都足立区、横浜市、北九州市に展開されております。寒川の施設は昨年12月にオープンしたばかりで分類としては住宅型有料老人ホームにあたり、付随する訪問介護事業所からヘルパーが派遣されるかたちで事実上の一体経営が行われていたとみられておりました。しかし、開所当初から施設運営が正常に行われない状態に陥っていたとのことです。そして突然、閉鎖が決まり、入居者には1週間以内に退去するよう告げられたということです。
私ども市議団にも関係者の方から懸念の声が多く寄せられました。そこで伺います。
1、施設閉鎖の事実を本市が把握したのはいつか。その後の対応はどうであったか。
- また、事前に職員、又は利用者・その家族などから相談はあったか。
3、本市の住宅型有料老人ホームの直近3か年の施設数の推移と直近の施設数はどうか。
- 千葉市有料老人ホーム設置運営指導指針で規定されている設置者の要件の内、経営基盤に関する要件はなにか。また、住宅型有料老人ホームに対する指導指針の役割とその法的根拠はなにか。
- 有料老人ホームにおける過去5年間の臨時的に行った立入検査も含む指導の内容や件数及び株式会社オンジュワールと類似した事例の有無についてお聞かせください。
- また、今回の事業所が職員不足を招いた要因と設置者の管理責任への市の見解をお示しください。
4.指定緊急避難場所の表示板について
中央区内には指定緊急避難場所が66カ所あるかとは思いますが、住民の方から避難場所を案内する表示板が真っ白になっていたり錆がひどかったりとかなり老朽化しており、設置目的を果たしていないのではないかとご意見を伺いました。1,新宿中、2,登戸小、3,南部青少年センター、4,末広公園、5,葛城公民館、6,寒川小、また、避難場所の表示板も見当たらないところもあると聞いています。7,末広公民館、8,葛城公民館、9,鶴沢小学校。近年のように地震・津波・大雨・洪水などによる甚大な被害が多発している状況の中、平常時から人々の目に触れることで災害の危険性や避難の重要性の認識・周知にも繋がり、災害発生時の避難場所への円滑な移動が期待できるのではと思います。そこで伺います。
1、日常的に表示板の点検は行っているのか。また、交換時期はいつか。
2、ホームページには全ての指定緊急避難場所に表示板があると書いてあります。目立つ箇所に設置が望ましいと思うがどうか。
<2回目>
1.不登校対策について
本市小中学校での不登校の児童生徒数は2,142人と過去最高になったとのことです。そんな折、先月28日に開かれた市総合教育会議で学びの多様化学校を2030年度に設置する方針が明らかになりました。学びの多様化学校が本市にも設置されることで、このノウハウを全校で共有し、実践をすることで、今後のより良い学校運営につながるのではないかとの期待もあります。しかし、現在、不登校で悩んでいる保護者の方や児童には残念ながら間に合いません。
- 本市でのライトポートの利用数も増えているとのことです。児童数が増えてしまったことで教室に通いづらくなっている児童もいると聞いています。また、徒歩で通える範囲でライトポートがあればとの声も聞かれています。ライトポートの更なる配置の拡充を検討すべきではないか。
- 他自治体では、不登校になっている子ども、不登校を経験した子どもたちと保護者を対象にアンケート調査を独自に実施しているところもあります。学校に行きたくない、休みたいと思った理由や、誰かに相談したか、どのような学校だったら楽しく通えると思うかなど、市独自にアンケートを行い、施策に生かすことが必要と考えますが、いかがですか。
- 経済的に困窮する家庭での子どもの不登校も問題です。困窮家庭の不登校の子のうち8割以上が日中家で過ごさざるを得ないという調査結果が出ています。フリースクールを利用したくても、経済的な負担が重く、利用できない。あるご家庭では、中学2年生の娘と二人暮らしで、その娘さんは中学1年生の冬休み明けから不登校になりました。朝起きられず、めまいや強い倦怠感が起きます。体調の良い時はできるだけ登校しようとしましたが「症状を理解してくれない」学校への不信感から、さらに足が遠のきました。「何もなければいいけれど」と朝、後ろ髪を引かれる思いで出勤するそうです。その間、娘さんは家で一人過ごしているそうです。フリースクールも考えたが「通うためのお金がない」。家賃を引いた生活費は月11万円ほど。物価高騰も追い打ちかけ、「生活はぎりぎりで、食品はできるだけ買わない」と話されます。先ほどの答弁で全国のフリースクールの授業料の平均は月額約3万3千円でした。経済的に困難を抱える子育て家庭を支援する、認定NPO「キッズドア」が困窮世帯を対象に昨年末に行ったアンケートでは、回答があった1,822世帯のうち、21%で「子どもが不登校、または不登校気味」だと答えました。そのうち83%が平日日中の過ごし方として「家にいる」と回答しています。日々の学習状況として52%が「何もしていない」と答え、多くの子どもたちが「学び」から取り残されている実態が浮きぼりになりました。自由記述には「フリースクールが高すぎる。無料や安価なフリースクールがあれば」「子どもの居場所がもっとあったら」という声が並びました。
東京都ではすでに利用料の助成をしています。千葉市でも、フリースクール授業料の助成の検討を求めますが、いかがですか。
- また、先ほどの朝起きられずに学校にいけない子がいることについて市としてどのような対応が理想だと思うか。見解を伺います。
- 保護者の方からはスクールカウンセラーが常駐してくれればとの話が良く出ます。担任の先生は忙しすぎるため、助けをもとめられないとのことです。今年度、スクールカウンセラーが拡充されましたが、更なる拡充が必要と考えますが見解を伺います。
- また、ステップルームティーチャーについても全校への配置が望ましいと考えますが見解を伺います。
- 国連子どもの権利委員会からは、日本の教育システムがあまりに競争的なため、子どもたちから、遊ぶ時間や、体を動かす時間、ゆっくり休む時間を奪い、子どもたちが強いストレスを感じていること、それが子どもたちに発達上の歪みを与え、子どもの体や精神の健康に悪影響を与えていることが指摘され、是正を求める勧告が繰り返しだされています。まずは、こうした子どもたちの学校生活における環境を改善することが求められていると思いますが、見解を伺います。
- また、学校生活の環境改善は教員が不足している状態では実現できません。我が会派の代表質問で安喰議員からもありましたが、半年も担任が不在で教頭が授業を行う、こういう未配置が起こっている事態、これはこれ以上放置することは許されません。改めて、育休、産休、病気休暇における代替教員のさらなる増員に努めるよう求めますが見解を伺います。
2.新型コロナワクチンについて
ワクチンに対する誤解や偏見は日本だけでなく世界中にあります。ただ日本は、接種後の重篤な副反応についての説明を国がきちんとしてこなかった歴史があり、「副反応は受け入れられない」といった風潮があります。今回、ワクチンは5種類に増えましたが、選択肢が増えることは望ましいことです。レプリコンワクチンは初認証のワクチンだけに、正確で科学的な情報を市民に分かりやすく提供する必要があります。
市は、市民に分かりやすく、リスクも含めた十分な情報提供を定期接種開始前に周知するべきだったと考えるが、どうか。
3.介護施設について
閉鎖の情報を把握してから2週間で全ての入居者の方が無事転居できたとのことで大変安堵しました。関わったケアマネージャーやボランティアの方々、また市職員の方々には、現場での奮闘に心から敬意を表したいと思います。
市内の住宅型有料老人ホームが年々少しずつ増加しているようです。背景には、高齢化の進行だけではなく、国が特別養護老人ホームの増設や増床を抑制し、民間活力の導入のために届出制にして、介護事業への参入を拡大してきたからではないかと考えます。平成29年に法改正された事業停止命令は、悪質な事業者を市場から退出させるためのものと言われていますが、この指導指針は、事業者の指導監督を行うための基準であり、本市も指導指針に基づく指導監督を行っていますが、その実効性が今回問われたのではないでしょうか。
賃金の不払いは労働基準法第24条に違反する犯罪です。このような悪質な事業者に対する指導監督を強化するために、本市の指導指針の見直しが必要と考えます。
そこで、2点質問します。
1、多くの職員を退職に追い込んだ設置者の労務管理に関する指導指針が必要ではないか。
- また、職員からの内部告発に対する行政機関の役割強化に関する指導指針が必要ではないか。以上、それぞれ見解をお示しください。
のじま友介議員の一般質問に対する答弁 2024.12.6
1、不登校対策について
【教育次長答弁】
まず、本市における直近3か年の小学生と中学生の不登校児童生徒数についてですが、 令和3年度は、小学生が507人、中学生が783人、4年度は、小学生が709人、中学生が 928人、昨年度は、小学生が930人、中学生が1,212人となっております。
次に、ライトポールの数及び直近3か年の入級者数についてですが、各行政区に1か所ずつ、計6か所整備しております。直近3か年の入級者数は、令和3年度は199人、4年度は313人、昨年度は408人となっております。
次に、ステップルームティーチャーの配置及び教室とは別の場所での指導等の実施についてですが、今年度は、小学校7校、中学校3校にステップルームティーチャーを配置しております。また、教室とは別の場所で指導、支援を実施した学校数については、昨年度は、小学校が94校、中学校が48校となっております。
次に、フリースクール等を利用している児童生徒数と平均利用料についてですが、昨年度は、市内外のフリースクールに延べ258人の児童生徒が利用しております。また、平均利用料については、文部科学省の調査によると、月額約3万3,000円となっております。
次に、スクールカウンセラーの拡充内容についてですが、配置人数は市全体で4人拡充し、計84人となっております。また、配置時間については、小学校は年間200時間配置の学校を6校から20校へ、年間160時間の配置を37校から49校へ拡充しております。さらに、私立校等学校校は、年間140時間へそれぞれ拡充しております。
最後に、「不登校ビジネ」についての本市の見解についてですが、民間が行なっている不登校児童生徒への支援は様々であり、個の状況を踏まえた適切な支援に繋げることが必要との認識があります。本市では、不登校児童生徒や保護者に、不登校状態であることに対する不安を軽減できるよう、各家庭に不登校児童生徒への支援に関する相談事業パンフレットの配布や、フリースクール等の情報をホームページに掲載することで、周知を図っておりますが、引き続き保護者が求める情報を適切に提供できるよう努めて参ります。
2、新型コロナワクチンについて
【保健福祉局長答弁】
まず、定期接種となった新型コロナワクチンの周知法についてですが、市政だよりや市ホームページへの掲載、公式SNSによる周知に加え、今年度は、定期接種の初年度であることから、対象者に対し、個別に通知をしております。
次に、予防接種健康被害救済制度の対象となる健康被害者や死亡者の状況についてですが、新型コロナワクチンでは、令和3年度から累計で、先月27日時点で52件の健康被害救済制度の申請があり、そのうち、29件が認定されております。認定された方のうち、死亡による申請は3件となっております。
次に、予防接種健康被害救済制度の申請や認定状況の公表についてですが、市ホームページにおいて、令和3年度以降の申請件数、申請があった方の主な症状及び審査結果を掲載しております。
次に、新型コロナワクチンの種類についてですが、オミクロン株「JN.1系統」に対応し、薬事承認を受けたワクチンは5つあり、そのうち、どのワクチンを使用するかは、各協力医療機関において決定しており、本市では公表は行っておりません。
次に、レプリコンワクチン接種者を診療していない医療機関の把握についてですが、 そのような状況は把握しておりません。
次に、レプリコンワクチンの有効性と安全性に対する見解についてですが、厚生労働省によりますと、臨床試験において発症予防効果や持続期間、有害事象の発現割合等について、他のメッセンジャーRNAワクチンと比較して、明確な差は認められないとの見解を示しております。
3、介護施設について
【保健福祉局長答弁】
まず、施設閉鎖を把握した時期とその後の対応についてですが、本年9月26日付けで、施設を閉鎖する旨の張り紙が建物内に貼り出され、その翌日に、法人関係者から情報提供を受けて把握しました。その後、施設長と連絡を取り、状況を確認したところ、給料の未払いなどによる従業者の離職があり、入居者へのケアが行き届かなくなる恐れがあったことから、担当ケアマネジャーが中心となって他の施設への転居を進めるとともに、ボランティアの方々や本市職員が食事の配下膳などを行い、10月11日までに、入居者全員の転居が完了しました。
次に、職員や利用者・その家族などからの事前の相談についてですが、事前の相談はありませんでした。
次に、本市の有料老人ホームのうち「住宅型」に関する直近3か年の施設数の推移についてですが、各年4月1日現在で、令和4年度が102施設、昨年度と今年度は106施設となっております。直近の施設数は、先月1日現在で、109施設となっております。
次に、有料老人ホームの設置者について経営基盤に関する要件と、指導指針の役割及び法的根拠についてですが、有料老人ホームの設置は届出制であり、届け出にあたっては、「事業を確実に遂行できるような経営基盤が整っているとともに、社会的信用の得られる経営主体であること」や「少数の個人株主等による独断専行的な経営が行なわれる可能性のある体制でないこと」、「他業を営んでいる場合には、その財務内容が適正であること」を求めております。また、指導指針は、有料老人ホームが民間の活力と創意工夫により運営されるものでありつつも、高齢者が長年にわたり生活する場であり、介護をはじめとするサービスに対する期待が大きいことなどから、行政としても、サービス水準を確保していく必要があるため策定しているものであり、老人福祉法の趣旨に基づくものです。
次に、過去5年間の指導の内容、件数及び株式会社オンジュワールと類似した事例の有無についてですが、概ね3年に1回の頻度で実施する定期的な立入検査の結果、「施設管理運営」や「サービス提供の状況」、「職員の配置」等について文書による指導を行った施設数は、令和元年度12、2年度は、新型コロナで立入検査を注視したため0、3年度は 13、4年度は6、昨年度は11ありました。このほか、施設職員や入居者家族からの通報により臨時的に調査を行い、その結果、身体拘束など虐待認定を行った施設が、4年度と昨年度に2施設、今年度は1施設ありました。なお、株式会社オンジュワールのように、入居者を残して突然施設閉鎖をした事例はありません。
最後に、職員不足を招いた要因と設置者の管理責任に対する市の見解についてですが、職員の大量離職は、給料の未払いが生じたことが大きな要因であると考えられます。また、必要なケアが提供されない状態に至らしめた設置者の責任は非常に重いと認識しております。
4、指定緊急避難場所の表示板について
【危機管理監答弁】
まず、日常的な点検と交換時期についてですが、避難場所等案内板は、駅前や市民センター等、多数の人が集まる場所に設置していますが、経年劣化等により表示内容が見づらくなっているとのご意見をいただいております。このこともふまえ、現在、表示内容の劣化具合や、支柱の老朽化など、状況調査を進めており、今年度中に全ての案内板を確認する予定としております。今後は、劣化の著しいものから順次、撤去していくとともに、ハザードマップを周知するなど、他の手段も含め、避難場所の位置などを平時から認識していただけるよう、啓発を図って参ります。
最後に、目立つ箇所への設置についてですが、指定緊急避難場所の表示板につきましては、見やすさ等を考慮しながら、すべての避難場所に設置しているものです。表示板は、洪水や高潮などの災害種別ごとに避難の可否を記載しており、普段から確認していただきたいものであるため、今後も、市民の皆さまのご意見などを踏まえながら、必要に応じて設置場所を移動するなど、日頃から目に触れ、確認いただけるよう努めて参ります。
<2回目>
1、不登校対策について
【教育次長答弁】
2回目のご質問にお答えします。
まず、ライトポートの拡充についてですが、不登校児童生徒へのさらなる支援策の一つとして現在策定中の「(仮称)第2次不登校対策パッケージ」の中で、検討して参ります。
次に、市独自の不登校に関する調査についてですが、昨年12月に千葉県が、本市も含めた不登校児童生徒と保護者に対し、実態調査をおこないました。この調査結果や学校現場からの声を踏まえ、必要な支援を検討して参ります。また、今後は、他の自治体の調査を参考にし、本市独自の調査の実施について研究して参ります。
次に、フリースクール授業料の助成についてですが、本市では経済的理由によって就学困難と認められる児童生徒の保護者に対し、ライトポートやフリースクール等に係る活動費及び通所費の助成を行っております。東京都が実施しているような利用料の助成については、今後、国や他自治体の動向を注視し、引き続き調査研究に努めて参ります。
次に、様々な理由により朝の時間に登校できない児童生徒への対応についてですが、本市としては、投稿時刻の設定等を柔軟に行なうことにより児童生徒の実態に合った居場所の確保が必要であると認識しております。具体的には、学校内の別室やライトポート等を設置するほか、オンラインの活用などにより、一人一人の実情に応じた適切な支援に努めております。
次に、スクールカウンセラーの充実についてですが、配置時間の拡充により、児童生徒の悩みや不安の軽減などに繋がっていると認識しておりますが、更なる拡充については、実態に応じて適切に対応して参ります。
次に、ステップルームティーチャーの配置についてですが、専任の支援員の配置により、児童生徒のきめ細かな支援につながっていると認識しております。ステップルームカウンセラーの全校配置については、現在のところ難しいと捉えており、必要な人員を適切に配置できるよう、計画的に体制を整備して参ります。
次に、子どもたちの学校生活における環境の改善についてですが、各学校では、自校の教育活動や学校運営の状況について、子どもたちや保護者、地域住民等からのアンケートのほか、教職員の自己評価を行い、学校生生活における環境等の改善に生かしております。また、教育委員会からは、授業時数や子どもたちの学校生活にゆとりを持たせるために国が定める標準授業時数を大きく上回って教育課程を編成している学校に対し、授業時数や学校行事の在り方の見直しを依頼し、改善を促しております。引き続き、子どもたちを取り巻く環境を多面的に把握し、改善に努めて参ります。
最後に、育休等における代替教員の増員についてですが、教員未配置が発生している状況を解消するための取組みとして、定期的な講師登録説明会を開催するほか、過去に本市で働いていた人材に電話連絡を行うなど、人材確保に努めております。なお、未配置が発生している学校については、正規休暇等補助教員や、会計年度任用職員を配置するなど、児童生徒のへの教育活動に影響がないように努めております。
2、新型コロナワクチンについて
【保健福祉局長答弁】
定期接種開始前に、十分な情報を提供することについてですが、本市では、個別通知や市ホームページ等において、接種方法のほか、接種により起こりうる副反応などを周知しており、丁寧な情報提供に努めております。また、市民の方からの問い合わせに対応するため、コールセンターを設置しており、様々な情報を提供しております。
3、介護施設について
【保健福祉局長答弁】
まず、設置者の労務管理に関する指導指針についてですが、給料の未払いにより大量離職が生じたことは誠に遺憾ですが、こうした労働条件に関する指導は、労働基準監督署の所管であると認識しており、従業者から相談があった場合には、労働基準監督署への相談を促すなど、引き続き、適切に対応して参りたいと考えております。
最後に、内部告発に対する行政機関の役割に関する指導指針についてですが、現在も、従事者から、有料老人ホームの指導指針に反する旨の内部告発があった時は、必要な調査を行い、違反に対する指導等を行っているほか、指導・処分権限がない内容であった場合には、権限を有する機関を紹介するなどしております。
以上でございます。
<3回目>
不登校対策について
不登校の原因は、児童によってさまざまで、いじめや勉強がわからない、友達とのトラブル、先生の叱責など、自分でもわからないことが少なくありません。実際に私も中学3年生から高校1年の2年間不登校でした。今もはっきりとした原因はわかりません。今思えば、私が求めていたのは、誰かに話しを聞いて欲しいということだったと思います。しかし、当時も先生は多忙でなかなか話しかけられず、このような状態で、当時、目の前に何も希望がありませんでした。心理的な負担がたまると、体を動かすのもつらい、何も考えることができないという状態になり、回復までにはある程度時間がかかりました。専門家によると、これが、心が“大けが”をしている状態だと。
仮に、身体に大けがを負うと、傷がふさがるまでの長い期間安静にして、回復させなくてはなりません。ところが精神的に“大けが”をしても、目に見えない。この状態で、無理に学校に行き続けることは、傷を少しずつ深めることになります。必要なのは、安全、安心な状態が長い期間確保された上で、その子がつらい思いを安心して伝えられる環境をつくることではないかと思います。 また、身体的なけがで長期間休んだらリハビリが必要になるのと同じように、心の傷も期間が長い場合は、社会に出るときにリハビリが必要です。
子どもからゲームや本、テレビなどの娯楽をすべて取り上げるように不登校ビジネスから指示されたという話を耳にしました。たしかにそれで学校に行く子もいるかもしれない。でも、それは心をけがしたままの登校かもしれません。
そうやってムリをすれば、再登校の“軌道”に乗ることはあり得ますが、家族関係を壊してしまい、子どもの居場所を奪うリスクがあります。それはその子の命にも関わります。ニーズあるところに、ビジネスありで、いろんな事業者が参入してきています。多様なサービスが増えることはよいことだと思いますが、問題は、利用者が「適切なサービス」を選べなくなってしまうことです。このようなことが起こらないように保護者へ情報提供を強化してください。
不登校は、社会や教育のあり方を背景にしたもので、本人や家庭の責任とすることは誤りです。
「学校強制でない教育への権利」「安心して休んでいいんだよという権利」「自分らしく生きられる権利」などを保障する立場から、子どもと親が安心して相談できる窓口の更なる拡充や、親の会などへの支援を拡充したり、フリースクールなど学校以外の学び場をきちんと認めて支援を拡充したり。また、学校復帰を前提とした施策は子どもや親を追いつめる可能性もあるので更なる調査研究を要望しておきます。
介護施設について
この法人が働く人の権利を尊重せず、法令を遵守しないような態度を取り続ける限り、現在、この法人で働く職員の処遇が懸念されます。私はこのような事業者に対する指導監督を強化するために、本市の指導指針の見直しの必要性を考えます。国も地域性を踏まえた指導指針の策定を認めています。民間の介護施設で職員が安心して働き続け、利用者がよい介護を受けられるようにするため調査研究を推進し、指導指針の見直しを検討してください。
これら要望しまして一般質問は終わります。