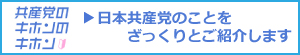プラスチックごみ分別はスタート時期を前倒しを! もりた真弓議員一般質問〔2024年第4回定例会〕
もりた真弓議員の一般質問および答弁 2024.12.10

1、プラスチックごみ分別について
【もりた真弓議員】
プラスチックごみによる環境への悪影響が深刻さを極めており、プラスチックごみを燃やすことによるCO2の排出で地球温暖化が加速することや、海洋でのプラスチック汚染が世界中で問題になっています。
全国で取り組まれてきた容器包装リサイクルなどの取組を先送りし、プラスチック分別の取組が遅れた千葉市は、政令市の中でも後発となる自治体です。早急な対策が必要な反面、先進市のプラごみ分別の取組について参考にして進めることができるととらえるならば、千葉市は今、これからのプラごみ減量、環境負荷軽減の大事な岐路に立っていると言えるのではないでしょうか。そこでおたずねします。
千葉市のモデル地区でのプラスチック一括回収は、8月から開始され4か月経過しました。今月末まで実施期間は残されていますが、スピード感をもって取り組みを進めることが求められています。
プラスチックごみ分別回収のモデル事業から見えてきた成果と課題について、現時点での受け止めと評価をお示しください。
【環境局長答弁】
モデル事業においては、8月から先月までの4か月間で約10トンのプラスチック資源が収集・再資源化されており、不適物の混入率は約2%であり、分別の制度が高くなっています。一方、製品プラスチックの分別に関するお問い合わせをいただいていることから、追加で分別早見表などを作成し、配布しました。今後、アンケート調査やごみ組成測定分析の結果を検証し、プラスチック資源の分別や周知の方法についてさらに検討して参ります。
【もりた真弓議員】
スクリーンに映しているのは千葉市が10月に追加で作成し、配布した分別早見表のパンフレットです。
現在、プラスチックごみの分別処理に取り組んでいない政令市は、千葉市を含めて3市ありますが、福岡市では令和8年度以降にプラスチック製容器包装及び製品プラスチックの一括回収の導入を予定しています。また、静岡市では令和10年度以降の開始を目指し業者選定方法などを検討しているとのことです。そこでうかがいます。
今後のスケジュールについてですが、千葉市はプラごみ分別処理の全市展開の開始をいつにするのか。目標は定めているのか、お答えください。
【環境局長答弁】
千葉市一般廃棄物(ごみ)処理基本計画に「プラスチックの分別収集及び再資源化の実施に向けた検討」を位置づけ、全市展開の開始時期は2029年度を目途とし、さらに前倒しについても検討することとしております。現在、千葉市廃棄物減量等推進審議会においてプラスチック資源の一括回収の方法等についてご審議いただいているところであり、今後、モデル事業で得られた検証結果を踏まえつつ、さらなる検討を進め、全市展開に向けた実施体制を整えてまいります。
【もりた真弓議員】
千葉市の計画では、全市展開の開始時期は2029年度、令和11年度とのことです。この計画のままでは政令市の中で最後までプラスチック分別に取組めない自治体として、ワーストワンとなります。
全市展開がこれだけ遅れる理由はなぜか、お答えください。
【環境局長答弁】
全市展開までには、千葉市廃棄物減量等推進審議会から答申をいただいた後、収集運搬体制の構築や再商品化ルート及び事業者の選定のほか、市民の皆様への丁寧な周知啓発等を実施することが必要であることから、計画上、全市展開の時期を2029年度を目途にしつつ、前倒しについても検討することとしております。
【もりた真弓議員】
横浜市では、すでに平成17年度からプラスチック容器包装の分別をしており、令和6年10月からは市内9区、まずは半分の行政区でプラスチック製品とプラスチック製容器包装を、同じ袋でプラスチック資源として回収を始めました。来年令和7年4月からは全18区で展開すると聞いています。
千葉市は令和11年の全市展開までに段階的にどこかの区を限定してプラスチック資源回収を進めるなど、方向性は検討されているのか、おたずねします。
【環境局長答弁】
プラスチック資源の一括回収の実施方法については、現在、千葉市廃棄物減量等推進審議会においてご審議いただいているところであり、モデル事業で得られた検証結果を踏まえつつ、引き続き検討を進めてまいります。
【もりた真弓議員】
現在、千葉市内あるいは近隣市も含めて、プラスチックごみを処理する中間施設、あるいは受け入れ可能な企業はあるのかうかがいます。
【環境局長答弁】
公益財団法人日本容器包装リサイクル協会の再生処理事業者として登録し、プラスチック容器包装及びプラスチック製品廃棄物の処理ができる施設は、市内や近隣市ではありませんが、県内に4施設あります。
【もりた真弓議員】
県内4施設はどこかうかがいます。暫定的にでも受け入れできる可能性はないのか、お答えください。
【環境局長答弁】
県内4施設の場所は、松戸市が1施設、君津市が1施設、富津市が2施設です。本市にとって最適な再商品化ルートを構築することが重要であることから、千葉市廃棄物減量等推進審議会の審議やサウンディング型市場調査のフォローアップの結果を踏まえ、再商品化事業者等を選定したいと考えております。
【もりた真弓議員】
先日、プラスチックごみ分別で特徴的な取り組みをしている名古屋市と神戸市の視察を行いました。それを踏まえていくつか質問致します。
スクリーンをご覧ください。名古屋市ではプラスチックごみ分別を始める前の平成11年2月、「ごみ非常事態宣言」を発出した当時、黒いごみ袋が一般的で、中身は確認できず何でもごみに出せる状態であったものを、現在は中が透けて見える指定袋へと変え、資源は種類別に分けて回収することで「徹底的なごみ減量」を「市民・事業者・行政の共同の取組み」とし、分別の効果をあげるごみ処理としたとのことでした。
千葉市の可燃ごみの指定袋は現在半透明ですが、分別状況がより分かるようなものに変更することは考えているか、おたずねします。
【環境局長答弁】
本市の可燃ごみ指定袋は、分別されていないものを視認できる一方、可燃ごみの性質上、個人のプライバシーが十分確保される必要があることや景観面も考慮して半透明としております。市民の皆様に定着していることからも、透明な袋に変更することは考えておりません。
【もりた真弓議員】
もちろんごみの分別は市民のみなさんの理解と協力があってのことです。多くの市民に協力いただいている中、資源としての雑紙が可燃ごみとして出されている現状もあります。更に複雑なプラスチック類を分別することになれば、私たち自身がごみを出す際に「資源はできるだけ燃やさない」との意識へと変化することは絶対に必要です。名古屋市では、主なごみ減量の対策としての事前周知と説明会について、「広報なごや」の配布、また、地域説明会で市民への説明会を2か月で2300回実施するなど「なぜ、分別をすることが必要なのか」を徹底してお知らせし、説明会には約21万人の市民が参加したとのことです。また、広報の他に、パンフレットやポスター等はもちろん、説明ビデオや、新聞広告、テレビ・ラジオCM、テレビ・ラジオ市政番組、広報誌掲載、映画館でのニュース、地下鉄・市バスへのポスター掲示などあらゆる媒体を駆使して周知を行ないました。
市民への周知方法として千葉市が活用する媒体について、お示しください。
【環境局長答弁】
全市展開を行う際は、パンフレットやポスター、市政だより、ごみ減量広報誌「GO!GO!へらそうくん」、ごみステーション看板、広報番組、ごみ説明動画、SNS等、様々な広報媒体の活用について検討して参ります。
【もりた真弓議員】
名古屋市ではプラスチックごみ分別開始後の市民からの問い合わせは2か月間で10万件あったとのことでした。分別と処理の理解を得ることは重要です。
スクリーンをご覧下さい。名古屋市の清掃工場の設置箇所です。
名古屋市では市民の協力の結果としてごみ処理量が約40%減少し、埋立処分量は約9割減少したとのことでした。そのため6か所ある清掃工場のうち、設備更新中で令和9年3月に完成予定の南陽工場は、日量1500トンであった処理量を560トン約3分の1近くにまで引き下げて整備中であると聞きました。
千葉市ではプラスチックごみ分別による、可燃ごみ削減を見越した新港清掃工場のリニューアル整備計画となっているのか、うかがいます。
【環境局長答弁】
次に、リニューアル整備を行う新清掃工場では、一般廃棄物処理施設基本計画において、将来的なプラスチック分別収集・再資源化を想定して算出した可燃ごみ量の推計値を基に施設の処理能力を設定しております。
【もりた真弓議員】
次に、回収したプラスチックのリサイクルについてうかがいます。神戸市では、分別による環境負荷低減の取組に学んできました。
スクリーンをご覧ください。コミスタ神戸(神戸市生涯学習支援センター)にあるあづま資源回収ステーションの写真です。施設のエントランス等いつでも出せる場所に、中身の見える透明な回収ボックスを設置しています。神戸市では、市内に「エコノバ」という資源回収ステーションを現在35か所設置し、市民がリサイクルに取組む環境を整備しています。今後200か所以上に設置するとのことでした。子どもから大人まで「ごみ出し」という誰でもが関わることをきっかけに、集まって交流できる場所としても位置付け、放課後の子どもの居場所や着なくなった服のリユースコーナーを設けたり、毎月地域団体が工作ワークショップを開催しているステーションもあるとのことでした。
利用者からの声では、「ごみ出しが楽しくなった」「いつでも出せて便利、容器包装プラスチックの指定袋を買わなくていい」「一人暮らしなので人の所へ行くと楽しくなる」「外出する機会が増えた」などが寄せられているそうです。
もうひとつ、特徴的な取り組みを紹介します。スクリーンをご覧ください。日本初の自動車部品へのリサイクルを目指す企業と連携し、豆腐容器、ゼリー容器、冷凍食品トレー、タッパー容器、ペットボトルキャップ以外のキャップを回収して、質の高いリサイクルを行なっていました。そこでうかがいます。
プラスチックごみの再資源化の方法はいくつか考えられます。環境負荷を最大限少なくする再資源化の方法についてはどんな検討をしているのか、お示しください。また、質の高いリサイクルについての見解をお答えください。
【環境局長答弁】
再資源化の方法については昨年、「家庭系プラスチックのリサイクルに関するサウンティング型市場調査」を実施したところであり、再生処理事業者登録の要件を満たす材料リサイクルまたはケミカルリサイクルを基本として検討を進めております。また、質の高いリサイクルについては、本庁舎においてコンタクトレンズ空ケース等の拠点回収を実施しており、引き続き企業と連携したプラスチックリサイクルに取り組んでまいります。
【もりた真弓議員】
神戸市では、乳酸菌飲料の容器も回収し、再び乳酸菌飲料容器へのリサイクルに取組むなど、あらたな分別・リサイクルに挑戦し、市民とともに環境問題の解決に努力されておられました。楽しく分別し、かつ環境負荷を軽減することができる、社会に役立つことで喜びや意欲を持てる取り組みは千葉市でも必要と考えます。他自治体での取り組みを参考により良いプラスチックごみ分別とするよう求めておきます。
2、花見川区の諸問題について
【もりた真弓議員】
(1)防災訓練と避難所の改善について
先日、地元さつきが丘2丁目町会の防災訓練に参加しました。久しぶりに体育館の様子を見て改めて老朽化した施設の改修の必要性を感じたところです。その際、避難所となるさつきが丘中学校の校舎及び体育館の改善計画について施設管理者である中学校の先生からのお話として、今後の学校施設の改修についての情報提供があり、その詳細についてうかがいます。
さつきが丘中学校の校舎と体育館の施設改修について、具体的な改修内容とスケジュールをおたずねします。
【教育次長答弁】
今年度に大規模改造及び体育館冷暖房設備設置の実施計画を行っており、主な内容としては、校舎及び体育館の外壁、屋上防水、屋根などの改修を行います。今後のスケジュールについては、来年度及び令和8年度の2か年で改修工事を予定しております。
【もりた真弓議員】
避難訓練時のお話の中に、大規模な災害が起きた場合、学校校舎のどこを遺体安置所としての使用を想定しているか、などの具体的な事例もあり、より臨場感を感じた内容にも触れておられました。そこでうかがいます。
避難所となる学校の施設管理責任者としての任務と役割について。また、遺体安置所の他、どのような場面を想定して災害時に備えることになっているのか、お示しください。
【危機管理監答弁】
学校長や教頭などの施設管理者は、震度5強以上の地震が発生した場合、まず、施設の安全点検や児童・生徒などの安全確保を行います。さらに、震度6弱以上の地震では、施設管理者を含む避難所運営委員会が主体となって、指定避難所の開設準備を行います。なお、指定避難所を開設した際、施設管理者は避難所運営委員会の一員として、施設の維持管理を行うこととしております。また、避難所開設・運営マニュアル例には、臨時遺体安置所のほか、要配慮者避難室、応急救護所、ペット避難場所、更衣室、授乳室などを設置することを例示しており、各種避難所運営委員会では、これらを踏まえたうえで地域の実情に合わせて、教室や体育館などを使用した用途ごとの区画割が行われているところです。
【もりた真弓議員】
通常は当然、子どもたちの教育の場、成長を育む場としての学校施設ですので、活用や改修も学校としての利便性が優先されると認識していますし、そうでなくてはならないと思います。そのうえで、あえてうかがいます。
学校校舎及び体育館について、避難所機能を考慮した施設として、千葉市全体としての考え方や方向性を確認します。お答えください。
【教育次長答弁】
学校施設の改修にあたっては、教育環境の保全や改善を目的として改修内容を決めておりますが、教室、体育館への冷暖房設備の設置など、教育環境の向上を目的としながら、学校施設が避難所として使用されることを考慮した回収も実施しております。避難所機能を考慮した学校施設の改修については、必要に応じて関係部局と協議を行って参ります。
【もりた真弓議員】
(2)交通不便地域の支援について
運転手不足によるバスの減便、ルートの廃止が相次ぐ中、12月1日からは花島公園から花見川団地、長作地域を回り、幕張駅まで運行しているシーサイドバスの減便の情報が届きました。地域の移動の手段がまた減らされることになりました。
こうした状況は路線バスだけではありません。「み春野地域に対する山王病院のバスの送迎が、今年の7月末で廃止となってしまい、住民の通院に支障をきたしている。」「千葉市で補助するなどして復活してもらえないか」と相談をいただきました。7月までは、一日7本往復するルートがありましたが、8月以降、全くなくなってしまいました。そもそも、み春野地域を運行している路線は、千葉内陸バスが、勝田台駅とみ春野を往復する路線がほとんどで、平日に限り勝田台駅から山王病院入り口を経由のみつわ台行きが午後3時過ぎに1本あるだけです。過去には京成バスの花まわる号が運行した時期もありましたが、それも今はありません。
み春野地域における公共交通について、千葉市の認識をうかがいます。
【都市局長答弁】
み春野地域では、地域内を通る路線バスが1日を通して運行しており、地域公共交通計画で公共交通不便地域には位置づけておりません。
【もりた真弓議員】
確かにみ春野地域では、千葉内陸バスの運行はされています。しかし、そのすべてが勝田台駅を発着拠点としており、最寄り駅も勝田台駅です。千葉市内のどこへ行くにも乗り継ぎを強いられ、買い物などの経済活動もお隣の自治体頼みです。今の答弁は地域住民の置かれた状況や心情からは納得できるものではありません。
み春野は交通不便地域ではないとの答弁でした。地域ではこれから高齢化が加速することは明らかです。目的の場所に行くための手段が限られ、時間も労力も数倍かかるみ春野のような地域は「公共交通不便地域」となるよう位置づけを改めるべきではないのか、お答えください。
【都市局長答弁】
千葉市地域公共交通計画では、公共交通の利便性について、鉄軌道駅やバス停までの距離や路線の運航頻度などにより、市域を4つの区分に分類し、この中で交通サービスレベルの極めて低いエリアを公共交通不便地域として位置付けております。なお、み春野地域は地区内を通る路線バスが、一日を通して運行しており、一定のサービスレベルがあるエリアと認識しております。
【もりた真弓議員】
医療機関では、患者さんが困るのがわかっていても、経営の厳しさから送迎バスの運行ルートを減らさざるを得ない状況であるとのことでした。
民間バス事業者が乗り入れていない地域で住民の健康を守る手段として、公共交通を補完する役割を担っている医療機関などの送迎バスに対する行政の支援策はないのか、お答えください。
【保健福祉局長答弁】
医療機関が実施している患者用の送迎バスの運行については、医療機関が患者サービスの一環として独自に実施しているものであり、これに対する支援は実施しておりません。
【もりた真弓議員】
以前、千葉県が医療機関に対して行なった「千葉県医療機関物価高騰給付金」は、その目的で「エネルギー・食料品価格の高騰による医療機関等の経営への影響を緩和し、もって医療提供体制を維持し県民の健康の保持に寄与することを目的とする」としています。
医療機関に対する支援について、しかるべきところに求め、送迎バス復活を望む住民の切実な願いに応えるべきではないのか、おたずねします。
【保健福祉局長答弁】
千葉県が実施した医療機関物価高騰給付金は、県民が医療を安定的に受けることができるよう、県内全域の病院や診療所等の医療機関を対象に、エネルギー価格の高騰などの影響を軽減するため、国の交付金を活用したものと承知しておりますが、医療機関が患者サービスの一環として、独自に実施している患者用の送迎バスの運行について、直接の支援を働きかけることは難しいと考えております。
【もりた真弓議員】
「路線バスが運行しているので公共交通不便地域ではない」「医療機関が独自に実施している患者用の送迎バスの運行について直接の支援を働きかけるのは難しい」これでは高齢者が長く安心して地域で生活できません。何らかの手立てをとって必要な医療を受けられるように対策を求め、次の質問に移ります。
- ジェンダー平等について
【もりた真弓議員】
男性を取り巻くジェンダー問題の視点についてうかがいます。
11月9日にハーモニープラザの千葉市男女共同参画センターで行われた、男性学講座「性差別に男性はどうするべきか~これからの男性の在り方を探る~」という講座に参加しました。
これまでもジェンダー問題に関しては議会でも何度か取り上げ、「男らしく」「女らしく」という「性別による役割分担」がいかに根深いかを見てきました。男性の立場や現状から見たジェンダーとしてとらえる機会は少なかったため、タイトルに惹かれ申し込みましたが、私自身、受講してみて大変勉強になりました。男性ならではの生きづらさの要因などにも気づかされ、男女問わず、また、年齢に関係なく多くの方に知っていただきたい内容でした。そこでうかがいます。
千葉市では男性学としてジェンダー問題を取り扱った講座はこれまでにどのくらい開催されてきたのかお示しください。
【市民局長答弁】
千葉市男女共同参画センターにおいて、今年度は9月と11月の2回、直近の3年間の合計では5回開催しております。
【もりた真弓議員】
講師をされた立教大学大学院特別研究員で臨床心理士である西井開先生は全国で講演されているとの事ですが、先日の講座での男性の参加率の多さに驚かれていました。当日は定員30名の会場に23人の参加で、うち男性が12人でした。
講座を行うにあたって、男性の参加を促す工夫をしているのか、うかがいます。
【市民局長答弁】
男性の参加を促す取り組みとしては、男性向けの家事・育児講座などを実施するとともに、週末など参加しやすい設定や男性講師の登用など工夫を行ってきたところです。
【もりた真弓議員】
講座のテーマは「男性の特権とは何か?」「男性がしてしまう女性への抑圧」「男性の生きづらさ」でしたが、はじめに「性差別とは何か?」と問い、女性への差別①家庭・恋人編、②組織編と基本を押さえたうえで、テーマに沿って講義を聞きました。「男性の生きづらさ」では、「組体操や棒倒しなどなぜ上半身裸でやるのか」や、どちらも危険な行為であるのに「遊びとしての電気あんまやカンチョー」など、男性の身体が雑に扱われる事例から、身体を大切に扱うという意識が育まれていないこと、また、男性に向けられる暴力として「男性集団内でのからかい」や「男性集団内の力学」など、改めて理解を深める場となりました。
「男性」は様々な特権を持っている反面、様々な代償を背負うことになり、「男であることを課す社会」での生きづらさがあることにも気づかされました。
「性差別は、女性にとっても男性にとっても辛い状況を生み出している。性差別に抵抗することは、男性にとっても大きなメリットがある」という講師の言葉はこれからのジェンダー問題の向き合い方を問われた気がしました。
「男の子なんだから、これぐらいやらなくちゃ」とか「家族のために責任を持たなきゃね」とか「そんなことぐらいでなよなよするな」など様々な「声」となって家族や教育、メディアや集団から降り注ぐ中で、私たちがいかに「学び直し」をしていくかは大きな課題だと思います。
教育現場での学びの役割を再認識しましたが、子ども時代に行う人権教育にその視点はあるのか、うかがいます。
【教育次長答弁】
児童生徒への人権教育については、本市の教育施策の基調である「人間尊重の教育」のもと、日常生活での見取りや声掛けなどはもとより、学習においては社会科での「人権に関する知識・理解」、道徳科「相互理解や思いやりの心」、体験学習における「他者との関わり合いによる人権感覚の涵養」など、教育活動全体を通して行っております。ジェンダー平等については、これまでも研修会等を通じて各学校に男女同権の重要性とジェンダーバイアスについて説明しており、引き続き人権教育の推進に努めて参ります。
【もりた真弓議員】
男性の生きづらさの裏返しとして、女性に対する暴力的なふるまいに繋がる面も否めないため、こうした男性学を取り上げ、企業や職場などでも開催することを求めるがどうか、お答えください。
【市民局長答弁】
男性の生きづらさに焦点を当て、固定的性別役割分担意識の弊害を再認識し、誰もが暮らしやすい社会の実現を目指すことは、女性の生きづらさを解消するためにも重要であり、現在実施している市政出前講座やデリバリー研修の中で、男性の生きづらさの視点を取り入れることを検討して参ります。