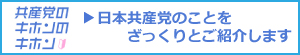災害時に活用可能なトイレトレーラーの整備を! 佐々木ゆうき議員一般質問〔2024年第4回定例会〕
佐々木ゆうき議員の一般質問および答弁 2024.12.11

1.防災・減災について
【佐々木ゆうき議員】
私は11月2日から4日にかけて、今年3度目の能登半島地震とその後の豪雨災害の支援、ボランティア活動に取り組みました。地盤が4メートル隆起した鹿磯漁港から北上した場所の深見地区に支援に入りました。
この地区は全戸に氾濫した河川の雨水や土砂が入る被害を受けており、私は一緒に行った青年・学生とともに、お墓に堆積した土砂を取り除きました。持ち主である高齢の女性から「キレイなお墓が見ることができた。ありがとう」と何度も感謝の言葉がありました。今回の支援活動でも、地震とその後の豪雨による被災、二重災害と支援のあり方について考えさせられたものがありますので、今後の防災・減災対策の充実を求め、質問します。
(1)9月26日に防災・減災対策調査特別委員会の際にも説明があった「災害派遣の経験を蓄積し教訓を継承」のところでは、スケジュールとして10月、11月と地域防災計画や防災マニュアルへの反映検討としていましたが、その内容について明らかにしてください。また、能登半島の豪雨災害後にも職員を派遣したと伺っていますが、その支援状況についても示してください。
【危機管理監答弁】
現在、避難所の運営や罹災証明交付業務等に関し、現時点で認識している課題や対応の方向性を整理しており、今後、地域防災計画をはじめとした各種計画やマニュアル等へ反映して参ります。また、能登半島豪雨による職員派遣は、石川県珠洲市からの要望もあり、能登半島地震の際と同様に罹災証明書の受付・交付業務の支援を行うため、同市に対し、10月3日から11月30日までの間、合計68人の職員を再び派遣しました。
【佐々木ゆうき議員】
(2)いわゆる「二重被災」「二重災害」について、能登半島の豪雨災害で指摘されているのは林業家の減少と林業の衰退で、倒れたり傾いたりした樹木の撤去などが間に合わず、流木となり、人家を襲ったと言われています。千葉市でも土砂災害警戒区域があることから、林業への対応と「二重災害」の被害想定の検討をしておくべきと考えますが、見解を伺います。
【危機管理監答弁】
令和元年台風で倒木被害を受けた森林について、国事業等を活用して森林整備を進めて参りましたが、その際、市内森林所有者で構成される「千葉市森林組合」が中心となって取り組んできており、そうした中で現在、若い担い手が育成されつつあることから、引き続きこうした団体と連携しながら、防災対策を含めた森林整備を進めてまいります。また、地震発生後の豪雨災害などのいわゆる「複合災害」については、来年度以降に実施を予定している防災アセスメント調査において、複合災害を想定した被害と対応を整理することとしております。
【佐々木ゆうき議員】
(3)住宅再建もままならず、高齢化の進む地域での豪雨災害による「二重被災」で、先ほど紹介したお墓に堆積した土砂の撤去や、住宅再建、生活全体を総合的に支援する必要性についての見解と、継続した支援体制を構築しておくことが必要ではないですか。
【危機管理監答弁】
被災者の生活再建を様々な視点から継続的に支援することは、大変重要であると認識しております。被災者一人ひとりの状況や課題等を把握し、関係者と連携しながら継続的に支援する、災害ケースマネジメントについて地域防災計画に位置づけているところであり、現在、継続した被災者支援の仕組みの構築に向けて検討を進めているところです。
【佐々木ゆうき議員】
(4)今回の能登豪雨で仮設住宅も床上浸水被害を受けるなどの課題もありました。千葉市では応急仮設住宅については賃貸住宅などを確保することでの対応を行うと伺っていますが、仮設住宅が被災することのないようにする位置づけとなっていますか。
【都市局長答弁】
本市では、応急仮設住宅を建設する場合に、土砂災害危険区域や河川の周辺などを避けた「二重災害」の危険性の低い場所を優先して建設することとしております。また、民間賃貸住宅を借り上げて「みなし仮設住宅」とする場合においても、物件を案内する際に、再度の災害に見舞われにくい物件を斡旋するよう、本市から宅建協会等の協力団体に働きかけていくこととしております。
【佐々木ゆうき議員】
(5)能登半島地震の仮設住宅における地域コミュニティについては、被災地域の地域コミュニティを重視して入居となっていますが、自治会などの自治組織がつくられていない課題もあります。千葉市では被災者の要望や意見などを吸い上げていくためにも、行政との窓口ともなる自治組織を公有地での仮設住宅、賃貸による仮設住宅の際にも組織することを計画等に盛り込んでおくべきではないですか。
【危機管理監答弁】
応急仮設住宅での入居者同士のコミュニティの存在は、孤立や支援漏れを防止する観点からも大変重要であることから、入居者のご要望やご意見を行政に繋げるための仕組みにつきまして、他市の事例等を研究して参ります。
【佐々木ゆうき議員】
(6)次に災害時のトイレ対策ですが、今年の防災リーダー研修会で講演された加藤篤氏が代表理事を務めるNPO法人日本トイレ研究所では、11月10日を「いいトイレの日」として、10日から19日までを「トイレweek」としていました。「災害時のトイレの大切さについて考えてみませんか」と千葉市の広報でも発信されました。この間、避難所運営委員会の訓練でもトイレ対策が位置づけられたところが多かったようですが、取り組みによる効果や評価など、見解を求めます。
【危機管理監答弁】
能登半島地震を機にトイレ対策を広めるため開催した今回の防災リーダー研修会の参加者へのアンケートによると、「災害時のトイレは、水や食料よりも優先すべきことだと認識した」「各家族単位で携帯トイレが必要だと感じた」など、主旨をご理解いただいた回答が多く、トイレに関する意識項羽上につながったものと認識しております。また、避難所開設・運営訓練の効果・検証につきましては、来年度に避難所運営委員会へのアンケートを行いますが、今年度から実際に携帯トイレを使った訓練を取り入れたことで、避難所におけるトイレ対策だけでなく、各家庭での携帯トイレの備蓄の必要性についても考えていただくきっかけになったと考えております。
【佐々木ゆうき議員】
能登のある自治体の民間の医療関係者からは「避難所の学校に600人が避難してきて、すぐにトイレは排せつ物であふれ、外の側溝も排せつ物だらけ、ごみ袋をかぶり汲み取りの作業。まさに生き地獄だった」と。3日後にトイレトレーラーが来た時には、そうした問題が解消したそうです。
(7)こうした証言や千葉市職員の派遣の経験など、今後、リアルに市民に伝えていき、千葉市の防災に生かしていくことと、マンホールトイレの整備は進んでいますが、様々なトイレ対策を実施する点でも、トイレトレーラーの整備をするよう求めます。
【危機管理監答弁】
防災リーダー研修会において、能登半島地震でのトイレ調査結果などを盛り込んだ講演を行ったほか、市民向け講座等で市職員が現地で体験したトイレ事情を市民の皆様に伝えているところであり、引き続き能登半島地震の教訓等を踏まえた、周知啓発を図って参ります。また、トイレトレーラーにつきましては、導入することや自治体間で相互提供する仕組みについても検討して参ります。
【佐々木ゆうき議員】
(8)トイレ対策の最後は、早期にマンホールトイレの整備を行い、市内の県立高校への整備に向けて取り組まれていますが、県立高校以降の公共施設等への整備の拡充に取り組むことを求めます。お答えください。
【危機管理監答弁】
県立高校への整備は、令和9年度までに完了する予定であり、その後は水源確保などの条件が整えられる避難所への整備を進めてまいります。
2.病院行政について
【佐々木ゆうき議員】
新病院開院に向けた診療体制と交通アクセスの充実について
8月末から短期間ではありましたが海浜病院移転後の新病院について、診療科目の充実、新病院への交通アクセス、療養環境の充実、医療・介護等の相談体制の充実をお聞きするアンケートに取り組みました。その内容にもとづいて、質問を行ないます。
(1)一番要望として寄せられたのが「新病院への交通アクセス」の充実です。これは以前からも私や美浜区選出議員からも繰り返し質問や要望が出されている課題です。アンケートに答えた市民からは「循環バスをお願いしたい」「市が責任をもって取り組んでほしい」など共通して出されています。
新病院の開院まで、あと2年ですが、交通アクセスの確保についての進捗状況を示してください。
【病院局次長答弁】
令和2年度から、近隣で路線を運営するバス事業者に対し、毎年情報提供を行って参りました。さらに、4年度からは新病院への路線バス乗り入れの可能性についてヒアリングを実施しております。
【佐々木ゆうき議員】
(2)この間の議会でも「新病院開院時に乗り入れができるよう、民間事業者に対して積極的に働きかけを行っていく」との答弁の繰り返しではなく、協議をどこまでに行い、バス路線を確保するのか、スケジュールを明確にするべきではないですか。
【病院局次長答弁】
新病院の周囲には、民間のバス事業者の既存の運行ルートがあり、これを活用することが最も効率的で実現可能性が高いものと考えております。一方で、バス路線の決定には、運転手の確保状況や利用者動向、新たな需要の見通しなど複数の要素が関係するため、事業者において慎重な検討が必要となります。こうした事情を踏まえ、事業者と具体的な決定時期を含めて、引き続き丁寧に協議を重ね、市民の皆様にとって利用しやすい交通手段の確保に努めて参ります。
【佐々木ゆうき議員】
(3)次に診療科目の充実についてですが、海浜病院における高齢者医療の中でも整形外科や泌尿器科の医師増員に早期に取り組むべきではないですか。脳神経外科も含め高齢者医療の診療科医師の確保の見通しについて伺います。
【病院局次長答弁】
地域の医療ニーズに応えるべく、今年度は脳神経外科、整形外科において医師を1名ずつ増員しております。引き続き泌尿器科を含めた医師の人材確保に努め、超高齢社会に求められる医療需要へ対応するための体制を整備して参ります。
【佐々木ゆうき議員】
(4)海浜病院において慢性的に介護福祉士が足りない、募集をかけても応募がない、それに対し「看護師の配置見直しを図って対応していく、必要に応じて介護福祉士や看護補助員の増員に取り組む」と第1回定例会で答弁されていましたが、そもそもの介護福祉士の基本給や諸手当を上げていかなければならないのではないですか。現在も、新病院開院に向けても処遇改善を図り、介護福祉士の確保に取り組むべきです。お答えください。
【病院局次長答弁】
本年2月から国の看護補助者処遇改善事業を活用し、介護福祉士等の給与を引き上げたところです。新病院開院に向けて、必要に応じて処遇改善を検討するとともに職員の確保に努めて参ります。
【佐々木ゆうき議員】
新病院の職員の福利厚生や外来患者への対応について
次に病院職員の福利厚生ですが、以前から指摘してきたことですが、この間、病院関係者からは「新病院に食堂がないのはおかしいのではないか。病院職員の福利厚生からも必要」との訴えがありました。
(1)あらためて伺いますが、設計段階から食堂を整備しないとした理由、最終決定は誰が行なったのか示して下さい。また現在の海浜病院の約600人もの病院職員、新病院では1日あたり約700人の外来患者が新病院では想定されている中で、コンビニやカフェだけで対応することができるのでしょうか。
【病院局次長答弁】
病院職員の福利厚生のための食堂の整備については、利用意向を調査するために職員アンケートを実施したほか、食堂事業者の参入意欲についても調査して参りました。その結果、職員の利用が限定的で新病院移転後も食堂の利用者の大幅な増加は見込めないこと、食堂事業者の参入意欲が低いことがわかりました。これを踏まえ、両病院の職員等で構成する「新病院整備に係る検討会」において、食堂に代わり職員が自由に食事をとれるスペースとしてラウンジを整備することといたしました。また、新病院における飲食の提供については、建物内にコンビニエンスストアや軽食を提供するカフェ形式の店舗を誘致する計画としておりますが、あわせて来院者が自由に食事をとれるラウンジも院内に確保するなど、不便が生じないように整備して参ります。
【佐々木ゆうき議員】
(2)福利厚生の面からも温かい食事を提供できる食堂の整備が今からでも計画することが必要ではないですか。
【病院局次長答弁】
新病院においては、建物内にコンビニやカフェを誘致する計画となっており、温かい食事が提供できる事業者の誘致に努め、来院者や病院職員の利便性向上を図って参ります。
【佐々木ゆうき議員】
新病院開院・移行後の市立海浜病院を含む跡地について
令和8年秋頃の新病院開院後に、海浜病院から医療機能の移行を行い、海浜病院はその後、解体、更地にして県へ返還することとなります。県救急医療センター跡地を合わせると約5万㎡もの土地となります。地域医療の拠点として果たしてきた役割から、近隣住民からも、今後どのようになるのか、関心として高まってきています。
(1)現在の海浜病院の土地の、現時点での大まかな返還スケジュールと必要な手続き、返還先の千葉県所管部局について伺います。
【病院局次長答弁】
海浜病院の土地は、海浜ニュータウンの医療整備計画に基づき、千葉県から病院整備を目的として貸し付けを受けたものです。新病院開設後に建物を除却し、更地にして返還することとなっており、千葉県健康福祉部と具体的な協議を進めていく予定であるため、今後のスケジュールや手続きについては未定です。
【佐々木ゆうき議員】
(2)この土地は千葉県企業局が管理するものではなく、千葉県健康福祉部、千葉県病院局です。この土地の用途地域は主に第二種中高層住居専用地域ですが、用途制限はありますか。引き続き、医療に関する土地の用途は可能なのか、伺います。
【病院局次長答弁】
海浜病院の土地の用途制限については、住環境の保護を基本としながら、必要な公共・医療サービスの提供を可能とするものとなっており、住宅をはじめ、小学校や中学校、病院や診療所、床面積1,500㎡以下の一定の店舗や事務所などの建築が可能です。一方で、規模の大きな商業施設や騒音や振動を伴う工場などの用途については建築が制限されております。
【佐々木ゆうき議員】
(3)8月末から取り組んだアンケートに取り組んで、土地の活用要望について周辺の住民にお聞きしてきました。いくつか紹介したいと思います。「高齢化が進んでおり、高齢者施設の充実をしてほしい」「マンションなどの企業に売却するのは絶対に反対」「公共のスペースとしての活用が望ましい」「何が住民にとって良いのか十分に議論され、声を施策に取り入れる姿勢を望む」というように、関心が寄せられています。現在はまだ海浜病院は存在していますが、こうした声に対する市としての見解と、有効活用の必要性について伺います。
【病院局次長答弁】
当該土地は県有地であり、返還後の利用計画については県の意向に基づくものと認識しております。現時点で具体的な計画は示されておりませんが、今後、県から情報提供があった際は、速やかに市民の皆様へお知らせするとともに、皆様のご意見を県に伝えてまいります。
3.新庁舎について
【佐々木ゆうき議員】
千葉市の新庁舎は久米設計・隈研吾建築都市設計の共同企業体が基本設計を行ないました。まちかど広場、縁側テラス、モノレール連絡通路などの天井に使用されている天然木ルーバーは、一般的に木の温かみを感じられ、穏やかな空間づくりに適しています。
一方で、何も加工をしていない場合は、雨風に当たるような屋外に設置すると、腐敗や虫害の恐れがあります。また、天然木であるため経年劣化は避けられず、反りや歪みが発生しやすいというデメリットがあるとされています。
この間、栃木県那珂川町の馬頭広重美術館の屋根及び庇(ひさし)が老朽化し改修に3億円。長岡市のアオーレ長岡がオープンしてから12年が経ち、大屋根鉄骨部の錆が目立ち、修繕費は当初計画よりも増え、実態に合わない状況のため、保全計画を改めて作成するとのことです。そこで、確認する意味も含めて伺います。
(1)天然木ルーバーを使用することとなった理由について伺います。また、天然木ルーバーの価格についても示していただきたい。
【財政局長答弁】
親しみやすく、周辺の緑と調和した街並みの形成を図るため、基本設計段階において設計者から天然木ルーバーを使用した提案があったこと、平成22年に制定された「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に基づき、本市においても「千葉市内の公共建築物等における木材利用促進方針」を定めており、木材の利用が求められていることから、実施設計に天然木の使用を反映させたものです。価格については、防腐処理を含め約5,000万円となります。
【佐々木ゆうき議員】
(2)この天然木ルーバーについての維持管理について修繕計画等にはどう位置づけられていますか。また定期的な点検、修繕などを実施し、維持管理の負担が増えないようにしていくことが必要ではないですか。
【財政局長答弁】
直接雨のかからない部分に使用しており、木材の防腐処理を行ったうえで保護塗装することにより、耐久性のある仕上げとしております。修繕計画は、今後策定していくことになりますが、計画の中で保護塗料の再塗装など適切なタイミングで行い、負担が増えないよう努めて参ります。
4.新湾岸道路について
【佐々木ゆうき議員】
「新湾岸道路について地域のみなさまへの情報発信と意見聴取を実施します」と、千葉市も「新湾岸道路プロジェクト」におけるコミュニケーション活動の運営主体に名を連ねて、オープンハウス=対話方式による説明会とアンケート調査が12月から沿線6自治体の公共施設や民間施設等で実施されることになり、12月2日の美浜区役所から開始されています。
(1)新湾岸道路についての市民への情報発信はこれまでにどのように行なってきたのか、また美浜区町内自治会連絡協議会などの団体への説明の実施状況と質問や意見の内容について伺います。
【建設局長答弁】
昨年度は、新湾岸道路の事業概要や期待される整備効果等をお伝えするため、市役所やショッピングセンターなど市内5か所でパネル展を開催しました。今年度は、改めて事業概要や整備効果をお伝えするとともに、地域の皆様と意見交換を行うため、今月から来年2月にかけ市内8か所においてパネル展と対話方式による説明会をオープンハウス形式で開催しております。このほか、新湾岸道路に関する情報をお知らせする特設ホームページの開設、ニューズレターの発行及びユーチューブ動画の配信などにより、市民の皆様へ情報発信を行っているところです。また、より多くの皆様に説明会やアンケートに参加いただくため、現在行っているコミュニケーション活動の内容について、美浜区全地区および中央区の湾岸部4地区の町内自治会連絡協議会に対しご説明したところ、事業を歓迎する声や海辺へのアクセスが変わることへの懸念の声などをいただいております。
【佐々木ゆうき議員】
今年8月2日に開催された第1回新湾岸道路有識者委員会等の資料の中の「計画検討は、道路計画策定プロセスを通じて概略計画を策定します。道路計画策定プロセスは、透明性、客観性、合理性、公正性の向上を図るため、地域のみなさまとの密接なコミュニケーションを通じ、地域の理解や協力を得ながら道路計画を策定するプロセス」と示されています。
計画検討手順として上から「計画検討の発議とプロセスの明確化」、「課題の共有と道路計画の必要性の確認」、「複数案の設定と評価項目の設定」、「複数案の比較評価(計画段階評価)」、「概略計画案を選定し、対応方針を決定」という流れになっています。
(2)「複数案の比較評価」では、ほぼ概略ルートが示される段階となります。最初の2項目は地域とのかかわりでは大きな比重を占めます。市として、住民・関係者等とのコミュニケーションプロセスをどのように図るのか、伺います。
【建設局長答弁】
来年2月末まで引き続き行うオープンハウス形式の説明会のほか、今後も計画検討の進捗に合わせ、国・千葉県及び沿線市と連携し、様々な形でコミュニケーション活動を行っていきたいと考えております。
【佐々木ゆうき議員】
(3)また資料によれば、「コミュニケーションを重ねながら段階的に進めます」とあります。説明会を何度も重ねていくということになるのか。その際、千葉県や千葉市、国道交通省など関係機関から新湾岸道路に関する情報を示し、メリット・デメリットを含めて説明することが必要ではないか。
【建設局長答弁】
より多くの地元の皆様に事業へのご理解を深めていただくため、本市湾岸地域における渋滞緩和や物流の効率化が図られることによる経済の活性化等、「期待される整備効果」と併せて、生活環境や海辺の景観などへの配慮について、進捗に応じ丁寧に説明していくことが必要と考えております。
【佐々木ゆうき議員】
(4)有識者委員会の資料の「湾岸地域の土地利用状況」では、美浜区の部分で「住宅団地等が広がり」と記載されています。私はここに着目しています。
わが会派のあぐい市議の代表質問で住環境に関する質問への答弁で、「周辺環境などに配慮された計画となるよう国に申し入れていく」にとどまっています。
配慮を国に申し入れるのではなく、住環境等への悪影響が出ることを千葉市が「計画の早期具体化」と言って進めることは許されませんが、見解を求めます。
【建設局長答弁】
今年度から、概略ルートや構造の検討を行う計画段階評価に着手したところであり、検討にあたっては沿線地域の生活環境や景観などに配慮された計画となるよう、また、本市が持つポテンシャルが十分に生かされる計画となるよう、国に要望して参ります。
【佐々木ゆうき議員】
(5)結局、「計画の早期具体化」として推進する立場です。必要性について代表質問の答弁で「広域的な道路ネットワークが強化され、持続的な発展に大きく寄与する」としています。この他、渋滞解消や国際競争力の向上などもあげています。
新湾岸道路によってどこの渋滞がどれだけ解消するのか、国際競争力の向上による効果など市民が納得できる根拠および具体的な数値を示すべきではないですか。
【建設局長答弁】
幹線道路の渋滞緩和や抜け道として利用されている生活道路の交通量の減少などの効果を見込んでいるところです。また今後、計画段階評価プロセスにおいて、有識者の意見を伺いながら検討を進め、具体的な効果などが示されていきますので、地域とのコミュニケーション活動により、丁寧に説明して参ります。
【佐々木ゆうき議員】
(6)以前、近隣の検見川・真砂スマートインター整備で約48億円のうち、接続道路など千葉市の負担は事業費の3分の1の約15億円ということから、新湾岸道路の事業費負担をお聞きしましたが、明確な答弁はありませんでした。あらためて伺いますが、建設費用は全体としてどの程度になると見込んでいるのか。考えられる事業負担割合については検討されていますか。
【建設局長答弁】
概算事業費などが示されていない状況であるため、本市の負担額についても算出できておりません。なお、大規模な事業となることから、ルート、構造及び整備手法の検討にあたっては、沿線地域の生活環境や景観への配慮に加え、地元負担が極力抑えられた計画となるよう国に対し申し入れてまいります。
【佐々木ゆうき議員】
(7)新湾岸道路の起点とされる高谷ジャンクションから埼玉県の三郷南インターチェンジまでの東京外環自動車道・千葉県区間は、都市計画決定から完成までに50年かかっています。この東京外環道・千葉県区間は15.5キロメートルで、インターチェンジなどの付随施設とあわせると約1.5兆円です。新湾岸道路がそうした規模にとどまることはないでしょう。
どの程度の財政負担が生じるかもわからない。千葉市の将来に大きな財政負担となることが明らかです。現段階でも新湾岸道路については中止する決断を求めます。お答え下さい。
【建設局長答弁】
新湾岸道路は、本市を含む千葉県湾岸地域における交通容量不足を解消させる抜本的な対策であり、市内渋滞の緩和や物流の効率化による経済の活性化などが期待できること、また、災害時の支援活動に重要となる複数ルートが確保されることで、防災力の強化が図られるなど、本市の持続的な発展に大きく寄与する極めて重要な道路であることから、引き続き本市負担への配慮を求めつつ、計画の早期具体化に向け国に協力して参ります。