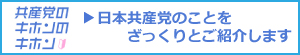千葉市斎場の開場時間と閉場時間を変更し火葬件数を増やせ! 野本信正議員一般質問〔2024年第4回定例会〕
野本信正議員の一般質問および答弁 2024.12.11

1、気候危機打開について
【野本信正議員】
(1)カーボンニュートラルについて
気候危機の打開は地球規模、全人類的課題である。2023年の世界の平均気温は、1805年の気温観測開始以来最も暑い年で、産業革命前に比べると1.48度上昇した。同時に日本国民にとっても、猛暑や豪雨災害が頻発し、農業や水産業にも大きな被害を与える待ったなしの課題である。
千葉市は2050年カーボンニュートラルに向けた新たな地球温暖化対策実行計画を策定し、目標年度を2030年度とし、温室効果ガス排出量を削減する。
2050年までにカーボンニュートラルの実現を目指す。としている。
環境局発表のデータによれば、業務、家庭、運輸の3部門合計で、2030年度温室効果ガス排出量を、2013度比48%削減を目指す。と書いてあるが可能性についてはどうか。
【環境局長答弁】
業務、家庭、運輸の3部門合計の温室効果ガス排出量は、直近の2020年度時点では2013年度比16.5%削減となっております。排出量は、着実に減少しておりますが、目標の達成に向けては、さらなる削減の加速化が不可欠であると考えております。
【野本信正議員】
次に千葉市のCO2排出量の60%余りを占める産業部門の2030年度の削減目標は30%と低い。他の部門に比べて産業部門の温室効果ガス削減目標が低い原因は何か。
【環境局長答弁】
地球温暖化対策実行計画における産業部門の削減目標は、排出量が多い事業者を中心に、各事業者が2050年のカーボンニュートラル達成に向けた独自の目標を設定していることを踏まえ、市内主要企業の目標値を参考に設定しております。
【野本信正議員】
市内の大企業は、JFEスチール(旧川鉄)および東京電力千葉発電所などが挙げられるが、この2社が協力しなければ千葉市のカーボンニュートラルは達成しない。日本のCO2多量発生企業は製鉄所、電力会社、セメント会社である。
〇千葉市はなぜ業務・家庭・運輸部門と同じように協力を求め規制しないのか。〇相手が大企業だと遠慮して相手の言いなりになってしまうのか。〇政府のエネルギー対策が火力発電所の維持なので東京電力千葉発電所に規制をかけられないのか。といった疑問がある。
これらを踏まえ、企業の温室効果ガス排出削減に対する市の取り組みについて伺う。
【環境局長答弁】
温室効果ガス排出量の多い産業部門の事業者においては、2050年のカーボンニュートラルの達成を目指したロードマップを作成し、計画的に取り組んでいるところであり、動向を注視して参ります。また、地球温暖化対策は、あらゆる主体が協力・連携して取り組むことが重要であり、大企業においても同様と考えております。なお、東京電力等の電力事業者については、国のエネルギー基本計画に基づき事業を進めていると認識しております。
【野本信正議員】
答弁で東京電力等の事業者は、国のエネルギー基本計画に基づき作業を進めているとあったが、電力会社は環境省の庇護のもエネルギー転換によって電力会社が発した電力を使う企業や消費者がCO2 発生元にカウントされる。
東京電力千葉火力発電所は2011年度に17万7559トンのCO2を発生していることになっているが、実際にはそれ以上排出している。千葉市が市内発生源を正確に把握してカーボンニュートラルを実現するためには、大量のCO2を発生する東京電力千葉発電所を無視することは不適切であることを指摘しておきたい。
また、カーボンニュートラル達成にはCO2削減とともに、再生可能エネルギーの増量にも力を注がなくてはならない。最近全国の取り組みの中で環境省から優れた成果を上げて評価された、千葉県匝瑳市のソーラーシェアリングは、広大な畑に背の高いパネルを張りその下で農作物を栽培し順調に生産している。ソーラーで作られた電力はすでに、何千世帯にも届いている。
千葉市もこの先進事例に学び、再生可能エネルギーの導入に取り組むことを求めるがどうか。
【環境局長答弁】
千葉市地球温暖化対策実行計画において、再エネ導入を重要施策と位置付けており、脱炭酸先行地域事業として、公共施設に太陽光発電設備と蓄電池の設置を進めるとともに、農地を活用したソーラーシェアリングの導入を図っております。また市民による再エネ導入に向けた取組みを後押しするため、太陽光発電設備や蓄電池の設置費に対する助成を行っております。
【野本信正議員】
千葉市は匝瑳市のソーラーシャアリングを視察し、すぐれた実態と、千葉市のソーラーシヤリング―との格段の違いを把握してから答弁すべきである。
(2)千葉市清掃工場から排出されるCO2の削減について
千葉市は常時清掃工場が稼働していてゴミ焼却を行い、それに伴ってCO2を排出している。千葉市はプラスチックごみを分別しないでほとんど燃やしているため、プラスチックを分別処理して清掃工場で燃やしていない他の政令市に比べて、ゴミ焼却量当たりのCO2排出量は多いと思うがどうか。
この際カーボンニュートラル達成のためプラスチックの全部を分別処理して清掃工場では燃やさないことを求めるがどうか。
【環境局長答弁】
清掃工場から排出されるCO2の量については、算出方法が自治体によって異なるため一概に比較できませんが、千葉市では、プラスチックの焼却量を算出の主な要素としているため、プラスチックの分別収集を行っている市と比べ多くなることが考えられます。プラスチック分別・再資源化については、現在、千葉市廃棄物減量等推進審議会においてプラスチック資源の一括回収の方法などについてご審議いただいているところであり、今後、モデル事業で得られた検証結果を踏まえつつ、さらなる検討を進め、全市展開に向けた実施体制を整えて参ります。
【野本信正議員】
若葉区北谷津に建設中の新清掃工場のCO2排出量は13年度の予測で、8万5,568トンである。この時のゴミ処理量は142,314トンである。
このCO2排出量は、ごみ処理量108,715トンの新港清掃工場5万5千トンに比べ3万トン余り多いし、北谷津清掃工場の稼働していたごみ処理量24,194トンの平成28年度の17,780トンの5倍になる。さらにゴミ処理量が増えればCO2排出量はどんどん増えてしまう。
原因は今までの清掃工場のストーカー方式が、焼却温度が850から900度に対して新清掃工場はガス化溶融炉のため1700から1800度の焼却温度でなんでも溶かしてしまう施設である。焼却温度を高温にするためガス化溶融炉は、助燃材としてコークスを年間5千678トンも燃やすのである。
化石燃料のコークスを燃やすためCO2を大量に排出するガス化溶融炉は有害である。共産党市議団はガス化溶融炉に反対した。しかし契約して作り出してからは反対しないで、メーカーに対しコークス使用を控え、技術革新でCO2削減をするよう市に申し入れてきたが変化はあったのか。
【環境局長答弁】
新清掃工場の建設・運営事業者からは、CO2排出の要因となるコークスの使用量を最小限にすることや将来のバイオコークスの活用検討を提案されており、引き続き、事業者と連携してCO2削減につながるような手法を検討して参ります。
【野本信正議員】
ごみの溶融化で最終処分場の延命などできるといってきたが、市にどんなメリットがあるのか。
【環境局長答弁】
新清掃工場が整備されることにより、他の清掃工場も含めた焼却主灰や、新浜リサイクルセンターで発生する破砕残渣について全量を再資源化することが可能となります。この結果外部委託をしていた再資源化費用が抑制されるとともに、最終処分量が減少することから、最終処分場の埋め立て完了は令和19年度まで6年間の延長が見込まれ、安定的な廃棄物の適正処理が行えるものと考えております。
【野本信正議員】
市のメリットは気候危機打開と比較して妥当なものなのか。
【環境局長答弁】
新清掃工場を整備するにあたり、焼却方式の選定については、最終処分場延命化を図ることができるよう、ガス化溶融式を採用しました。この方式はコークスを助燃材として使用しますが、焼却量当たりのCO2排出量は旧清掃工場と同程度です。また、新清掃工場は、焼却により発生した蒸気を活用し、高効率の発電を行うことが可能です。本市では、その電力を自己託送し、再エネメニューの活用と組み合わせることにより、2026年に市有地における使用電力の脱炭素化を目指します。
【野本信正議員】
新清掃工場は高効率の発電を行い、その電力を自己託送して、再エネメニューの活用で2026年に市有施設における使用電力の脱炭素化を目指すとの答弁だが、2026年から稼働する新清掃工場が30年間もコークスを大量に燃やしCO2をまき散らしている矛盾をどう説明するのか。
また、環境省の土井健太郎環境再生・資源循環局長は「将来的に脱炭素化が進展して電気のCO2排出係数がゼロに向かっていくと、ごみ焼却施設から得られる電力が、「汚い電気」になってしまい切り替えなければならない」と述べている。将来性のない「汚い電気」を使うのはやめるべきだ。
まったなしと言われている地球温暖化防止に比べて、千葉市のメリット最終処分場の6年間延長はバランスが取れるのか。
カーボンニュートラルで市民や民間企業のCO2排出削減を求めている千葉市が、新清掃工場で30年間もコークスを燃やし続けCO2を排出し続けることは市民を始め全国で気候危機打開に取り組んでいる人々の理解は得られない。最終処分場の6年間延命という千葉市のメリットと引き換えに、地球温暖化防止の足を引っ張る、新清掃工場のコークス使用を中止すべきである。
【環境局長答弁】
最終処分場は、清掃工場での焼却処理後の再資源化できない廃棄物の処分のため欠かすことのできない施設であり、将来にわたって安定的な稼働を継続していかなければなりません。そのため、新清掃工場では溶融式を採用して、焼却残渣を溶融スラグ化し、より一層の最終処分量の低減及び再生利用率の向上を図ります。今後新清掃工場の稼働にあたり、排出されるCO2を御抑制するために、引き続き手法を検討して参ります。
2、千葉市斎場について
【野本信正議員】
千葉市斎場は火葬待ちが深刻化している。今議会で審議されている令和7年度からの指定管理期間においては、友引の日に火葬を行うことと開場時間の延長を行うことにより、令和5年度との比較で令和11年度には46の追加開場で、1512件の効果をシュミレーションしている。この改善で火葬待ちはなくなるのか。
火葬件数から死亡者数を引き算すると令和5年度は5月マイナス47件、8月マイナス87件、令和6年1月マイナス187件の火葬ができないでいわゆる火葬待ちとなっているが、来年4月からは火葬待ちは解消されるのか、どうか。
令和7年度から11年度までの5年間の火葬は、6日間の火葬待ちがあるとの答弁である。5年後、10年後はどうなるのか。
【保健福祉局長答弁】
次期指定管理者の公募にあたり、成果指標として「火葬需要に応じた斎場運営」を設定し、6日以内に火葬予約できる状況が8割以上あることを数値目標としたほか、年間の友引開場日の目安を示して、火葬需要の増加に対応できる提案を求めたところです。今後、指定管理者と連携し、目標の達成に向けての取組みを確認し、火葬待ちの抑制に努めて参ります。
【野本信正議員】
令和5年度の死亡者数は11,031人である。その後の死亡者数は、千葉市 総合政策局の死亡者数統計を見ると、5年ごとの国勢調査での数値のため1年間の平均数値になるが、令和7年から5か年平均の死亡者数は11,689人で増加数は658人であるため、市外から引き受ける数を含めても、友引効果等1519件で全部の火葬は可能なのか無理なのかわからない。
次に、令和17年からの死亡者統計を令和5年度と比べてみると、2287件増えるために、友引開場の効果では間に合わずに、およそ748件が火葬できなくなることになる。すなわち友引効果と20分繰り上げで当面火葬待ちを改善できても、10年後不透明で、15年後は不能となり、現斎場の増築か第2斎場建設が必要であるがその見通しはどうか。5年後に見通し出るのか。
【保健福祉局長答弁】
高齢化の進展に伴い、今後も火葬需要の増大が見込まれる中、年間の火葬需要が現斎場の供給能力を超えることも予想されます。今後の火葬需要に対応するためには、更なる火葬枠の拡大、施設の整備の拡充や増設などの手法が考えられますが、今年度、外部委託にて火葬需要や供給能力などの調査を行っているところであり、その結果を踏まえて、必要な対応策を検討して参ります。
【野本信正議員】
私は現斎場で火葬件数を増やすため研究し、他自治体の施設を調査してみた結果、火葬開始時間を早めることによって火葬件数を増やすことができると分かった。千葉市斎場は開場時間9時で閉場時間が5時であり、この際開場時間を8時30分にして閉場時間を5時30分にすることを提案する。このことによって一日当たりの 火葬件数を2~5件、1か月あたり100件以上増やせると思う。
千葉県内14の斎場を調査したところ、開場時間8時30分が8施設。閉場時間5時15分が5施設となっており、それぞれ努力している。
今議会で指定管理が決まったとしても、5年後に現斎場の増設や新斎場建設は間に合わないので、5年後を想定して開場時間と閉場時間を変更し、ひと月当たり100件からの火葬件数を増やすよう提案するがどうか。
【保健福祉局長答弁】
火葬待ちが深刻化していることの対応について、次期指定管理予定候補からは、火葬集中時期に9時から受け入れを開始し、1日最大42件の火葬を実施する提案があり、本市としても、友引開場の拡大と合わせて実施し、必要な火葬枠を確保することで長期間の火葬待ちを改善できるものと見込んでおります。火葬需要は今後も増加が見込まれることから、開場時間など5年後の運営体制についても検討して参ります。
【野本信正議員】
地方自治体の仕事は、ゆりかごから墓場までと言われているが、火葬場・斎場の運営は、千葉市に住み続けたいと思う市民全体に安心感を持ってもらう大事な仕事であると思うがどうか。議会の提案を真剣に受け止めるべきだが。
【保健福祉局長答弁】
火葬は、人生最後の行政サービスとも言われ、斎場を必要とするタイミングは突然訪れるものでありますが、長期間の火葬待ちをせず、火葬できるように体制を整えておくことは、市民の皆さまの安心感につながり、遺族の気持ちに寄り添った対応が求められる施設として重要であると認識しております。ご提案を真摯に受け止め、今後も増加する火葬需要への対応に向け、取り組みを進めて参ります。
3、都賀駅の環境整備について
【野本信正議員】
(1)JR都賀駅は一日の乗車人数19,376人、若葉区の玄関口となっており、東口の駅前広場JR側歩道は幅員7メートル、延長70メートルで、多数の人が利用している。問題は夕方から夜になると歩道が暗くて対面する人の顔も確認できない状況である。原因は歩道を照らす照明灯が4本だけ建っているが外側を向いていて、照度が低い。また歩道の上には幅員4メートル、延長50メートルに渡るモノレールの自由通路があり、照明灯の明かりを遮っているため暗い歩道になっている。
都賀駅西口の駅前広場JR側歩道も調査したところ、照明灯が少なく幅員3.3メートル、延長40メートルの区間は暗い歩道となっている。市当局は多数の人が利用する都賀駅の歩道が暗いことを承知しているのか。速やかに照明灯を設置して明るく安全な都賀駅に改善することを求めるがどうか。
【建設局長答弁】
現地を確認したところ、照明灯は設置されておりますが、上空通路や外階段の影で一部歩道が暗いと感じられるため、照度などを調査し、必要な改善を行なって参ります。
【野本信正議員】
(2)都賀駅東口にエレベーター設置について
市は東口にエレベーター設置の必要性を認め、JRや千葉都市モノレール会社と設置場所や用地などについて協議を進めていることは、駅利用者に喜ばれている。質問は、取り組みの進捗状況と見通しについて問うと共に、エレベーター事業予算化は千葉市実施計画事業に計上されることが必要なのか、だとすれば令和8年度からスタートする次期実施計画事業に組み込むことを求めるがどうか。
【建設局長答弁】
エレベーター設置については、モノレール側エレベーターなど、既存施設の更新時期及び将来にわたる維持管理費用等を考慮しつつ、設置の必要性及び最適な配慮について、継続して検討しております。なお、設置を検討している階段付近の用地が、JR東日本の敷地であり、JR利用者の利便性向上にもつながることから、無償提供などを求めておりますが、JR側の有償での売却方針が変わっていないため、引き続き協議を行うとともに、その進捗を踏まえ、次期実施計画への位置づけを検討して参ります。
4、商店街街路灯について
【野本信正議員】
商店街灯は商店街のPRだけでなく周辺住民の防犯・安全安心の街づくりに多大な貢献をしている。商店街灯を管理している商店会は近年閉店する商店が増え続け街灯の電気代など維持管理が困難になっている。
若葉区千城台中通り商店会は商店会の活動はなく、代表一人が27基(54灯)の電気料金などの会計管理や補助金の手続きを行ってきたが、令和5年に亡くなり商店会は消滅した。現在の状況は、電気代未納で送電停止により街灯が消えて真っ暗になり、防犯に由々しい事態となっており、今後、維持管理未更新で危険な街灯として残ることになる。市は今後の維持管理について地元自治会と相談していると聞いているが、維持管理に多額の費用が必要で、古くなった危険な街灯を自治会が受け入れることは無理である。
急いで必要なことは、電気代未納、送電停止で商店街灯が消えてしまった現状において、速やかに防犯街灯を設置して夜の街を明るくするために、市が責任をもって取り組み自治会との話もすめることについて見解を質したい。どうか。
なお、電柱などを利用してすれば比較的簡易に取り付けられると思うが。
【市民局長答弁】
当該商店街街路灯については、区役所から、当該商店会関係者に対して、申請により市から電気料金の補助を行えることを伝えるとともに、地域の町内自治会に対しては、既存の商店街街路灯を防犯街灯として移管できることを説明しております。併せて、新たに町内自治会の防犯街灯を電柱に取り付ける形で設置することができること、また、防犯街灯の設置や管理にあたっては、市から補助が実施できることにつきましても、当該町内自治会に対して説明しているところです。
【野本信正議員】
私は、地元のことなので毎日の夜見回りをしているが、数日前から商店街灯は全部消えてしまい、道路の両側は暗い中を歩いている歩行者にトラブルが無いように心から願っている。市は速やかに防犯街灯を設置して明るく安全にすること。取り付けた防犯街灯の維持管理の相談はその後でもいいのではないか。
ともかく、市の責任で防犯街灯をつけて街を明るくすることを最優先で取り組むよう求める。
【市民局長答弁】
当該箇所の商店街の街路灯が点火しなくなったことについては把握しており、現在、関係町内自治会等と今後の方針について話し合いを行っているところであります。防犯街灯の設置に係る今年度の申請期間は終了しておりますが、自治会から申請があり、必要性があると認められるものについては、直ちに対応して参ります。
【野本信正議員】
市民局長は現場を見たのか。真っ暗な街になってしまった現場の実情を確認したのか。まず市民の安全のため防犯街灯の取り付けが必要、市の制度に沿って進めるというが、通常の取り組みでは数ケ月先になる事もありこれでは安全を確保できない。
自治会も理解をしてくれているようなので、市が局長を先頭に自治会と話し合い、一番早く街灯が設置されて明るい街になる取り組みを求めるがどうか。
【市民局長答弁】
当該箇所においては、昨年から区役所が商店会関係者や地域の町内自治会から今後の方針について相談を受けており、地域の意向に基づいて速やかに対応できるよう、準備しているところであります。先般、担当課とともに私も現地に伺い、モノレール千城台北駅からローソンまでの、モノレール沿線の約200メートルの範囲において、商店街の街路灯が点灯していないことや、道路や店舗の照明による歩道の明るさの状況等を確認しております。防犯街灯の設置につきましては、電柱管理者への申請や、工事などに必要な期間を踏まえると、今月中の完了は難しいものと考えておりますが、地域から申請があった際には、その意向が早期に反映できるよう努めて参ります。
【野本信正議員】
また、現在の商店街灯の取り外しについては管理者がいないもとで、将来危険な状態となるとやむを得ず行政の代執行で行うことになると思うがどうか。
【市民局長答弁】
現在、地元の町内自治会等が区役所と相談しながら対応を検討しているところであり、その意向を反映できるよう、引き続き、地域の町内自治会等のご意見を伺いながら、関係者と検討を進め、必要性があると認められるものについては、直ちに対応して参ります。
【野本信正議員】
市内の商店会は商店街灯の維持管理が困難になっている会が増えていると思うが、市が商店会と話し合い、千城台のような事態になる前に適切な対策をすること。自治会にだけ頼るのではなく市が責任を持つ緊急対策として、予算も確保することを提案する。防犯と安全安心の街にするため前向きに取り組むべきと思うがどうか。
【市民局長答弁】
商店街街路灯の維持が困難になった場合には、商店街街路灯を地域の町内自治会等へ移管できる制度を設けており、移管後は、防犯街灯として、市が電気料金や、電球交換などの修理費に対し、補助を実施しているところです。また、令和2年度から、設置から10年以上が経過するなど、一定の要件を満たす商店街街路灯については、撤去費用に対する補助を実施しているところであります。