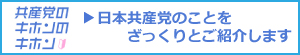幕張メッセ武器見本市は中止を!市民福祉向上の予算を! 中村きみえ議員代質疑【2025年第1回定例会】
中村きみえ議員の代表質疑 2025.2.12

- 市政運営の基本姿勢について
(1)国政について
石破自公政権は少数与党となり、予算案を与党だけで成立できない状況ですが、裏金問題は無反省、企業団体献金に固執し、能登半島への支援は3千億円に満たないのに、軍事費に9千億円もの補正予算を投入し税金の使い方が間違っています。国民の要望実現のために、選択的夫婦別姓、学校給食無償化、学費値上げ中止、マイナ保険証強制をやめ現行保険証の存続、消費税減税、企業・団体献金の禁止を進めていくべきと思われますが、市長の見解をお聞かせください。
(2)予算編成について
1つに、新年度予算は一般会計5,500億円、特別会計4,600億円と1兆100億円と対前年度比で約600億円も増加しています。新清掃工場の予算が280億円とピークに達していることや児童手当、民間保育園の経費でそれぞれ47億円の増額が計上され、公共施設の老朽化対策などが、主な要因だとしていますが、私ども日本共産党市議団が求めてきた要望として子育て支援、中小企業支援なども含めてどう反映されてきたのかお聞かせください。
2つに、市長の政治資金パーティーについてです。いま政治とカネの問題がこれだけクローズアップされ政治家としての倫理が問われている時期に、市長は、一人2万円のパーティーを行いました。参加した顔ぶれでは、市内の企業が多く、企業から献金を受けているのと同じことになるのではないですか。企業に忖度した政治を行わないためにも政治資金パーティーは実施すべきではありません。見解を求めます。
3つに、物価高騰が続き、1月にも食品の相次ぐ値上げで、賃金や年金はまともに上がらず、市民のくらしは、厳しいものです。千葉市では、物価高騰でどのような予算編成をしてきたのかお聞かせください。
4つに、能登地震に続き、1月13日にも宮崎で震度5の地震が発生し、南海トラフとの関連も議論されています。災害時に避難所となる学校の体育館のエアコン設置は新年度ようやく30校ほどの中学校で整備されますが、年間30校程度では、5年も6年もかかってしまいます。防災の起債を活用しもっと計画を前倒しして整備すべきではありませんか。お答えください。
5つに、県の水道料金の値上げを2割すると言われています。下水道使用料も1か月20m³で320円の値上げ、国保料の値上げも出されています。それぞれの不足額と市民への影響額はいくらですか。
6つに、県との不公平な県単独事業補助金についてです。そもそも県との不公平な県単独事業補助金によって21億円は財源が確保されるともいわれており、県に対して市の財源確保をなぜ求めていないのですか。
7つに、水道の事業では毎年8億円の赤字が生じており、県との水道事業についてその解消はどうなっていますか。
8つに、宿泊税についてです。県が早々と150円を徴収することは決まっているようですが、市議会でも宿泊税のあり方について慎重にすべきとの意見書が全会一致で可決されたことを踏まえ、千葉市で徴収のあり方に県に異議を唱えていくべきではありませんか。
(3)大型開発について
国際スポーツイベント誘致では、議会が開会する前にすでにチケット販売が先行しており、問題です。千葉駅周辺の活性化として中央公園通町公園の連結強化に7億192万円、中央公園プロムナード周辺のまちづくりビジョンの策定に3千万円、千葉駅周辺市街地再開発に4億9千万円、千葉駅周辺官民連携まちづくりに8千万円と千葉駅周辺に特化して、税金投入がされ続けています。千葉駅周辺に特化して、整備を進めていますが、なぜ中心部だけ異常に多額の予算を投じて整備を急ぐのですか。さらに県も市も、新湾岸道路建設も浦安から市原まで産業道路を整備するとして巨額の税金を投入しようとしています。整備されても20数年後、人口は減少、交通量も減り続ける中で、莫大な税金を投入して、予算を講じることになります。
環境破壊をして巨額の税金を投入してまで実施すべきではありません。千葉駅周辺の整備と、新湾岸道路プロジェクトは中止すべきです。お答えください。
(4)中小企業への支援について
1つに中小企業への支援策について
新年度予算では、企業立地促進で21億5,811万4千円計上し、昨年度よりも増額し、158社に経費を助成しようとしています。首都圏の政令市で、川崎やさいたまでは3-4億程度に過ぎず、21億もの税金を投入しようとしており、その分、地域で活動している中小企業や商店街への支援策に講じるべきではありませんか。
2つに、公契約条例の制定についてです。
昨年の第3回定例会でわが党が公契約条例の制定検討委員会設置条例の提案をしました。市が行う契約において労働者の適正な労働環境や公共事業の品質を確保し、市民サービスの向上、地域経済の活性化を図ることを目的に公契約条例の制定について調査検討を行う検討委員会の設置を求めました。残念ながら否決されてしまいましたが、現在90の自治体で条例化されており、都内は過半数制定されています。物価高騰で資材も高騰し、事業も思うように進んでいないのが現状です。千葉市で労働者の適正な環境を守り、市民サービス向上、地域経済活性化を進めていくためにも公契約条例の制定を求めます。お答えください。
(5)武器見本市について
5月21日から23日まで開催されるDSEIJapan2025が、幕張メッセで開催され、2023年の3月にもイスラエルの企業が16社も出展し、パレスチナへの攻撃を続けている企業もあり、世界中から非難されています。開催中止を求めて幕張メッセでの武器見本市に反対する会、安保法制に反対するママの会などが1月22日に2千筆を超える署名を県に提出しています。公共施設である幕張メッセで、こうした武器の売り買いをする場を提供することは武器の売り買いに加担することにつながると思わないのですか。
(6)学校給食の無償化
新年度予算では学校給食の無償化は第三子のままです。子育ては経済的な負担が重いために、今後産み育てたいと思えるように、お金の心配なく給食を食べられるようにすることが自治体としての務めではありませんか。
(7)災害に強いまちづくりを
能登の震災から1年以上が経過しましたが、復興の見通しは道半ばです。石川県全体の被害が広範囲に及び、石川県が国に対しての災害復興支援を求める立場が弱いことも関係者から指摘されています。千葉市では、能登への支援に延べ400人ほど派遣され、12月に報告書が出ています。被災者や被災自治体の職員と交流する中で、職員の中での復興への手助けをしたい熱意に敬意を表します。寝泊まりする環境も整わずに戸惑いつつ、奮闘されている感想も見受けました。女性の職員の派遣も様々な配慮が必要です。
職員の率直な思いも含めて派遣される側と送り出す側の体制の環境を整えることも大事だと痛感します。
1つに、職員派遣にあたり職場環境もふくめ体制をより充実させることも大事ではないか。
私も昨年12月に佐々木市議とともに石川県羽咋市にある能登半島地震被災者共同支援センターに行き、現地で被災者の荷物の運び出しや仮設住宅に食材や日用品を届けながら実態を伺い、要望の聞き取りも行いました。今回の震災では、罹災証明が他の自治体の応援もあり、迅速にできたと喜ばれる一方、外見だけで判断し、中をよく見て審査すると準半壊が半壊と判定が違う場合もあり、再判定に時間を要し、何の支援も得られないとの声も聞きました。
2つに、罹災証明の在り方は、課題も示されていますが、今後千葉市ではどのように対応していくのですか。
3つに、全壊となったお宅に被災者生活再建支援法で300万ほど支給されても家を再建するには程遠いため、国にもっと支援額を増額するように求めていくべきではありませんか。
4つに、若者はボランティアに出かけ、又行ってみたいとの感想も寄せています。まだまだボランティアを必要としていると思われますが、千葉市ではどのように受け入れ態勢をつくっていきますか。
5つに、トイレはマンホールトイレをかねてより求めてきましたが、新年度はどこに何か所整備しますか。トイレトレーラーは、緊急防災減災事業債を活用して、予算化することを求めます。
6つに、個別避難計画では新年度で約1,170件になるとしていますが、対象は何人で何%となりますか。いつ起こってもおかしくない災害のためにもすべての対象者の計画を簡易的でも計画すべきではありませんか。
2.市民行政について
(1)市民会館の建て替えについて
現在、習志野、船橋、県文化会館が利用できず現在、千葉市民会館の利用が集中しています。1月24日にあぐい市議とともにミューザ川崎シンフォニーホールを見学しました。川崎市では市政80周年に音楽の拠点となる施設が整備され車いす席10席を含め1,997席、360度席に囲まれて音楽に特化した施設となっており、東京交響楽団とフランチャイズ提携し、ベルリンフィルなどが演奏するほどの立派な施設になっており、総事業費は約217億4千万円です。オフィスビルとの複合施設で駅前の再開発を行っている中で、川崎駅直結で、整備はされていますが、リハーサル室や小ホールはありません。会議室も少しはありますが、そもそも各区に500から1,000程度のホールが整備されており、なおかつカルツ川崎という2,000ホールで多目的に使えるホールが川崎駅の別の場所にも整備されており、文化的に豊かな街だと感じました。
千葉市が興行目的で1,500席で市民会館を整備しようとしていますが、本来市民が交流できる施設として長年親しまれてきた利用についても損なわれないようにしていくことが求められます。
1つに、市は、川崎などの視察をしたようですが、その結果市としてどのように計画に反映していこうと考えましたか。
2つに、演劇の関係者からは、1,000席でなければ音響の面で運営は厳しいとの意見も寄せられていますが、運用についてどのように考えますか。
3つに、川崎は、舞台などを想定していないので、荷物の搬入もそれほど大きなものを入れるようにはなっていません。その意味でも、複合施設の整備では限界があるのではないですか。
4つに、市役所の国道わきに整備を求めます。市民参加で整備について検討すべきです。お答えください。
- ジェンダー平等について
沖縄での米兵の少女暴行事件、学校での教師の生徒への性加害、フジテレビでの女性職員に対する対応が大問題となっています。
1つに、事件となったのは氷山の一角でどこでも様々な問題をはらんでいるかと思われますが、同じようなことが起きないような取り組みと、その際の相談場所としての周知が必要ですが、市の対応をお聞かせください。
2つに、性被害を防止するための子どもの時からの教育が必要ですが、取り組みについて伺います。
3.保健福祉行政について
- 帯状疱疹予防接種について
わが党は、帯状疱疹の予防接種の予算化を求めてきましたが、ようやく予算化することになりました。今回の対象者と予防接種の種類と自己負担額はどうなっているのかお示しください。
(2)障害者政策について
その1、天海訴訟について
65歳になった天海さんが介護保険を優先させることで自己負担が生じ、それを拒否した天海さんがサービスを使えず自費で支払うこととなり、障害者を年齢で差別して介護保険を優先させることがないように千葉市に訴訟していました。障害者総合支援法第7条の介護保険優先の原則はあるものの申請者個別の状況に応じて対応することは必要です。その後最高裁判所への上告受理の申し立て後の現状はどうなっていますか。12月24日に県に申し入れ、県は、介護保険優先原則の適用について一律にすることはないという立場でしたが、市はどうしていきますか。
その2、旧優生保護法にかかわる補償金について
対象者の周知が、難しいと言われており、県は窓口を設置しましたが、市の取り組みはどうされるのですか。
(3)生活保護行政について
1つに、物価高騰していながら、そもそも単価もまともに上がっていないもとで食べるのも控えざるを得ない実態があり、市として国に要望しながらも基準の単価引き上げるべきではありませんか。
2つに、新年度予算ではケースワーカー一人当たり何世帯を担当することになるのですか。
(4)動物愛護センターの建設
(仮称)動物愛護センターの整備について、整備候補地の選定状況と、今後どのように建設予定地周辺住民への理解を得ていくのか、市の取り組みについてお聞かせください。
(5)補聴器助成を
補聴器の助成を行うよう党市議団は一貫して求めてきました。耳が聞こえなくなることで、人前に出なくなり、それが認知症を進めてしまい、余計に悪循環につながります。補聴器そのものは購入すると高額のものも多く、年金生活では購入のハードルが高いと言われています。ぜひ、先進自治体にならって実施を求めます。お答えください。
(6)特養ホームの数、介護職員の改善
特養ホームは予算がついてもこの間、年度の途中でキャンセルが相次いでおり、整備は遅れています。待機者は1,400人で市は新年度20床というわずかな整備にとどまっていますが、もっと増やすべきです。また介護職員もなり手がないと現場から悲鳴の声が上がっており、対策を講じるべきです。市独自での手当の上乗せを求めます。お答えください。
(7)国立病院機構について
千葉市内で千葉医療センター、千葉東病院、下総精神医療センターがあり、市民の命を守るうえで欠かせません。しかし、経営状況を理由に基本給や賞与改定を見送り、下総精神医療センターで基本給30万円の方が月給、賞与も含めると年間14万6千円の賃金引き下げになってしまうと関係者から指摘があり、地域手当を引き下げようとしており、又千葉医療センターでは、この3月で付属の看護学校を閉鎖するとのこと。大学化と言っても看護師になろうとしている場合、必ずしも経済的に恵まれた家庭の方ばかりではなく、学費が支払えないために資格を取り条件も狭められることになります。
国が行っていることとはいえ、市民の命と健康を守るうえでも欠かせない病院の役割を継続できるように市としても国に要望し改善を求めていくべきではありませんか。
4.こども未来行政について
(1)千葉市こども若者基本条例について
1つに、市長は若者支援を強調し、党市議団では10年ほど前から求めてきました。私も昨年6月議会で若者課の設置を求めました。今回こども企画課にこども若者支援室が整備されることになりますが、どのような役割を果たしますか。また何歳までの若者を対象とするのかお示しください。
2つに、こども若者基本条例について、千葉市では、こども・若者施策について子どもたちからアンケートを募り、関係者との協議やワークショップ、シンポジウムなどを行ってきましたが、その中での子どもたちの実態からの課題は何か、そのための対策としては、今後どのようにしていくのですか。今回、条例制定をすることで子どもの意見表明はどのように保障されますか。どこに相談したらよいか迷っている場合、案内も含めて周知はどのようにしていきますか。
3つに、学生は学費の値上げでバイトをしても追いつかない状況があります。市独自で返済不要の給付型奨学金制度も検討すべきではありませんか。
(2)児童相談所設置について
新たに東部児童相談所が中央区末広で建設されることとなりました。国が新たに一時保護施設の設備及び運営に関する基準が制定されたために、条例の制定が提案されています。
1つに、その中では、心理療法担当職員が児童概ね10人に1人となっていますが、基準を満たせていないようですが、今後の職員の採用の計画についてお聞かせください。
2つに、千葉市児童相談所条例の一部改正については、現在の事務所では相談件数増加に伴い執務スペースが不足するためとなりのはまのわ療育センター分館に移転するそうですが、現在の施設も老朽化しており、東部児童相談所が設置されて以降は、大規模改修を行うのかその予定についてもお示しください。
(3)児童虐待の対応について
2023年7月に生後11か月の男児千巴弥ちゃんが母親によって児童虐待の疑いで死亡する事件が発生しました。千葉市から船橋に転居後死亡しており、現在千葉県。船橋市、千葉市においてそれぞれ検証委員会が設置されて検討しているかと思われます。先日、児童相談所での対応について情報公開請求をしましたが、ほぼすべて黒塗りで、公開される以外の情報は、全くわかりませんでした。生後5日からネグレクトで一時保護、乳児院で過ごす乳児が結果として、命が奪われる結果は関わった自治体として、二度と繰り返してはならないと思います。自治体間の切れ目のない支援と、引継ぎは適切だったのか伺います。
(4)児童養護施設職員の待遇改善について
民間保育園の保育士の待遇は月額3万円から4万円に引き上げられ、現場では歓迎される一方で、児童養護施設では施設の独自の経営努力ではなかなか働く職員確保が難しいと言われており、もっと改善していくことが求められますがどうか。
(5)保育所について
公立も民間も定員割れしている地域もあり、今後少子化の中で、民営化を進めていっても宮野木のように手が上がらないために苦戦している事例も出ており、公立保育所は令和4年度雨漏りがあった際に、市内各地の保育所職員が結集して対策を講じるなど、公の保育を守るという点でも欠かせない役割を担っています。公立保育所は民営化を進めるよりも、公立のままで建て替えていくべきではありませんか。
5.環境行政について
- プラスチック分別について
現在2地区でのモデル事業が12月で終了しましたが、その実績と課題は何か。早期に計画を前倒しして、プラスチックの分別を進めるべきですが、見解を求めます。
- CO2排出について
脱炭素の取り組みで、市は脱炭素先行地域に選定されていますが、そもそもCO2の排
出が千葉県は全国で一番多く、その中でも千葉市が市原市に次いで2番目に排出が多いと言われています。産業部門は、市内の排出量の6割を占めており、いかに削減できるかが、地球温暖化を抑制していく要になります。産業部門に含まれるJFEなどに対してCO2の削減をするように求めるべきですが見解を伺います。
6.経済農政について
(1)買い物支援
若葉区での移動販売車が1月20日から週5日多部田、大宮台、若松町、貝塚愛生、みつわ台など高齢者施設にも販売場所になり、マックスバリューが実施となりました。一方、トップマートが中央区、花見川区をはじめ相次いで2月に閉店となるため、地域で買い物ができなくなると不安の声が寄せられています。市は、どのように対策を講じようとしているのですか。
(2)農業のあり方
農家の平均年齢は68歳、2020年農業センサスでは、全国で農業従事者116万人のうち、70-74歳は26.4万人、75-79歳は19.6万人、80歳以上が23.6万人で、今年2025年の農業センサスで、さらに高齢化が進むことが予想され、深刻な高齢化は待ったなしです。食料・農業農村基本法改定が与党と維新の賛成で成立し、食料自給率を軽視し、輸入に依存し、新規就農策もなく、価格保障や所得補償も拒否し農業従事者は2000年に240万人から2023年には116万人と激減。国際物流が停止すれば世界の餓死者が日本に集中し、人口の6割7,200万人にも及ぶと指摘されています。1980年の農林水産予算は3.58兆円から2024年に2.27兆円に下がる一方で、防衛予算は2.23兆円から11兆円と5倍近くと歪んだお金の使い方が問題です。地球温暖化で農家の作物の収穫への影響も起こっています。
稲作農家は、時給10円とも言われており、高齢化も進み、深刻な実態であり、食糧増産をしていくためにも新規就農支援は待ったなしですが、新規就農支援では施設機械導入の経費2分の1補助のみにとどまっています。価格保障や直接所得補償を充実すべきではありませんか。
(3)地方卸売市場について
現在の場所に移転開場してから45年経過し、市場を取り巻く環境も大きく変化する中で、千葉市の台所として、今後も役目を果たしてもらえるよう期待するものです。市は、経営戦略を立て、建て替えの計画を出しました。12年にも及ぶ間に、現在の老朽化した施設で対応できるのか、先日党市議団で現場を視察させてもらいましたが、水産棟の屋根は雨漏りし、パイプのカバーはカラスがつついてぼろぼろになっており、トイレも男性も和式になるなど寒い中、水を扱うような人たちにせめてトイレなどを先に建て替えて環境を整えていくべきではありませんか。
7.都市行政について
公共交通のあり方について
1つに、地域公共交通の対策では、生活交通バス路線維持支援に7,500万円計上し、デマンド型交通では、緑区大椎台、上大和田、下大和田地区から平山町が追加され、高津戸町地区は本格運行となりますが、市内でも若葉区をはじめ交通問題が深刻な地域が多々あり、その解消に向けて全市展開すべきではありませんか。お答えください。
2つに、運転手不足の免許取得支援や求人支援で4,126万円に過ぎません。現在、2路線が廃止し、減便の路線も多く、バスの継続運行も深刻な事態となっており、熊本市などのようにバス事業者に支援をして高齢者外出応援パスの導入をするよう求めます。お答えください。
3つに、地域公共交通計画は、市内の公共交通等について基本的な計画を作成するものですが、議員の関与はありません。もっと計画段階から関与できることも求めます。
バス対策担当課長が設置されますが、バス事業者との折衝だけでなく、利用者の声も聴きながらどのように進めていきますか。
- 建設行政について
(1)(仮称)検見川・真砂スマートインターチェンジと合わせて整備を行う検見川立体について
検見川立体の総事業費と、新年度予算はいくらですか。千葉西警察入口交差点の渋滞解消につながるのかお聞かせください。
(2)土木事務所関係予算について
身近な道路の渋滞解消や交通安全対策などで土木事務所関係予算の増額を私どもは一貫して求めてきました。新年度予算について増額となったのか伺います。
- 病院行政について
両市立病院の医師の働き方改革では、残業時間の改善に向けた取り組みが求められますが、
1つに、現状は改善されたのか、医師の増員は負担が多い科に是正はされているのですか。
2つに、介護度が高まる中、介護福祉士の採用は順調なのかお示しください。
海浜病院はあらたに「幕張海浜病院」となるようです。
3つに、海浜病院では、小児科の専攻医は、現在何名ですか。多数配置する必要性について根拠を示してください。
4つに、政策医療として市から繰り入れを必要な場合は否定しませんが、小児科医が多すぎて人件費を圧迫し、他の科とのバランスがあまりにもとれていない場合は、医師の確保のあり方も見直すべきではないのかお聞かせください。
10.教育行政について
(1)教員について
1月1日現在、教員の未配置は44名で13人分は会計年度任用職員を配置し、そのほか31名は教務主任が担任を代理するという事態になっています。千葉県は近隣1都3県で非正規教員の給与が最も低くなっています。東京都、埼玉県、神奈川県では正規も非正規も給与が同じですが、千葉県では30歳頃で正規は328,846円に対して、非正規は302,697円と低く、40歳頃では、正規は410,010円が非正規では338,015円と6万円以上の開きがあります。そのうえ、千葉県では非正規教員の同一校継続勤務を認めてきませんでしたが他の都道府県では3年連続して勤務ができます。
1つに、新年度は未配置とならないようにすること。
2つに、正規教員と臨時的任用講師の大卒の初任給、経験年数10年、平均年齢における給与の格差はありますか。
3つに、県では、臨時的任用講師の格付を1級から2級に見直しています。市が講師の格付を地域手当が高いことで見直そうとしないのは問題です。県と同様に見直しを求めます。お答えください。
- 就学援助について
物価高騰で子育て世帯の負担が増し、所得の低い小中学生のいる家庭で就学援助制度の充実を求める声が高まっていますが、自公政権は国庫負担を廃止し、縮小しようとしています。対象を生活保護基準の1.5倍まで広げて支給額も増額し利用しやすくすることが求められます。千葉市は生活保護所得基準の1倍にとどまっており、全国では1.3倍としている自治体も多く、大きくかけ離れています。所得基準を引き上げ、国はオンライン学習や卒業アルバムを拡充したようですが市も対象費目を充実すべきですが見解を求めます。
(3)アフタースクールについて
市は、子どもルームをアフタースクールに変えていこうと年間10校程度に切り替えようとしています。しかし、子どもルームでは、保育が必要なお子さんへのケアを中心に行っているものをアフタースクールでは全児童対策で子ども全体の見守りが主眼となり、気になるお子さんへのケアが行き届かなくなります。市長は、障害のあるお子さんは放課後デイケアに行けばよいとおっしゃっていたと思いますが、アフタースクールへの意向をこのまま進めるのではなく障害のあるお子さんとともに共生社会をつくっていくうえでもきめ細かいケアをしていく子どもルームを存続していくべきではありませんか。
11.選挙管理行政について
3月16日には県知事選、市長選があり、7月には参議院選挙もあります。場合によっては衆参同時選挙ともいわれています。弁護士会が主体となって小学生に模擬投票を実施している事例では、子どもたちが選挙に関心を持って政策を検討できる場になっていると大変好評です。選挙に行かれるように投票率をあげていくための取り組みと共通投票所の設置や投票所をもっと増やすべきですが、見解を求めます。
2回目の質問を行います。
1、市政運営の基本姿勢について
(1)国政について
国政についての石破政権について質問しましたが、国会で議論すべき、動向を注視するという答弁です。具体的にお聞きしますが
1つに、選択的夫婦別姓については、一般紙でもすすめていくべきと主張されていますが、市長は選択的夫婦別姓は、実施していくべきだという理解でよろしいでしょうか。
2つに、昨年日本被団協がノーベル平和賞を受賞し、今年は被爆80年と言われており、核兵器禁止条約に批准するために政府は取り組むことを強く求めていますが、市長も核兵器禁止条約を早期に批准すべきだという認識ですか。国に対して、その立場で主張すべきと思いますが見解を伺います。
3つに、企業団体献金の禁止については、世論は、禁止すべきが多数を占めていますが、市長はどう思うのかお示しください。
(2)政治資金パーティーについて
次に政治資金パーティーについてです。
1つに、政治資金パーティーに参加した場合、個人で支出するというよりも会社の経費で参加していれば、企業から献金を受け取ることになるのではありませんか。
2つに、企業立地を進めて固定資産税の免除してきた企業が参加している場合は、優遇したということでパーティー参加したことになり、見返りを求めて参加を呼びかけるということにならないのですか。
そもそも自民党政権では政治資金パーティーが大問題となっていました。政治資金パーティーの代金は「対価」として支払うため、寄付と違い、規制が緩く受け取る政治家も名前を出したくない企業にも使い勝手が良い仕組みであり、政治献金の隠れ蓑となっていると言われています。
3つに、市長が実施したパーティーでの利益率はいくらで、購入者が判明している透明度は、何%ですか。お示しください。
4つに、一人、2万円ですが何口も購入しているケースはありますか。お聞かせください。
(3)予算編成について
新年度予算編成についてですが、私どもは、物価高騰の下で、市民本位のくらしを応援する政治を求めてきました。
中小企業への物価高騰対策は、光熱水費などが月に3万円ほどの方に5万円支給するというのは、この間復活を求めてきたために、一歩前進と言えますが、しかし、光熱水費が月額3万円以下で細々と自営業を営んでいる対象も少なくありません。
1つに、なぜそういった対象者にまで拡大しなかったのですか。光熱水費が2万円以上3万円未満まで対象者を広げて救済すべきです。
学校や保育所、社会福祉施設や公共交通などの事業者への支援はあるものの一般的にこの物価高騰で困っている市民への手立ては、国から示された対策にとどまっています。
2つに、市民向けに物価高騰への対策を講じるよう国の補助金を活用して実施を求めます。お答えください。
(4)大型開発について
⑧(大型開発)新年度の予算額では、令和6年度からの繰り越し明許費を含めると、中央公園・通町連結強化に15億9,603万円、千葉駅周辺の活性化グランドデザインの改定等で、3千万円、千葉駅東口西銀座B地区優良建築物等整備に11億9千万円、千葉駅周辺ウォーカブル推進に7,000万円、稲毛海浜公園リニューアルで6,900万円、(仮称)検見川・真砂スマートインター整備に1億4,400万円、千葉公園の再整備に2億7,860万円で、蘇我駅東口駅前地区のまちづくりや新清掃工場整備を除くと、33億7,763万円にのぼります。
1月20日にも都市計画審議会があり、その中で、千葉駅から中央公園までの区間を1、2階は新たに建設するときには、商業施設にするような制約を持たせましたが、現在は、⑨(パチンコ)千葉駅から西銀座側の通りに入ると、大きなパチンコ店、⑩(漫画喫茶)質屋、漫画喫茶などがあり、パチンコ店の呼び込みの音楽が流れて、とても歩きたくなるような場所とは思えません。⑪(ホテル・ビル)マンションは建ち始めていますが、市民が千葉駅に来て歩きたくなるような仕掛けがあるでしょうか。パルコがなくなり、三越もなくなり、ただ歩くだけなら呼び込みがないため歩きやすいなどと皮肉めいた記事が朝日新聞にも掲載されていました。都市計画審議会の中でも委員からは、1,2階を商業施設にしたところで、ウォーカブルなまちになるとは限らないとの意見が多くの委員から出されていました。
1つに、千葉市では、市内の郊外に多くの大型店があり、わざわざ千葉市・千葉駅に来たくなるような理由がないのに、なぜここまでして熱心に進めているのですか。
2つに、地権者から要望されたためにこうした開発を進めているのですか。全く急ぐ必要がないと思われます。見直しを求めます。お答えください。
3つに、⑫検見川立体は、300億円もかけて行うのは、あくまで高速を使って、浅間神社まで通過する車が便利になるだけであり、それ以外の通常の車の渋滞解消策は入っておらず、しかも10年もかかる頃には、交通量も変化しており、必要性がないのに莫大な税金をかけて行う必要がまったくない事業に湯水のように注ぐことはやめるべきです。お答えください。
4つに、新湾岸道路については、費用が決まっていないのに見切り発車で莫大な税金を投入することを正当化しています。30年先に道路ができたころには、全く必要がないものを財政負担をしてまでする必要性が出てきません。ゼネコンに儲かるために道路整備が進められようとしているのではないかと思われますが、県と一緒になって進めようとしていますが、今こそやめるべきです。お答えください。
(5)公共料金の値上げについて
市民のくらしが大変な時に、県では、水道料金の引き上げを進めています。
1つに、そもそもこれだけ暮らしが大変な時に、値上げすべきではないと県になぜ言わないのですか。水道料金の値上げの中止を県に求めるべきです。お答えください。
2つに、下水道使用料は、令和8年から9年にかけて43億円も資金が不足すると見込んで圧縮をしたとはいえ、下水道使用料の値上げに対して、引き下げを求める署名に取り組んでいます。市民からは「引き上げないでほしい」といった声が多く寄せられています。市はこの声にこたえて引き上げをやめるべきです。お答えください。
3つに、国保料は、一人当たり年額2515円の値上げが予定されています。国民健康保険事業で医療費の増加で6億9千万円の歳入が不足すると言っていますが、市は一般会計からの繰り入れは約1億5千万円に過ぎません。そのため、保険料が値上げされてしまいます。国保料の負担こそ一般会計からの繰り入れを増やして、据え置くべきです。お答えください。
(6)体育館のエアコン・学校給食の無償化について
体育館のエアコン整備も多額の費用を要すると答弁。この異常な暑さの中4年も5年も体育館にエアコンのない状況は耐えられません。
1つに、早急に前倒しして、体育館へのエアコン設置の予算をさらに前倒しして実施を求めます。
学校給食の無償化についても年間約38億円の追加費用が必要だとして財源確保を強調しています。
2つに、市長に聞きますが、学校給食は、国の動きを注視するのに、大型の開発は必要だからとお金を注ぎ、新湾岸道路は、必要だと言って財源のあるなしで進めており、矛盾していると思いませんか。就学援助を受ける家庭でなくても給食費の工面は子育て家庭には大きな負担となっています。市長選では、神谷市長は給食の無償化は行わない立場だということですか。
(7)帯状疱疹予防接種について
新年度予算が付いたことは前進ですが、市民にこの問題を伝えると、なぜ5歳刻みなのか4年も待たなければならないのか。50代から発症すると言われているのに免疫機能の障害がある方は60歳からですが、基本はなぜ65歳からなのか。希望する方に、ワクチン接種をさせればよいのではありませんか。
お答えください。
(8)企業立地以外に商店街への支援を確認したところ、68ある商店街に1商店街当たりわずかに65万円ほどの補助に過ぎないそうです。今個人のお店の閉店が相次ぎ、承継者がいないこと。いても継いだ後の展望がなければ踏み切れるか迷っていることなどもあるようです。そんな時に、もっと個々のお店にあったアドバイスも含めて行っていくべきではありませんか。四国では、地方銀行が出資しながら承継者がいない企業へのアドバイスなどもしながら地域の活性化を進めています。そうした工夫も含めて予算も人も配置して商店街への支援の対策を講じるべきではありませんか。
(9)補聴器の購入助成について
先日も、党市議団が予算説明会を開催し、高齢者の方から都内の補助内容の説明を受けました。台東区では65歳以上の必要な方には非課税・生活保護を受けている方は144,900円で課税者も上限は72,450円となっています。また港区は新年度予算から60歳以上で必要とされる方に同じく上限は非課税の方は144,900円、課税者は72450円と台東区と同じと用件で示されています。
市は、熊谷市長時代に、もともとあった補聴器の助成制度をなくしてしまいました。本来は年収400万ほどの高齢者もこの補助制度が使えて、2万から3万円ほどの補助となっていました。認知症が増えて、介護給付費が増えていくよりも補聴器購入補助を増やして元気で活き活きできる高齢者を増やしていくことこそ求められているのではありませんか。台東区や港区のように購入助成を求めます。お答えください。
(10)高齢者外出応援パスについて
市のバス事業者への生活交通バス路線維持確保補助は、わずか7,500万円程度に過ぎません。熊本市では10億円を計上しています。堺市では5億円ほどで私たちの提案を実現しています。事業者のサービスでは、毎日のように乗った場合はお得なパス券のほか、免許返納後は半額になる制度もありますが、70歳以上で発行後2年間と限られており、よほどバスを利用する人以外はなかなか購入するまでとは、いかないサービスが多く見受けられます。
高齢者の年金はわずかな場合が多く、外出にわずか100円程度ならその分、外出先での買い物や食事などに費やすことができます。
地域経済の効果があり、医療費の抑制効果もあり、外出応援ができる、バス事業者も安定した経営ができると1石3鳥です。高齢者の外出応援パスを実施すべきです。お答えください。
(11)下水道施設に起因した道路陥没について
土木事務所関係予算は今年度と同額とのことですが、埼玉県八潮市では、道路上に陥没があり、トラック運転手の消息は、いまだ不明です。連日の報道で市民から千葉市は大大丈夫なのかと不安の声が寄せられています。また、国からも緊急点検を行うように通知されたと聞いております。千葉市では2019年にも緑区あすみが丘で道路の陥没があったことから、今回の件を受けて緊急対応をするよう求めますが、お答えください。
(12)武器見本市について
答弁は幕張メッセの指定管理者が県条例等に基づき、施設利用の可否を判断したものについてその内容を個別に評価することは適当ではないとなんら、抗議の声すら上げない立場に終始しています。
武器見本市を公共施設で実施しているのは全国で千葉県、千葉市だけです。1月30日に記者会見をして市長予定候補となったあたらしい千葉みんなの会の寺尾さとしさんは、川崎市でテロサイバー対策の装備品の展示という名目で川崎市のとどろきアリーナで、実施されたことを紹介し、市長が武器が展示されたら認められないと言っており、テロサイバー装備品の見本市の会場で武器のカタログが配られて、市の職員が回収したとのことでした。その後二度と川崎ではこうした装備品の展示は行われていません。
1つに、千葉市はどうでしょうか。私は2023年に中に入りましたが、銃のカタログも置いてあり、このように展示してありました。それでも神谷市長は、なんら抗議をしないということですね?
2つに千葉市は幕張メッセでは、千葉県、株式会社日本政策投資銀行に次いで、3番目の大株主となっています。12.5%も出資しているのですから、当然発言できるのではありませんか。
3つに、しかも、幕張メッセの建設事業に係る千葉市の負担金は、平成3年度から平成27年度まで総額134億5700万円も赤字の補填として負担をしてきました。市が、県任せでなく、多額の財政負担もしてきたのですから、当然中止を主張すべきではありませんか。お答えください。
中村きみえ議員の代表質疑に対する答弁 2025.2.12
【神谷市長答弁】
はじめに、国政についてお答えします。
国民の要望実現のための施策の推進についてですが、国政における課題や論点については様々な意見があると承知しておりますが、国会において議論すべきものであり。その動向を注視してまいります。
次に、予算編成についてお答えします。
まず、予算要望の反映状況についてですが、新年度予算においては、進展する少子・高齢化に対応するための扶助費等の義務的経費の増加や、各種情報ネットワークシステムの運用をはじめとした行政コストの高騰に加え、市民の生活環境を維持するために不可欠な新清掃工場の整備や、良好な教育環境を確保するための若葉区住宅地区の小学校新設といった建設事業がピークを迎えるなど、多額の財政需要が見込まれておりました。このような状況においても、喫緊に取り組むべき課題として、子ども・教育分野では、子育てと仕事を両立できる環境づくりつぃて、待機児童ゼロを継続するため、保育士等の給与改善支援を拡充するほか、多様な保育ニーズに対応するため、病児・病後児保育の運営を支援し、新規開設を促進して参ります。また、一時保護所の生活環境の改善を図るため、居室。学習室等を拡張するとともに、虐待等の未然防止を図るとともに、現に虐待等の課題に直面している家庭を支援するために、親子関係の形成及び再構築のためのペアレント・トレーニングや個別支援を新たに実施致します。さらに、不登校対策の更なる推進を図るため、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの配置体制を充実するとともに、特別支援教育の充実を図るため、特別支援教育指導員の増員や、介助員サポーターの新規配置を進めて参ります。また、中小企業者への支援についても、エネルギー価格等のコスト増加の影響を受ける事業者に対して、事業継続のための支援金を支給するとともに、引き続き、新商品の開発や販路拡大、商業者の課題解決や販売力向上を支援して参ります。加えて、人手不足が生じている業種の人材確保のための資格取得支援を拡充するとともに、市内企業の成長等を支援するため、海外での研修に向けたプログラムに新たに取り組むこととしたところです。こうした取り組みに限られた財源を重点的に配分したことにより、市民生活・市民福祉の向上と中小企業者の事業継続につながるものと考えており、引き続き、各種施策の推進を図って参ります。
次に、市政報告会に関する見解についてですが、昨年12月に開催した市政報告会は、政治資金規正法に基づき適切に開催したものです。また、いただいた会費によって本市の政策判断が影響を受けることは一切ございません。
次に、物価高騰への予算上の対応についてですが、消費者物価指数、企業物価指数ともに、依然として上昇基調であり、企業活動だけでなく市民生活への影響が続いている中、実質賃金指数については、直近の令和6年12月の速報値では、2か月連続で前年比プラスとなるなど、改善の兆しが見られており、国の対策等を通じて更なる好転を期待しているところです。こういた状況の中、現下の物価高騰への対応を含む、国の総合経済対策の決定に呼応し、昨年12月の補正予算において、住民税非課税世帯への給付金の支給について、専決処分により、迅速に対応することとしました。また、2月補正予算では、国による臨時交付金の追加配分を受け、定額減税に伴う調整給付金の不足分の給付のほか、本市独自の取組みとして、交付金を有効に活用しながら、中小企業者への支援に加え、経営コストが増加している社会福祉施設や公共交通事業者、畜産農家等に対する支援金の給付に取り組むこととしております。加えて、新年度予算においても、影響が大きい子育て世帯党の負担軽減を図るため、引き続き、学校・保育施設等の給食費高騰分の支援のほか、下水道使用料について、令和5年度より、料金の大幅な改正を抑制するための支援に取り組んでいるところです。引き続き、国からの財源を最大限有効活用しつつ、国や県の施策との整合を図りながら、必要な対応に努めて参ります。
次に、学校体育館のエアコン整備についてですが、近年の猛暑や、災害の発生状況に鑑み、児童生徒の熱中症対策や、避難所としての環境整備のため、体育館への冷暖房設備の整備が必要であると認識しております。しかしながら、市立小学校すべてに設置するためには、非常に多くの費用が必要となることが見込まれることから、国において新たに創設された、令和15年度までを期間とする「空調設備整備臨時特例交付金」に加え、財源的に有利な市債である「防災・減災・国土強靭化緊急対策事業債」や「緊急防災・減災事業債」を活用し、財源を確保しつつ、次期実施計画等に位置付けるなど、できるだけ早期に整備したいと考えております。
次に、宿泊税の徴収のあり方に対する県への意見提案についてですが、本市は、先月開催された県との意見交換会において、単独で宿泊税を徴収した場合のコスト負担が大きいことから、県による一括徴収を要望しているところであります。これまでも、県の制度案に対しては、「宿泊者数等の適正な方法により算出した交付金による市町村支援」等の要望を行うなどしてきており、その結果、補助金ではなく交付金による支援となり、その算出も宿泊者数と旅行者数を考慮した方法が示されるなど、本市の要望が受け入れられております。本市観光の振興を図るため、引き続き、本市の考えを的確に県へ伝え、調整を図っていくこととしております。
次に、都市基盤についてお答えします。
千葉駅周辺の活性化や新湾岸道路についてですが、県都の玄関口である千葉駅周辺については、市民生活の向上と本市の持続的発展に向けて、活性化グランドデザインに基づき、県都の都心にふさわしい都市機能の強化や、官民連携によるウォーカブルなまちづくりを推進するべく、財源の効果的・効率的な配分に努めながら、各種施策を展開して参ります。また、新湾岸道路については、広域的な道路ネットワークの強化により、市内渋滞の緩和や物流の効率化を通じて、経済の活性化や防災機能の強化につながるものであり、本市の持続的発展に大きく寄与することから、引き続き、計画の早期具体化に向け、取り組みを推進して参ります。なお、千葉駅周辺のみならず、都川や花見川、鹿島川などの河川を活用した魅力あるまちづくりを推進するとともに特別史跡加曾利貝塚と周辺地域の価値や魅力の更なる向上を図るため、新博物館の整備を推進するほか、住宅開発が進む幕張新都心若葉住宅地区における児童の良好な教育環境を確保するため、新設校の建設を着実に進めるなど、引き続き、各区の地域の特性を活かしたまちづくりを推進して参ります。
次に、中小企業への支援についてお答えします。
中小企業等への支援についてですが、企業立地促進事業は、立地した企業が取得した土地や建物等に係る固定資産税相当額などを、一定期間補助金として交付するもので、企業の定着ないし事業規模の拡大により、域内雇用の創出・拡大に加えて、子育てや教育、地域福祉の充実、中小企業等への支援のための税源涵養が図られるものであり、本市が、今後も持続的に発展していくためには、必要不可欠なものであると考え、重点的に取り組んでいるものであります。また、企業立地補助制度は、様々な規模の企業に対応したメニューを用意しており、中小企業を含めた市内企業の持続的成長や経営の安定化に向けた支援ともなっております。
最後に、学校給食の無償化についてお答えします。
お金の心配なく給食を食べられるようにすることについてですが、学校給食については、現状の運営においても、人件費や施設管理運営費等に市債を投じ、必要な栄養バランスを考慮しながら、安全安心な給食の提供に取り組んでいるところです。また、第3子以降のほか、生活保護や就学援助制度により、昨年度は合計17.5%の児童生徒が給食費無償化の対象となり、事業費6億円を投じていることに加え、完全無償化を実施する場合は更に年間約38億円の追加費用が必要となります。国において、昨年12月に、学校給食に関する全国調査の結果を踏まえ、法制面、児童生徒間の公平性、国と地方の役割分担、政策効果といった観点からの課題が整理されたことから、今後の具体的方策の検討について、引き続き国の動きを注視して参ります。今後、超高齢化社会の進展への対応や公共施設の老朽化対策、学校体育館根の冷暖房設備の整備を予定しており、財政需要の増加が見込まれる中、教育や子育て支援の施策全体においても、限られた財源の中で優先度を見極めて、実施すべき施策を総合的に検討する必要があり、現時点では、市単独での完全無償化の実施は困難であると考えておりますが、こうした子育て施策については、地域間格差が生じないよう国の責任において実施するべきであり、今後も強く国へ申し入れたいと考えております。以上で答弁を終わります。
私の答弁以外につきましては、両副市長、病院事業管理者、教育長並びに選挙管理委員会事務局長から答弁を致します。
【大木副市長答弁】
はじめに、予算編成についてお答えします。
県単独事業補助金について県に対して市の財源確保をなぜ求めないのかについてですが、県単独事業補助金については、令和3年7月に、知事と市長との意見交換の場において、市長から知事に県単独事業補助金の改善を要求し、これを受けて、現在、窓口を県市とも一元化しており、引き続き、新設の補助金については、他市町村と同様とすることを求めるとともに、既存の補助金についても、社会情勢の変化や、市民の皆様等への影響などを考慮しながら、県に対して改善を求めて参ります。
次に、中小企業者への支援についてお答えします。
公契約条例の制定についてですが、賃金等の労働条件は、国の法令である最低賃金法等の枠組みの中で、労使間で自主的に決定することとされております。その上で、本市における契約では、物価や労務等の上昇を見込んだ予定価格を作成するとともに、最低制限価格を設定することで過度な競争やダンピングを防ぐ仕組みとしているほか、公共工事等については、契約期間中の物価や労務費等の上昇を反映させるスライド条項を適用するなど、適切な金額での契約締結に努めているところです。公契約条例は、その効果が限定的であること、民間企業との契約のみで運営している事業者との間で公平性が保てないことなど、さまざま課題があることから、制定については、現在のところ考えておりませんが、引き続き国の動向を注視するとともに、公正・公平な入札・契約制度の構築に取り組んで参ります。
次に、災害に強いまちづくりについてお答えします。
まず、職員派遣の体制をより充実させることについてですが、派遣職員の現地における生活環境については、能登半島地震での経験を踏まえ、安全安心に応援業務当たれるよう、現地で自活できる資機材や装備品等を充実させるなど、改善に努めて参ります。一方、国では地方公共団体の業務として、応援職員等を受け入れる際の宿泊場所として活用可能な施設等のリスト化を定めており、全国的に災害派遣における生活環境の向上が図られているところです。また、送り出す職場側の環境については、大規模な被災地派遣を行う場合に幹部会議において、市長から派遣の意義や必要性等を発信し、全庁一丸となって支援に取り組むという機運の醸成を図るとともに、派遣職員が不在の間の業務調整や役割分担の見直し等、協力体制が円滑なものとなるよう取り組んでおります。さらに、人事考課において、派遣される職員だけでなく、動員職員の業務を引き継いだ職員や動員の影響により担当外業務に協力している職員など、直接動員されていない職員の積極性や貢献性等も適切に評価を行っております。
次に、罹災証明書の課題に対する本市の対応についてですが、過去の大規模災害
において、被害認定調査に時間がかかることや、判定結果への理解が得られず再調査を要したことなどにより、罹災証明書発行の遅れが問題となっていました。この課題を解決するために、タブレット端末を使った現地調査により、大幅に調査時間を短縮し、調査員により判定の違いをなくすことができる。被害認定調査システムを石川県をはじめとする一部の自治体が導入しています。能登半島地震の支援で被害認定調査業務に従事した職員も、システムを操作し、その有効性を体験しており、本市でも導入を予定しているところです。
次に、国に住宅再建の支援金増額を求めることについてですが、現行の被災者生活再建支援制度では、住宅が全壊した世帯に対し、基礎支援金、加算支援金を合わせて最大300万円が支給されることとなっております。このほか、能登半島地震においては、国の臨時交付金を財源として、対象世帯へ最大300万円の給付金等が措置されております。制度の拡充については、大都市民生主管局長会議において被災世帯が速やかに生活を再建できるよう、国に要望しているところです。
次に、本市でのボランティア受け入れ体制についてですが、大規模災害発生時には、市社会福祉協議会と連携して災害ボランティアセンターを開設し、一般ボランティアの募集、受け入れや活動調整を行うこととしております。また、円滑な受け入れのため、平時からセンター開設訓練を行ない、関係機関と連携を深めるなど、適切な支援が提供できるよう準備を進めております。災害発生時に迅速かつ効果的にボランティアを受け入れる体制を構築できるよう、引き続き取り組んで参ります。
次に、マンホールトイレのっ整備とトイレトレーラーの予算化についてですが、まず、マンホールトイレにつきましては、来年度は、千葉工業高校、千葉南高校、生浜高校、泉高校、千葉大宮高校および土気高校の6校に整備予定です。 また、トイレトレーラーにつきましては、現在、国において準備を進めている車両を登録し、データベース化する仕組みや、平時における効果的な活用方法などと併せて、これまで推進してきました本市の災害時のトイレ対策の総合的な枠組みの中で検討するものとしています。
次に、個別避難計画の対象者の人数と割合、また、全ての対象者について計画を作成すべきについてですが、本市では、土砂災害警戒区域にお住まいの方や、重症心身障害児者など、5つの要件に該当する方、約3,000人のうち同意を得られた1,171人を対象に個別避難計画の作成を進めております。そのうち、今年度末までに657人分、残りの514人分を来年度作成することで、対象者全員分の計画作成を予定しています。なお、今後も、新たに対象となる方や、今回は同意されなかった方についても、制度の重要性等を丁寧に説明しながら、作成を進めて参ります。
次に、市民会館の建替えについてお答えします。
まず、川崎市の視察結果の再整備計画への反映についてですが、ターミナル駅に隣接した文化ホールと民間施設との融合施設における整備の考え方やスケジュールについて意見交換を行い、令和3年度の千葉市民会館再整備に係る基本計画策定の参考といたしました。
次に、席数の運用についてですが、千葉市民会館再整備に係る基本計画における、文化芸術の振興や地域活性化などの基本コンセプトを実現するため、新市民会館の大ホールは、演劇やミュージカル、バレエなどの大型舞台芸術や、クラシック、ポピュラー音楽などのプロの大規模公演から、市民団体の公演や全国レベルの大会、大規模イベントの誘致まで、様々なジャンルに対応していく必要があることから、大ホールを1,500席程度としたところであり、引き続き、本計画に基づき検討を進めて参ります。
次に、複合施設の整備での荷物の搬入についてですが、千葉市民会館再整備に係る基本計画において、大ホールは、演劇やミュージカル、バレエなどの大型舞台芸術も含め、様々なジャンルに対応することとしており、これに基づき、荷物の搬入についても、今後、検討を進めて参ります。
次に、建設地と市民参加での整備についてですが、新市民会館の整備場所については、現在、JR東日本との協議を継続しながら、市有地での整備を含め、JR東日本千葉支社跡地と市有地で建設した場合と比較検証するため、概算建設費の積算や周辺環境等の条件整備を行うとともに、交通アクセスや商業施設の立地状況など総合的な観点から検討しているところです。
次に、市民参加での整備についてですが、千葉市民会館再整備に係る基本計画の策定にあたり、市民意見募集の実施や策定後の説明会の開催など、市民のご意見を伺いながら取組みを進めてきたところであり、今後も再整備を進める中で、必要に応じて利用者等のご意見を伺って参ります。
次に、ジェンダー平等についてお答えします。
性被害などを防ぐ取り組みと相談場所の周知についてですが、性犯罪や性暴力、配偶者等からの暴力、いわゆる「DV」やセクシャルハラスメントなどの行為は重大な人権侵害であり、決して許されるものではないと考えております。このような暴力を防止するため、学校などへのリーフレットの配布をはじめ、国の「女性に対する暴力をなくす運動」期間や男女共同参画センターでの関連講座の際にも周知するなど、様々な機会を捉えて市民意識の醸成に努めております。また、相談については、男女共同参画センターのハーモニー相談や、「NPO法人千葉性暴力被害者支援センターちさと」「公益社団法人千葉犯罪被害者支援センター」、ワンストップ支援センターへつながる全国共通短縮ダイヤル「#8891」、千葉県警察本部の性犯罪被害に関する相談窓口の短縮ダイヤル「#8103」等があり、案内の配布や市ホームページへの掲載などにより周知を図っているところです。
次に、帯状疱疹予防接種についてお答えします。
まず、今回の定期接種の対象者についてですが、各年度中に65歳を超える方、及び60歳から64歳で、ヒト免疫不全ウイルスにより、免疫機能に身体障害者手帳1級相当の障害がある方、また5年間の経過措置として、各年度中に70歳、75歳といった5歳刻みの年齢を迎える方、さらに、来年度に限り、100歳以上の全ての方が対象となります。
次に、ワクチンの種類についてですが、1回接種の生ワクチンと、2回接種の不活性化ワクチンの2種類があり、どちらか一つのワクチンを選択して、接種を受けていただくことになります。
次に、非接種者の自己負担額についてですが、生ワクチンが4,000円、不活性ワクチンが1回あたり1万円としております。
次に、障害者施策についてお答えします。
まず、天海訴訟の最高裁判所への上告受理の申し立て後の現状についてですが、 上告受理申立書の提出後、現在まで、最高裁判所から連絡はありません。
次に、介護保険優先原則の適用についてですが、国通知により、一律に介護保険サービスを優先するのではなく、具体的な申告者の利用意向等を把握した上で、必要としている支援内容を介護保険サービスで受けることが可能かを適切に判断するよう助言されており、本市においても国通知に基づき対応しております。
次に、旧優生保護法に関わる補償金の支給についてですが、補償金の申請窓口は県であり、本市は対象者への周知の協力を行っております。リーフレットを市役所本庁舎や各区役所・保健福祉センターなどに配架するとともに、障害者団体や施設等に周知を依頼しております。また、対象者やそのご親族の方が補償金の申請をされる際、戸籍事項証明書の添付が必要となる場合がありますが、本制度の趣旨に鑑み、無料で証明書を交付することとしております。
次に、生活保護行政についてお答えします。
まず、基準単価の引き上げについてですが、生活保護基準は、国において一般低所得世帯の消費実態との均衡が図れるよう、5年に一度定期的な見直しが行われており、直近では令和5年10月に改正されております。コロナ禍による影響やエネルギー・食料品を中心とした物価上昇の影響を考慮し、昨年度及び今年度は、臨時的・特例的な措置として、一人当たり月額1,000円が加算されております。さらに、来年度及び8年度は、500円を加算し、月額1,500の特例的加算が行われるものと承知しております。
次に、ケースワーカーの担当世帯数についてですが、昨年4月時点のケースワーカーは201人で、一人当たりの担当世帯数は約88世帯であり、国が示している配置標準である一人当たり80世帯を上回っております。ケースワーカーの新年度における一人当たりの担当世帯数については、現時点で算出することはできませんが、引き続き、適正な配置に努めて参ります。
次に、動物愛護センターの建設についてお答えします。
まず、建設候補地選定の状況についてですが、現在、整備予定地の決定に向け調整を行っております。
次に、周辺住民への説明についてですが、新たなセンターの整備にあたっては、住民の方のご理解をいただけることが重要であると考えており、近隣の町内自治会長に整備計画についてお知らせするとともに、周辺にお住まいの方を対象とした説明会を開催するなど丁寧な説明を行なって参ります。
次に、補聴器助成についてお答えします。
補聴器の購入助成の実施についてですが、耳の聞こえづらさを感じている人は、日常生活の中で支障が多く生じていると承知しておりますが、高齢者人口の増加やニーズが多様化する中で、助成制度の検討にあたっては優先順位を考慮する必要があると考えております。なお、国に対して他の政令指定都市とともに、全国一律の助成制度の創設を要望しているところであり、引き続き、その動向を注視して参ります。
次に、特養ホームの数、介護職員の改善についてお答えします。
まず、整備数についてですが、特別養護老人ホームは、入所を待つ方がいまだ一定数いることから、介護保険事業計画に沿って着実に整備できるよう努めて参ります。
次に、介護職員の処遇改善についてですが、一義的には国の責任において対応すべきであり、市独自の手当の支給は考えておりません。本市としては、 これまでも国に対し、改善を求めてきたところであり、人材育成の取り組みに対する介護報酬の加算など、段階的な設置が講じられてきたものの、引き続き、更なる改善を要望して参ります。
次に、国立病院機構についてお答えします。
国立病院機構が運営する病院への支援を国に要望することについてですが、本市においては、救急医療を担う医療施設などに対する支援や、実態に即した診療報酬とすることなどについて、大都市衛生主管局長会議などを通じて国に対し要望を行っており、今後も国による市内医療機関への財政支援について要望して参ります。
次に、千葉市こども若者基本条例についてお答えします。
まず、こども若者支援室の役割としては、こども・若者基本条例の制定を契機に、こどもや若者に関する施策を全庁的に推進するとともに、特にこれまで行政の支援が届きにくかった年代へのサポートを強化するほか、こども・若者の意見表明や社会参画のさらなる促進を図ることなどを考えております。また、対象となる若者の年齢については、国の「こども大綱」を踏まえ、青年期にある概ね30才未満とし、施策によってはそれ以降の年齢の方まで対象とすることしております。
次に、こどもたちの課題とその対策や意見表明の保障、相談に関する周知についてです。
まず、こどもたちを対象としたアンケート調査やワークショップなどの取組みにおいて、こどもの権利に関する理解をこどもも大人もより深めることが課題との意見があったことから、年代別のリーフレットや動画などを作成し、様々な機会を通じて、こどもや若者から大人まで幅広い年代の方への周知を図って参ります。また、意見表明の保障については、こどもや若者が意見を表明する場として会議体を新たに設置するほか、日常的に自分の意見や考えを表明することができるよう、家庭や学校などにおける意見表明の重要性について周知して参ります。さらに、相談に関する周知については、子ども・若者総合センター「Link」をはじめとする様々な相談機関を、リーフレットへ掲載するなど、効果的な周知方法について検討して参ります。
次に、市独自の給付型奨学金の制度化についてですが、高等教育費の負担軽減については、令和2年4月より「高等教育の修学支援新制度」として、国において大学等の授業料等減免及び給付型奨学金が実施されており、令和5年12月に閣議決定された「こども未来戦略」における「こども・子育て支援加速化プラン」の中では、授業料等減免及び給付型奨学金の中間層への拡大や多子世帯の授業料無償化など、当該制度のさらなる充実が示されております。このため、現時点において本市独自の給付型奨学金制度の創設は考えておりませんが、引き続き、必要な情報提供や相談対応に努めて参ります。
次に、児童相談所設置についてお答えします。
まず、一時保護所の心理療法担当職員の今後の採用計画についてですが、条例案では、内閣府令に合わせ、令和8年3月末まで経過措置を設けており、現状では、必要な心理療法担当職員を配置するとともに、東西児童相談所に配置されている児童心理司が一時保護児童の心理ケアを適切に行っております。また、経過措置期間満了後の令和8年4月には、職員の採用を行う事で、条例の基準を満たす配置を行なって参ります。
次に、現在の児童相談所の大規模改修の予定についてですが、開設からおおよそ30年が経過した現在の児童相談所については、施設の老朽化が進んでいることから、東部児童相談所の移転後に、引き続き使用するためには改修が必要であると認識しております。改修の時期や具体的な内容等については、東部児童相談所の移転整備の進捗状況も踏まえ、検討して参ります。
次に、児童虐待の対応についてお答えします。
船橋市で発生した死亡事案の検証についてですが、本市では千葉市社会福祉審議会児童福祉専門分科会の下部組織である処遇検討部会において、千葉県及び船橋市が設置したそれぞれの検証委員会と連携の上、事案の検証を実施しており、自治体間の支援や引継ぎについても検証を行なって参ります。
次に、児童養護施設職員の待遇改善についてお答えします。
職員確保につながる待遇改善についてですが、児童養護施設で働く職員に対しては職員の負担軽減に向け、夜間業務等への補助職員配置をはじめとして複数の補助制度を設け、これまでも待遇改善を図ってきております。今後も、児童養護施設職員が働きやすい環境を整えることにより、子どもたちへの充実した支援が行なえるよう取り組んで参ります。
最後に、保育所についてお答えします。
公立保育所は、公立のままで建て替えていくべきではないかについてですが、認可保育所における保育については、保育所保育指針のほか、法令等に基づく基準や市の条例等に則り実施されることから、公立か民間かによる優劣はないものと考えております。一方で、公立保育所については、民間保育施設に対する指導監督や支援・助言のために必要な能力・経験を有する職員の育成のほか、民間の参入が見込まれない地域における保育の提供の保障など、本市が果たすべき役割があることを踏まえ策定した「公立保育所の施設管理に関する基本方針」に基づき、建て替えを進めて参ります。
以上でございます。
【橋本副市長答弁】
はじめに、予算編成についてお答えします。
まず、県の水道料金、下水道使用料、について国民健康保険料の不足額と値上げによる市民への影響額についてですが、県営水道は、令和8年度からの次期中長期経営計画の財政収支見直し赤字が見込まれるとしているものの、不足額については明らかにしておらず、水道料金については、今後、基本料金や従量料金などの料金体系に係る検討を行い、規定案を取りまとめるとしていることから、現時点では影響額をお示しできません。下水道事業については、現時点で試算したところ、8年度から9年度の2年間で、43億円程度の資金が不足すると見込んでいます。8年度から規定を行った場合、1カ月当たり20立方メートルを使用する一般的な家庭の影響額は、月額で320円程度となり、市民の皆様の負担軽減ができないか検討することとしております。来年度の国民健康保険事業については、医療費の増加により、6億9,000万円の歳入が不足すると見込んでいます。保険料改定にあたっては市民の皆様への影響も考慮し、1億8,000万円の財政調整基金の繰り入れも行う事としており、被保険者ごとの影響額は、所得状況などにより異なりますが、1人当たりに換算しますと、年額で2,515円となります。
次に、水道事業の赤字の解消についてですが、昨年11月に行なわれた第3回千葉県と千葉市の連絡推進会議において、県企業局の施設となる予定の長柄浄水場から第三者委託により市営水道に送水することについて検討を進めていくことで、県と基本的な方向性を確認したところです。このことによって、所有する水利権等の活用による水源費用の二重負担の解消や老朽化した土気浄水場の廃止などを図ることができると考えており、現在、県市双方の事務レベルで詳細な条件等を協議しております。
次に、幕張メッセでの展示会の開催についてお答えします。
展示会に対する受け止めについてですが、幕張メッセの指定管理者が、県条例等に基づき、施設利用の可否を判断したものについて、その内容を個別に評価することは適当ではないと考えております。
次に、プラスチックス分別についてお答えします。
まず、モデル事業の実績と課題についてですが、モデル事業における組成分析の結果から、世帯当たりの排出量や再商品化の対象外となる不適物の割合のほか、収集車の積載可能量などのデータを把握することができました。課題としてはより合理的でわかりやすい分別ルートにすることや、ゴミ袋の飛散防止の対策が必要であることなどが挙げられます。
次に、計画の前倒しについてですが、「千葉市一般廃棄物(ごみ)処理基本計画」においても「前倒しでの実施の可能性あり」としているとこであり、2029年度の実施を目途にしつつ、前倒しについても検討していることとしております。
次に、CO2排出についてお答えします。
産業部門の事業者に対してCO2の排出削減を求めることについてですが、各事業者は2050年のカーボンニュートラルの達成に向けてロードマップを作成し、計画的にCO2の排出削減に取り組んでいることから、本市においては、排出削減効果の高い革新的技術開発や設備投資への財政支援を国へ要望するなど、各事業者の取組みが着実に進むよう支援しております。
次に、買い物支援についてお答えします。
本市の対策についてですが、地域からの買い物支援に関するご相談やご要望をいただいた場合には、関係局部の連携のもと、大手スーパーや移動販売事業者などへ情報提供するとともに、あんしんケアセンターなどの相談機関において、買い物が困難になっている方の実情に応じ、利用可能な福祉サービスや地域ボランティアによる支え合い活動、事業者が行なっている宅配などの買い物サービスの案内等を行っているところです。
次に、農業のあり方についてお答えします。
新規就農支援についてですが、国の制度において、就農前に「就農準備資金」が最長2年間、就農後は「経営開始資金」が最長3年間支給され、就農時に必要な機械・施設の導入に対しては、「経営発展支援事業」による補助制度が用意されております。また、本市独自の取組みとしても、就農前に農業に関する知識や技術を学ぶ「ニューファーマー育成研修」を実施するとともに、就農時の経費負担抑制のため、市内農業者の中古農業用機械等の新規就農者へのマッチングを行うほか、「未来の千葉市農業創造事業」においても、機器導入等に係る新規就農者向けのメニューを用意するなど、就農前から就農後まで多岐にわたる支援を行っているところです。
次に、地方卸売市場についてお答えします。
現施設の老朽化対応についてですが、市場運営を継続するために必要な施設の修繕や設備の更新につきましては、施設機能の維持と場内の安全性を最優先として、これまでも場内事業者の意見を伺いながら、適宜、実施してきたところです。今後、新市場への建替えなど、再整備の進行状況や費用対効果を踏まえ、必要に応じて対応することとしております。
次に、公共交通のあり方についてお答えします。
まず、デマンド型交通の全展開についてですが、地域の暮らしを支えるために、だれもが移動しやすい環境を整えることは重要であると考ええおり、既存路線バスの維持やコミュニティバスの運行、公共交通を補完するデマンドタクシーやグリーンスローモビリティなど様々な施策を組み合わせて取り組んでおります。デマンド型交通の全市域への導入は、既存バス路線との競合が避けられず、路線の維持に影響を及ぼす可能性があることから、引き続き公共交通不便地域を対象に、導入を検討して参ります。
次に、高齢者外出応援パスの導入についてですが、路線バスは市民の皆様の移動を支える重要な社会インフラであることから、昨今のバス事業者の厳しい経営環境を踏まえ、路線の維持・存続のために運転手養成支援や燃料費高騰に係る事業継続支援等を実施しております。高齢者向けサービスとしましては、既に市内のバス事業者が自ら、運転免許の返納者への運賃割引や乗り放題となる年間パスポートの販売を行っており、外出応援パスの導入は考えておりません。引き続き、庁内関係部局とも連携し路線バス事業の持続性を高めるため、事業者への支援などに取り組んで参ります。
次に、公共交通計画についてですが、本市では、来年度地域公共交通計画の改定に取り組むこととしております。検討にあたっては、千葉市地域公共交通活性化協議会で議論いただくこととしており、同協議会の設置条例に基づき、鉄軌道事業者や、千葉県バス協会、千葉県タクシー協会などの公共交通の業界団体のほか、千葉商工会議所、公募による市民の方々など、それぞれの委員から利用者としての立場も含めた幅広いご意見を伺う予定です。また、利用者ニーズを踏まえた持続可能な公共交通ネットワークの形成が図れるよう、広く利用者の皆様を対象としたアンケート調査も予定しております。
次に、(仮称)検見川・真砂スマートインターチェンジと合わせて整備を行う検見川立体についてお答えします。
検見川立体の総事業費と新年度予算についてですが、事業主体である、国土交通省千葉国道事務所から、総事業費は約300億円、来年度予算は成立していないため、お示しすることができないと伺っております。また、検見川立体の整備による千葉西警察入口交差点の渋滞解消についてですが、国道357号の市原方面に向かう車線が当該交差点を立体で超えることから、交差点付近の交通の流れが改善され混雑緩和が図られるものと考えております。
最後に、土木事務関係予算についてお答えします。
新年度予算についてですが、本議会に提案しております補正予算を含め98億円で、今年度予算と同額となっております。
以上でございます。
【病院事業管理者答弁】
病院行政についてお答えします。
まず、医師の働き方改革についてですが、両病院において策定した医師労働時間短縮計画に基づき、他職種へのタスクシフト・タスクシェア、業務の見直しのほか面接指導医による面接促進などの取組を進めているところです。なお、両病院の医師1人当たりの時間外勤務の時間数は、今年度の4月から12月までと前年度の同期間を比較すると、月平均で約4時間短縮しております。引き続き、医師の負担軽減を図るため、医師労働時間短縮計画に基づく各種取組みなどを進めるほか、各診療科の実情に応じた必要な人材・人員の確保に努めて参ります。
次に、介護福祉士の採用についてですが、今年度において会計年度任用職員を2人採用し、本年2月1日現在、両病院で合わせて、正規職員9人、会計年度任用職員人を配置しております。引き続き、必要に応じて介護福祉士の確保に努めて参ります。
次に、海浜病院の小児科の専攻医は現在何名か、多数配置する必要性があるのかについてですが、本年2月1日現在、海浜病院の小児科と新生児科で合わせて11名の専攻医が在籍しております。海浜病院は、小児科領域の専門医研修基幹施設として、これまでに数多くの専攻医を育成し、千葉県内の小児医療水準の向上を図ってまいりました。その結果、小児科専門医を目指す研修医から、専門研修プログラムを受ける機関として、千葉県内で最も多くの応募があり、憂きれているところです。引き続き専門医研修基幹施設として、多様な症状や疾患への対応ができる小児科医を育成して参ります。
最後に、小児科医が多く、他の診療科とのバランスがとれていない場合には医師確保のあり方を見直すべきについてですが、海浜病院は地域小児科センターとして365日24時間、内科、下架の疾患を問わず前年度においては年間約3,000件の小児の救急車運搬を受け入れており、夜間の救急外来においても、緊急性が高い病気の小児患者に迅速で適切な対応を行う体制を整えております。市内唯一の小児科二次輪番病院として機能するために、現在、夜間の救急外来は原則2名で対応しております。医師の働き方改革に観点からも、宿直等の回数には制限があるため、正規の医師のほか専攻医を含め、配置が必要であると考えております。海浜病院の果たす役割と市民が必要とする安全・安心な医療を一人でも多くの市民に提供する観点から、引き続き体制の充実・強化に取り組んで参ります。
以上でございます。
【教育長答弁】
はじめに、ジェンダー平等についてお答えします。
性被害を防止するための子どもの時からの教育についてですが、本市では、毎年4月を「生命(いのち)の安全教育月間」とし、全市立学校でリーフレットを活用し、子どもの権利を学習するほか、小学校におけるCAP(キャップ)絵本の読み聞かせや、中学校・高校における動画教材の視聴など、発達段階に応じた教育を実施しております。このほか、子どもたちが自分自身を守る力を養う「CAPワークショップ」の実施や、郵便料金不要で手紙による相談ができる「子どもにこにこサポート」など、性暴力被害を防止し、早期に発見するため、啓発や相談体制の整備に取り組んで参ります。今後も、子どもの権利や、自他ともに尊重される関係性などについて、学校教育全体を通じて理解促進を図るとともに、子どもへの性暴力を根絶するため、外部有識者による研修を実施するなど、着実かつ効果的な取り組みを一層推進して参ります。
次に、教員についてお答えします。
新年度は未配置とならないようにすることについてですが、臨時的任用講師を確保するため、定期的な講師登録説明会を開催するほか、過去に本市で働いていた人材に電話連絡を行うなど、新年度を迎えるにあたり未配置が発生しないよう努めて参ります。また、年度当初において、産前産後休暇等の取得予定がある教職員に対しては、4月当初から前倒しで代替職員を配置し、円滑な引継ぎを行えるように配慮して参ります。
次に、正規教員と臨時的任用講師の給与の格差についてですが、任期の定めのない教員、いわゆる正規教員は、大卒の初任給で比較すると、給料月額・地域手当等の合計が305,546円に対し、臨時的任用講師は、303,513円となっております。
同様に、経験年数10年では、382,116円に対し、356,759円、正規教員の平均年齢38歳では、432,372円に対し、380,102円となっております。
次に、臨時的任用講師の格付けの見直しについてですが、正規教員は学校の運営全般や長期的な教育方針の策定などにも携わっている一方、臨時的任用講師は臨時的な人員補充として任用していることから、長期的な計画に関わることが正規教員と比較して少ないなど、業務内容にも一定の差が生じております。格付けについては、正規教員と臨時的任用講師が学校内で担っている役割分担の再整理などを含め、今後、見直しの必要性について研究して参ります。
次に、就学援助についてお答えします。
所得基準の引き上げ及び対象費目の充実についてですが、就学援助の算定にあたっては、国の生活保護基準を準用しております。国の生活保護基準は、令和5年の改定により見直されたものの、平成24年の水準には達していないため、本市では、24年の生活保護基準をそのまま採用することで、就学援助を受けられなくなる児童生徒が出ないよう配慮しております。また、対象費目の充実については、自治体により採用する費目が異なることから、引き続き国および他自治体の動向を注視し、適切に対応して参ります。なお、オンライン学習通信費については、対象費目としておりませんが、通信環境が整っていない家庭に対して、Wi-Fiルーターの貸し出しを行っております。
最後に、アフタースクールについてお答えします。
アフタースクールへの移行についてですが、障害のある児童の放課後の居場所としてはアフタースクールや放課後デイケアなどもあります。そのため、アフタースクールへの移行にあたっては、子どもルームにおいて培われた「安全・安心な居場所」及び「健全育成の場」としての役割を適切に継承する取り組みを行っております。具体的には、子どもルームと同様に、医療的ケアを必要とする児童を含む全ての児童が住所出来るよう体制を整えており、支援員等の資質向上や配慮が必要な児童への職員の追加配置のほか、看護師を派遣するなど、自児童の実情に応じた対応に取り組んでおります。
以上でございます。
【選挙管理委員会事務局長答弁】
選挙についてお答えします。
まず、投票率を上げていくための取組みについてですが、市長・知事選挙をはじめ、今年予定されております選挙においては、選挙に認知度を高めるための選挙時啓発として、投票所入場整理券や市政だより、市ホームページなどによる選挙期日や投票所等の周知に加え、横断幕等の屋外広告、街頭啓発や広報宣伝車による巡回啓発、市広報番組や市公式SNSによる周知など、様々な媒体を活用した啓発を実施する予定です。特に、市長選挙では、これらの啓発に加え、新たに市内の映画館において映画上映前に動画広告を放映するほか、JR千葉駅のペリエビジョンなどのデジタルサイネージを利用した広告や、若者向けのSNS・Web広告を強化するなど、積極的な投票参加につながるよう周知啓発を実施して参ります。また、将来の有権者への啓発と保護者の投票を促すための「親子で投票に行こうキャンペーン」や、若者の政治意識を高めるため、実際の選挙事務を体験してもらう高校生の選挙事務従事など、若年層を意識した啓発にも努めて参ります。
最後に、共通投票所の設置と投票所の増設についてですが、共通投票所を設置することは、選挙人にとって投票できる場所が増える効果が期待でき、投票環境の向上に資する方法の一つと認識しておりますが、課題として二重投票防止のためのネットワークに対応した当日投票システムの改修が必要となります。この改修にあたっては、国が推進する自治体情報システムの標準化によるシステム改修・切り替えの影響を受けることから、その見通しが立ち次第、実施できるよう引き続き研究して参ります。
以上でございます。
<2回目>
【神谷市長答弁】
はじめに、国政についてお答えします。
まず、選択制夫婦別姓についてですが、仕事をする上での支障があることなどを理由に、経済団体等から導入を求める意見がある一方で、アンケート調査などでは意見が分かれております。現状の維持、また導入のいずれも課題が指摘されていますが、国の法制審議会が答申した案が示されてから長い年月が経過しており、今国会において具体的な議論が行なわれると期待しています。
次に、核兵器禁止条約の早期批准についてですが、本市が平成21年から加盟し、すべての政令指定都市を含む国内1,740都市が加盟する平和首長会議において、先月17日に日本政府に対し、核兵器禁止条約の早期署名・批准を含む核兵器廃絶に向けた取組みの推進について要請したところであり、引き続き同会議を通じて批准等を求めて参ります。
次に、政治活動における寄附のあり方についてですが、様々な意見があることは承知しておりますが、国会において議論すべきものであり、その動向を注視して参ります。
次に、私の市政報告会についてお答えします。
会社の経費による参加の場合、企業からの寄付を受けることになるのではないかなど4点のご質問をいただきましたが、関連がありますので、一括してお答えします。昨年12月に開催した市政報告会は、政治資金規正法に基づき適正に開催したものであり、収支の報告についても、今後、適正に処理して参ります。なお、いただいた会費によって本市の政策判断が影響を受けることは一切ございません。
次に、予算編成についてお答えします。
まず、中小企業への物価高騰対策についてですが、支援金の給付要件につきましては、市内事業者への聞き取り結果や他市の事例などを踏まえて設定するとともに、電気、ガス、ガソリン等に係る費用の合計が月3万円に満たない場合でも、原材料費等を含めた合計が3か月平均で月50万円以上の場合は給付対象としております。これまでに同様な要件で実施した支援でも、第1弾は9,408件、第2弾は8,868件の実績があり、多くの事業者にご活用いただける要件設定であると考えております。対象となる事業者の皆様に漏れなくご活用いただけるよう、周知等に取り組んで参ります。
次は、市民向けの物価高騰対策についてですが、繰り返しとなりますが、昨年12月の補正予算では、住民税非課税世帯への給付金の支給を迅速に予算化するとともに、新年度予算でも、子育て世帯等に対する学校・保育施設等の給食費高騰分の支援のほか、下水道使用料について、令和5年度より、料金の大幅な改定を抑制するための支援に取り組んでおり、国の交付金は、配当額全てを活用することとしております。なお、国においては、ガソリン価格や電気・ガス料金の負担軽減策、県においても、LPガスの高騰対策等を、本市も含めて実施することとしており、引き続き、国や県の施策との整合を図りながら、必要な対応に努めて参ります。
次に、都市基盤についてお答えします。
まず、千葉駅周辺の取組を進める理由についてですが、千葉駅周辺を含む千葉都心は、県都である本市の中心的な拠点であり、高次都市機能や交通機能の集積による広域的・中枢的な役割を担う地域として、さらなる発展を目指しております。 このため、経済、産業、文化等の機能の充実とともに、さらに多様な人々が集まり交流する、魅力と活力ある拠点として、育成・整備していく必要があると考えております。
次に、千葉駅周辺の都市基盤の見直しについてですが、千葉駅ビルの建替えや周辺の再開発事業などを契機とした千葉都心全体のリニューアルにより、エリア全体の活性化につなげていくために、西銀座地域などに駅前業務・商業コアを形成し、人の流れをまちに引き込み、恒常的な賑わいを創出し、回遊性を高めることで、新たな価値の創造につながると考えており、中央公園プロムナードなど、都心部の個性的なエリア間をつなぐ軸について、ひとつの大きな広場・公園の様な空間形成を推進し、「車中心」から「人中心」へのウォーカブルなまちづくりを進めることとしております。これらの取組みは「千葉駅周辺の活性化グランドデザイン」や「ちば・まち・ビジョン」に位置付けて進めているところであり、今後も、財源の効果的な配分に努めながら、各種施策を展開して参ります。
次に、検見川立体及び新湾岸道路の整備については、関連がありますので、併せてお答えします。検見川立体は、国道357号の「千葉西警察入口交差点」から「稲毛浅間神社前交差点」区間が渋滞しており、地域課題となっていることに加え、将来推計においても交通量の増加が見込まれており、この区間の渋滞を緩和するために必要なリノベーションであると考えております。また、新湾岸道路についても、今後、千葉港(ちばこう)の機能強化や物流施設の立地により、さらなる交通渋滞の増大が見込まれる千葉県湾岸地域の交通容量不足を解消し、本市の広域的な道路ネットワークの強化に必要な道路であると考えております。このことから、両事業は、将来にわたる本市の持続的な発展のために、極めて重要であると認識しており、丁寧な情報発信や市民の皆様のご意見を踏まえた国への働きかけなどを行いつつ、引き続き、事業主体である国に協力して参ります。
次に、体育館のエアコン・学校給食の無償化についてお答えします。
まず、体育館へのエアコン設置についてですが、繰り返しになりますが、国において新たに創設された、「空間設備整備臨時特別交付金」に加え、財源的に有利な市債を活用し、財源を確保しつつ、次期実施計画等に位置付けるなど、できるだけ早期に整備したいと考えております。
最後に、学校給食の無償化についてですが、繰り返しになりますが、第3子以降のほか、生活保護や就学援助制度により、支援が必要な家庭には概ね無償化を実施しているところです。
以上でございます。
【大木副市長答弁】
はじめに、公共料金の値上げについてお答えします。
一般会計からの繰り入れを増やし、国民健康保険料を据え置くことについてですが、国民健康保険事業の運営は、必要な額を保険料及び法定の公費で賄うことが本来の姿であり、将来にわたって持続可能な事業の運営を図るためには、高齢化や医療の高度化などにより医療費の増加が続く中、一定の保険料を被保険者にご負担いただくことはやむを得ないものと考えております。また、国民健康保険料の引き上げ幅の抑制のため、来年度も財政調整基金より、1億8,000万円を繰り入れすることとしております。引き続き、保険者として実施できる歳入確保と歳出抑制の取組みを推進し、保険料上昇の抑制に努めるとともに、国に対して、被保険者の保険料高騰を抑制する財政支援措置を働きかけて参ります。
次に、帯状疱疹予防接種についてお答えします。
定期接種の対象者についてですが、国の厚生科学審議会において検討した結果、帯状疱疹の罹患患者数が70歳代にピークを迎えることや、ワクチンの有効期間等を考慮し、対象者が65歳と決定されたものです。また、同審議会における議論の中で、65歳以上の人口が多いことや、ワクチンの安定供給等を考慮し、5年間の経過措置として、5歳刻みの年齢を対象に加えたところであり、本市におきましても、国の方針に沿って対象者を決定しました。
最後に、補聴器の購入助成についてお答えします。
購入助成の実施についてですが、今後、高齢者の増加に伴い、介護、医療、生活支援などのニーズがさらに増加・多様化することが見込まれていることから、検討にあたっては、他の施策との優先順位や財政の確保策を考慮する必要があると考えております。なお、他の政令指定都市とともに、国に対して全国一律の助成制度の創設を要望しており、その動向を注視して参ります。
以上でございます。
【橋本副市長答弁】
はじめに、公共料金の値上げについてお答えします。
まず、水道料金の値上げについてですが、近年、資材価格や電気代など光熱費の高騰で、上下水道も含め、事業を行っていく際の経費が増加しており、同様な状況にある県営水道におきましても、今後数年間の財政収支見通しは厳しいものになっていると承知しています。一方で、料金の値上げは、長期化する物価高騰により、厳しい状況にある市民生活に影響を与えることから、県には、値上げ幅の抑制や市民への丁寧な説明をしていただきたいと考えております。
次に、下水道使用料についてですが、千葉県の流域下水道事業に係る負担金が来年度から引き上げられることや、企業債金利の上昇も見込まれることなどから、安全で安定した下水道サービスを提供していくためには、下水道使用料の引き上げの必要性は高いと考えておりますが、抑制策を検討し、可能な限り市民の皆様の負担の軽減を図って参ります。
次に、中小企業者への支援についてお答えします。
商店街への支援についてですが、昨年度から、本市職員と千葉市産業振興財団のコーディネーターが全商店街を訪問し、商店街や個店が抱える課題や支援ニーズの把握に努めています。そうした中で、本市としては、まずは各個店の経営安定や事業変革への支援が求められているものと把握しており、訪問時には、商店街や個店が活用できる、資金融資や生産性向上などの中小企業支援メニューや、千葉県等の補助制度を含めた商店街支援制度を紹介し、その利用促進に取り組んでいるところです。今後も引き続き、商店街の現状及び支援ニーズを把握し、より効果的な支援策を検討、実施して参ります。
次に、高齢者外出応援パスについてお答えします。
高齢者外出応援パス実施についてですが、既に市内バス事業者、自らが、運転免許の返納者への運賃割引や乗り放題となる年間パスポートの販売を行っており、65歳以上から利用できる年間パスポートや年限の限定なしに割引適用される事業者もあると承知しておりまして、本市が高齢者向けの外出応援パスを実施することは考えておりません。引き続き、庁内関係部局とも連携して、路線バス事業の持続性を高めるため、事業者への支援に取り組んで参ります。
次に、下水道施設に起因した道路陥没についてお答えします。
緊急対応についてですが、今回の事故を受け、国が緊急点検を要請した対象に、本市で管理する管路は該当しておりませんが、市独自の対応として、処理量の多い南部浄化センターに接続する管路や、過去の点検結果に基づき改築を予定している管路の目視点検と路面状態の調査を先月30日から緊急実施しており、今月5日までに完了しております。この調査で異常は確認されませんでしたが、引き続き、計画的な点検と改築を行う予防保全型の維持管理を実施し、市民の皆様の安全・安心の確保に努めて参ります。
最後に、幕張メッセでの展示会の開催についてお答えします。
展示への抗議、株主としての発言及び催事の中止の主張については、関連がありますので、併せてお答えします。民間事業者が実施する展示会の開催そのものや、当該施設の指定管理者が県条例等に基づき施設利用の可否を判断したものについて、その内容を個別に評価し、施設利用の是非を申し上げることは適当でないと考えており、また、法律等に反しない限り、民間や団体の活動を最大限に配慮すべきものと認識しております。なお、市民共通の願いである世界の恒久平和の実現に向けては、市民の皆様に本市の平和都市宣言の理解を深めていただくとともに、戦争の悲惨さや平和の尊さを伝えていくことが重要と考えております。
以上でございます。