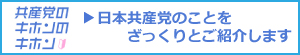介護職員の処遇改善支援を! のじま友介議員一般質問〔2025年第1回定例会〕
のじま友介議員の一般質問 2025.2.25

1、PFASについて
PFASについては昨年、第一回定例会におきまして一般質問にて取り上げました。PFASは人工的につくられた化学物質で数千~1万種類以上あります。環境中で分解されにくい特徴から「永遠の化学物質」と呼ばれます。フライパンなどのフッ素樹脂加工や半導体製造、泡消火剤など多様な用途で使われてきました。代表的なPFOS、PFOAについては、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約で製造や使用などが制限されています。しかし、すでに米軍基地や工場周辺などでは深刻な汚染が広がっており、世界的に規制の流れが強まっています。
昨年6月には、食品についても国の食品安全委員会が健康影響に関する評価書を公表しました。「ヒトが一生涯にわたって毎日摂取し続けても健康への悪影響がないと推定される」とする耐容1日摂取量の指標値を、PFOSとPFOAについてそれぞれ体重1キロ当たり20ナノグラムと設定されました。これはアメリカやヨーロッパと比べると非常に緩い値で、米欧の数十~数百倍の摂取を問題ないとするものです。これで、本当に国民の健康が守れるのか、疑問が残る内容となりました。
そんな中、政府は、全国の水道業者に水質調査を行い昨年9月末までの報告を求めていました。結果を速やかに公表し、汚染が確認された地域では住民の血液調査などを行って実態を把握する必要があります。そこで伺います。
1,前年度、河川4地点と飲用井戸3地点において調査を実施し、全ての地点で暫定目標値以下となっていたが、その後の調査結果はどうか。
2,昨年の答弁でPFOS、PFOAを要監視項目に追加し、暫定目標値50ナノグラム・パー・リットルを定め、汚染実態の把握に努めると答弁があった。この暫定目標値の取扱いについて、最新の科学的知見に基づき検討中であるとのこと。その後の検討状況はどうか。
3,更に市民への水道水に係るPFASの周知について、検査結果や水道水の安全性について、より分かりやすくお知らせできるように検討していくと答弁がありましたがその後の検討状況はどうか。
4,市民から、これまでどのぐらいの相談件数があったのか。また、相談の主な内容はどういうものなのか。
5,井戸水に関してPFASによる健康影響についての市民の不安、心配について、市はどのように捉えているか。そして、これまでどのような対策を講じてきたか。
6,河川におけるPFASの監視は必要だと思われますが、汚染源を断つことも並行して行わないと汚染が広がる事が予想されます。千葉県内で金山落(名内橋)、高田川(白石取水場)、平蔵川(雷橋)などの河川で暫定目標値を上回っているということですが本市への影響はどうか。
- また、千葉市水道局の未普及地域をお示しください。
8,また、環境保健研究所における千葉市の水域における有機フッ素化合物調査(第14報)によると例年、動物公園近くの六方都市下水路や葭川でPFOS・PFOAの合算値が高濃度を示しています。この数値はどうみていますか。
9,この間のテレビ報道で半導体やエアコンなどを製造している、いわゆる工業地帯と言われる地域でのPFASの値の高さが指摘されているところです。千葉市では工場等からのPFASの排出状況を把握されているのでしょうか。
10,今後、健康被害を早期発見していくためには早期の検査が必要になってくると思われますけれども、市内にPFASの血中濃度の検査が可能な医療機関や民間事業者はあるのでしょうか。
2、介護について
(介護保険料について)
まず、介護保険料についてです。介護保険事業計画は3年ごとに改定され、本市においても、2024年度から2026年度までの第9期千葉市介護保険事業計画が策定されています。この中では、保険料について定められています。昨今、保険料が高すぎるという声が多くの高齢者からあがっています。保険料は所得に応じて13段階に設定されています。
1,基準額となる第5段階の保険料は、前期のときと比べいくら上がっているか、あわせて前期と比べて保険料が下がっている段階はあるのか。
- 介護保険料の改定について市民からどのような意見が出ているのか伺います。
3,また、一般会計から補填して引き下げることはできないのか、お考えをお示しください。
4,加えて一般会計から補填として繰り入れを行っている他の自治体があるのかお示しください。
(訪問介護報酬について)
次に、必要な介護サービスが保障されているのかという問題についてです。今年度、社会問題になっている訪問介護事業について質問してまいります。昨年の第三回定例会におきましても取り上げて参りましたが、朝日新聞の報道によりますと、昨年4月から6月の介護事業所の倒産件数が前年同期の1.5倍に達し、そのうち訪問介護が約半数を占め、人材不足や物価高騰に加え、昨年春の訪問介護事業所への基本報酬引き下げが影響した可能性も指摘されていると報じています。本市の訪問介護も、この影響で経営が大きく圧迫されていることがだんだんと明らかになっています。
1,そこで訪問介護の報酬が改定前と後でどれだけ下がったのか、お示しください。
(介護人材不足について)
訪問介護事業所の大きな悩みは、報酬引き下げだけではありません。人材不足の問題も深刻です。元々介護人材については重労働に比して処遇が悪すぎることにより慢性的な不足に陥り、社会問題化してきました。とりわけ訪問介護が本当に深刻です。ここに報酬改定引き下げが襲いかかり、更なる人材不足が起きている状況です。
1,訪問介護の第9期計画のニーズの見込みと必要な訪問介護職員数をお示しください。
専門職であり重労働であるにも関わらずその処遇があまりに低いことが、訪問介護職員の不足に繋がっています。
2,施設の介護職員に比べ、地域の高齢者の自宅へ訪問する訪問介護は1対1の対応であり、閉鎖された空間でハラスメントなどのリスクも高くなります。訪問介護には特段の専門性が求められ、困難性が多いために人材不足になるのではないかと思うが、見解を伺います。
3,また、今期の訪問介護における人材確保の目標値をお示しください。
<2回目>
PFASについて
川崎市は、昨年1月に実施した市内5カ所の井戸水の検査で、PFASの濃度が暫定指針値1リットルあたり50ナノグラムを超える地点が2カ所あったと発表しており、最も高い地点では3倍を超える160ナノグラム、2地点目でも2倍近い91ナノグラムだったと発表しております。5地点の水はいずれも飲用には使われておらず、市は「健康被害が今すぐ出るとは考えていないが、市民の健康に配慮して今後も年1回検査を続ける」として、今年度は新たに13地点の調査を行ったとのことです。答弁で千葉市でも新たに井戸12地点で調査を実施したとのことで、どの地点でも暫定目標値を下回っているとのことでした。現在、問題になっているのがこの井戸水についてです。井戸水は、飲まなくても洗い物、入浴や散水のときなどの生活用水として今後も使用され、土地や地下水に残り続けることが考えられます。土壌の検査や地下水脈の検査については、本市だけでは解決することはとても困難な問題だということは認識しております。
1,市内の飲用のもの、飲用でないものの井戸の総数はどれくらいか。また、市内の土壌汚染も含めた汚染状況の把握のためにも民間の井戸も含めた市内の井戸の水質検査を大々的に実施をすべきと考えるがどうか。
工業地帯については熊本では台湾の世界的大手半導体メーカーTSMCの日本子会社JASMが使用するPFASについて先日、公表がされました。JASMが使用するPFASについては3種類であると回答がありまして、そのうちのPFBSが甲状腺、発達、腎臓への影響との関連が特定されたことを米国環境保護庁が発表しています。経口での一定量のばく露で、健康に影響がでる可能性が高いということです。
2,PFASを製造、輸入、利用していた企業の実態について、過去に遡って市として調べることが必要ではないでしょうか。
3,千葉市水道局の未普及地域が中野町や富田町など6地域あるということです。6つの地域の内、2つの地域では地下水の調査が行われているようですが、残りの4つの地域でも早急な調査を行うべきです。見解を伺います。
昨年9月に「母親のPFASばく露と子どもの染色体異常:子どもの健康と環境に関する全国調査(エコチル調査)」に関する研究論文が発表されまして、妊娠中の母親の血中PFAS濃度と子どもの染色体異常の関連の有無について公表されました。その結果、母親の血中PFAS濃度が高いと子どもの染色体異常の発生が多い傾向が見られました。しかし、今回得られた結果をもって、すぐにPFASと染色体異常の関連性を結論づけることはできないとのことです。理由としまして、症例がまだまだ少ないことと、染色体異常のほとんどが妊娠12週までに流産となり、12週以前に流産した妊婦の情報が得られていないためとのことです。しかし、今回の調査対象は、PFAS汚染地域でない一般の集団でした。比較的低いレベルの血中濃度で今回のような結果が出たことは大変深刻です。
1,子供の影響については、専門家は、暴露から時間がたつほど、成長希釈によって血中濃度が低下をして汚染実態が過小評価されるということを指摘しています。子供への健康影響調査の必要性について見解を伺います。
不安に思っているご家庭での井戸水対策はどうすればいいのか。一般的には浄水器を使う方法があるかと思います。活性炭による除去が一般的で、メーカーによってはPFAS除去をうたう製品も販売されています。価格は数千円~数万円です。答弁では、上水道敷設および浄水器設置の補助があるということなのですが、井戸にPFAS汚染があった場合に限るということでなかなか助成を受けるのは難しいと感じます。アメリカなどでは日本の20分の1以下の暫定目標値だと前の質問で紹介しましたが「日本の現在の暫定目標値は信用できない。」と市民の中には、安心して水が飲めないという方が確かにいらっしゃいます。せめて、
1,千葉市水道局の未普及地域にお住いの方への補助の拡充が必要なのではないでしょうか。本市での見解を伺います。
検査機関については、把握はしていると答弁がありました。私が調べたところ、病院だとすると、立川市や昭島市にある医療機関で行っているとのことでした。しかし、採血は現地で行うことになると聞いております。また、検査に際しては高度な分析機器が必要となるようであり、費用には幅があり、1件当たり1万円程度から10万円程度かかるとのことです。交通費や検査費用はかなり高額になり負担を感じます。
2,自身の健康状態に不安を感じている住民の方への対応として、血液検査の検査費用に対して助成を行うことが必要と考えるがどうか。
環境省が、昨年11月改定した自治体向け「対応の手引き」で、健康不安の声が上がっている地域においては、地域保健を担当する各地方公共団体が、地域保健活動の一環として、直ちに取り組める対応として、「疫学研究を行う上で血液検査を行うことも考えられる」と明記したこと、これは大変重要であると考えます。
3,今後の学術的な研究のために、大規模な血液濃度の疫学調査を実施すべきではないでしょうか。見解を伺います。
介護について
(介護保険料について)
13段階全ての段階で値上げになっています。答弁で市民からのご意見の中に「昨年と収入がほぼ変わらないのに、なぜ保険料が高くなったのか」とありました。当然の疑問だと思います。私が声を聞いた70代のご夫婦は、お2人とも年収が125万円以下という6段階の方ですが、月々5670円だった保険料が6930円と1260円も上がり、年間8万3160円もの保険料で、お2人で16万6320円です。引き上げ幅は3万240円にもなります。年金は目減りし、物価高騰が襲う中、保険料が上がり、生活ができないと話されています。
- このようなご家庭の話を聞いてどう思うでしょうか?見解をお示しください。
今期、保険料の上昇を抑制するため、介護給付準備基金を全額活用したということですが、間に合っていません。本市の保険料は政令市で16番目ですが、県内では5番目の高さとなっています。問題は引き上げ幅が政令市でいうと大阪市についで2位となったことです。この引き上げ幅を最小におさえるべきではなかったかということです。保険料抑制のため、基金から16億円を投入しましたが、市の財源活用で、保険料を8期のまま据え置くことができなかったでしょうか。私たちは、少なくともより低所得層の第1段階から9段階までの保険料を据え置くことが必要であったと考えます。
2,今回、県内でも17の自治体で介護保険料を据え置き、もしくは引き下げています。本市でも保険料を引き上げないことは可能だったのではないかと思いますが見解を伺います。
一般会計から繰り入れについては「介護保険法などにより、その割合が定められており、市町村が独自に補填することは制度上想定されていない」と答弁されました。しかしこれは実際には可能なのではないでしょうか。
3,厚生労働省が「不適切」と示しているのは単なる「助言」に過ぎず、「自治体がそれに従うべき義務はないこと」を2002年に当時の厚生労働省の局長が答弁しています。一般会計から繰り入れたからといって罰則はありません。従って、一般会計からの繰り入れを行い、保険料を引き下げることは可能と思われますが見解を伺います。
(訪問介護報酬について)
答弁で身体介護は99円、生活介護では55円の引き下げになったとありました。一人当たり6~7件のお宅を周るとして、一日に一人当たり最大で700円近い減収となってしまうということです。国はこの報酬引き下げをごまかすため処遇改善加算を見直しましたが、その加算Ⅰを取得するためには特定事業所加算を算定しなければならないことを要件に加えました。私が伺った小規模の訪問介護事業所では、この特定加算を受けるために利用者のサービス単位を減らさなければならず、重度の方などはその単位を超えると10割負担となります。そもそも特定事業加算を受けた事業所からサービスを受ける利用者は利用料が上がります。さらに事業所は研修の実施や会議の開催などの負担が増えるため、この制度の利用率は大変低くなっています。つまりこの特定事業所加算は利用者のサービス削減や利用料引き上げ、事業所の負担増大と一体のものです。
先日、市内の訪問介護事業所と懇談を行いました。減収分の補填をするため、訪問件数を無理に増やしている。サービス提供責任者もいつも以上に現場に入らなくてはならず、事務作業は連日夜遅くまでかかると。それでも年間の赤字の額は360万円にも登ると話されています。更に答弁にありましたように生活介護は身体介護に比べ同じ時間でも報酬が2千円近く少ないので、今後はより身体介護を選ばざるをえなくなるとも話されていました。訪問介護職員は本人の表情、動作で体調の変化をつかみ、部屋の状態や冷蔵庫の中身を見て異常がないか確認します。もし、事業所が報酬削減でこの生活援助を削って、身体介護ばかりをやる事業所ばかりになってしまったら、利用者の全体像が見えなくなり、介護の質にも関わります。
- このような事業所の実態を聞いてどう感じますか。市の見解を伺います。
2,また、生活援助を身体介護と比べて不当に低く見るのをやめ、同じ報酬にするよう国に求めるべきと考えますが見解を伺います。
先ほどの事業所では職員募集では人が集まらないので人材紹介業者を利用していたと言います。しかし、高額な紹介手数料を払っても定着には至らず、3か月ほどで退職してしまう方ばかりだと。今、この職業紹介手数料の高騰が事業者の経営を圧迫しています。有料職業紹介事業の常用就職1件当たり紹介手数料は、5年前に比べ、介護職で平均21万円から42万円に高騰。紹介料を貰ったあとは退職する、これを繰り返す渡り派遣なんていうのも問題になっています。
3,事業所の経営を圧迫している人材派遣会社に払う紹介料の補助を市で行うべきではないでしょうか。
(介護人材不足について)
必要な介護人材数については正確にはつかまれていないと答弁がありました。必要性をつかまないと始まらないと思います。第9期計画の「第8期介護保険事業計画の実績」では、訪問介護はR3年度、R4年度で計画よりも実績の方が上回っておりました。来年度、再来年度と見込まれる人数は300人ずつ増加すると答弁がありましたが、今後も最初の見込みよりも訪問介護のニーズは増え続けていくのではないかと思います。
1,人材の減少と高齢化が進んでおり、既に新規サービスを提供できなくなっている。そういった状況の中で介護人材の必要数を把握しないというのはあり得ません。このままでは訪問介護が成り立たなくなるのではないかと思いますが、見解を伺います。
千葉市のある訪問介護事業所は、毎年応募をかけても人が集まらず、6年前の2018年の登録ヘルパー数95人が2024年には71人にまで減っています。この事業所では職員の平均年齢は62歳、最高年齢は79歳。ベテランがリタイヤしているが平均年齢が下がらないと言われています。主力は60代、70代が多いところもあります。
2,今期も訪問介護職員の実態をつかまず、人材獲得の数値目標もないのでは、あまりに無責任な対応ではないでしょうか。見解を伺います。
そもそも国が言っている「処遇が改善されている」っていうのがすでにまやかしだと思います。専門職が訪問するからこそできる役割をもっと評価するべきだと思います。国が目玉とする処遇改善加算は1人当たり月6000円を見込んでいますが、全産業平均より7万円低いと言われる中、「桁が一つ違う」というのが現場の声です。そこで専門性を求められるのに低い処遇である現状を抜本的に改善しなければ人材確保は改善されないと思います。
3,訪問介護事業所や訪問介護職員とともに、介護に関わる全ての職員の処遇改善のために、流山市が行っているような、月額9000円の給与補助を千葉市でも行うべきと考えますが、見解を伺います。
今年度、世田谷区では、介護サービス事業所・施設等を運営する法人に対し、人材確保や経営に必要な経費を補い、福祉サービスの事業継続を支えるため、緊急安定経営事業者支援給付金を交付しました。給付の対象となるのは訪問介護等事業所のほか、居宅系サービス事業所、通所・入所系の高齢者施設、障害者施設などです。このうち訪問介護事業所には1事業所あたり88万円が支給されました。すでに処遇改善は自治体単位でも行われているということです。
4,千葉市でも物価高騰対策支援事業として支援金を支給しておりますが訪問介護事業所への支給額をお示しください。また、支給額の上乗せが必要と考えますが見解を伺います。
のじま友介議員の一般質問に対する答弁 2025.2.
1、PFASについて
【環境局長答弁】
まず、その後の調査結果についてですが、PFASに対する社会的関心が高まっていることから、これまでの河川4地点と井戸3地点に加え、河川6地点と井戸12地点で調査を実施し、全ての地点で暫定目標値を下回っております。
次に、暫定目標値の検討状況についてですが、環境省の諮問機関である中央環境審議会の小委員会が今月6日に開催され、河川や海域のよう監視項目としての「暫定目標値」を「指針値」とし、50ng/L(ナノグラム・パー・リットル)は変更なしとする方針を了承したと聞いております。
次に、市民からの相談件数及び主な内容についてですが、今年度、本市には約20件の相談があり、主に井戸水や水道水は大丈夫なのかとの問い合わせが寄せられております。
次に、PFASによる市民の不安への対策についてですが、法令に基づき調査し、全ての地点で暫定目標値を下回っており、市ホームページで情報提供しております。また、今年度から井戸水にPFAS汚染があった場合に利用できるよう、上水道敷設及び浄水器設置の補助制度にPFASを対象とする制度改正をいたしました。
次に、他自治体の河川におけるPFASの本市への影響についてですが、他自治体の河川で高濃度が検出された地点から遠距離であることから、本市への影響はないものと考えております。
次に、環境保健研究所の調査結果への見解についてですが、法令に基づき今年度調査した速報値では、六方調整池下流となる葭川の2地点を含めた全地点で暫定目標値を下回っており、今後も河川における調査を実施し、状況を把握してまいります。
最後に、工場等からのPFASの排出状況を把握しているのかについてですが、PFASのうちPFOS及びPFOAは、「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」に基づき、事業者は国に排出量及び移動量を届け出することとなっており、直近の令和4年度の集計結果において、本市に係る届出はありません。
【水道局長答弁】
まず、市民への水道水に係るPFASの周知についてですが、県営水道・市営水道とも、かねてより他の検査項目とあわせPFOS・PFOAの検査結果をホームページで公表してきたところです。本市では令和6年3月より、市民の皆様のご理解をより深めていただくため、検査結果が国の目標値を大きく下回っていることを検査結果に添えて明記したほか、PFOS・PFOAに関するQ&Aを合わせて掲載し、周知に努めてきたところです。
最後に、市営水道の未普及地域についてですが、小間子町、富田町、和泉町、古泉町及び佐和町の6町となっております。
【保健福祉局長答弁】
血中濃度の検査が可能な医療機関や民間事業者についてですが、検査を行なっている医療機関や市内の医療機関から検体を受け付ける民間事業者はあると伺っておりますが、正確な数は把握しておりません。
2、介護について
【保健福祉局長答弁】
介護保険料についてお答えします。
まず、介護保険料の改定状況についてですが、基準額となる第5段階の保険料は、月額で前期より900円の引き上げで、全ての段階で増額改定をしております。なお、第1段階から第3段階の低所得者の方につきましては、改定幅が緩やかになるよう配慮しております。
次に、介護保険料の改定に対する市民からの意見についてですが、「昨年と収入がほぼ変わらないのに、なぜ保険料が高くなったのか理由を教えてほしい」「保険料の算定方法を説明してほしい」などのご意見を頂いております。介護サービスの需要が増大していることなど、改定理由や算定方法を丁寧に説明し、ご理解いただけるよう努めております。
次に、一般会計からの補填による保険料の引き下げについてですが、市町村の一般会計からの負担は、介護保険法などにより、その割合が定められており、市町村が独自に補填することは制度上想定されておりません。
次に、一般会計から補填して繰り入れを行なっている自治体についてですが、法令により市町村の負担割合が定められていることから、繰り入れを行なっている市町村はないと認識しております。
訪問介護報酬についてお答えします。
訪問介護の報酬の引き下げについてですが、今年度の介護報酬改定により、基本報酬が引き下げられており、主なものでは、身体介護を30分以上1時間未満で提供するものについて、4,375円から4,276円と99円の引き下げとなっております。また、生活援助を45分以上提供するものについては、2,486円から2,431円と55円の引き下げとなっております。
介護人材不足についてお答えします。
まず、第9期介護保険事業計画における訪問介護を利用すると見込まれる人数についてですが、今年度は8,673人、来年度は8,959人、令和8年度は9,220人と毎年300人ずつ増加していくものと見込んでおります。このニーズに対して、具体的に必要な職員数までは積算しておりません。
次に、訪問介護員の人材不足の要因についてですが、令和3年に国が行った調査によれば、訪問介護事業所への就業希望者が少ない理由として、一人で利用者宅に訪問してケアを提供することへの不安が一番多く、次に、実質的な拘束時間が長い割りに効率的に収入が得られないことが多くなっております。入所や通所などと異なり、一人で訪問してサービスを提供することの負担や、一定以上の資格を求められることが就業が少ない理由であると考えております。
最後に、訪問介護における人材確保の目標値についてですが、利用者の身体状況や住環境などに応じた多様なサービス提供が必要であり、職員一人当たりの訪問回数など、サービス提供料が一律でないことから、訪問介護職員の人数の目標値は設定しておりません。訪問介護事業所の休止や閉鎖が増えていることを踏まえ、必要なサービス料を確保できるよう介護人材の確保・定着に努めてまいります。
<2回目の答弁>
1、PFASについて
【環境局長答弁】
まず、井戸の総数及び検査についてですが、井戸の総数については把握しておりません。検査については、法令に基づき、市内全域を72区画に分け、計画的に実施することとしており、今年度は15地点で実施しました。
次に、PFASを製造、輸入、利用していた企業の実態を過去に遡って調べる必要性についてですが、PFASのうち、PAOSは2010年、PFOAは2021年から法令に基づき、事業者は排出量及び移動量を届け出ることになっておりますが、これまで本市に係る届出はありません。
最後に、水道未普及地域の地下水調査についてですが、古泉町については令和5年度に調査し、暫定目標値を下回っており、その他の地域についても引き続き計画的に調査してまいります。
【保健福祉局長答弁】
子どもへの健康影響調査の必要性、不安を感じている住民への血液検査の検査費用の助成、大規模な血液濃度の疫学調査については、関連がありますので併せてお答えします。現時点での知見では、どの程度の血中濃度でどのような健康影響が個人に生じるか明らかとなっておらず、血液検査の結果のみをもって健康影響を把握することは困難であるとされております。現在も国際的に様々な知見に基づく基準値等の検討が進められていることから、、現時点においては本市として検査などの実施は考えておりません。今後、国において公表される内容について注視してまいります。
【市民局長答弁】
補助の拡充についてですが、新しく上水道を引く場合について、既設の水道本管からの敷設距離が1戸当たり20メートルまでは全額水道局が負担し、20メートルを超える場合には、利用者がその費用の2分の1を負担することとなっています。この利用者の負担を軽減するため、工事にかかる費用の3分の1、または20万円のいずれか低い金額を上水配水管敷設事業補助金として補助をしており、世帯単位でご利用いただけるといった使い勝手や補助金額などで、県内他市と比較しても充分で使いやすい制度となっているものと考えております。
2、介護について
【保健福祉局長答弁】
介護保険料についてお答えします。
まず、物価高騰の中での保険料引き上げについてですが、保険料は第1号被保険者数や介護サービス量の見込みなどから、3年ごとに見直しを行なっており、介護サービス量が増大することから、全ての段階で増額改定となりました。なお、保険料上昇を抑えるため、介護給付準備基金を全額取り崩し、活用しております。
次に、県内自治体における保険料の据え置き・引き下げについてですが、自治体ごとに、高齢化率や介護サービスの利用状況が異なるため、一律に比較することはできませんが、一部の自治体では介護給付準備金を活用することなどにより、保険料の据え置きや引き下げを図ったものと承知しております。本市においては、これまでも介護給付準備基金を活用し、可能な限り保険料上昇を抑制してきたところですが、今回の改定では、後期高齢者数の伸びが特に大きく、それに伴い介護給付費の増加が見込まれることから、介護給付準備基金を全額取り崩してもなお、増額改定が生じたものです。
次に、一般会計からの繰入による保険料の引き下げについてですが、介護保険制度は全国共通の制度であり、制度の枠外で一般会計からの繰入を行うことは、健全な介護保険制度の運営と財政規律の保持の観点から適当ではないと国の判断が示されており、負担割合を超える繰り入れは考えておりません。
訪問介護報酬についてお答えします。
まず、報酬改定後の事業所の実態に対する本市の見解についてですが、訪問介護は、住み慣れた地域での暮らしを続けていくうえで重要なサービスであり、1件ずつ自宅を訪問してサービスを提供している事業所にとって、今回の報酬改定は安定した事業運営に影響を及ぼしていると認識しております。本市としましては国に対し、引き続き報酬改定の影響の検証と実情に応じた報酬体系の構築を検討するよう求めてまいります。
次に、生活援助と身体介護を同じ報酬にするよう国に求めることについてですが、入浴や排せつなどの直接的な介護を行う身体介護と、調理や掃除など家事を提供する生活援助では、サービス提供にかかる負担が異なるため、より負担のかかる身体介護の報酬を高く設定することは合理的であると考えます。
次に、人材派遣会社に支払う紹介料の補助についてですが、本市では人材確保のために研修受講費用の助成や就職説明会などを行なっておりますが、紹介料に対して補助をすることは考えておりません。
介護人材不足についてお答えします。
まず、訪問介護の人材不足についてですが、高齢化の進展により、今後、訪問介護のニーズが増大することが見込まれる一方で、人口減少により人材不足が深刻化し、必要なサービス量を確保することが困難になると考えております。今後のさらなるサービス需要に応えられるよう、引き続き人材確保・定着に取り組んでまいります。
次に、訪問介護職員の実態把握及び目標設定についてですが、必要な人数及び目標の人数は設定しておりませんが、介護保険事業所に対して実態調査を行い、現状の従業員数と理想とする従業員数の差など、サービス提供に係る課題の把握に努めており、介護人材確保・定着に向けた施策に活かしております。
次に、介護職員に対する給与補助についてですが、一義的には国の責任において対応すべきであり、本市独自の給与補助は考えておりません。本市としては、これまでも国に対し、改善を求めてきたところであり、人材育成の取り組みに対する介護報酬の加算など、段階的な措置が講じられてきたものの、まだ十分ではないため、引き続き更なる改善を要望してまいります。
最後に、物価高騰対策支援事業における訪問介護事業所への支給についてですが、訪問介護事業所に対しては、県が1事業所当たり1万円の支援金を支給することを予定しておりますが、燃料費が高止まりしている状況を踏まえ、本市としましては県の支給に上乗せして、10万円を支給する予定です。
<3回目>
PFASについて
過去に大きな公害問題、そして今も続いておりますけれども、水俣病の問題があります。PFASの問題を第二の水俣にしてはいけないと心から思います。全国では米軍基地や自衛隊基地による汚染が疑われる地域、PFAS製造・使用企業のある地域、産廃処分場からの汚染が明らかになった地域で運動が広がっています。PFAS汚染は新しい公害というべき問題で、本市におきましても、市民の健康を守るために何をすればいいのか、県や国と十分に話し合い、声を上げ、この問題についての解決に向けてご奮闘いただきますことを要望しておきます。
介護保険料の一般会計繰り入れについては当時の坂口厚生労働大臣は「自治体の中で、この原則を乗り越えてやるというところも百幾つもあるわけで、それは私達の言うことからはみ出ているから絶対駄目だと、やめろとまで私達は言ってない」と答弁し、自治体の裁量を認めています。一般会計、財政調整基金などあらゆる手段を講じて保険料の引き下げを図るべきと思います。国会で大臣が良いと認めているのですから保険料を引き下げるべきと強く求めておきます。
今回の報酬改定は、訪問介護事業所に悪影響を及ぼしています。そもそもコロナ後も続く物価高騰で経営状況が厳しい中、コロナの補助が打ち切られ、さらに感染症の蔓延が介護現場を襲っています。この経営危機を何とかしてほしいと悲痛な叫びが寄せられているのにこのまま報酬が下がることを放置したら、サービスの縮小などで帳尻を合わせようとしても立ち行かず、やむなく閉鎖するという事業所が今後更に出てくるのではないかと思います。
人材確保に対する危機感も足りないのではと思います。訪問介護職員が人材不足になっているもとで、ひとり暮らし高齢世帯の多い本市では今後、介護サービスを受けられない高齢者が増えていくのは明らかです。第9期計画では「高齢者数、高齢化率の推移」で高齢者人口は来年度は26万7千人、2040年には、31万1千人になり、高齢化率は33.2%まで上昇することが見込まれています。このままでは、保険料や利用料の値上がりと、介護人材の不足により、必要な介護サービスを利用できない人が増大し、高齢者の生活を守れないのではないでしょうか。今手を打たなければ介護の基盤が崩れていくことになります。「保険あって介護なし」が現実のものになってしまいます。第9期計画の中には「必要なサービスが必要なときに高齢者や家族に届く安心なサービス提供体制を目指している」と書かれています。であるならば、あらゆる手段を講じて、訪問介護事業所支援を行うべきと思います。また、人材確保のために使わざるを得ない紹介会社に支払う紹介料が、厳しい経営をさらに圧迫する事態となっています。人材確保に高い紹介料を払わなければならないという異常な事態の根本原因は、介護職員の労働条件が劣悪だからではないでしょうか。
当然、国の制度も悪いわけですから、国に意見も言いがら、国がきちんとした制度をつくるまでの間、市として独自の対策を取るというのは当然のことではないかと思います。介護人材確保のために市独自の実効性のある賃金引上げ策を実施してほしいと重ねて要望しまして質問を終わります。