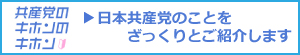物価高騰化下での上下水道値上げやめよ!保育料多子世帯負担軽減を! かばさわ洋平議員代表質問〔2025年第2回定例会〕
1かばさわ洋平議員の代表質問 2025.6.12

【1】市政運営の基本姿勢について
先の市長選では、日本共産党市議団は寺尾さとし候補を支援し、上下水道料金値上げ中止から、給食費や保育料無償化、高齢者外出応援制度の実現など訴え、水道料金値上げ反対はNHK出口調査でも多数派となりました。日本共産党千葉市議団は市民が本当に住んで良かったと思える千葉市とするために、引き続き全力を尽くしていく決意を申し上げ、2期目の市政運営となる神谷市長に市政の基本姿勢について質問いたします。
①はじめに、米国のトランプ関税への対応についてであります。米政権が輸入自動車に対して25%の追加関税の適用との問題ですが、2019年の日米貿易協定では自動車などに「追加関税を課さない」と明記しており、追加関税は同協定違反であるため、撤回を求めるべきと考えますが所見を伺います。また、市内企業への影響をどのように分析しているのか、輸出下請け企業など、新たな支援策に取組むべきと考えますが、併せてお答えください。
②次に、物価高騰対策について伺います。物価高騰が続くもとで市民生活の苦境が広がるなか、消費税の減税を望む国民世論は新聞の世論調査でも7割と増加しています。日本共産党は、消費税創設時から消費税の廃止、現在は緊急に5%に減税しインボイスを廃止すべきと求め続けてきました。物価高騰対策の決定打である消費税減税を国に要望すべきではありませんか。また、同時に物価高騰に負けない賃上げ支援が必要であり、先の議会でも提案した賃上げ支援金など、物価高騰対策に取組むべきではありませんか。
③千葉県知事選挙と市長選挙で大きな争点となった上下水道料金値上げについてお尋ねします。2026年度から千葉県が水道料金を18.6%値上げする意向を表明しており、本市も同時期に下水道使用料を13.6%も値上げする予定とされています。公共料金のダブル値上げにおける平均世帯の料金はどの程度増える見通しなのか。また、今は市民生活が厳しい局面のため、市長が県知事に水道料金値上げ抑制を強く求めること、本市としても一般会計から繰入を増やして下水道使用料の値上げを抑制すべきではありませんか。答弁を求めます。
④次に、下水道管の老朽化対策についてです。埼玉県八潮市における下水道陥没事案以降、下水道への老朽化対策における不安も高まっていますが、すでに2019年に緑区あすみが丘で下水道陥没事案が発生、陥没した道路に車が落ちるという事案がありました。これ以降も下水道管に起因する陥没や取付管の陥没が発生していると聞いています。そこで、本市において、下水道管や取付管に起因する陥没事案件数と下水道管の改築予算の直近3年間の推移を伺います。また、早急に下水道老朽化対策を進めるためにも、国からの財政措置を強く求めるべきと考えますが見解を伺います。
⑤次に、子育て支援策の充実についてです。昨年の議会にて私は第3子カウントが小学生に上がると外れるという保育料の小1の壁の改善を求めてきましたが、今議会にて保育料無償化拡充の補正予算が提案されたことは前進です。多子世帯の認定基準が小学校就学と同時に外れる保育料の小1の壁見直しとなる保育料無償化拡充の概要と開始時期について、併せて保育料第2子無償化への決断も求めますが、市長の見解をお聞かせください。
⑥続いて、若者支援について市長に伺います。4月にこども・若者基本条例が施行され、新たにこども若者支援室も設置されました。若者支援を求めた我が党の第1回定例会の代表質疑に市長は「これまで行政の支援が届きにくかった年代へのサポートを強化する」と答弁しました。そこで伺います。支援が乏しい世代として、高校生・大学生から学費負担軽減や家賃を含めた住まいの支援などを求める請願も出されているため、これらの若者全般の支援拡充を求めますが、見解を伺います。また、今年度設置の「こども・若者会議」において、学費負担軽減や住まいへの支援に関する意見があった場合には、施策への反映を検討すべきと考えますがいかがですか。
⑦続いて、高額療養費制度の負担上限額の見直しについてです。がん患者から引上げられたら、「治療を諦めなくてはならなくなる」など、切実な声が届いているため、国に高額療養費制度の自己負担限度額を据え置くよう求めるべきと考えますが、市長の見解をお聞かせください。
⑧次に、防災の仮設住宅についてです。先般能登半島地震災害ボランティアに参加し、輪島市の仮設住宅を訪問しました。2人暮らしで4畳の1Kで狭くて苦痛との声や他にも退去後に災害復興住宅に入居できるかなど、住まいへの心配の声が寄せられました。本市では応急仮設住宅の建設予定地が196か所あるとのことですが、最大で何世帯の仮設住宅への入居が可能なのか伺います。また、仮設住宅を速やかに整備できるよう民間との連携強化を図るべきと考えますが、これまでの取組と今後の対応について伺います。
⑨防災対策の避難所トイレについて伺います。昨年の第1回定例会で提案したトイレトレーラーですが、県内で導入した君津市を視察してきました。洋式トイレ4室を備え、鏡や手洗い場も完備、感染症対策として殺菌灯を各室に設置してあるなど想像以上にしっかりとしたトイレ空間で、今回の能登地震支援では輪島市の病院敷地に派遣、約1万人以上が利用し、被災者から大変喜ばれたとのことでした。そこで伺います。災害時に課題となる避難所トイレ環境の向上、さらには災害時他都市への支援にも活用できるトイレトレーラーを導入するよう求めますが、見解を伺います。
⑩次は、学校体育館エアコン整備の前倒しについてです。令和7年度から一部の中学校など整備工事が開始されますが、年間30校整備となると、整備期間は6年以上かかる見通しです。近年の地球温暖化は深刻であり、子ども達を熱中症から守るためにも、また、災害時の避難所としての環境向上も急務であるため、学校体育館エアコンを3年程度で整備できるよう計画の前倒しを求めますが、今後の取組についてお聞かせください。
⑪次に、JR京葉線の快速復元とホームドア設置についてです。本年のダイヤ改正において、一部快速電車が復元されたものの、当初のダイヤ見直し前と比較すると、快速電車の復元率は約30%です。来年3月のJRダイヤ改正に向けて、市長が再度リーダーシップを発揮して、京葉線の通勤快速の復活や朝夕の快速電車の更なる増発を強くJRに要望すべきと考えますが、市長の見解を伺います。また、千葉駅の1、2番線に新たにホームドア設置されましたが、市内の駅に早期にホームドアを設置できるよう支援強化を求めますが、今後の整備予定含めてお聞かせください。
⑫バス路線維持に向けた取組についても伺います。市長の所信表明において、「バス路線の維持・確保のためには、バスを利用していただくことが不可欠であり、課題を地域とも共有したい」と語られました。バス路線を維持するために、運転手確保の支援、バス路線維持への支援強化と共に、バス利用者を増やすために無料デーや高齢者への運賃負担軽減策を検討するよう求めますがいかがですか。また、路線廃止の大椎台地域へのバス路線復活、あすみが丘との循環バス路線を実現するよう求めますが、取組を伺います。
⑬次に、町内自治会の加入向上に向けた取組についてです。自治会の担い手が不足しているとともに自治会加入率は近年低下傾向であり、令和6年度59%と低下への歯止めがかかっていません。また、自治会の解散件数についても令和6年度7件と毎年一定数の自治会が解散しているのが実態です。持続可能な自治会運営となるよう加入率の改善と地域づくりの担い手確保は急務と考えますが、今後どのように取組む考えなのか伺います。
⑭次は、幕張メッセでの武器見本市開催についてです。5/21から開催されたDSEIジャパンでは、ガザでのジェノサイドに国際的批判が高まっているイスラエル企業など、過去最高の470社が出展したとのことでした。全国でも公共施設を武器見本市で貸し出している自治体は千葉県千葉市のみです。当日はパレスチナ人からも「虐殺の共犯者」と武器見本市開催中止を求め、350人もの多くの市民が幕張メッセ入口で声を上げました。そこで伺いますが、市長は、市民の公共施設での武器見本市の開催はやめてほしいという平和を願う声をどう受け止めていますか。また、自民党議員は入場を許可される一方で、共産党の地方議員のみならず国会議員までも入場を認めないという、差別的対応が行われたことは極めて問題と考えますが、見解を求めます。
⑮千葉マリンスタジアム建替えについてお聞きします。本市は新たに千葉マリンスタジアムを、幕張メッセの駐車場への移転し、屋外型で約650億円かけて整備する方針を示しました。昨今の地球温暖化による観戦者の熱中症対策は急務であるため、観客席への屋根設置やミストシャワーなど対応を図るよう求めますが見解を伺います。また、現時点でも商業施設付近での渋滞は深刻化するため、交通対策に取組むべきと考えますが、併せて見解を伺います。
⑯市政だよりへの多言語翻訳に対応した広報紙閲覧サービス導入についてです。市内の在住の外国人も増加するなかで横浜市は10言語の翻訳機能もある広報紙閲覧サービス「カタログポケット」を市政だよりで導入しています。二次元コードへもダイレクトアクセスできるということで、「広報紙閲覧アプリ」はどの年代でも20%を越えているとのことです。本市在住の外国人も4万人を超えるなかで、市政情報に適切にアクセスできるよう、また市民がスマホから市政だよりをより見やすくできる多言語翻訳に対応した広報紙閲覧サービスの導入を求めますが、見解を伺います。
⑰公益通報制度について伺います。兵庫県では元県民局長の公益通報における対応について、第三者委員会から違法との指摘も出されており、今国会において、改正公益通報者保護法が可決、成立するなど、波紋を広げています。本市における内部通報の近年の通報件数と通報に伴う是正措置がどのように図られているのか伺います。また、今回の法改正に即して、通報しやすい体制と通報者保護の取組について、体制強化に取組むべきと考えますが対応を伺います。
⑱女性職員の活躍への取組について伺います。本市においては、政策への女性の参画拡大を進めるために、市職員の管理職に占める女性割合を令和7年度までに30%とすることを目標として取組を進めてきました。市長の所信表明では、主査級に占める女性職員比率40%にすることを目指すとされましたが、最新の主査級と管理職のそれぞれに占める女性職員比率についてお示しください。また、令和5年度 職員の給与の男女の差異の情報公表によると、全職員においては男女の給与差異が80%となっていますが、男女間の賃金格差の差異が生じている理由について伺うとともに、女性が働きやすい環境の充実を図るべきと考えますが、見解を伺います。
⑲次に、防犯カメラ設置について伺います。闇バイトによる自宅への強盗事件が県内でも複数発生するなかで、市民の防犯への意識が高まっています。そうしたなか自治体の独自支援も広がっており、太田市では家庭用防犯カメラ設置補助として最大2万円を助成する取組みを行っています。市長は所信表明で「犯罪を起こさせない、安全で安心なまちづくりを推進していく」とも語っているため、市民要望が増えている家庭用防犯カメラ設置助成に取組むべきと考えますが、見解を伺います。また、市内JR各駅の未設置駅及び京成電鉄駅においても早期の設置を求めますがいかがですか。
⑳次に、SNS上の誹謗中傷防止対策についてです。兵庫県の元県議などがSNSの誹謗中傷により自殺する事案もあり、SNS上での住所さらし行為など一定の対策強化が必要です。新たに情報流通プラットフォーム対処法が施行され、一定期間内の削除申出への対応などの規制が新たに設けられています。SNSによる誹謗中傷被害が広がるなか市民の人権を守るためにSNS誹謗中傷防止条例を検討すべきではありませんか。また、削除要請への対処など、市民への支援体制強化を図るべきではありませんか。答弁を求めます。
㉑続いて、市民会館整備について伺います。令和9年度に開館するとしてきた市民会館整備ですが、工事費高騰に伴いJRとの見直し協議が続けられてきました。我が会派としては、あまり興行目的化せず市民が使い勝手がよい1000席の大ホール整備や建設コストが安く済む本庁舎の将来活用検討地での整備を提案してきましたが、当初の予定通りのJR千葉支社跡地に整備する方針が示されました。将来活用検討地とJR千葉支社跡地の整備コストの違い、大ホールの整備方針、整備時期について伺います。また、会議室等の諸室を増やすよう求めてきましたが、機能強化が図られるのか伺います。
㉒続いて、斎場整備について市長にお聞きしたいと思います。2023年の一般質問において千葉市斎場の火葬待ちが最大14日にも及んでおり、市民の遺体保管費用が過重となっているため、第2斎場整備を提案してきました。昨年度、斎場のあり方を検討するため、将来需要予測、斎場整備案などの検討をおこなったようですが、火葬待ちの一刻も早い解消に向けて、速やかに第2斎場整備に向けて取組むよう求めますがいかがですか。また、斎場整備まで時間がかかるため、千葉市斎場の開場時間の拡大を図るよう求めますが、対応についてお聞かせください。
㉓次に、オンラインカジノ対策についてです。警察庁の実態調査によると、国内でオンラインカジノを利用したことがある経験者は336万人、年代別分布は、20代で30%、30代28%で全体の6割近くが若者であり、対策は急務と考えます。本市としてオンラインカジノへの防止対策に積極的に取組むべきではありませんか。また、中学・高校・大学等と連携して周知啓発強化に取組むよう求めますが、見解を伺います。
㉔次に、新動物愛護センターと多頭飼育崩壊防止の取組についてです。動物保護指導センターの建替えにおいては、災害時のシェルター機能、動物福祉の向上、動物の命を学べる学習機能など、新センターの機能強化を求めてきましたが、新センターにおける機能強化内容と整備スケジュールについて伺います。また、先般視察した京都市では多頭飼育崩壊防止の取組として、届け出する条例、さらには啓発チラシを配布するなど取組みを進めています。先般、本市で多頭飼育崩壊が発生し、動物センターに猫50頭も緊急収容する事態が発生しているため、多頭飼育の届出する条例改正及び啓発や福祉部門との一層の連携と対応強化を図るべきではありませんか。
㉕千葉市少年自然の家についてです。私は長きにわたり、千葉市少年自然の家運営協議会委員として様々提言を行うなかで、新たにキャンプサイトの開設、申込方法の改善など、一定の改善が図られたことを評価しています。少子化が進展するなか利用者の確保が課題となるなか、大人利用者を増やしていく取組みも必要不可欠であるため、少年自然の家を体験した子ども達が大人になっても利用が進むよう、キャンプサイト、ログハウスなどの一層の充実、利用しやすい環境づくりを求めますが、見解を伺います。
㉖次に、宅配ボックス購入支援についてです。EC市場は増加し続けており、最大手のAmazon利用者数は6742万人、楽天市場も6613万人と多くの市民が日々通販を利用しており、宅配事業は増加し続けています。そうしたなか、山梨県のHPのように多くの自治体で家庭用宅配ボックスの設置支援の取組を進めています。宅配ボックスの設置は、物流業界の人手不足の解決策としても有効で、宅配事業者の負担軽減と、CO2削減の効果が上がる施策と考えますが、本市の見解を伺います。また、宅配ボックス購入支援の検討を求めますがいかがですか。
㉗次に、メガソーラー規制条例の制定について伺います。先般、メガソーラー規制条例を制定した神戸市を視察しました。土砂災害警戒区域のみならず、住居地域でも市に届出許可が必要なこと、山林での開発の場合は一定の山林面積の保全、太陽光発電地盤に侵食防止対策を求めており、条例施行後、大規模なメガソーラー申請が減少するなど、条例効果が上がっているとのことでした。そこで市長に伺います。本市でも速やかにメガソーラー規制条例を制定し、災害防止や山林面積の保全などに取組むべきではありませんか。また、越智町のメガソーラー発電については、先の議会で建設中止すべきと求めてきましたが、市の対応とその後の事業者の対応状況について伺います。
㉘次に、カスタマーハラスメント対策についてです。客から理不尽な要求や暴言などを受けるカスタマーハラスメントの防止をめざす条例が東京都や北海道、群馬県で施行されました。また、総務省が地方自治体職員を対象とした初のハラスメント実態調査の結果を公表し、回答者の35%が、理不尽な要求や暴言などのカスタマーハラスメントを受けたことがあると回答しており、対策強化が必要と考えます。そこで、カスタマーハラスメントを少しでも減らすよう防止条例の制定、市職員を含む対策強化を図るべきと考えますが、市長の見解をお聞かせください。
㉙次に、稲作農家と有機農家支援について伺います。スーパーでのコメの平均価格は、5キロあたり4,223円となるなど、昨年の2倍となる異常な事態となっています。減反政策により需要と供給のバランスが崩れていることが最大の要因であるため、稲作農家への支援強化が強く求められています。参考にすべきは、千葉県いすみ市であり、有機栽培を行う農家を支援し2017年に学校給食をすべて有機米に変え、昨年10月には給食費を無償化し、有機給食が知られ、移住相談が2021年度に741件まで増加するなど、まちづくりの面でも好循環が生まれています。本市内で安心して米づくりができるよう稲作農家への支援強化を求めます。また、いすみ市のように有機米や有機野菜農家を増やすための支援に取組むべきではありませんか。答弁を求めます。
㉚千葉駅周辺の開発についてです。中央公園・通町公園の連結強化は、年間約70万人のイベント来場者がある中央公園と、年間約100万人の参拝者がある千葉神社を回遊させるために総額30億円も投じる計画であり、これまでも費用対効果の面からも見直しを求めてきました。新たに中央公園プロムナード周辺のまちづくりビジョンの策定に予算が組まれるなど、中心市街地への予算偏重は市民からも批判の声が寄せられています。そこで、中央公園通町公園連結事業を見直し、6区のまちづくり、行政施設の配分など、バランスとったまちづくりを進めるべきではありませんか。
㉛続いて、桜の再生についてお聞きします。4月に開催された『おゆみ野さくらさくさくウォークラリー』に参加したところ、おゆみ野四季の道で綺麗に咲き誇る桜も老朽化が進行しているため、桜の再生への取組の要望をいただきました。そこで伺います。本市において、桜の再生にどのように取組んでいるのか伺います。また、おゆみ野四季の道の桜は、緑区民にとって貴重な地域資源のため、桜の保全に取組むよう求めます。お答えください。
㉜新湾岸道路整備について伺います。地域でオープンハウスが開催されたものの、道路形状から整備期間、コストなど重要なことが示されていません。住民からは美浜区の住環境・景観、住民の健康悪化、資産価値の低下を心配する声も届いているため、住民の懸念や整備反対の声も国に伝達し、道路整備を中止すべきではありませんか。また、人口減少となる局面での大型道路整備に莫大な税金を投入するのではなく、白線が消えている箇所も多いため、道路の区画線、ガードレール・歩道整備など、身近な交通安全対策予算を増やし市民要望に応えることこそ必要と考えますが見解を伺います。
㉝ミッシングリンクの解消について伺います。緑区民への市民要望アンケートで毎年多数の要望が寄せられるのは、大網街道バイパス道路整備や生実本納線の整備であります。そこで、大網街道の渋滞は深刻であり、塩田町誉田町線、生実本納線の早期整備が急務であるため、最新の進捗を伺うと共に、大幅に予算増額しての早期整備を求めます。お答えください。
㉞雨水対策強化についてであります。近年のゲリラ豪雨、線状降水帯による集中的かつ継続的な豪雨による道路冠水等の相談は増加しています。道路冠水が起きやすい箇所が市内に何か所あるのか伺います。また、誉田東小学校前の道路において冠水被害への軽減対策に取組むよう求めますが、対応をお聞かせいただけますか。
㉟次に、不登校対策についてお尋ねします。5月に日本共産党は『子どもの権利を尊重し、子どもも親も安心できる支援を、過度の競争と管理をやめ、子どもを人間として大切にする学校を』という不登校対策への提言を公表しました。併せて、日本共産党市議団は浦安市の学びの多様化学校を視察しました。黒板が3つあり、学習の習熟度に応じた学びを実践することや教室の授業が困難な時はリフレッシュルームでの学習、カウンセラーの常駐など、手厚い支援は参考になりました。そこで伺いますが、我が党の不登校対策提言を活かした取組を進めていただきたいと思いますがいかがですか。また、学びの多様化学校においては、市内で1か所となると通学できる生徒が限られるため、東部地域にも学びの多様化学校の開設を検討すべきと考えますが、見解を求めます。
㊱最後に、先月、千葉市若葉区で中学3年の男子生徒が80代の女性を刺し死亡させた事件について伺います。お亡くなりになられた市民に哀悼の意を表します。「誰でも良かった」という趣旨の供述をしているとの報道もあり、通り魔的な事件であったことも、市民に衝撃を広げています。本件の加害者である男子生徒においては、私生活の悩みなど、教員やスクールカウンセラー、青少年サポートセンター等に相談が寄せられていたのか、相談の対応状況についてお聞かせください。また、今後こうした痛ましい事件をなくすためにも、学校生活や家庭などにおける生徒の悩みに寄り添って対応できるよう、教員の増員とスクールカウンセラーを増員し、各学校に常駐体制とすること及び、青少年のサポート体制を強化すべきではありませんか。
【神谷市長答弁】
ただいま、日本共産党千葉市議会議員団を代表されまして、椛澤洋平議員より市政各般にわたるご質問をいただきましたので、順次お答えいたします。
はじめに、米国の関税措置への対応についてお答えします。
まず、政府の対応に対する見解についてですが、閣僚級による日米関税交渉に当たり、一連の関税措置の撤廃を求める方針で臨まれているものと確認しております。
次に、市内企業への影響と支援策についてですが、市内企業及び関係機関への聞き取りでは、市内においては輸出に占める米国の割合はそれほど大きくないことなどから、現時点では大きな影響は現れていないものの、今後の経済情勢の先行きに対する懸念が高まっているものと認識しております。現在、本市及び千葉市産業振興財団に相談窓口を開設しているところですが、引き続き関係機関と連携して市内企業への影響の把握に努めるとともに、国の動向を注視しながら、適切な支援を検討して参ります。
次に、物価高騰対策についてお答えします。
まず、消費税減税についてですが、消費税については、少子・超高齢社会が進展する状況において、社会保障の充実及び安定化を図るための財源を確保するとともに、税制全体としての世代間などの負担の公平性の観点から、国が消費税制度の導入を判断し、実施しているものと認識しております。今般の物価高騰の状況により、市民生活に影響が生じていることは承知しておりますが、消費税減税が実施された場合には、本市において約270億円ある地方消費税交付金の減額も予想され、住民サービスへの影響が懸念されます。税制については、国において社会経済構造の変化含め、総合的な観点から検討されるものと承知しておりますが、地方財政への影響などを踏まえ、代替財源についても併せて議論すべきと認識しております。
次に、賃上げ支援金支給などの物価高騰対策についてですが、ベースアップを含む実質賃上げを図るためには、企業において必要な原資を持続的に確保することが重要であると認識しております。このため、本市におきましては、労務費を含むコスト全体の価格転嫁の促進と、企業の設備投資や人材育成などの生産性向上による収益力強化の支援に取り組んでいるところです。なお、物価高騰支援についても、エネルギー価格高騰の影響を受ける中小企業者や公共交通事業者に対する支援金など、特に物価高騰に影響を受けている事業者向けの施策を令和6年度2月補正予算に計上し、支援に取り組んでいるところです。
次に、上下水道料金の値上げについてお答えします。
まず、千葉県の水道料金及び本市の下水道使用料の値上げによる市民の皆様への影響額についてですが、県の水道料金につきましては、千葉県より、口径20ミリメートルで1か月当たり20立方メートルを使用する一般的な家庭への影響額は、600円程度と聞いております。その場合の下水道料については、288円程度となる予定です。
次に、県の水道料金値上げに対する対応についてですが、近年、資材価格や電気代など光熱費の高騰で、上下水道とも、事業を行っていく際の経費が増加しており、令和7年度第1回千葉県水道事業運営審議会における県の説明では、料金の値上げを行わない場合、令和8年度から赤字となり、資金不足も発生するとされております。一方で、料金の値上げは長期化する物価高騰により、厳しい状況にある市民生活に影響を与えることから、県には、値上げ幅の抑制や市民への丁寧な説明をしていただきたいと考えております。
次に、一般会計から繰入を増やして下水道使用料の値上げを抑制することについてですが、下水道事業会計は独立採算が原則であることから、資金不足については使用料改定により賄うべきであると考えております。市民の皆様のご負担を可能な限り軽減するため、抑制策を反映し、改めて試算した結果、改定率を15パーセントから13.6パーセント程度へ抑制することが可能となりました。なお、昨年度の使用料改定では、ウクライナ情勢に伴う世界的な電力価格の急騰による市民生活への影響を考慮し、電力価格の高騰分を一般会計から繰り入れしたものです。今後は、市政だより等を活用して下水道事業の経営状況や必要性・重要性を丁寧に説明し、市民の皆様にご理解、ご協力をいただけるよう努めて参ります。
次に、子育て支援策の充実についてお答えします。
保育料負担軽減の概要と開始時期等についてですが、まず、負担軽減策の概要としましては、保育の必要性があり、かつ、生計を同一にしている多子世帯の経済的負担の軽減を図るため、認可保育施設における所得制限や年齢制限等を撤廃し、保育料の第2子半額、第3子以降無償化を実施するとともに、認可外保育施設や幼稚園・認定こども園の預かり保育における保育料の負担軽減を図るものであり、開始時期は本年9月を予定しております。なお、第2子無償化については、さらに多額の財源を要するため、既存事業の廃止・見直しも含めた検討が必要となってくることから、他事業への影響も考慮しながら、子育て支援施策全体の中で優先順位を勘案し、実施の判断をして参ります。
次に、防災対策の仮設住宅についてお答えします。
仮設住宅に入居可能な世帯数についてですが、建設型の仮設住宅の候補地196か所に、約30平方メートルの標準的な住戸を整備した場合、5,246世帯の入居が可能になると試算しております。また、速やかに整備するための民間との連携強化についてですが、仮設住宅の建設に早期に着手できるよう、千葉県建設業協会等の3団体に加えて、昨年8月に、新たに2団体と協定を締結するとともに、応急仮設住宅供給マニュアルを基に、毎年、協定団体と訓練を行っております。今後も、他都市の被災時における対応状況なども検証しながら、民間団体とも連携し、事前の準備を充実させて参ります。
次に、学校体育館冷暖房設備整備の前倒しについてお答えします。
今後の取り組みについてですが、まずは、部活動がある中学校・中等教育学校・高等学校・特別支援学校を優先して進め、来年度末までに整備完了を予定しております。小学校については、令和12年度までの整備を想定していましたが、近年の猛暑や災害の発生状況を踏まえ、児童生徒の熱中症対策及び避難所としての環境整備の観点から、令和11年度までに全校への整備を目指しつつ、さらなる前倒しについても検討を進めて参ります。
次に、JR京葉線の快速復元とホームドア設置についてお答えします。
令和5年12月にJR東日本からダイヤ改正の発表がなされて以降、本市などの働きかけにより快速電車の一部が数次にわたって復便されたほか、快速電車の所要時間が短縮されたところです。一方で、更なる快速の復便が望まれる夕方、夜間のピーク時間帯の下り列車については、JR東日本によれば、新木場駅の混雑状況から利用者の安全確保に課題があるため、快速運転化が困難とのことですが、本市としては鉄道事業者としての安全対策の検討を求めるとともに、新木場駅の混雑緩和にも寄与すると考えられる、りんかい線と京葉線の相互直通の実現について、要望しております。また、夕方ピーク時間帯の上り列車やピーク後の夜間帯の下り列車の快速化等についても、更なる改善に向けて、協議しております。今後も、JR東日本、千葉商工会議所、本市の三者で行う協議の場を活用し、駅周辺のまちづくりとあわせて、市民生活や経済活動の実態に見合ったダイヤ編成に向けて、引き続き働きかけて参ります。
次に、ホームドア設置についてですが、JR東日本のこれまでの発表によると、令和13年度末頃までに、市内の総武緩行線の、幕張駅、新検見川駅、稲毛駅、西千葉駅で年内供用開始を目指して整備が行なわれています。このうち、稲毛駅については、今月の21日に供用開始の予定となっております。本市としましては、特に乗降客数の多い千葉駅、稲毛駅、海浜幕張駅において、整備促進を図るために整備費の一部を補助することとしており、その他の駅へのホームドア設置につきましても、千葉県JR線複線化等促進期成同盟を通じて、引き続き要望して参ります。
次に、町内自治会の加入向上に向けた取り組みについてお答えします。
加入率の改善と地域づくりの担い手確保に向けた取組みについてですが、本市への転入者に対し、町内自治会の役割や活動内容等を分かりやすく掲載したチラシを各区役所で配布し、新規加入を促しているほか、宅地建物取引業協会千葉支部や宅地開発業者に協力を要請し、加入の呼びかけを行っております。更に、全地区に地域担当職員を配置し、顔の見える関係を構築するとともに、町内自治会とNPO等の団体が連携し、複雑・多様化する課題解決に取り組めるよう、団体同士が新たにつながるきっかけづくりに努めているところです。今後は、デジタルツールを活用した情報共有手段の効率化に関する検討を進めるとともに、市から町内自治会へ依頼している業務の棚卸しを行うなど、事務負担の軽減を図り、地域の担い手の確保を支援して参ります。
次に、千葉マリンスタジアム建て替えについてお答えします。
まず、熱中症対策への対応についてですが、今後、屋外型スタジアムとしての整備に向けて検討を進めて参りますが、その中で、例えば、観客席上部への屋根設置やミストシャワーの設置など、熱中症対策と快適性の向上に向けて、要する費用も勘案しながら、より効率の高い対策について、千葉ロッテマリーンズや事業協力者となる民間事業者とともに、検討していくこととしております。
次に、交通対策への取組みについてですが、新たなスタジアムの候補地は、現スタジアムより駅から近い場所となることから、公共交通機関を利用しやすい環境となります。また、候補地のある豊砂地区では、これまでウォーカブルの促進にも取り組んできており、公共交通機関利用者の増加などの効果も得られています。こうした環境や効果を活かし、一層の公共交通期間の利用を促してまいりたいと考えております。このような考えを念頭に置きながら、スタジアムへの玄関口となる駅が変わり、幕張新都心全体での自動車や歩行者など交通の流れに変化を及ぼすことも想定されるため、今後の基本計画の検討の中で、新たなスタジアムの再構築に伴う交通量を分析することにより、具体的な交通対策を検討し、千葉県警察や交通事業者とも協議、調整を進めて参ります。
次に、市民会館の再整備についてお答えします。
まず、将来活用検討地とJR東日本千葉支社跡地の整備コストの違いについてですが、敷地形状の違いによる建物建設費用や、土地取得にかかる費用などに差が生じますが、利用者のアクセス性や千葉駅周辺の活性化など総合的に検討した結果、JR東日本千葉支社跡地で整備することとしたものであります。大ホールの整備方針については、令和3年11月に策定した「千葉市民会館再整備にかかる基本計画」において、演劇やミュージカル、クラシックやポピュラー音楽等のプロの大規模な公演から、市民団体の公演や全国レベルの大会まで、様々なジャンルに対応するため、多目的ホールとして、客席数は1,500席程度で検討を進めることとしております。 また、整備時期については、JR東日本との協議が必要なことから、現時点で具体的にはお示しできませんが、現市民会館の老朽化の状況も踏まえ、着実に整備を進めて参ります。
次に、会議室等諸室の機能強化についてですが、市民会館における会議室等の諸室につきましては、令和3年度策定した「千葉市民会館再整備にかかる基本計画」で定めた内容を基本としつつ、今後行う基本計画の修正等において、市民会館の諸室として、必要な機能や規模等を精査しつつ、多目的な利用などの工夫を含め、検討して参ります。
次に、斎場整備についてお答えします。
まず、斎場の整備に向けた取組みについてですが、近年、高齢者人口並びに死亡者の増加に伴い、特に1月から2月にかけて、死亡から火葬までに長期間お待たせする状況が常態化しております。昨年度、今後の斎場のあり方を検討するため、死亡者数や火葬件数の推計、現状でどの程度対応が可能なのかについてのシミュレーションや現在の斎場における設備増設、新規の可能性について調査研究を行ったところです。今後も高齢化が進展し、火葬需要の増大が見込まれる中で、長期間の火葬待ちが生じないよう対策を講じることは、市民の安心感につながり、重要であると考えております。こうした点を踏まえ、将来の火葬需要に適切に対応するため、新設も含めた斎場整備の検討を早急に進めて参ります。
次に、斎場の開場時間の拡大についてですが、本年度より、火葬が集中した際は、友引日会場の拡大と合わせて開始時間の繰り上げ、繰り下げを行い、火災受付枠を一日最大42件まで拡大し、市民の火葬需要に対応して参ります。
次に、新動物愛護センターと多頭飼育崩壊防止の取り組みについてお答えします。
新センターにおける機能強化内容と整備スケジュールについてですが、昨年度は、施設整備の基本方針、必要な機能、規模等を定める整備基本計画を策定するとともに、施設の整備予定地を決定しました。このうち、基本方針において、施設の方向性を「動物とのかかわり方を発信し、学びを提供する施設」、「動物に寄り添った管理を実践する施設」、「行政や市民、関係者が交流し、互いに理解を深める施設」の3つに整理し、それぞれの方向に沿って個別管理を行う収容室、譲渡希望者と収容動物のふれあい室、講習会や研修を行い災害時にはシェルターとしても活用できる多目的ホール、普及啓発のための展示スペースなどの設置を計画しております。整備スケジュールとしては、今年度は基本設計等を実施することとしており、可能な限り早期の着工に向けて取り組んで参ります。
最後に、新湾岸道路整備についてお答えします。
まず、道路整備についてですが、湾岸道路は、湾岸地域における交通容量不足を解消させ、市内の渋滞緩和や物流の効率化による経済の活性化が期待されるほか、災害時における複数ルートの確保による防災力の強化が図られるなど、将来の社会基盤を構築する上で、必要不可欠な道路であることから、引き続き、計画の早期具体化に向け、概略ルート案などの情勢発信を行いながら、市民の皆様のご意見を踏まえた、本市にとってより整備効果の高い計画となるよう国に働きかけて参ります。
また、区画線や歩道の整備など、身近な交通安全対策予算の増額についてですが、引き続き、安全・安心なまちづくりに向け、必要な予算の確保に努めて参ります。
以上で答弁を終わります。私の答弁以外につきましては、両副市長並びに教育長が答弁を致します。
【大木副市長答弁】
市長答弁以外の所管についてお答えいたします。
はじめに、若者支援についてお答えします。
高校生・大学生に対する支援の拡充及び「こども・若者会議」の意見反映についてですが、まず、学費負担軽減については、現在、国において、高等学校等の授業料の実質無償化に向けた取組みが進められているほか、「高等教育の修学支援新制度」においては、令和7年度より多子世帯の学生を対象に、所得制限なく、大学等の授業料の無償化が拡充されたところです。本市においては、経済的理由により修学が困難な市立高等学校等の生徒に対し、「千葉市育英資金」として学資の支給を行っており、引き続き、国の動向を踏まえながら、必要な支援を行なって参ります。
次に、住まいについては、市営住宅において、高齢化が進む団地の活性化を目的に、上層階に空き室が多くある団地への大学生の一時入居について、団地の近くの大学と意見交換を行っているところです。また、「こども・若者会議」において聴取した意見等については、施策への反映を検討することとしております。
次に、高額医療費制度についてお答えします。
負担上限額の見直しについてですが、高額療養費制度については、国において、本年8月から所得区分ごとの自己負担限度額の引き上げなどの段階的見直しが予定されておりましたが、検討プロセスへの指摘などを踏まえ、実施が見送られているところです。現在、利用者の医療費負担を抑制するセーフティーネットとしての役割と、医療費の給付を支えるすべての世代の保険料負担のバランスなどの観点から、患者団体も交えた議論が進められているところであり、引き続きその動向について注視して参ります。
次に、防災対策の避難所トイレについてお答えします。
避難所トイレ環境の向上及びトイレトレーラーの導入についてですが、まず、避難所トイレ環境の向上につきましては、これまで市立学校166校にマンホールトイレを整備し、今後は令和9年度までに市内の県立高校22校への整備を進める予定です。さらに、現在のビニール式のテント上屋に加え、より衛生的で安全かつプライバシーが確保でき、悪天候でも安心して使用できる、堅牢なパネル式の上屋を導入することとし、今年度は172か所の指定避難所に1基ずつ整備して参ります。
次に、トイレトレーラーにつきましては、国において今月1日にせこうされた被災自治体がトイレトレーラー等を相互に活用する「災害対応車両登録制度」の動向を注視するとともに、平時における効果的な活用方法などと併せて、これまで推進してきました本市の災害時のトイレ対策の総合的な枠組みの中で検討するものとしています。
次に、市政だよりへの多言語翻訳に対応した広報紙閲覧サービスについてお答えします。
サービスの導入についてですが、外国人など、広報紙を理解することが難しい方へも情報を届けることは重要であるため、現在、本市ホームページにHTML版の市政だよりを掲載し、インターネットの翻訳機能などを使っていただくことで多言語に対応しているとこです。多言語音声読み上げ機能を有する、有償の広報紙閲覧サービスがあることは承知しておりますが、技術の進展によりスマートフォンなどでも手軽に翻訳機が使えることから、当該サービスを導入する予定はありません。引き続き、翻訳して閲覧される場合を含め、必要な方に必要な情報を、分かりやすく、正確に伝えることのできるホームページの構成となるよう努めて参ります。
次に公益通報制度についてお答えします。
内部通報の近年の通報件数、通報に伴う是正措置、通報しやすい体制と通報者保護の取組みについてですが、通報件数は、直近3年間で、令和4年度は3件、5年度は4件、6年度は7件となっております。本市では、「千葉市職員等からの公益通報に関する要綱」に基づき、内部通報制度を運用しております。要綱では、通報を受けて調査を実施した結果、法令違反や不適正な行為が明らかになったものについては、速やかに発生の防止策や適正な対応策を講じることとしており、調査終了後も、是正措置が図られているか適切な時期に確認し、必要がある場合は、新たな対策を講ずることとしております。通報しやすい体制としては、匿名による通報も受け付けているほか、庁内に設置した窓口だけでなく、指定した弁護士に直接通報できる外部窓口への通報も可能としております。また、通報者保護の取組みとして、通報者は通報を行ったことを理由として、いかなる不利益な取り扱いも受けないこととしており、調査の実施に当たっては、通報者が特定されないよう十分に配慮しております。今国会において、労働者に対する公益通報対応体制の周知の義務化など、改正公益通報者保護法が可決、成立したことから、改正内容の趣旨を踏まえ、引き続き、適切に対応して参ります。
次に 女性職員の活躍への取組みについてお答えします。
まず、主査級と管理職のそれぞれに占める女性職員比率についてですが、本年4月1日時点で主査級は32.3%、管理職は24.8%となっております。
次に、男女間の賃金の差異が生じている理由についてですが、公表した数値は、性別ごとの職員の給与の総額を人数で割った数値を比較しており、女性については、勤務時間の短い会計年度任用職員の比率が高いことなどが割合を引き下げる要因と考えております。なお、本市職員の給与は、条例に定める給料表に基づき決定されており、性別を理由とした給料決定は行っておりません。
次に、女性職員の活躍に向けた取組の充実についてですが、本市では、これまでも能力や意欲のある女性職員を政策決定に関わる部門に積極的に配置してきたほか、所属管理職との定期的な面談や女性の管理監督職も参加するランチミーティングの開催等により、女性職員のキャリア形成に対する意識の醸成・啓発に取り組んで参りました。このほか、業務や家庭生活の状況に応じて、職員が始業・終業の時刻を柔軟に選択できるよう、勤務パターンを拡充したほか、自宅以外の場所でのテレワークを可能とするなど、子育てや介護など、それぞれの多様な事情を受け入れ、柔軟に対応できる職場環境を整備しているところです。引き続き、女性職員の更なる活躍に向け、本年4月に策定した「千葉市職員子育て支援・女性活躍推進計画」に基づき、計画的な育成やキャリア形成支援、働きやすい環境整備などに積極的に取り組んで参ります。
次に、防犯カメラの設置についてお答えします。
まず、家庭用防犯カメラの設置助成についてですが、本市では、犯罪に抑制にあたっては、広範囲での対策を講じていくことが重要であると考えております。町内自治会等からは昨今の犯罪状況等を踏まえ、防犯カメラの設置補助へのご要望を多数いただいておりますことから、地域団体への支援強化を進めているところです。現在、家庭用防犯カメラの設置への助成は考えておりませんが、安全・安心メール等による防犯情報の発信や地域の防犯対策の講座などを通じ、市民の防犯意識の更なる向上を図って参ります。
次に、JR各駅の未設置駅と京成電鉄駅への早期設置についてですが、JR駅周辺へのカメラ設置は、刑法犯認知件数や乗車人員などの諸要件を踏まえ、現在、12駅83台の防犯カメラを設置しており、未設置の駅へも順次設置していくこととしております。京成電鉄駅を含めたその他の場所につきましては、不特定多数の人通りがあり、犯罪発生件数が多い場所について必要箇所の選定方針を検討して参ります。
次に、SNS上の誹謗中傷防止対策についてお答えします。
条例の制定及び被害者支援体制の強化についてですが、本市の支援策として、被害者からの相談については、男女共同参画センターや青少年サポートセンターの窓口、「SNS相談@ちば」などで対応するとともに、市ホームページではインターネット上でのトラブルや違法・有害情報に関する相談、通報受け付けについての相談窓口をご案内しております。また、人権擁護委員が小中学校を訪問し、いじめやインターネット上の人権侵害をテーマに人権教室を実施しているほか、冊子の配布等による意識啓蒙に努めております。条例の制定につきましては、以上のことから、現在、考えておりませんが、被害者の必要とする相談窓口を簡単に探すことができるよう、市ホームページの案内の表記を工夫するなど、被害者支援の充実に努めて参ります。
次に、オンラインカジノについてお答えします。
オンラインカジノへの防止対策や周知啓発についてですが、現在、本市においては、オンラインカジノを利用した賭博は犯罪である旨を市ホームページに掲載するとともに、消費者庁や千葉県警察へのリンクを掲載し、周知に努めているところです。今後も、千葉県警察や大学などと連携し、より一層、オンラインカジノを利用した賭博は犯罪であることについて周知啓発を図って参りたいと考えております。
次に新動物愛護センターと多頭飼育崩壊防止の取組みについてお答えします。
多頭飼育崩壊防止の取組みについてですが、現在、本市では、多頭飼育による問題について、飼い主本人や家族からの相談、近隣住民や福祉専門部等からの通報に基づき、現地を確認した上で、飼い主に対する指導、助言を行うほか、必要に応じて、動物愛護推進委員や獣医師会等の協力も得ながら、動物の飼養状況の改善に向けた支援を行っております。また、飼い主の生活改善支援が必要な場合は、福祉部門と情報を共有した上で、支援につなげていくケースもあります。多頭飼育届出制度を条例で定めることについて、現時点では考えておりませんが、今後、既に条例化している自治体における効果や課題を踏まえ、引き続き研究をして参ります。 また、庁内外の関係機関、団体との連携を強化し、多頭飼育事案の把握や問題が発生した場合の適切な対応、再発防止に努めるとともに、適正飼養に向けた周知啓発に取り組んで参ります。
最後に、千葉市少年自然の家についてお答えします。
大人の利用者を増やしていく取り組みについてですが、児童数の減少が見込まれることから、学校行事以外での利用促進に取り組んでいくことが必要であると認識しております。その取り組みの一環として、令和7年の「千葉市二十歳のつどい」を契機に、20歳を迎えた方を対象とした割引プランを開始したことに加え、高校生以上の利用料金を半額にする期間を2か月延長するほか、ログハウスにおいて、子ども達の利用に支障をきたさない範囲でアルコール飲料の持ち込みを可能とするなど、大人利用の促進を図っております。また、ファミリーキャンプやログハウス内での飲食プランの提供など、家族で楽しめる様々な企画を取り入れ、学校行事いがでの利用促進にも取り組んでおります。さらに、電子マネーでの支払いを可能とするなど、利便性の向上にも取り組んでおり、引き続き、利用者アンケートや運営協議会のご意見などを踏まえ、施設の利用促進に努めて参ります。
以上でございます。
【橋本副市長答弁】
市長答弁以外の所管についてお答えします。
はじめに、下水道管の老朽化対策についてお答えします。
本市における下水道管や取り付け管に起因する道路陥没の発生件数についてですが、下水道管は、令和4年度が13件、5年度が4件、6年度が4件、取り付け管は、4年度が7件、5年度が24件、6年度が19件であり、いずれも小規模なもので、速やかに復旧対応を行っております。下水管の改築予算については、前年度予算を含め5年度は39億円、6年度は36億円、7年度は24億円となっています。今後、老朽化対策に係る予算につきましては、必要な財源を確保するよう、引き続き、国に要望することとしております。
次に、バス路線維持に向けた取組についてお答えします。
まず、バス利用者を増やすため、の、無料デーや高齢者への運賃負担軽減策についてですが、地域公共交通計画に基づく利用促進策の一つとして、既に、市内のバス事業者が自ら、運転免許返納者への運賃割引のほか、乗り放題となる年間パスポートの販売を行っていることから、現時点では無料デーや高齢者への運賃軽減策を実施することは考えておりません。なお、バス路線の維持・確保のためには、バスを利用していただくことが不可欠であることから、このことを市民の皆様と共有するとともに、引き続き、バス停へのベンチの設置など利用環境の改善や、転入者向けのリーフレットの配布などの公共交通の利用促進施策について、庁内で連携して取り組んで参ります。
次に、大椎台へのバス路線復活やあすみが丘との循環バスの早期実現についてですが、昨年4月に大椎台から土気駅を結ぶ路線バスが廃止となったことを受け、買い物や通院などの日中の移動手段として、デマンド型タクシーの運行を社会実験として取り組んでおります。また、朝晩の通勤通学時間帯における移動手段の確保が課題となっていることから、廃止となったバス路線の復便について、地元交通対策協議会が、バス事業者に陳情をしてきており、今後は、具体的な需要や運行を希望する時間帯などを把握するため、住民アンケートを実施する予定と聞いております。
バス事業者からは、運転手不足等の課題があるものの、対策は続けたい旨の意向が示されておりますので、本市としましては、同協会での議論を見守りつつ、引き続き可能な支援の実施に努めて参ります。
次に、幕張メッセで開催される展示会についてお答えします。
まず、DSEI開催をやめてほしいという声への受け止めについてですが、現地でDSEIの開催に関して反対の声があげられていたことは承知していますが、施設の指定管理者である株式会社幕張メッセが千葉県の日本コンベンションセンター国際展示場設置管理条例等に基づき、会場としての施設提供の判断をするものと認識しております。
次に、議員の入場が認められないという対応が行われたことへの見解についてですが、施設の所有者である千葉県及び主催者に、どのような理由で入場を認めなかったということについて確認しましたが、回答はなく、このため見解を申し上げることはできません。
次に、宅配ボックスの購入支援についてお答えします。
まず、設置に対する本市の見解についてですが、各家庭に設置が進むことは再配達を減らすことになり、CO2の削減や、人手不足の解消につながり得るものと考えております。
次に、購入支援の検討についてですが、本市では、再配達を減らす取組みとして、民間事業者との連携により、本庁舎や区役所などに宅配ロッカーを設置しており、各家庭への宅配ボックスの設置についても、他自治体の実施状況を調査しているところです。
次に、メガソーラーについてお答えします。
まず、メガソーラー規制条例の制定についてですが、昨年4月の再エネ特措法の改正により、周辺住民への説明会等による事前周知が義務付けられるなど、FIT等の対象となるメガソーラーの設置については、国の認定を受ける必要があり、適切な事業実施が求められていることから、条例の制定については、引き続き国や他自治体の動向を注視して参ります。
次に、越智町のメガソーラー発電に関する、市の対応とその後の事業者の対応についてですが、これまでも国に対し、地域住民の声を伝えるとともに、事業者へは住民への丁寧な対応を求めてきたところであり、引き続き事業者の動向等を注視して参ります。
次に、カスタマーハラスメント対策についてお答えします。
条例の制定及び対策強化についてですが、市内事業者への取組みについては、カスタマーハラスメントの基礎知識の習得や対応が進むよう周知に努めているところです。さらに、国において、カスタマーハラスメントから従業員を守る対策を事業主に義務づける、「改正労働施策総合推進法」が先週、成立したところであり、今後、対策の具体的な内容が示されることとなっているため、国の動向を注視しつつ、引き続き周知啓発に努めて参ります。なお、本市職員への取組みについては、職員が安心して働けるよう、名札をフルネームから名字のみに変更したところであり、カスタマーハラスメント対策にもつながるものですが、より包括的な対策に向けて、昨年度実施した職員アンケートにより、本市の現状や課題を把握し、先進自治体の取り組み状況等も踏まえ、必要な対策を検討して参ります。
次に、稲作農家と有機農家支援についてお答えします。
まず、稲作農家への支援強化についてですが、稲作農家の経営を安定させるため、国の「経営所得安定対策等」の交付金を活用した収入減少時の補填などの支援を行っております。また、生産性の向上や省力化を図るため、「未来の千葉市農業創造事業」により、施設整備や機械導入に対し、助成を行っております。
次に、有機米や有機野菜農家への支援についてですが、市内農業者が新たに有機農業に取り組む際の営農指導に結び付けられるよう、昨年度から、農政センターに整備したパイプハウスにおいて、葉物野菜の有機栽培実証を行っております。また、有機農業についての理解を促進するため、令和5年度から農政センターにおいて、有機農業に取り組む農業者や有機農業に関心のある農業者などを対象に「有機農業勉強会」を開催しております。
次に、千葉駅周辺の開発についてお答えします。
中央公園・通町公園連結強化事業の見直しについてですが、千葉駅周辺については、活性化グランドデザインに基づき、県都の都心にふさわしい都市機能の強化や、官民連携によるウォーカブルなまちづくりを推進するべく各種施策を展開しております。中央公園・通町公園の連結強化事業は、賑わいと回遊性を高める空間の整備を通じて、地域資源や民間活力を活用した新たな魅力の創出や周辺地域の活性化を図るものであり、千葉市らしさを感じられるまちづくりによって、本市の良さや魅力を将来につなげる、「未来を創る」取組であると考えております。今後も、各区、各エリアの特徴を最大限生かせるよう都市デザインの考え方を取り入れ、市全体の魅力と活力の向上へ繋がるまちづくりを進めることで、市民サービスの維持・向上を図りながら、持続的な都市経営に取り組んで参ります。
次に、桜の再生についてお答えします。
まず、桜の再生への取組みについてですが、市内では、泉自然公園や昭和の森、亥鼻公園などがサクラの名所として親しまれていますが、多くの公園でサクラの老木化が進んでおり、花が少ない、枯れ枝が多くなるなどの状況が生じております。 このうち、亥鼻公園では千葉開府900年に向けて、千葉城さくらまつり実行委員会から頂いた寄附金を活用し、平成30年度から令和5年度にかけて、生育不良の老木を間引くとともに。新たに若木を50本植樹しました。また、泉自然公園や昭和の森においても、昨年度、保全や再生に向けた現況調査を行ったところです。
次に、おゆみ野四季の道における桜の保全についてですが、四季の道は、草花や樹木により季節の移ろいを楽しむことができる総延長6.4キロメートルの自転車歩行者専用道路です。まち開きから約40年が経過し、「春の道」のサクラも大きく成長しており、地域の皆様の散策と憩いの場として親しまれております。現在は、日常管理の中で、枯れ枝や病気の発生がないか確認するとともに、必要に応じて樹木剪定や害虫防除を行っており、今後もサクラの育成状況に留意しながら、適切に保全して参ります。
次に、ミッシングリンクの解消についてお答えします。
塩田町誉田町線及び生実本納線の進捗と早期整備についてですが、両路線ともに重要路線に位置付け、早期整備に向けて取り組んでおります。進捗については、塩田町誉田町線の誉田地区では、用地取得率が70%、塩田地区では、用地取得率が98%で、工事については、橋りょうの橋脚工事を行っているところです。生実本納線の高田インターチェンジでは、フル化に向け擁壁工事を行っており、赤井町地区では用地取得率が92%で、工事については、本線部の整地工事を行っているところです。
最後に、雨水対策強化についてお答えします。
まず、市内で道路冠水が起きやすい箇所についてですが、道路冠水の恐れがあり、事前にパトロールや清掃を行っている箇所は、約100か所あります。
次に、誉田東小学校前の道路における冠水被害軽減対策についてですが、地元自治会からご要望が寄せられていることから、昨年度より被害軽減に向けた対策の検討を進めているところです。
以上でございます。
【教育長答弁】
はじめに、不登校対策についてお答えいたします。
まず、不登校対策の取り組みについてですが、本市では、「人権尊重の教育」を教育施策の基調とし、児童生徒一人一人を尊重し、よさや可能性を大切にする教育を推進しています。不登校児童生徒への支援としましては、「不登校対策パッケージ」に沿って、個々の置かれた状況を踏まえつつ、学校復帰を含めた社会的自立を目指した取り組みを進めて参りました。今年度からは、新たに策定した「第2次不登校対策パッケージ」に基づき、ステップルームティーチャーの増員やライトポートカウンセラーを全6所へ配属するなど、提言にも記載されておりますように、支援体制の充実に取り組んでいるところです。また、保護者交流会の開催機会を増やすことによる保護者との連携や支援の強化、フリースクール等民間施設との連携などを進めて参ります。
次に、学びの多様化学校についてですが、今年度より、開校に向けた設置検討委員会を設置し、コンセプトなどの基本計画について協議を始めました。通学にあたっては、市内全域からの生徒が受け入れられるよう、できる限り、交通の便がいい場所を候補地として、旧高洲第二中学校の跡地を利活用することにしました。現状、東部地域への開設は考えておりませんが、まずは1校目を開校し、様々な実態把握や効果検証を行った上で、さらなる課題については調査研究して参ります。
次に、先月若葉区で起きた事件についてお答えします。
まず、本件の加害者である男子生徒についてですが、公的機関の発表において、個人が特定されていないため、対応状況などは把握しておりません。しかし、本市で起きた痛ましい事件の児童生徒への影響を鑑み、全市立学校に対し、「児童生徒への心のケアについて」の依頼文書を発出し、児童生徒の不安や動揺などに寄り添うよう指示するとともに、保護者に対しても家庭での見守りを働きかける「保護者向けお子様の心のケアについて」の文書により協力を呼びかけ、学校と家庭との連携を図りました。今後も、児童生徒が安全・安心な学校生活を過ごせるよう、保護者や地域の方々の協力をいただきながら支援に努めて参ります。
最後に、教員とスクールカウンセラーを増員し各学校に常駐体制とすることについてですが、これまでも、児童生徒の悩みや不安に寄り添い、相談しやすい体制を整えるため、校内支援体制の構築はもとより、スクールカウンセラーやステップルームティーチャーの配置拡充等に取り組んで参りました。今後は、多種多様な要因を背景とした児童生徒の相談に対し、地域とのネットワーク強化や医療や福祉の専門家との連携など、相談体制のさらなる充実に努めて参ります。また、青少年のサポート体制についてですが、青少年サポートセンターや児童相談所、こども・若者総合相談センター「Link(リンク)」において、相談員等の増員や精神保健福祉士等の有資格者を配置するなど、これまでも、相談支援体制の充実を図ってきたところです。 今後も、児童・生徒への各種相談機関についての周知を図り、早期の相談に繋げていくとともに、多様化、複雑化する相談内容に対応するため、支援機関との必要な連携強化を図るなど、相談支援体制の充実に努めて参ります。
以上でございます。
【2回目】
不登校対策についてです。改めて強く協調したいのは、スクールカウンセラーとステップルームティチャーの配置であり、とりわけ誰でも相談が可能なスクールカウンセラーは中学校では週1回程度の派遣であります。市民からは「学業だけではなく家庭の悩みも相談できて良かった」とある一方で、「週1回だけの対応で予約が埋まっていることもあり相談しづらい」との声も届いています。
①若葉区で中学生が起こしたような悲惨な事件をなくすためにも、少なくとも生徒が相談したい時に相談できる体制整備が重要だと考えませんか。また、不登校者数が10年で3倍に増えているため、全校に特に中規模大規模校にはスクールカウンセラーの配置時間を増やすよう、改めて強く求めます。お答えください。
次に、農業対策についてです。本市の農家の7割は300万円未満で2005年には1446戸あった農家を2020年には658まで減らし続けてきたことへの検証とそれに基づく、従前の枠組みにとらわれない対策強化が必要だということです。特に、青年農家に聞けば機械の設備投資500万円や1000万円は厳しい、農機具の共有などへの要望も寄せられています。
②減り続ける小規模農家、家族農家、青年農家を増やす対策として、中古農機具やハウスなどの共有事業に取組むこと、お米と野菜農家が継承持続させていくために、いすみ市のように農家への所得補償を真剣に検討すべきではありませんか。見解を伺います。
続いて、子育て支援の充実についてです。日本経済新聞社等による「共働き子育てしやすい街ランキング」 が公表され、本市は近年順位を下げ続けて、43位であります。1位となった神戸市では、待機児童対策等は勿論のこと、高校生向けに通学定期代の無償化を実施したことです。神戸市へ調査を実施したところ、高校生等のいる幅広い世帯への経済的支援の拡充、市内の多様な高校教育環境の維持、年少人口が減少する中でも若年・子育て世帯に選ばれるまちにという目的のもと、通学定期代を無償化し、利用者が22,000人となり、子育て世帯から感謝されているとのことでした。本市の子育て世帯からは「保育等も大事ですが、一番子育てでお金のかかる時期にもっと支援してほしい」という声が高まるもとで、支援を拡充していくべきと考えます。
③神戸市の先進的取組に学び、本市としても高校生の通学定期代無償化を検討していただきたいと思いますがいかがですか。また、最も子育て家庭の経済的負担が高まる時期への支援策を真剣に検討すべきと考えますが、どのように取り組むのか伺います。
次に、バス事業者支援と高齢者外出支援についてであります。ここ2年間のバス減便数は市内でも1380便も減少しているなか、減便止めるための利用者を増やす取組は急務でやはり運転免許返納時からの利用のインセティブは重要です。横浜市では75歳以上になってから運転免許証を自主返納し、敬老パスを申請した方に、敬老パスを3年間無料で交付する事業を開始するとのことです。注目すべきは過去に敬老パスを5年間継続保有した方は、保有していない方と比較して、その後の5年間で要介護認定を受けることが10%程度少ない傾向がみられるとの効果検証がされている点です。本市でも5月からバス事業者各社と本市がより緊密に連携を図っていくべく、ワーキンググループを今後開催していく旨を、市長は先般の記者会見で述べられていました。ぜひそこでバス利用促進のために、何が必要なのかを真剣な議論をお願いしたいと思います。
④本市の要介護認定者が現状より10%低下した場合の年間の財政削減額についてお示しください。また、バス路線を減便、廃止を食い止めるためにバス利用者を増やすことは急務であり、バス事業者とのワーキンググループにおいてバス事業者への運行経費支援拡充とともに、高齢者の負担軽減、市民の利用促進策の議論を進めるよう強く求めます。お答えください。
次に、下水道管の老朽化対策についてです。令和6年度で23件もの下水道管や取付管の陥没事案がある一方で、前年度より12億円も予算が減少しています。また、下水道維持課の職員についても配置変えもあって、17名による職員しかいないのが実態です。老朽化対策の需要が今後さら高まるもとで、専門職員は重要であるため、更なる増員も必要と考えます。
⑤2019年に緑区あすみが丘の下水道管陥没以降も、小規模な陥没事案が年間20件程度毎年発生しているため、市民生活の安全を守るためにも予算を増額して下水道管の点検調査・老朽化対策に取組むよう求めますが見解を伺います。同時に、ドローンなど技術の活用と、今後増える維持改修へ取組む専門職員の増員を求めますがいかがですか。
次に、水道料金・下水道使用料の値上げと物価高騰対策についてです。水道600円下水道使用料288円、合計で約900円の負担増、年間では1万円以上負担が増える見通しです。県には「水道料金値上げ抑制していただきたい」と答弁する一方で、市の下水道使用料については一般会計の繰入をしないとのことです。ここで府に落ちないのは、令和6年の下水道使用料改定5.4%へと引き上げる際に、一般会計からの繰入額は、約4億円出していることです。一般会計から繰入れをした理由は「ウクライナ情勢に伴う世界的な電力価格の急激な高騰による、市民生活への影響を考慮した」とのことですが、当時と比較しても今はお米が2倍に値上げするなど、物価高騰による生活の厳しさは増しているのではないでしょうか。日本共産党千葉市議団による市民要望アンケートですが、5月に配布したばかりですが、すでに1,000通を超える回答が寄せられています。生活状況については「悪くなった」「やや悪くなった」合わせると約9割の方生活が悪くなったと回答しており、毎年の調査と比較しても過去最悪の悪化は深刻な事態です。実際のアンケートの声を一部紹介します。30代女性「美容室を減らしている」。40代女性「こどもへのおやつをなくした。将来が不安しかない」。70代男性「年金が上がらず物価だけ上がって苦しい。スーパーは夕方に安くなる時に行くが買わない時もある」。80代男性「風呂を2日に1回にして、食事も3食を2食に減らしている」など、長引く物価高騰でやっとの思いで生活しているという市民の声が多数寄せられています。
⑥市長の認識を改めて問いたいのですが、令和6年より今年のほうが米価も2倍となるなど長引く物価高騰下、市民生活状況の悪化を真剣に捉え、市民向けの物価高騰対策に取組むよう求めますが見解をお聞かせください。また、先般党市議団は市民団体と上下水道値上げ中止求める署名を7千筆も提出しましたが、市民の声を受け止め、前回の料金改定時のように一般会計繰り入れをして値上げを抑制するよう重ねて求めます。お答えください。
次に、武器見本市についてです。今回のDSEIジャパンでは、実際に中に入られた方から提供いただいた写真をご覧ください。イスラエル企業が20社も参加しており、イスラエルのエルビットシステムズ社ブースでは、4月にガザで避難民テントを爆撃して、子ども14人を含む30人を虐殺したと報道されている殺傷兵器、自爆型ドローン「スカイストライカー」が展示されていたとのことであります。本市の平和都市宣言ですが、「私たちは、核兵器などによる戦争への脅威をなくし、市民共通の願いである世界の恒久平和を求め、ここに平和都市を宣言する。」と高らかにうたっており、こうした宣言に矛盾しているのではないでしょうか。そして、共産党が排除された問題では6月4日の国会でわが党のたつみコータロー衆院議員が取り上げましたところ、イベント後援している経産大臣からは一般論としつつも「特定のグループを排除することは公益性にそぐわない」という答弁をされています。
⑦ガザでジェノサイドを続けるイスラエル企業の戦地で実証されている自爆型ドローンや多くの武器を千葉市の公共施設幕張メッセで展示し世界に武器を拡散していくことについて、千葉市平和都市宣言の核兵器などの脅威をなくし、との宣言と矛盾しているのではありませんか。また、約130億円以上の税金を投入して整備された公共施設で開かれるイベントにおいて、特定のグループを排除するような反民主的運営について公益性にそぐわないと思わないのか、主催者に事情を確認して是正するよう求めるべきではありませんか。
2回目
【神谷市長答弁】
2回目のご質問にお答えいたします。
水道料金・下水道使用料の値上げと物価高騰対策についてお答えします。
まず、市民向けの物価高騰対策についてですが、物価高騰による市民生活への影響が継続していることは承知しており、本市としても、子育て世帯に対する学校・保育施設の給食費高騰分の支援などに取り組んでいるところです。また、住民税非課税世帯を対象とした価格高騰重点支援給付金についても本年3月から順次支給しているところであり、引き続き、適切に対応して参ります。
最後に、一般会計繰り入れによる下水道使用料の値上げの抑制についてですが、 市民の皆様のご負担を可能な限り軽減するため、抑制策を反映し、改定率を抑制することが可能となったところであり、雨水処理や高度処理に要する経費など、一般会計が負担すべきものについては、既に繰り入れを行っていることや、下水道事業会計は独立採算が原則であることから、改定率の抑制を目的とした、一般会計からの繰入れは考えておりません。
以上でございます。
【大木副市長答弁】
子育て支援の充実についてお答えします。
高校生の通学定期代無償化及び高校生や大学生への学費の支援策についてですが、 神戸市の通学定期代無償化については、多くの高校生に市内の高校に通学してほしいという思いから、神戸市独自の制度として取り組まれたものであると承知しておりますが、本市に住む高校生にとって優先的に行う施策であるかは研究する必要があると考えております。また、高校生や大学生への学費の支援策については、国において、高等学校等の授業料の実質無償かに向けた取組みが進められているほか、多子世帯の学生を対象とした大学等の授業料等の無償化が始まるなど、「高等教育の修学支援新制度」の充実が図られてきていることから、その実施状況を把握するとともに、引き続き国の動向等にも注視して参ります。
以上でございます。
【橋本副市長答弁】
はじめに、農業対策についてお答えします。
まず、中古農機具の共有事業についてですが、市内農業者から、貸し出しや販売が可能な中古農業機械等の情報を収集し、その情報を新規就農者へ優先的に提供しており、実際に中古施設のマッチングを行っております。また、農家への所得対策についてですが、収入の減少を広く補填する「収入保険」制度の加入促進、野菜価格が下落した際に対策である「野菜価格安定対策事業」への支援に加え、米価格の下落に対しては、国の「経営所得安定対策」制度により、支援しております。現在、国においてコメ農家に対する所得補償について検討が進められているところであり、引き続き、国の動向を注視して参ります。
次に、バス事業者支援と高齢者外出支援についてお答えします。
まず、本市の要介護認定者が現状より10%低下した場合の年間の財政削減額についてですが、一般的には要介護認定率の低下が給付費の減少に影響を及ぼすと想定されますが、横浜市の事例は、敬老パスを保有していたかどうかのみ限定的な条件のもとでのものであり、本市において同様に算出することは困難であると考えております。また、ワーキンググループにおいて、高齢者の負担軽減、市民の利用促進策についても議論を進めることについてですが、バス事業者とワーキンググループでは、中長期的な視点で路線維持のあり方や路線再編を含めた効率的なバスネットワークの形成について検討を進めていくこととしており、この中で利用促進施策等についても議論することとしております。
次に、下水道管の老朽化対策についてお答えします。
予算の増額や、ドローンなど技術の活用と職員の増員についてですが、下水道は市民生活に欠かすことのできない生活インフラであることから予防保全型の維持管理をするための点検調査や老朽化対策が重要であると考えております。こうした取組みを確実に進めるため、必要な予算と人員確保に努めるほか、ドローンなど、新技術の活用については、点検手法の構築に向けて、実証実験を行っているところです。
最後に、幕張メッセでの展示会についてお答えします。
展示会の開催と本市の平和都市宣言及び展示会運営の是非を求めることについては、関連がありますので併せてお答えします。民間事業者が実施する展示会の開催そのものや、当該施設の指定管理者が県条例等に基づき施設利用の可否を判断したものについては、その内容を個別に評価し、施設利用の是非を申し上げることは適当でないと考えており、また、法律等に反しない限り、民間や団体の活動を最大限に配慮すべきものと認識しております。議員の入場が認められないことについては、どのような理由で入場が認められなかったのか分かりかねるため、見解を申し上げることはできません。改めて、県及び主催者側に確認して参ります。なお、市民共通の願いである世界の恒久平和の実現に向けては、市民の皆様に本市の平和都市宣言の理解を深めていただくとともに、戦争の悲惨さや平和の尊さを伝えていくことが重要だと考えており、引き続き平和啓発事業に注力して参ります。
以上でございます。
【教育長答弁】
不登校対策についてお答えします。
相談できる体制の重要性について及びスクールカウンセラーの配置時間については、関連がありますので、併せてお答えします。心身の成長期にある児童生徒には、学習や人間関係等、様々な悩みが生じることから、多様な相談窓口による相談しやすい体制を整備することは、不安や悩みの軽減、個々が抱える問題の深刻化を防ぐ効果があると認識しています。スクールカウンセラーの配置時間充実を含め、第3次千葉市学校教育推進計画に基づき、更なる相談体制の充実に努めて参ります。
以上でございます。
【3回目】
武器見本市平和行政についてです。そもそも市民局は今回の現場にすら視察もしていないお粗末な状況です。川崎市では「とどろきアリーナ」での展示会で銃などの武器展示を確認した際にカタログを職員が撤去するなど、その後は開催されておりません。今こそ平和都市宣言に則り、武器を広げていく展示会を開催しないよう県に働きかけるべきです。そして、経産大臣もいうよう特定グループを排除することが公共施設で行われたことは公益性に反しているわけです。見解を持てないこと自体が、差別を見過ごす、助長する人権的見地からも極めて問題のある答弁だと言わなければなりません。今回、答弁した副市長が責任もって、今後主催者への理由確認と併せて是正措置を行うよう強く求めるものであります。
現在、備蓄米放出が進むなか、深刻なコメ不足と米価高騰を招いた自民党農政の責任は重大です。第1は、減反・減産を農家に押し付けてきたこと、第2は、民主党政権時にできた所得補償制度を2018年には全廃し離農者を増やし供給が追い付かない状況です。農林水産予算は1980年度の約3.5兆円から、2025年度の2.2兆円にまで、約3分の2に削減されました。他方で世界を見ますと、農業関係予算を大幅に増やしており、特に予算に占める直接支払いの割合はEUで72%など高い一方で、日本は28%と最も低いのが実態であります。本市の農家を増やし安心してお米や野菜が消費できるよう所得・価格補償を行うために農業予算を大幅に増やすよう国に強く要望すること、そして、いすみ市のように農家への直接支払いを行うよう求めるものであります。
次に、高齢者の外出支援です。本市の要介護認定者が10%低下した場合については、70億円も削減されます。当然、全ての人が敬老パスを利用しないので、この額をそのまま当てはめることはできませんが、仮に新たなシルバーパス等で高齢者の外出が増え健康になることで1%要介護認定者が低下した場合は7億円の財政効果があるのです。横浜市は30万人という大規模な人数の調査を実施しており、トレンドは確かであり、高齢者の外出支援の拡充を真剣に検討すべきであります。市内バス事業者が運転免許返納者へのノーカー優待証を発行して運賃を半額にする支援を行っています。しかし、小湊バス以外は、軒並み2年間の限定となっています。運転免許を返納した後の2年間だけはなく継続的な支援をしてほしいという声が複数寄せられています。まずは少なくとも、小湊バスのように運賃半額措置を希望すれば延長できるよう、本市が財政措置を行うなど支援すべきであります。今後のワーキンググループで真剣に議題にのせて対応を図るよう重ねて強く要望しておきます。
最後に、子育て支援です。千葉市こどもプラン策定にかかるアンケート調査結果ですが、「千葉市は子育てしやすいまちだと思うか」との問いに、「そう思わない」と回答した方にどのような理由か聞いた結果であります。次いで多いのが「高校や大学などへの進学に係る費用の経済的支援が充実した環境がない」が51%との回答です。高校や大学への進学にかかるあまりに重すぎる経済的負担への支援については、ほぼ無策状態になっていることは市民の不満としてアンケート結果で明確に示されています。市長は、所信表明でも「対話と現場主義」を掲げておられる、アンケートでも明確に市民から示された最も経済的負担が重い時期の子育て世帯への新たな支援をぜひ施策化していただき、住んで良かったと思えて、安心して暮らせる千葉市とすべく早急な検討を強く求め、会派を代表しての代表質問を終わります。