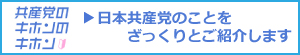臨海部における降下ばいじん対策の強化を! のじま友介議員一般質問〔2025年第2回定例会〕
野島友介議員の一般質問 2025.6.20

それでは通告に従いまして質問に入ります。
なお、通告のうち、「中央区の住みよいまちづくりについて」の3つ目、「みやこ図書館白旗分館のトイレについて」は、都合によりまして、質問を取り下げます。
臨海部における降下ばいじん対策について
日本共産党千葉市議団は毎年市民要求アンケートに取り組んでおりますが、その中で多くの人から、降下ばいじんによる被害の実態や対策を求める意見が出されました。「自動車や網戸が汚されて大変。ばいじん対策をもっと厳しくしてもらいたい」「歳をとって急に咳が出るようになって止まらない。医者から気管支炎といわれた。ばいじんとの関係があるのではないか」また「マンションを買ってきたが、ばいじんで部屋が真っ黒。子どもの足も汚れている。小児喘息にならないか心配」など、次から次にばいじんに対する怒りの声がでました。さらに、マンションを経営している方からは、「美浜の地域ではマンションに入居する際に説明は不要だが、蘇我地区のマンションに入居する人には、ばいじんについて説明するので困っている。」と切実な要望がよせられています。
1、市は降下ばいじんのために、窓が常時開けられない状況や、ばいじんに苦しめられている、このような声は把握しているのか。
2、先ほどの気管支炎のような症状がある市民の健康被害に関しての相談について保健所ではどのように対応していますか。お示しください。
3、蘇我地区のある事業所からも駐車場の車が真っ黒になったと苦情が出ておりました。身体だけでなく、その他の被害について伺います。
- 本市の現在の降下ばいじんの環境目標値は、どうか。
- 環境目標値は、何を参考にどのように決めているのか。
6、高炉が存在する他市における降下ばいじんに係る目標値の状況について、お聞かせください。
7、降下ばいじんの千葉市の測定地点の数と年間の測定回数。また環境目標値超過月は過去2年間でどれくらいか。
8、また、本市が降下ばいじん対策としてどのようなことを行っているのかお示しください。特に、これまで発生源とされる事業所に対し、どのような指導と低減策が実施され、そうした指導や低減策により住民が日常感じるような低減が図られていると考えているのでしょうか。あわせて答弁を求めます。
介護について
この間の一般質問では訪問介護報酬の削減で打撃を受けている事業所への支援や介護職員の賃金引上げなどを要望して参りました。今回は介護支援専門員、ケアマネージャーについて質問したいと思います。
高齢者やその家族の相談に乗り、適切な介護サービスを受けられるように調整する、このケアマネジャーさんですが、今、業務の過密化や人手不足、低い報酬など何重もの苦難に直面しています。なぜ、業務が過密化しているのか。あるケアマネさんは「利用者の困りごとを把握するのはヘルパーやケアマネ。介護保険の制約でヘルパーが対応できない場合も多く、自分たちでやることになる」と言っています。緊急対応の多くは介護保険制度で評価されず「シャドーワーク」と呼ばれる無報酬労働になっているとのことです。
1、市はこのケアマネージャーのシャドーワークについてどのように認識していますか?
過密化の原因はシャドーワークだけではありません。国による介護サービスの利用抑制がケアマネジャーを締め付けていることも関係しております。ある県で実際に行われていたことですが、ある利用者のケアプランが行政に「点検」されたことがあるといいます。生活援助回数が多すぎるというのです。
厚労省は2018年から生活援助に回数制限を設け、要介護1では月27回までとなっています。超える場合は、理由を行政に説明し認めてもらう必要があります。この事業所で管理者を務めるこの方は同僚のケアマネと行政への説明を念入りに準備し、結果的に元のプランを守ることができました。このケアマネさんは「認めてもらうまで大変だった。基準を超えたプランはつくれないと思うケアマネがいてもおかしくない」と語っています。
2、本市の生活援助の多数回利用のケースとしてどのようなものがありますか。事例をお示しください。
- また、本市でも同様の点検は行われていますか。
そして、もう一つさらに国の失策とも言えると思いますが、昨年度からケアマネジャーが担当できる件数を増やし、これが過密化を更に加速させていると感じています。担当件数の上限を39件から44件に変更し、条件を満たせばさらに緩和されます。さらに要支援の人を、これまでの2分の1換算から3分の1換算に変更しました。ケアマネさんからは「いまでも過密なのに、44件担当は無理。運営基準の項目をまっとうできず、報酬の減算も受けることになる」とおっしゃっています。
4、このような声が現場から出ている状況は把握していますか。また、ケアマネージャーさんからどのような意見が出ているかお聞かせください。
中央区の住みよいまちづくりについて
- 大森台駅バリアフリー化の進捗状況について
京成千原線の大森台駅のエレベーター設置工事がついに開始しました。完了予定は今年の12月との事です。前市議の福永洋議員がこの問題を市民と30年以上にわたり運動し、私も2年前の一般質問で取り上げ、それ以降も住民の方と京成電鉄本社に直接、署名を持っていくなど実現に向けて取り組んでまいりました。あとは道路から改札までのスロープが完成すれば完全なバリアフリー化といえます。すでに工事も始まっているように思いますが、スロープの供用開始時期についてお示しください。
- 神明歩道橋について
写真① こちらも住民要望アンケートから数年にわたり、要望が入っておりまして、写真は数年前に撮ったものですが、階段部分も 写真② 通路の部分もだいぶ腐食が進んでおり、錆も目立つものとなっておりました。使用している住民の方は「あまり通りたくないが仕方なく使用している。渡るのが怖い」や近隣にお住いの方からは「今にも崩れそうで下を歩きたくない」と心配の声が多数ありました。この間、当局へも要請をしてきた経緯があります。その時の回答では「国交省千葉国道事務所の管理になり、国に確認したところ、明確な時期は示せないが予算が確保できた段階で補修工事に着手する」とのことでした。こちらも工事が始まっているように思いますが、終了の時期などの状況について伺います。
- 今井3丁目にある大網里道踏切の歩道について 写真③
JR内房線にある大網里道踏切の歩行空間は木材で、簡易舗装のままです。高齢者の方が歩いていて杖が挟まって転んでケガをした、シルバーカーのタイヤが挟まり抜け出せなくなるかと思った。また、自転車の車輪がはまり怖い思いをした、などの報告がありました。 写真④ それだけでなく踏切内の歩行空間の幅員が狭く、交通事故の危険性が高い状況であると思います。踏切内の歩行空間の拡幅工事を行うことで、歩行者・自転車が安心して通行できる空間を確保すべきと思います。これまで当局へ申し入れを行いまして鉄道事業者へ早急な対応の要請を行っていただきました。その後の歩行空間整備の進捗状況をお聞かせください。
- 葭川公園近辺のムクドリ対策について 写真⑤
ムクドリは農作物の害虫を食べる益鳥とのことなのですが、近年は外敵が少ない都市部の街路樹にねぐらを移し、けたたましい鳴き声やフン害が問題になっております。葭川公園付近のベンチや 写真⑥ 道路はフンで汚れ、写真⑦ 住民の方からは「悪臭がひどい」「鳴き声がうるさい」等々の苦情が絶えません。また、葭川公園から羽衣公園までの周辺は人気のゲーム・アニメの聖地としても有名であり、全国、全世界から聖地巡礼に来られております。この聖地巡礼のためのガイドみたいなものもインターネット上で出ておりましたが、「この道はムクドリのフンがあり危険。」「迂回ルートはこちら」などの記載もありました。最近では、アニメ聖地巡礼をきっかけに移住をするなんてことも珍しくありません。街の美化は、住み心地の向上に直接つながるだけでなく更なる観光客を呼び込み、地域の経済を活性化させる、更には聖地移住というものを推進させるためにも必要ではないでしょうか。
これまで、様々な取り組みがなされてきたと思いますが、現在のムクドリの今後の対策について伺います。
1、臨海部における降下ばいじん対策について
【環境局長答弁】
まず、市は降下ばいじんに関する市民の声を把握しているのか、についてですが、直近5年間の平均では、年間10件程度のご意見、ご相談をいただいております。
次に、降下ばいじんによる身体以外の被害についてですが、建物の壁、洗濯物、自動車が黒くなるなどの声が寄せられております。
次に、現在の降下ばいじんの環境目標値についてですが、本市の環境目標値は月間1平方キロメートルあたり10トン以下となります。
次に、環境目標値の決定方法についてですが、環境目標値につきましては、環境審議会の専門委員会における検討結果を踏まえ、令和3年度に設定したものであり、生活環境保全上支障がないと考えられる水準として、苦情が寄せられていない内陸部の測定データを基に決定しております。
次に、高炉が存在する市の降下ばいじんの目標値についてですが、本市以外の自治体では、3市がそれぞれ目標値を設定しております。具体的には、1平方キロメートルあたり、大分市は、本市と同様に月額値が10トン以下、東海市では、全地点での年間平均値を平均した値が2.9トン以下、室蘭市では、水に溶けない物質のみを対象として、全地点での年間平均値を平均した値が、2.6トン以下となっております。
次に、測定値の数と年間の測定回数、また、直近2年間の環境目標値超過数についてですが、測定地点は市内12地点で、原則として月1回、年間で合計144回測定しており、直近2年間は280回測定し、環境目標値を超過したのは28回となっております。
最後に、降下ばいじん対策についてですが、臨海部を中心とした市内12地点における定期的な測定により、降下ばいじんの状況を把握し、市ホームページで測定結果を周知するとともに、発生を抑制するための行動を呼びかけております。また、主な発生源とされる事業者に対しては、立入検査により状況を把握するとともに、低減策の実施を促しております。なお、当該事業が飛散を防止するための散水等を行っているほか、昨年度には防風フェンスを設置し、対策を強化していることを確認しております。今後は、測定結果等に対する環境審議会委員の意見を参考にしながら、対策の効果等を検証して参ります。
【保健福祉局長答弁】
健康相談に関する保健所での対応についてですが、本市保健所では医療安全窓口を設けており、身体症状について相談があった場合には、状況をお聞きした上で、症状にあった診療科目の医療機関等を案内するなどの対応をしております。
2、介護について
【保健福祉局長答弁】
介護についてお答えします。
まず、ケアマネジャーのシャドウワークに対する市の認識についてですが、 利用者、家族から様々な相談や依頼を受け止め、利用者の生活を支えるために、本来業務の範囲を超えて緊急対応等をしているケースがあることは把握しております。本市としては、ケアマネジャーが個々の利用者に対するケアマネジメント業務に注力できるようにすることが必要であると考えており、ケアマネジャーを支える役割を担うあんしんケアセンターが、困難ケースへの対応を一緒に検討しているほか、関係機関との調整や、介護保険以外の生活支援サービスの情報提供などの支援を行っております。
次に、生活援助を多数回にわたって利用している事例についてですが、高齢者のみの世帯で、配偶者が食事を作ることができず、毎日、生活援助で調理を行っている者や、心身の状況から家事全般を行うことができない一人暮らしの高齢者に対して、それらの家事を提供するものなどがあります。
次に、本市における一定回数以上の生活援助を位置付けたケアプラン点検状況についてですが、生活援助の回数の目安は、利用者の自立支援・重度化防止の観点で要介護度別に設けられているものであり、点検も国の省令で行うこととされているため、本市でも点検を行っております。
最後に、制度改正後の現場の状況の把握とケアマネジャーからの意見についてですが、詳細な調査を行っているわけではありませんが、業務の中でケアマネジャーからは、「要支援の方をより多く担当できるよう人数のカウント方法が見直されたが、業務負担に変りはないので、担当件数を増やすことは難しい」、「対人対応が求められるケアマネジメントにおいては、IT化を進めたとしても大きな業務負担軽減にはつながらず、1人で44件対応できるほど効果は期待できない」などの意見を聞いており、基準が緩和されても件数を増やすことが、実際には困難な場合もあるものと把握しております。
3、中央区の住みよいまちづくりについて
【建設局長答弁】
はじめに、大森台駅バリアフリー化の進捗状況についてお答えします。
スロープの供用開始時期についてですが、現在、年内完成を目指して工事を進めておりますが、供用開始時機については、駅構内のエレベーター設置工事の進捗状況を見ながら、調整することとしております。
次に、神明歩道橋についてお答えします。
補修工事の進捗状況についてですが、施設管理者である国土交通省千葉国道事務所から、「傷んだ箇所の補修と塗装などを実施しており、概ね50パーセントの進捗で、来月末の完了予定」と伺っております。
最後に、今井3丁目にある大網里道踏切についてお答えします。
踏切を管理しているJR東日本及びJR貨物に対し、歩行面を広げ、平坦性を確保することについて申し入れており、現在、JRにおいて改良に向けた検討が行われているとこです。
【都市局長答弁】
葭川公園付近のムクドリ対策についてお答えします。
今後の対策についてですが、ムクドリは野生の生き物であるとともに、個体数が非常に多いため完全な対策を講ずることは困難でありますが、近年の対策としては、多くのムクドリが街なかに集まり始める初夏の時期などに、鳥の嫌がる警戒音や光による追い払いを実施しております。また、公園広場や歩道に落ちたフンの定期的な清掃により環境維持にも努めており、今後も被害の低減に向け、可能な対策を実施して参ります。
<2回目>
事業所において、これまで飛散を防止するための散水や昨年度には防風フェンスを設置など確かに継続的な対策が行われております。しかし、日常生活において、真っ黒、ざらざらが著しく減ったという現状ではありません。写真⑧ これはポートタワーより事業所の野積みを撮影したものです。これが風で舞い上がるわけです。
千葉中央臨海部大気環境を考える会・蘇我の会へ寄せられた声を少し紹介します。
写真⑨ 他県から出洲港が見えるベランダがとても気に入り、その景観を大きな決め手として賃貸物件を契約し、千葉市へ引っ越してきた方、入居前の内見時に外壁や床面に黒い汚れがあったため、不動産会社に確認したところ、「鉄の錆びです」との説明を受けました。しかし、入居初日、クリーニング済みのはずの室内を少し歩き回っただけでスリッパの裏が真っ黒になったと。写真⑩ また、換気扇も真っ黒です。
中央区千葉寺町にお住いのお方は自宅バルコニーを昨年末に掃除しましたが、 写真⑪ わずか一月後の1月に強い西風によりバルコニーは再び降下ばいじんで汚れてしまったと。表現は少し大げさですが砂漠のような模様がついて溜まっています。写真⑫ 箒で掃きとった後の状態です。塵取りの中にばいじんがあります。当然バルコニー以外の車などにも被害は出ているということです。
そこで伺います
1、2019年12月に千葉市環境審議会から市長へ提言が行われています。その一つに「事業者・地域住民・千葉市の三者間における情報共有を図ること」がありますが、この5年間に「情報共有」はどのような形で進んでいるのか。また、地域住民とはどのような方が選ばれているのか伺います。
2、更にこの提言のなかには「目標値の見直し後も、苦情の状況等を確認し」とありました。答弁では市に寄せられている意見や相談は年間10件程度とのことです。しかし、蘇我の会では毎年アンケートを行い、100件以上のご意見が毎回毎回あるそうです。一つの苦情からは同じマンションや地域に住む、その他大勢の方の苦難があると思います。まずはこの苦しんでいる方がどれだけいるのかを正確に把握するためにも、本市で降下ばいじんに関する実態調査アンケートを行うべきではないでしょうか。
3、答弁で測定地点は12地点と示していただきました。写真⑬ しかし、この測定地点が沿岸部に偏っていないかと感じます。降下ばいじんは飛来して、地面に落ちてとどまり、2度でも3度でも風が吹くたびに舞い上がります。特に屋根にたまっているばいじんならば、風で舞い上がることは、ごくごく自然なことです。住民が日常受けるばいじんは、今降下しているばいじん、そして過去に落ちたばいじんが再度舞い上がった複合ばいじんであると言えると思います。地域の方々は、その中で生活をしていらっしゃいます。被害実態を明確にするためにも、測定地点を増やして、市民生活の場に入り込んでいるばいじんを測定する必要があるのではないでしょうか。
4、このような中で、特に、児童生徒の口に水が直接入る学校のプールは心配です。以前、環境審議会における降下ばいじんの調査で、ばいじん量の多かった寒川小学校では、プールにてばいじんを除去するための対応について、どのようなことをしているのか。また、清掃に関わる費用は年間でどれぐらいかかっているのか。
5、また、公共施設の清掃に係る費用負担については、費用全額を税で賄うのではなく、発生源の事業所に半額程度の費用負担を求めることも必要ではないか。
6、答弁で現在、降下ばいじんの環境目標値については、月1平方キロ当たり10トンと設定されているということです。この10トンというのはどれぐらいなのか。たとえば、100平米(30坪)で1か月間放置した後に掃除をしたら1kgのざらざらしたゴミが集まるといった数値です。この量を許すのかと。しかもこの数値は、先ほど答弁でもありましたが、2年間で280回測定して28回も超過していると。
ただでさえこの環境目標値では生活被害の実態とかけ離れていると思いますが、これからさらに減らしていくという数値とは思えません。大分市では、日本製鉄九州製鉄所と大分県と大分市の3者で達成することが望ましい値として、今年10月から管理目標値を引き下げるとしています。本市でも生活環境改善のために数値の見直しが必要であると考えます。環境目標値の引下げについて、2023年の環境目標値の強化以降、どのような検討がされているのかをお示しください。
介護について
ケアマネージャーのシャドーワークについては厚生労働省の検討会が昨年12月、シャドーワークを分類し「保険外サービスとして対応しうる」「他機関につなぐべき」「対応困難」としました。シャドーワークが存在することを認め、その中身を明らかにしようとしたのは良い変化だと思います。本市でも把握しているという答弁がありました。利用者や家族が頼るのはまず身近なケアマネジャーです。家庭に入り込んでいるケアマネだからこそ対応できることも多いです。実際に入退院の準備や同行、役所手続き、ヘルパーに依頼できない買い物、更には介護サービスが入る環境を整えるため、退院前に鍵を預かってゴミであふれた家を掃除するなんてこともしています。このような緊急の問題にはまずケアマネが対応している現状があります。
1、答弁で、本市ではケアマネージャーを支える役割をあんしんケアセンターが行い、困難ケースへの対応を一緒に検討しているとのことでした。しかし、そのあんしんケアセンターも人員不足であり、業務を割り振る先を見つけるのが困難になっているのではないでしょうか。結局、ケアマネがやることになるのではないか。あんしんケアセンターの更なる人員の拡充が必要と考えるがどうか。
生活援助の回数制限についてですが、多数回利用の必要なケースとして答弁であったものの他に独居で認知症のため服薬の管理が必要、せん妄等のため他のサービス利用は難しい、などがあります。答弁で自立支援や重度化防止の観点で設けられているとありましたが、機械的な回数制限でこの介護を取り上げてしまったら、在宅での生活が立ち行かなくなり、重度化を更に招きかねません。
2、点検の名で、重箱の隅をつつくような質問が繰り返される。これでは行政の確認のためのケアプランになりかねなません。また、ケアマネージャーさんの心身の負担も大変なものとなります。過度な点検は改めるべきと思いますがいかがでしょうか。
答弁でケアマネージャーさんからこれ以上は担当件数は増やせないと実情を伺いました。ある事業所ではケアマネジャー5人はそれぞれ要介護32~35人と、要支援8人程度を担当していると。緩和前の上限も下回りますが、スケジュール帳は休日以外すべて埋まっているといいます。実際、先ほどのケアマネージャーさんのお話もありましたが40件以上を担当することは無理なのではないでしょうか。利用者や家族と向き合えず、件数制限のそもそもの目的であった「質の確保」がおろそかになってしまいます。
3、このような担当件数の増加はケアマネの負担軽減にも逆行しており、元に戻すべきと考えますが市の見解を伺います。
<2回目>
臨海部における降下ばいじん対策について
【環境局長答弁】
まず、情報共有の方法についてですが、本市は、ホームページ等で毎月の降下ばいじんの測定結果や成分量データを周知しているとともに、適宜、事業者と対策状況等の情報共有を図っております。また、事業者が定期的に周辺住民と情報共有を行っていることを把握しております。なお、提言における地域住民は、主に臨海部の地域にお住まいの方を想定しております。
次に、アンケートについてですが、アンケートの予定はありませんが、市民の皆様から相談があった場合は、現地を訪問するなど、直接状況を確認して参ります。
次に、測定地点を増やすことについてですが、降下ばいじんの測定地点は環境審議会の提言を受け設定したものであり、測定データの継続性の観点から、測定地点の見直しは予定しておりません。
次に、公共施設の清掃に係る費用負担についてですが、降下ばいじんの発生源は様々であり、因果関係の程度を立証することが難しいことから、費用負担を求めることは困難と考えております。
最後に、環境目標値の引き下げについてですが、現在の環境目標値は令和4年度から適用したものであり、降下ばいじんについては、気象状況等の影響もあることから、測定結果を蓄積し評価する必要があると考えております。
【教育次長答弁】
プールにおけるばいじんを除去するための対応、また、清掃に関わる費用についてですが、プール用自動清掃機を使用して、水泳学習前にばいじん等の浮遊物を取り除いております。さらに、水の入れ替えやオーバーフローなどを行っております。また、清掃に関わる費用については、把握しておりません。
介護について
【保健福祉局長答弁】
介護についてお答えします。
まず、あんしんケアセンターの人員の拡充についてですが、あんしんケアセンターについては、国の基準を踏まえ、高齢者人口などに応じて包括三職種職員を配置しているところであります。支援が必要となる後期高齢者や要支援認定者も増加する中で、センターの負担が大きくなっていることは認識しており、今後も適正な人員配置に努めて参ります。
次に、ケアプラン点検についてですが、本市では、利用者の身体や生活の状況に対して、提供されるサービスが適当であるかどうかという観点でケアプランを確認していますが、あらかじめ提出されたケアプランでは確認できない部分を質問するなど、ケアマネジャーの過度な負担とならないよう配慮しております。
最後に、ケアマネジャーの担当件数を元に戻すことについてですが、昨年度の介護報酬改定によるケアマネジャー1人当たりの取扱件数の見直しは、引き上げられた件数まで担当することを強いるものではなく、減額されずに報酬を受け取ることができる範囲を広げたものであり。件数の上限を元に戻すべきとは考えておりません。
<3回目>
葭川公園のムクドリですが、我孫子市が天敵のタカを使って効果を上げています。鷹匠(たかじょう)に依頼してタカを放ち、約1万3千羽いたムクドリが約2カ月間で激減したなんて話を聞きました。本市でも効果を確認したうえでタカの活用を検討していただきたいと思います。
降下ばいじんについてですが実態調査のアンケートも行わないという答弁は残念です。他会派の別の質問への答弁で、「今後の蘇我駅周辺のまち作りを考える上での参考とするため人々の街の評価やニーズを把握するためのアンケート調査を市政だより5月号の中央区版へ掲載して実施した」と伺いました。同様の事が降下ばいじん対策として行なえないものなのでしょうか。寒川町に小さいお子さんとお住まいの方で、家屋の汚れ、換気ができないなど、様々な問題がありますが、1番の悩みは子供の喘息だと。このままこの地域に住んでいて良いのかと思うそうです。こういう声を拾い上げなければいけないと思います。
我が会派はこれからも住民の皆さんと要請や要望も繰り返し行いながら、ばいじん対策の強化を引き続き求めていきます。
今の全国的なケアマネジャー不足は、低賃金を押しつけてきた結果でもあります。今や介護職員よりさらに給与が低くなっており、募集をしても集まらないのは当然です。国は介護職員の賃金を増やす処遇改善策からケアマネジャーを除外してきました。専門性に見合う報酬への引き上げを国へ強く要望するよう意見しまして質問を終わります。