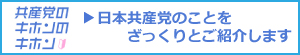プラスチック分別収集前倒し実施を! もりた真弓議員一般質問〔2025年第2回定例会〕
もりた真弓議員の一般質問および答弁 2025.6.23

1.ごみ分別と環境問題について
【もりた真弓議員】
(1)プラスチックごみ分別の促進について
千葉市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」)は、4月21日付で千葉市長あてに「家庭系プラスチック資源の分別・再資源化施策について」の答申を行いました。審議会は2024年10月に千葉市から諮問を受け、その後、5回の審議会が開催されそこでの議論を経て、家庭系プラスチック資源の回収についての答申がまとめられ提出されたものです。気候変動、地球温暖化の一つの要因であるプラスチックの分別回収について、千葉市もようやくスタートラインに立ちました。これまで可燃ごみとして燃やされてきたプラスチックを分別し、千葉市のCO2削減に向けて、市民とともに協働の取組みを進める必要があります。そこでうかがいます。
はじめに、千葉市に提出された「家庭系プラスチック資源の分別・再資源化施策について」の答申に対する千葉市の受け止め、及び見解についてうかがいます。
【環境局長答弁】
審議会の答申では、分別排出から収集運搬、再商品化までの実施体制を整えて頂きたいなど、様々なご意見をいただいたことから審議会の答申を踏まえ、市民や市議会などの関係者の皆様のご理解を得ながら、早期に事業実施できるよう取り組んでまいります。
【もりた真弓議員】
政令市20市中、プラスチック資源分別収集について、現在も未実施の自治体は3市であり、福岡市と静岡市と千葉市です。
プラスチックごみ分別の後発自治体である千葉市におけるプラスチック分別の課題と具体的な取り組みについてお示しください。
【環境局長答弁】
効率的な収集運搬及び再商品化ルートを構築するとともに、市民の皆様への周知啓発など取り組むことが必要であり、取り組む施策については、先行自治体の事例を参考にしながら、今後作成する「プラスチック資源の分別収集・再資源化事業実施計画」に位置付け、対応して参ります。
【もりた真弓議員】
家庭系プラスチックごみ分別収集の開始時期については、福岡市は2026年度、静岡市は2028年度、千葉市は2029年度とされています。千葉市が20政令市の中で一番遅いスタートとなる計画です。
千葉市の実施時期が2029年度になる理由について、おたずねします。
【環境局長答弁】
収集運搬車両の確保など収集運搬体制の十分な準備期間が必要なことや、再商品化ルート及び事業者の選定のほか、市民の皆様への丁寧な周知啓発等を行うことから、実施までには一定の期間を要すると考えております。
【もりた真弓議員】
審議会の席でも環境局は「可能な限り前倒しして取り組む」との意向を示されていました。
現時点で、どの程度早められると見込んでいるのか。また、どんな条件がクリアできれば前倒しできるのか、お答えください。
【環境局長答弁】
「プラスチック資源の分別収集・再資源化事業実施計画」の作成を進め、必要な準備期間を整理した上で、準備期間を定めて参ります。
【もりた真弓議員】
千葉市が取り組むプラスチック資源回収は、一つには現在事業者が行っている「店頭回収」と、もう一つは今後新たに始める週1回のごみステーションでの回収の2本立てです。
はじめに、事業者が行っている店頭回収についてうかがいます。
- 食品トレーや卵のパックなど、より質の高いリサイクルのため商業施設ではプラスチック資源の回収を継続して行いますが、現在の店頭回収の状況についてお示しください。
また、回収を行なっている事業者は市内にどのくらいあるのか、うかがいます。
【環境局長答弁】
令和5年度末時点で年間約130トンの食品トレイを29事業者、80店舗で回収しております。
【もりた真弓議員】
身近に立ち寄れる場所で、プラスチック資源の回収を行えることが肝だと考えます。分別した資源プラスチックを持って買い物したお店に、または買い物に行くお店に持っていくことで、毎日の生活の中で資源循環が自然と行われることになります。
事業者が新たにプラスチック回収を始めるといった場合の負担や障害は何か、うかがいます。
【環境局長答弁】
回収ボックスの設置や対象外の品目の除去・整理のほか、プラスチックを資源物として引き取る事業者の確保などが必要となります。
【もりた真弓議員】
わざわざ遠くの店舗に出向いてプラスチックの資源回収物を持っていくのはかなり手間のかかる仕事です。気軽に、散歩や買い物などのついでに、出すことができる場所を増やすことは効果的だと考えます。
千葉市は、これまで協力してきた大手スーパーやコンビニなどに加え、市内の企業・事業者、小売店、個人商店等に対して、店頭でのプラスチック分別の回収の協力を積極的に働きかけることを求めるがどうか、おたずねします。
【環境局長答弁】
ごみ減量のための行動指針である「ちばルール」の取り組みに協力いただけるよう、「ちばルール」行動協定の未締結事業者に積極的に働きかけて参ります。
【もりた真弓議員】
分別したプラスチックがきちんとリサイクルされるのか市民に疑問を持たれては、分別回収の協力を得られません。
現在検討されているプラスチック資源分別収集では、回収したプラスチックは、何%リサイクルされるのか、うかがいます。
【環境局長答弁】
一般社団法人プラスチック循環利用協会によると、令和5年度に同協会が引き取ったプラスチックは65.6万トンであるのに対し、再商品化量は43.4万トンとなっており、約66%はリサイクルされていることになります。
【もりた真弓議員】
以前、一般質問で紹介した神戸市の「資源回収ステーション」は場所さえ確保できればすぐにでも取り組める事業です。
スクリーンをご覧ください。以前に視察をさせていただき、議会でも取り上げた神戸市で取り組まれている取り組みのチラシです。
神戸市では、2021年11月から「質の高いリサイクルを目指してプラスチック資源等を回収して、「回り続けるリサイクル」を実践する拠点として、資源回収ステーション(エコノバ)を増やしています。私が視察した2024年の11月時点で神戸市内に35か所設置されており、今後200か所以上に設置することを目標にしているとのことでした。今現在、50箇所まで増設されたそうです。
千葉市では、他都市と比べて可燃ごみ袋へと入れてしまえば、なんでも燃やしてしまえる仕組みで長年過ぎてきてしまいましたから、プラスチック資源分別収集へと移行することに対して、「高齢になって複雑な分別が難しい」とか「外国籍の住民に協力してもらえるのか」など不安の声も聞かれることも無理はありません。しかし、以前「ダストボックス」でビンもカンもペットボトルもすべて一つの袋で収集してまるごとごみ扱いしていた時代から、資源ごみなどの5分別体制へと変化させてきたことを考えれば、やれないことではないし、また進めなければならない課題であることは言うまでもありません。要は、行政が予算も人も手厚くして、町内会等が管理しているごみステーションでの回収に際して混乱が生じることが無いようにする手立てが必要と考えます。
店頭回収に取り組む事業者を広げつつ、神戸市での「資源回収ステーション」と同様の取組みを始めることを求めるがどうか。市民が無理なく行ける場所、例えば、学校・公共施設、商店街の空き店舗等を活用して、各居住地域にごみ分別の理解促進のための拠点を設けてはどうか、お答えください。
【環境局長答弁】
本市では、公共施設などで使用済み小型電化、単一素材製品プラスチックや廃食油などの拠点回収を実施しております。拠点回収の増設については、費用対効果や市民の利便性、施設の安全管理などから、総合的に検討して参ります。
【もりた真弓議員】
次に、新たに始める「ごみステーションでの分別収集」についてうかがいます。日常生活において多様化したプラスチックを分別して、週1回のステーション回収に協力してもらうためには、広く市民のみなさんに分別方法を周知徹底することが必要と考えます。
- 「プラスチックは燃やさず資源に」と分別の必要性をわかりやすく伝え、市民への理解をどのように進めていくのかうかがいます。
【環境局長答弁】
プラスチック資源が、再商品化によりどのような製品に生まれ変わり、CO2削減に貢献しているかを実感できるように、イラスト等を活用した資料を用いてわかりやすく伝えることにより、市民の理解を促進して参ります。
【もりた真弓議員】
神戸市でのプラスチックに特化したこのような取り組みは日本初とのことですが、ユニークで誰もが関わる「ごみ出し」をきっかけに新たな交流が生まれるコミュニティ拠点として、ぜひ千葉市でも参考にしていただきたいと思います。
次にプラスチックごみ分別のうち、プラスチック回収用の新たなごみ袋についてうかがいます。審議会でも袋そのものに「回収する品目」を表記するなどの提案もあり、今後、具体的な検討がされるものと承知しています。分別の理解を深め、わかりやすい表示で市民の協力を促進できるように回収袋のデザインは工夫するべきと考えます。さらにプラスチック回収袋については価格を抑え市民負担を軽減することで、より積極的に分別を進める効果が期待できると考えます。
新たに作成するプラスチックごみ回収袋の金額はいくらに設定するのか。プラスチック資源回収に協力する市民の負担を最小限にし、分別の協力を促進するべきと考えるがどうか、お答えください。
【環境局長答弁】
今後作成する「プラスチック資源の分別収集・再資源化事業実施計画」において検討して参ります。
【もりた真弓議員】
次に、ごみ分別と環境問題について質問します。ここ最近の物価高騰を受けて、全てのものが値上がりし、消費は冷え込んでいます。使えるものは最後まで使い、ものを大事にする意識は以前よりずっと浸透してきているとも言えます。これまでの大量生産・大量消費・大量廃棄の経済活動から、限られた資源を有効に使って自然環境に負荷をかけない生活スタイルへと変わっています。千葉市はこれまでも、リユース、リデュース、リサイクルと3Rの取組みをしてきました。今後も継続した取り組みが行われるものと思います。そこでうかがいます。
千葉市が取組んできた3Rの事業について、最も効果が高いと評価する事業は何か、お示しください。
【環境局長答弁】
焼却ごみ量の削減に効果的であるのは、古紙の資源回収や、剪定枝等のごみステーションにおける収集などが挙げられます。コストがかからずごみ減量に効果的であるのは、ジモティースポット千葉や、千葉市リユースショップガイド掲載の民間事業者が行なう取組が挙げられます。
【もりた真弓議員】
逆に進んでいない分野は何で、支障になっている要因や課題は何かおたずねします。
【環境局長答弁】
生ごみ分別収集については、過去に一部地域でモデル実施しましたが、全市で実施するには多額の収集コストが見込まれることや、十分な再資源処理能力を有する施設の確保が難しいことなどにより、既に事業を修了しております。
【もりた真弓議員】
次にリサイクル基金についてうかがいます。
リサイクル基金のそもそもの設置の目的とこれまでどのように活用されてきたのか、実績及び基金の現状についてお示しください。
【環境局長答弁】
本市では、市民及び事業者等のリサイクル活動などを支援するため、平成10年にリサイクル等推進基金を設置し、家庭ごみ手数料徴収運営事業やごみ減量推進事業に充当しております。令和5年度末の基金残高は約37億5,000万円となっております。
【もりた真弓議員】
スクリーンをご覧ください。千葉市リサイクル基金の残高の推移のグラフです。2021年度32億8200万円、2022年度35億1300万円、2023年度37億5500万円と年々2億3000万円~4000万円を積み増している状況です。
リサイクル基金の活用計画についておたずねします。
【環境局長答弁】
今後も、市民及び事業者等のリサイクル活動などを支援するため、効果的に基金を活用して参ります。
【もりた真弓議員】
リサイクル基金は千葉市の「条例」で、その使い道を①リサイクル等に係る市民、事業者等への啓発に関する事業②リサイクル等に係る市民、事業者等が行う活動の支援に関する事業③その他リサイクル等の推進に関し必要な事業とされています。今後作成する「実施計画」にも位置づけて、プラスチック資源収集や市民、事業者への啓発・活動へと活用するよう求めて、次の質問に移ります。
2.交通問題について
【もりた真弓議員】
(1)バス事業再編・統合について
4月末に、こてはし台地域の住民の方と京成バスの本社を訪れました。長年要望してきた横戸町23号線の拡幅工事が終わったことから、「道路拡幅完了の際には検討する」としていた勝田台駅からこてはし台・横戸台方面のバスを循環ルートにする件を申し入れるためです。そこで、新たにわかったことが京成グループのバス事業の再編と統合についてでした。
スクリーンをご覧ください。京成グループは、今年2025年4月1日からこれまでの京成グループのバス会社15社を東京都内1社、千葉県内は西部、中央部、東部の3社に再編し、それぞれ名前も変えて、「京成バス 東京」「京成バス ウエスト」「京成バス セントラル」「京成バス イースト」としてすでに運行しており、京成バスと京成自動車整備は完全子会社したとのことです。また一年後の2026年4月には京成バスのさらなる再編・統合を行うとしています。京成グループの再編・統合は会社にとっても大きな事ですが、住民にとっても大変に関心の高い問題です。私たちが届けた「循環バスのルート」についての要望は、京成グループの再編・統合の準備期間であり、対応していられないと実質先送りとなりました。
千葉市はこれまで、一般路線バス事業者10社と市内公共交通ネットワーク構築のため、協議を重ねてきています。そこでうかがいます。
千葉市として京成グループのバス事業再編・統合を把握していたのか。把握していたとすればいつの時点か、お答えください。
【都市局長答弁】
昨年9月に、京成電鉄株式会社より、バス事業の中間持株会社の設立ならびにバス事業の再編に関して、書面にて情報提供を受けております。
【もりた真弓議員】
京成グループで、なぜ今回のバス事業再編・統合するに至ったのかについて、私は、この間の路線バスの利用低迷や物価高騰で経営が厳しいため、バス事業の再編・統合を進めているものではないかと理解しています。会社の今後の経営等考慮して、不採算の路線やルートを今後も維持していくとするのか。今回の京成グループのバス事業の再編・統合により今後、サービス提供の影響や利用者が不利益を被る可能性があるのではないのかと考えます。そこで、うかがいます。
バスの減便により、現在でも日常生活に支障をきたす事態となり、通院や買い物などの生活サイクルが回らず、これまでの生活が維持できなくなる不安が地域から寄せられています。こうしたバスの減便等の事態に千葉市としてどんな対策を行なっているか、お示しください。
【都市局長答弁】
減便の主な理由は、運転手不足であることから、これまでも、大型二種免許取得に要した費用を助成してきており、昨年度は求人広告費などの人材確保の取組みにも支援しております。さらに、昨年度は生活交通バス路線維持確保事業により、今後、廃止や減便となった場合に、市民生活へ大きな影響を及ぼすと考えられる系統を選定し、運行便数を維持することを前提に、運行経費の一部を支援しております。
【もりた真弓議員】
千葉市は、R6年度とR7年度の生活交通バス路線維持支援に7,500万円ずつの予算をつけています。赤字路線への支援として「予算の範囲内で効果的に図れるように予算の確保に努める」とされていますが、何系統に使っているのか、また、予算は足りているのか、おたずねします。
【都市局長答弁】
昨年度23系統を選定し支援をしており、今年度も必要な予算を確保しております。
【もりた真弓議員】
一般路線バス事業者と市内公共交通ネットワーク構築のため、協議を重ねてきていると聞いていますが、その取り組みの概要についてお示しください。
【都市局長答弁】
バス事業を取り巻く厳しい状況を踏まえ、市民生活の基盤である市内の路線バスの持続性を高めていく必要があることから、先月、市内の7社のバス事業者と、今後の対応を協議する場としてワーキンググループを設立しました。ワーキンググループでは、運行便数や利用者数などの客観的なバス情報や、事業者などの現状を踏まえ、路線バスを維持するための課題などを整理し、中長期的な視点で、路線維持のあり方や路線再編を含めた効率的なバスネットワークの形成などについて検討を進めていく考えです。
【もりた真弓議員】
(2)交通不便地域への交通手段とその支援について
日本共産党千葉市議団は今年も恒例の「市民要望アンケート」を実施しており、日常生活で困っている切実な内容が書き込まれています。
「区役所に行くのにバスの本数が少なく、タクシーで行くしかなく経済的に大変です。」「バスの減便、値上げを何とかして欲しい。」「み春野団地と勝田台駅へのバス便が少ない。」「運転免許を返納した後の交通手段に不安がある」「千葉市中心部への移動の公共交通機関の設立、特に高齢者の配慮を願いたい。」「千葉市のはじにある街でとても不便である。バスの増便を望む。」などです。
そもそも、バスの運行がない地域や、バスはあっても恐ろしく本数が減らされた地域など、車がなければ日常生活を営めない地域で、高齢のための免許返納となる事態はますます増えています。
千葉市では、交通不便地域での公共交通としてデマンド型タクシーの運行や、グリーンスローモビリティなどの支え合い交通に取組んでいますが、一部地域に限られており、モデル事業や実証調査の域を超えず、支え手の見込めない地域は置き去りの状況となっています。そこでうかがいます。
千葉市が取組んできた支え合い交通の評価についてお示しください。
【都市局長答弁】
公共交通不便地域に導入いているデマンド型交通は、令和5年3月に高津戸町地区で社会実験を開始し、昨年度からは隣接する大椎台・大木戸台地区などを含む3地区で運行しております。毎月の地元協議会での検討により、運行時間や停留所の位置等の運行計画を改善してきたほか、地区内における理解が進んだことで住民の日常生活を支える移動手段として定着してきているものと考えております。また、スポット的に公共交通へのアクセスが困難な場所等に導入しているグリーンスローモビリティについては、桜木地区など3つの地区で住民ボランティアによって運行されており、地域の身近な移動手段として活用され、地域の回遊性向上にもつながると考えております。
【もりた真弓議員】
先日、こてはし台地域で行われた地域の学習会へと参加しましたが、高齢化する中で買い物や医者に行く手段がないとの声が相次ぎました。
こてはし台地域ではグリーンスローモビリティの実証調査を行いましたが、その後、地域での展開はありません。実証調査をしたが、実際の運行までに至らなかった結果をどう見るのか、お答えください。
【都市局長答弁】
短期実証調査では、住民ボランティアによる継続的な運行スタッフの確保が出来なかったことなどから、長中期の実証調査までに至らなかったものと考えております。
【もりた真弓議員】
こてはし台のように、グリーンスローモビリティの支え手・担い手のいない地域で、高齢者が買い物や医者に行くための移動手段をどう確保するのか。例えばNPO法人の運営する事業所との連携による移動手段の確保などを行なっているのか、おたずねします。
【都市局長答弁】
本市のグリーンスローモビリティは、先行地区において、効率的な運行や地区内の商業施設等からも協力いただくなどの、ノウハウが蓄積されてきており、地域の取組を支援する際は、これらも活用して参りたいと考えております。また、高齢による身体の衰えなどにより、公共交通を自力で利用することが困難な方の移動手段確保のために、NPO法人や社会福祉法人等が実施する福祉有償運送事業の運営を支援しております。
【もりた真弓議員】
以前、花見川区のみ春野地区への山王病院の送迎バスが廃止されたことについて質問したところ、「み春野地区にはバスも通っており、交通不便地域には当たらない」との見解で大変驚きました。住民の認識とは大きく隔たりがあり、実態を捉えていないと指摘せざるを得ません。
交通不便地域の定義についてあらためてお示しください。
【都市局長答弁】
千葉市地域公共交通計画では、公共交通の利便性について、鉄軌道駅やバス停までの距離や路線の運行頻度などにより、市域を4つの区内に分類し、この中で交通サービスレベルの極めて低いエリアを、公共交通不便地域と定義しております。
【もりた真弓議員】
1日数本の路線バスでは住民の移動ニーズに応えていません。実態に合わせて定義を見直すべきではないのか、うかがいます。
【都市局長答弁】
公共交通不便地域は、市域の中でも公共交通サービスが極めて低いエリアとして、移動手段を確保するための支え合い交通の導入を優先して検討することとしており、現時点ではその定義を見直すことは考えておりません。
【もりた真弓議員】
高齢化と地域間格差が広がるバスの減便に対して、これ以上、不便になったら今の場所で生活を続けていくことができない「住み続けられない」という市民の声に向き合うべきだと申し上げて、次の質問に移ります。
3.安心して住み続けるための支援について
【もりた真弓議員】
(1)地域の買い物事情について
さつきが丘は約4,000世帯で、UR団地の周りに戸建て住宅が広がる地域です。2月24日に関東近県のトップマートが一斉に閉店し、さつきが丘でも当初「毎日の買い物はどうしたらいいのか」との困惑の声が多数寄せられました。トップマート店の閉店発表が突然だったことで、団地はじめ周辺の住民にも不安が広がりましたが、間もなく従業員募集のチラシが配られ、およそ2か月後の4月30日に「スーパーのアオキ」が出店しました。開店初日から買い物客は長蛇の列となり、駐車場に入れない車が道路にはみ出し、食品を扱う店舗がいかに待たれていたかがはっきりと示されました。
そこで、身近で生鮮食品などを買える店舗が果たしている役割についてうかがいます。
【経済農政局長答弁】
日々の買い物の場を提供することで、地域住民の生活を支えているものと認識しております。
【もりた真弓議員】
さつきが丘団地には名店街があり、40数年前には買い物をする住民で商店街に人があふれ、肩と肩とが触れ合うほどだったと聞いています。残念ながら現在さつきが丘名店街に残っているのは、飲食店兼飲み屋さん1軒、お団子屋さん、おもちゃとお菓子のお店、他には理美容店、自転車屋さん、靴屋さん、接骨院などです。今回のように食品を扱う店舗が閉店となった場合、バスなどの交通機関を使って遠くまで買い物にいかなければなりません。
そもそも、団地の商店街が現在のようにシャッター通りと言われるような状況になったのはなぜか、おたずねします。
【経済農政局長答弁】
地域の人口減少や高齢化の進行に加え、インターネットショッピングの広まりなど、消費行動の大きな変化により、当該地域における買物需要が減少したこと、また、さつきが丘団地の商店街においては、自宅兼店舗が多く、新たに開店する余地がないことが要因と考えられます。
【もりた真弓議員】
千葉市は企業立地には年間20億円の予算をつけ熱心に誘致に取り組んでいますが、市民の食生活を支えている地元商店や業者に対しては撤退するもしないも自己責任です。
お店が撤退すれば住民が困ることを知っていながら放置する方針なのか、お答えください。
【経済農政局長答弁】
商店街や個店に対しては、本市職員や千葉市産業振興財団のコーディネーターが訪問等を実施し、課題や支援ニーズの把握に努めるとともに、商店街や個店が活用できる中小企業支援メニューの紹介や、商店街アドバイザー派遣事業の利用、さらには、商業者向けの販売力向上セミナーへの参加を促すなど、経営安定や経営力強化に係る支援を実施しています。店舗の撤退等により、地域から、買い物支援に関するご相談やご要望をいただいた場合には、関係部局の連携のもと、対策を講じております。具体的には、スーパーや移動販売事業者などへ情報提供するとともに、あんしんケアセンターなどの相談機関において、買い物が困難となっている方の実情に応じて、利用可能な福祉サービスや地域ボランティアによる支え合い活動、さらには、事業者が行なっている宅配などの買い物サービスの案内などを行なっているところです。
【もりた真弓議員】
千葉市の様々な支援があるとのことですが、残念ながら今のところ地域や商店街の状況が良くなっているとは感じられておりません。
次に、団地の活性化についてうかがいます。
花見川団地では4月3日に、花見川団地を拠点とした地域生活圏の活性化に関する連携協定に基づく、「花見川団地商店街北街区交流拠点」が完成したと報道されました。千葉市・株式会社良品計画・株式会社MUJI HOUSU・独立行政法人都市再生機構のこれまでの4者に加えて花見川団地自治会、花見川住宅自治会、花見川団地商店街振興組合の7者で「花見川団地を拠点とした地域生活圏の活性化推進協議会」が立ち上げられたとのことです。今後、交流拠点を起点としながら、さらなる地域生活圏の活性化を推進していくと述べられています。
2022年5月に花見川団地で4者協定が締結されてから今年で丸3年が経過しました。そこでうかがいます。
花見川団地ではこれまでどのような取り組みがなされてきたのか、うかがいます。
【都市局長答弁】
居住環境整備としての住戸のリノベーション、商店街の活性化に向けたコミュニティカフェなどの交流拠点の整備やイベントの実施、地域で活躍する人材の発掘や活動支援として、タウンミーティングの開催、地域資源の活用として、花島公園と連携したイベントの実施などに取り組んで参りました。また、本年1月に設立した活性化推進協議会を通じて、地域の関係者の方々との連携をより深めながら、活性化の取組みを推進しております。
【もりた真弓議員】
花見川団地の取組みについて、事業の結果と評価をお示しください。
【都市局長答弁】
リノベーションされた住戸は若い世代を中心に人気があり商店街は新たな店舗の出店や民間事業者による会員制の交流スペースの開設など、様々な主体による多様な活動の場として認識され、若い世代の流入や新たな担い手の呼び込みに結びついております。また、本年4月3日に開設した交流拠点は、花見川団地における新たな賑わい・交流の創出につながる場所として期待されており、新聞などでも紹介されております。
【もりた真弓議員】
高経年住宅団地対策についてうかがいます。花見川団地では、URと無印良品とのリノベーション事業や、UR都市機構として子育て世帯向けの家賃補助など、いくつかの事業を実施してきました。
- 千葉市でもこの間、団地住替え支援事業に取り組んできましたが、その後の経過と取組の実績についてうかがいます。
【都市局長答弁】
若年層の流入促進による活性化を目的として、住替えに係る費用について助成する「結婚新生活支援事業」の要件を、令和3年度から高経年住宅団地への転居に限定することとし、令和3年度は16件、4年度は22件、5年度は27件の利用がありました。 昨年度は、これらの2事業を統合して、「団地住替え支援事業」として実施し、45件の利用がありました。
【もりた真弓議員】
R5年度、R6年度に住宅政策課が行なった、高経年住宅団地への転居者に係る保育所優先利用モデル事業についての概要をおたずねします。
【都市局長答弁】
子育て世帯の高経年住宅への流入促進を図るため、花見川団地へ転居する子育て世帯が、団地内の保育施設への4月入所を希望する場合の、優先的な入所の調整をモデル事業として行っているものです。
【もりた真弓議員】
「保育所優先利用モデル事業」について花見川団地だけを対象とした理由についておたずねします。
【都市局長答弁】
既に活性化の様々な施策に取り組んでいることや、団地内に複数の保育所が整備されていることを考慮し、花見川団地をモデル事業の対象として選定しております。
【もりた真弓議員】
「保育所優先利用モデル事業」の取り組みで、この事業を利用した入所の状況についてお示しください。
【都市局長答弁】
昨年4月は4人、本年4月は2人の入所がありました。
【もりた真弓議員】
千葉市内のUR団地は賃貸・分譲もあり、それぞれの団地で規模の大小の違いもありますが、何処でも共通した課題を抱えています。美浜区の幸町団地、稲毛区の千草台団地やあやめ台団地、花見川区で言えば、さつきが丘団地や西小中台団地などです。暮らしていく場所として必要だった店舗や医療機関が撤退もしくは閉鎖となっています。団地での日常生活に徐々に不便を感じつつ、先々まで住み続けることができるだろうかという不安な思いを深めているのが正直なところです。
まちづくりの観点から見たUR団地についての課題と、その解決のための横展開について千葉市の考えをお示しください。
【都市局長答弁】
UR団地を含め、高経年住宅団地では、居住者の高齢化や人口減少が進展しており、団地の活性化が喫緊の課題となっております。活性化に向けては、住宅団地への若年層の流入促進が有効な施策の一つと考えており、花見川団地での取組みを検証しつつ、団地それぞれの状況が異なることを踏まえ、また、様々な主体との連携を模索しながら事業の横展開を進めて参ります。
【もりた真弓議員】
住んでいる市民からの「住み続けられなくなる」との不安の声を放置すれば、地域から人が去り、街は成り立たなくなってしまいます。観光で人を呼び込むことに熱心なあまり、いつの間にか「住めない地域」になってしまっていたとならない様に特段の努力をお願いして、質問を終わります。